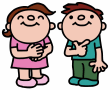日本経済新聞 2017年4月12日配信  http://www.nikkei.com/article/DGXLZO15173040R10C17A4L01000/
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO15173040R10C17A4L01000/
秋田県は手話や点字などの普及を進める「手話言語条例」を施行した。聴覚障害者に限定せず、すべての障害者が円滑に意思疎通できる社会を目指す。地銀が新入行員の研修に手話の講習会を盛り込むなど、条例施行を受けた動きが県内企業に広がっている。
条例は2月県議会で可決され、4月1日施行された。県が手話や点字などの普及や手話通釈者の育成などに必要な施策を行うと規定した。山形県が3月21日に手話言語条例を施行し、東北では2県目となるが「手話に限定しない手話条例は全国でも珍しい」(秋田県障害福祉課)という。
北都銀行は今年度から新入行員の研修に手話講習会を盛り込んだ。11日に新入行員31人に約1時間、手話秋田普及センターの協力で手話への理解やコミュニケーション術を教えた。県内の支店では同センターの活動を紹介する展示も始めた。
秋田銀行は10、17日の2回に分け、新入行員88人に約2時間の手話教室を実施する。県聴力障害者協会と全国手話通訳問題研究会秋田支部が協力する。同行は手話教室を14年度から導入。「幅広いお客様とコミュニケーションを取ることの大切さを、手話を通じて新入行員に学んでほしい」(経営管理部)という狙いがある。
ーーーーー
関連記事
ーーーーー
全国の自治体としては76番目、県レベルでは10番目でした。
おめでとうございます。
聴覚障害者に限定せず、すべての障害者が円滑に意思疎通できる社会を目指す県条例は素晴らしいですね。