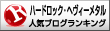※こちらは舞台「This is a お感情博士!2021」の本編以降と、公式コンセプトアートブックの世界観とをミックスして作り出したファンフィクションです。公式各所との関係は一切ございません。
Source of soul
環境破壊が進み、人類の生存年齢が短くなりつつある世界で、人間に取って代わるスピードで増えていたのはロボット。元々は人間をサポートするために作られたそれらが、人間と同じように感情を持ち、恋をして、結婚し、ロボットの子どもを作り出す様になると、その数は加速度的に増えていった。人間と違って環境の悪化も影響は無く、パーツさえ入れ替えれば永遠の命を持つことも可能な彼らが生き残るのは自然の摂理にも似ている。たとえ設計上で寿命を設定したとしても、新たな個体を生み出す技術がある限りは途切れることなく続いていくだろう。
自立し、自我を持ち、繁殖する。おおよそ生命の基本的なモノを持ち合わせたそれは新たなる生命種とも呼べる存在にもなり、ただ絶滅を待つのみの人類無き後で、ロボットだけが生き続ける世界がそう遠くない未来に訪れるかもしれない。
唯一彼らが持ち合わせていないものは、生命としての"魂"だけ――――。
「孝介、これがお前が望んだ未来なのか……」
モニターから流れる映像をぼんやりと眺めつつ、史上初のロボットの大統領が誕生したことをメディアはこぞって喧伝している。人間とロボットが自由に愛し合い暮らしていく幸せな未来は、ロボットの子供を持つことにより少子化は加速し、人類の絶対数の減少により徐々に変貌していき、今では人間は希少価値の高い種として保護条例が出るなどの措置が取られている。国によっては人間と人間との結婚が推奨され、その子供には手厚いサポートが付くようになっていた。そんな中、人権を与えられ、自由意思で働き、納税し、そこから政治にも参加できるようになり、政治家をロボットがやるようになるのに時間はかからず、人間もそれを受け入れたのだ。ロボットはもはや「ヒト」と呼べる存在だった。
日本の片田舎、環境破壊が進んで山林は激減したものの0ではない、豊かとは言い難いがそれなりにある緑地の中に人里離れた一軒家がポツンとある。庭のかわりに植物の成育に適していない土壌に無理やり作られたこじんまりとした菜園、大きくはないもののそれなりに野菜が育っていた。人間の食物は全てプラント工場で効率的に生産されているため、昔ながらの畑はひどく珍しく、そしてロボットのAIでもなかなか上手く育てられなかった。
住んでいるのはたった一人の老人、残りは彼の作り出したロボット達だ。家の扉に小さく馬来田と表札が出ている。
馬来田は生涯結婚をしなかった。ロボットの改造や事業の拡大が忙しいのもあったが、一種の贖罪でもあったかもしれない。年老い、一線を退いたものの、趣味でロボットの改造は続けていた。まだ現役当時「二酸化炭素を吸って弱音を吐く」ロボットは、昨今の環境悪化の一因を解消できるのではないかと一時期世界的ブームにもなったりしたものだ。(あまりに弱音が多すぎでクレームになる事もあったが)
小さな工場から始まった乗せ換え事業は大手参入もあって今や世界規模の産業となり、創始者である馬来田は楽隠居を決め込んで、好きなロボット改造に勤しんでいた。現在はロボットに人権が認められており本人の同意のない改造はできないので、あくまでお感情博士の入ってない旧世代機を自分の生活サポート用にではあるが。
そんな折、馬来田のもとを諒平が訪れた。彼の頭も随分と白くなっていた。電動車椅子で出迎えた馬来田は年は取っているものの前と変わらず明るかった。
「お久しぶりですね、馬来田さん。お元気そうで何よりです」
「おー!諒平か!なんだなんだ?また胡散臭い事業の話か?」
「胡散臭いはひどいなぁ〜」
「ままま、座れ座れ、年寄り一人で機械いじりばかりだと飽きてくるからな、話し相手になってくれ」
「相変わらず、変な改造してるんですか?」
「変なって言うなよ、今度のはすげぇんだぞ。なんと、めちゃめちゃ美味い卵焼きを作れるロボットだ!」
「確かに、まともそうですね」
「そのかわり、作った後太陽に向かって走りながら愛の告白をする」
「…………なぜ……………。」
「三日くらい戻ってこねぇから、三日間卵焼き食えねぇんだよな〜」
「突っ込むところそこですか?!」
目を輝かせながら改造話をする姿は、数十年前と少しも変わっておらず、諒平は切なさにも似た郷愁を抱いた。
「それより、今日は何の用なんだ?なんかあったんだろ?」
「ああ、それですけど、もうご存知かもしれないですけど、あの、社長が……、刑務所で亡くなりました……」
一瞬目を見開いたが、貼り付けた様な笑顔を浮かべ、馬来田は自分の後ろの窓を振り返った。外には菜園を手入れするロボットたちの姿がある。人間と寸分違わぬ姿の彼ら、だがその心はなく、虚ろだ。長い長い沈黙の後、小さく呟いたのを諒平は聞き逃さなかった。
「…………………………………そうか…………。先を越されたな…………」
「葬儀は………僕らだけで行いますが、馬来田さんも……」
姿勢を戻して諒平を見る馬来田の表情は、やはり貼り付けた様な笑顔のままだった。悲しみも、後悔も、何もかも隠して。
「俺は、いいわ。湿っぽいの嫌いだからさ、孝介も辛気臭い俺の顔なんて見たくないだろうし」
「でも、…………いえ、わかりました。みなさんには僕から言っておきます」
「悪いな」
「それでは、帰ります。馬来田さんもお身体お大事にしてくださいね」
「おおよ、俺はいつも元気だぜ」
ヒラヒラと軽く手をふる姿を諒平は後によく思い出す事になる。
それからほどなくして、馬来田の元に一通のビデオメールが届いた。最初真っ暗だった画面が徐々に明るくなり、ただ音声はずっと聞こえていた。
『……これどうなってんだ?』
『ちゃんと撮れてる?』
『待ってください、もう始まりますから』
『やだ、もう始まってんじゃん!』
『おいおいしっかりしてくれよ~』
『Hi!馬来田っちー!元気ー?』
『馬来田さんお久しぶりです』
『相変わらず変な改造してるんですかねぇ』
『俺たち久しぶりに集まったから、来ればよかったのに』
『馬来田さん、車椅子なんであまり遠出は難しいみたいなんですよ』
『そっかー、今度はそっちに集まろうか』
『いいね』
『なぁなぁ、俺たちの新しい家族を紹介するぜ』
騒がしい面々の後ろから引っ張り出されたのは、白石健太郎と乃亜夫婦。そして………。
『先日産まれた乃亜と健太郎の赤ちゃんだ』
『希望(のぞみ)ちゃんでーす!』
『乃亜のちっちゃい頃に似せて作ったから、かっわいいのよ~』
『えー、そうなんだ』
『なんでアンタが知らないのよ』
『馬来田さんにも見せたかったから、また体治して遊びに来てよね』
『絶対だからな』
『それじゃ、またな』
みんなが大きく手を振る様子が映ったまま、映像はそこで切れた。
「相変わらず騒がしい奴らだなぁ……」
最後の映像を止めて彼らの端に佇む姿を馬来田は目を細めて眺めた。世界で初めて産まれたロボットの子ども、孝介と愛菜の子ども、未来。孝介が提案して成長する度に心と知能を乗せ換えて大きくなったその姿。それを成したのは馬来田でもある。それから世界中でたくさんのロボットの子どもたちが産まれ、育ち、親になっていた。それを手がけているのは工場を引き継いだ未来。
「孝介、お前達の子ども、立派になったんだぜ、見せてやりたかったな……」
人間と違って壁や檻を破壊することもできるロボットは、刑務所への面会は禁じられており、100%人間と同じ権利を有している訳ではない部分でもあった。未来は一度も父親である孝介と会うことはなかった。馬来田にはそれが唯一の心残りだったのに。
「あーあ、改造にも疲れたな……。ちょっとだけ、眠らせてくれ」
目を閉じた馬来田が、再び目覚めることはなかった。
2100年台後半、人間は絶滅危惧種と認定され、ロボットによる保護管理下に置かれる事となった。個体番号で識別され、安全な施設の中で飼育され、繁殖もコントロールされた。ロボットだけの世界となっても、ロボットは生き続ける事は可能なはずなのに、なぜ人間と言う種に固執するのか。
それは、彼らが永遠に手にすることができない、生命にしか持つことが許されない、"魂"への執着でもあった。
ヒトを模して作られながら、ヒトには成りきれない。表面上の平和で幸せな世界を持ちながら、存在する意味も起源も持たない憐れな存在。
それでも、意味を求め、魂を求め、ロボットたちは生命の輪廻を模倣し続けていく。
終わり
読んでくれてありがとうございます。
やー、なんか舞台の世界はとてもとても前向きで幸せな世界なんですけど、どうもコンセプトアートブックを見ると、なんだかそれだけではないような、ぶっちゃけ人類に未来ないなって感じしかしなかったので、書いてみました。
あとBlu-rayの最後に後日談が簡単に文章で出てて、自首した後の人間組も元気そうではあったのだけど、人類早死にっぽかったので、ちょっと死に様書いてみました。乃亜が24歳、となると自首してからざっくり30年後くらいがあのエンディングかなーと。30代の馬来田さんも孝介も還暦過ぎたじいさんですよ。むしろあの環境では長生きの部類の気もします。
あとSF的に恋愛対象となる自我のあるロボットなら、人権持ってヒトと同じになってねーか?って部分もあったので、それをちょっとまとめてみました。ある意味私の中の情報と妄想の整理のために書いたので、異論がある方はそっとブラウザ閉じてください。
それにつけても、舞台は本当に素晴らしいものでした!ついついSF考察したくなっちゃうガノタの悪い癖が出てしまいましたが、楽しくて、悲しくて、前向きになれるステキな舞台でした。理想論でもいいんだ。理不尽な現代を生きる我々には理想郷が必要なんだよ。個性的なキャラクターが生き生きと表現されてて、お感情博士、いつかできるといいなぁと思ったり。