前回VOL.30で、共同海損事件処理の過程で、NVOCC業界が遭遇する問題、あるいは、抱える課題が浮き彫りになったのではないかと考える。
このNVOCCが遭遇する問題、あるいは、課題は、「スピードを要求される国際物流に少なからず悪影響を及ぼす」ことも理解できるであろう。
NVOCCが実輸送人である船会社に輸送を委託したコンテナ詰め貨物が、共同海損の担保となる手続き、もしくは、救助報酬の担保を提供する手続きを個別荷主に行なわせるのに、多大なエネルギーを注がなければならず、また、多大な時間を要することになる。
それまでの間、実輸送人である船会社は、貨物の詰め込まれたコンテナをNVOCCもしくはNVOCCの現地側エージェントに引き渡さない。
つまり、「共同海損の費用分担精算が担保される手段」が確実に提供されれていないため、「確実な共同海損精算」手段を確保するため、実際の海上運送人である船会社は、船荷証券(B/L)に規定されている「積荷の留置権(LIEN)」を行使して、コンテナを引き渡さないということである。
権利行使はリスク回避のために必然的にとられる手段であり、この点で、船会社は「当然とるべきリスク回避手段」を実行しているに過ぎず、この手段行使の否定することはできないし、また、それを否定することは合理的とはいえない。
以上のように検討してくると、解決手段はないように見える。
しかし、保険会社にリスクをヘッジする手段はあり、保険会社の合理的にそのような対応を行なうのは可能ではないかと考えられるため、その点について検討を加える。
●保険会社が保険でカバーする合理的根拠はあるか?
前回VOL.30で、NVOCCの「企業リスク回避手段としての責任保険」について説明を加えた。
この、保険の概要は、次の通りである。
○責任保険であること
NVOCCが企業として、第三者から法律的な損害賠償請求を受けることがあり、それを引き受ける保険であること。
○責任保険の対象
NVOCCが利用する責任保険は、国際物流の分野に限れば、「輸送を受託した貨物の所有者」に対する損害賠償の問題であること。
○責任保険のカバー範囲
通常荷主が付保する海上保険等で、損害が発生した場合に保険金支払の対象となるような事故に伴い、NVOCCが法律上責任を問われ、損害賠償金を支払った場合に、一定の免責金額を控除して保険金を支払い、NVOCCの経済的な損失をカバーするものである。
海上保険の説明に入り込んでいくと、また、膨大な説明をしていく必要があるため、端的するために、「責任保険のカバーの範囲」から検討を開始していくことにする。
●責任保険のカバー範囲
積荷貨物に対する損害賠償事案が発生する際に、責任保険が発動する基礎になる約束事がある。
それがいわゆる、基本となる保険の約定書、いわゆる、「責任保険に係わる特約書」である。つまり、責任保険の対象(いわゆる「保険の目的」)に対してNVOCCが法律的に損害賠償責任を負う場合に、このような約束事に従い損害賠償が行われた場合に、この保険が発動するということを示す「保険約款」が列挙されている。
具体的に、その基本となる約定が"ICC(Institute Cargo Clauses)"である。
この約款は、海上保険が発展したイギリスの保険業界が、ロイズ保険組合を中心に、海上保険約款制定委員会で論議が積み重ねられ、19世紀後半に、その基本約款が制定された。
そこで制定された標準約款が、国際貿易に伴うリスクヘッジ手段として、信用状取引に伴う必要書類の一環となる「貨物海上保険証券」の基本約款として定着してきた。
日本の保険会社も、国際貿易の舞台で、海上保険引き受けサービスを提供する場合、イギリスの約款委員会で制定された標準約款を取り入れている。その理由は、イギリスの標準約款の採用がなければ、信用引き受けの主体である銀行等により拒絶されるため、そのようにせざるを得ないという背景があるためである。
○ICC標準約款で共同海損損害は保険填補の範囲
この標準約款で、「共同海損事件が発生し、船会社から一定の手続きを進めることを要求されたり、貨物の所有者として損害分担に応じなければならず、それによる損失が発生する場合に、その損失を保険でカバーする」と規定している。
この標準約款を根拠に、貨物の所有権者のために、保険会社は「共同海損保証状(Letter of Guarantee)を荷主の代わりに発行し、共同海損精算人に提示することになる。
救助報酬分担に関し、救助報酬分担保証状(Salvage Security)を発行し、救助業者もしくは救助報酬精算に従事する業者に提示するのも、同じ意義を持つ。
逆に、NVOCCを含む船会社は、船荷証券(B/L)の裏面に、細かい文字で、共同海損の際の処置として、ヨーク・アントワープ規則に沿い、手続きを進めるとの制限を設けていることになる。
また、既にNVOCCが出荷主の立場に立つことがあると説明したが、実海上運送人としての船会社にコンテナ単位の輸送を依頼していく場合に、その実輸送人の発行する船荷証券(B/L)の表面に、出荷主として明示される。
○貨物の形式的な名義人に対して保険会社は保証を行なうか?
現状、既に触れたところから明らかなように、NVOCCにその道は開かれていない。
しかし、責任保険の基本約定、および、損害賠償責任が法律的に発生する場合に、「その損害をカバーするのが責任保険である」との兼ね合いで、理論的には、「保険会社が保証状を発行しなければならない立場に立つ可能性」はあり得る。
このVOL.31もそこそこのボリュームになってきているため、VOL.31はこれで閉じることとし、次のVOL.32で「保険会社が保証状を発行しなければならない立場に立つ可能性」について、さらに検討を加えていくこととする。
Written by Tatsuro Satoh on 7th Oct., 2007
最新の画像[もっと見る]
-
 さらなる進化を遂げる、ロンドンのジャパニーズ・レストラン
16年前
さらなる進化を遂げる、ロンドンのジャパニーズ・レストラン
16年前
-
 パリのクリスマス
17年前
パリのクリスマス
17年前
-
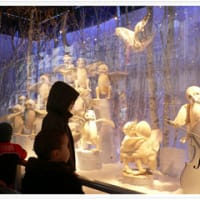 パリのクリスマス
17年前
パリのクリスマス
17年前
-
 パリのクリスマス
17年前
パリのクリスマス
17年前
-
 “ネオ・クラシック”が象徴 2007年のNYトレンド
17年前
“ネオ・クラシック”が象徴 2007年のNYトレンド
17年前
-
 “ネオ・クラシック”が象徴 2007年のNYトレンド
17年前
“ネオ・クラシック”が象徴 2007年のNYトレンド
17年前
-
 “ネオ・クラシック”が象徴 2007年のNYトレンド
17年前
“ネオ・クラシック”が象徴 2007年のNYトレンド
17年前
-
 “ネオ・クラシック”が象徴 2007年のNYトレンド
17年前
“ネオ・クラシック”が象徴 2007年のNYトレンド
17年前
-
 “ネオ・クラシック”が象徴 2007年のNYトレンド
17年前
“ネオ・クラシック”が象徴 2007年のNYトレンド
17年前
-
 神戸ルミナリエ開幕
17年前
神戸ルミナリエ開幕
17年前









