前回VOL.27で、共同海損処理の過程で発生した特異事例のひとつを取り上げた。つまり、コンテナおよびそのコンテナに積み込まれた貨物が海没してしまった場合、共同海損処理の中でどのように扱われるのか、共同海損分担額が発生するのかしないのか等について言及した。
このVOL.28においても、その他の特異な事例を取り上げ、それについて説明を加えていくこととする。
●権利放棄貨物の取り扱い
今回、事件発生から本来の仕向地に向けて代船輸送が仕組まれ、仕向地に貨物が到着するまでに、相当の時間を要することになった。
このような際に、例えば、展示会に出品するために展示品を海上輸送したが、展示会終了後に仕向地に貨物が到着した、という事態も想定される。まさに、受荷主の立場に立つ場合、「受け取る価値がない」ということになり得る。
現に、今回マレーシアのポートケラン向け貨物でその種の権利放棄貨物の問題が発生した。詳細は、固有の情報に関わるため触れないが、そのような権利放棄貨物が共同海損処理の過程でどのように取り扱われることになるかという問題が生じることになる。
〇権利放棄貨物は共同海損損害を分担するか?
結論から入ると、「仕向地において本船から荷卸しされた時点で経済価値がある」限りにおいて、理論的には共同海損分担する利害関係者に加わらなければならないということになる。
それでは、どのように共同海損を分担していくことになるかについて、検討を加えていくこととする。
〇権利放棄を立証するための手続
共同海損精算人は、この種の権利放棄貨物が出てくる場合、「受荷主が確かに貨物を受領する権利を放棄する」旨の受荷主の責任者の署名、サインの入った書面を取り付ける。
その権利放棄を示す書類により、権利放棄された貨物の処分を行なっていくことになる。
〇権利放棄貨物の処分
共同海損精算人は、船主もしくは船会社と協力して、権利放棄された貨物の処分を行なっていくことになるが、具体的な処分方法は、競売ということになる。
競売に伴い発生するコストを極力低くするようにして、積荷の荷揚港で、第三者に競売し、その競売代金を受領し、競売に伴うコストを支払い、正味の競売代金を手にすることになる。
この競売により取得した代価が、共同海損および今回の事例の場合には救助報酬に関わる現金供託金を賄っていくための原資となる。
今回の場合、共同海損を賄う現金供託割合はC&Fの価額に対し5%、救助報酬を賄う現金供託割合はC&F価額に対し30%であった。
従って、権利放棄貨物のC&F価額を算出し、その価額がAである場合、現金供託額は次のように計算される。
(A×5%)+(A×30%)=A×35%=共同海損および救助報酬に関わる現金供託金(B)
ここで、競売に伴う正味収入がCである場合、C>Bであれば共同海損および救助報酬に相当する現金供託金は全額賄えて、残額が発生することになる。
逆に、C<Bである場合、共同海損および救助報酬に関わる現金供託金は賄うことができず、それに伴う損失が発生することになる。
〇競売に伴う差額としての残額および不足額の取り扱いは?
前の項での説明で、競売に伴い、共同海損精算および救助報酬精算に伴うリスクを抱えることになる点について理解できたことと考える。
この過不足額はどのように取り扱われることになるのだろうか?
超過額が発生する場合、現金供託金の共同海損精算および救助報酬精算時点の取扱しついて説明した部分で、「超過部分は受荷主に還元される」点について説明した。
この取扱との関係で論理的に考えると、超過額については、「権利放棄した受荷主に返還する」という考え方がひとつ成立する。
他方で、法律的に権利放棄している関係で、「権利放棄した受荷主に返還する義務は発生しない」との考え方も成立し得る。
共同海損精算人に具体的なケースを設定し、確認する必要があるが、「返還する義務はない」との考え方が合理的である。
権利放棄貨物が複数権発生する場合に、競売の結果、「賄って余りある場合」と「不足する場合」が発生する確率は、50:50の関係と考えて支障ない。しかも、不足が生じる場合に、その不足分を支払うよう受荷主に求めることは、「権利放棄」を共同海損精算人として追認している以上、現実的に不可能である。
以上の背景を考慮する場合に、「損失が発生する競売」と「残額の発生する競売」のリスク割合が同程度であるため、共同海損精算書の中に含め、例えば、「別途収入」、「別途損失」等の項目で処理することになるのが合理的であると考えられる。
しかしながら、以上の論点は、共同海損精算人に確認しているところではなく、また、共同海損精算人に課せられている実務規定等を確認しているわけではない。従って、正確性を期す意味で、確認することが慣用であるので、この点にあえて触れることとした。
以上で、積荷貨物に対する権利放棄が発生した場合の処置のあり方についての説明を完了させ、このVOL.28の説明を終わることとする。
次回VOL.29において、その他の共同海損精算の簡素化、シンプル化の観点に立ち、「特異事例項目として取り扱うことのある項目」について取り上げ、若干の検討を加えることとする。
Written by Tatsuro Satoh on 7th Oct., 2007
最新の画像[もっと見る]
-
 さらなる進化を遂げる、ロンドンのジャパニーズ・レストラン
16年前
さらなる進化を遂げる、ロンドンのジャパニーズ・レストラン
16年前
-
 パリのクリスマス
17年前
パリのクリスマス
17年前
-
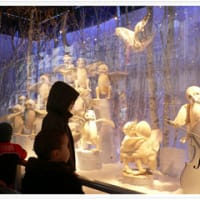 パリのクリスマス
17年前
パリのクリスマス
17年前
-
 パリのクリスマス
17年前
パリのクリスマス
17年前
-
 “ネオ・クラシック”が象徴 2007年のNYトレンド
17年前
“ネオ・クラシック”が象徴 2007年のNYトレンド
17年前
-
 “ネオ・クラシック”が象徴 2007年のNYトレンド
17年前
“ネオ・クラシック”が象徴 2007年のNYトレンド
17年前
-
 “ネオ・クラシック”が象徴 2007年のNYトレンド
17年前
“ネオ・クラシック”が象徴 2007年のNYトレンド
17年前
-
 “ネオ・クラシック”が象徴 2007年のNYトレンド
17年前
“ネオ・クラシック”が象徴 2007年のNYトレンド
17年前
-
 “ネオ・クラシック”が象徴 2007年のNYトレンド
17年前
“ネオ・クラシック”が象徴 2007年のNYトレンド
17年前
-
 神戸ルミナリエ開幕
17年前
神戸ルミナリエ開幕
17年前









