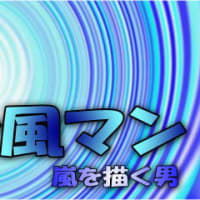伝説の野外コンサート
1970年フォークジャンボリー青春画報
「だからそこに行く!その4」
しばらくブラブラしていたら、後ろで俺を呼ぶ声がした。
「酒井君も来とったのかね?」山本さん夫婦である。
山本さんは同じ岐阜市に住んでいる画家で、肩まで有る長い長髪をなびかせ穴の開いたジーンズを穿いたヒッピーのようないでたちである。
「さっき来たばっかやけどね!」俺は答える。
「これ作ったんやけど、あげるわ」と云いながら、”ちんちんかもかも”というタイトルの書かれたミニコミ誌をくれた。
当時はパソコンのプリンターなどというものは存在すらしない時代である、そのミニコミ誌はガリ版摺りの手作りのわら半紙をホッチキスで留めただけの質素な小冊子であった。
「ありがとう」と言いながら内容を見ると、自作の絵や詩をつらねた詩集のようなものだった。
「じゃ、また・・」と言いながら、山本夫妻は去っていきながら、また別の人に自作のミニコミ誌を配っていた。
深山幽谷とまでもいかないが、こうした山深い場所で日本の新しい音楽文化が勢いをつけ始めようとは、誰も予測できなかったことである。
空は真夏の青さを保ったまま山々に覆いかぶさるように輝いていた。
空気は、木々の緑の匂いと湖の水の匂いを漂わせ、時折吹く風が肌にあたるとき爽やかな涼しさを感じさせてくれた。
そのとき突然のように「アマチュアで出演希望の人は、ステージの後ろに集まってください!」と、会場全体に響く大きな音でアナウンスが流れた。
「えっ?飛び入りで歌えるのか!」そう思ったら、矢も立てもたまらずステージで歌いたい衝動に駆られていく自分であった。
俺は慌てて戻り、ギターをケースから出し、ギターを抱えてすぐさまステージ裏に急いだ。
せっかく重いギターを担いで遥々やってきたのである、飛び入り参加しない手はない!そんな興奮した思いが駆け巡って顔が紅潮していくのが分かる。
そんな思いを抱きながら、ステージ裏で自分の出演順をドキドキしながら待っていると、「次、酒井さんです」と声が掛かった。
興奮してボーッとして夢うつつのまま、いつの間にか俺はステージの上に立っていた。
俺の横には、マイクを挟んで司会の”はしだのりひこ”が立っていた。
「どこから来られたんですか?」はしだのりひこは、ラジオやレコードで聞いたあの声のまま、今俺と会話している。
「近所からです・・」俺は、自分が何処かへ吹っ飛んでしまって、何を答えているのか自覚していない。
「近所と言うと、どこですかね?」
「町です」
「はぁ・・・家とかいっぱいあるとこですね」
「山もあります・・」
「片田舎ちゅーやつですね」
始終チグハグの会話のまま、いつの間にか俺は本番の唄に突入していた。
俺は、マイクに向かって「”月光仮面の唄”やります!」そう言うと唄い始める。
”ど~こ~の誰か~は知らないけ~れ~ど~・・”
そう、あの昭和30年代の和製ヒーロー”月光仮面”の主題歌である。
会場に居る2千人ほどの観客が、ドッと沸いているのがわかった。
”月光仮面”は、俺の一発勝負の受け狙いの1曲だったのだ。
夢を見ているような気分で曲が終わり、心ここに在らず状態な俺だったが、会場がどよめき拍手の嵐であったことは理解できた。
「どうも有り難うございました、次の人・・・・」はしだのりひこが閉めの会話をし、俺はステージの後ろに帰っていった。
そして、ステージ裏に出て行った瞬間、突然のように見たことあるような女が、俺にマイクをつきつけてきた。
その女というのは、フォークジャンボリー記録映画”だからここに来た!”の司会の”吉田日出子”だった。
「なんで月光仮面を唄ったんですか?」吉田日出子はニコニコしながら、こう俺に質問してきた。
「一発勝負の受け狙いです」ハァハァ呼吸が荒いまま、俺は答えている。
「なんで、一発勝負の受け狙いですか?」吉田日出子が突っ込んで聞き返してくる。
「フォークジャンボリーの思い出に・・・!」
そう答えたような気がするが、興奮したままの状態なので、自分でも何を言っているのか無自覚のままインタビューは終わってしまった。
数千人の前で歌を歌い、はしだのりひこと話をし、吉田日出子インタビューを受け、そして今こうやって興奮冷めやらぬまま椛の湖畔に佇んでいる。
それが一瞬の出来事でもあるような、またとても長い出来事でもあるような、そんな不思議な心持だった。
陣取った席に帰ると平井君が俺に向かって言った。
「ものすごく、うけとったぞっ!」
「受けた!?」俺は、してやったり!の気分一杯で言った。
しばらくすると興奮も冷め、ステージ上で繰り広がられるアマチュアの歌い手と”はしだのりひこ”の掛け合いを眺めていた。
後にソルティシュガーの”ハナゲの唄”で一世を風靡する”ひがしのひとし”の”鼻毛に関する社会科学的考察”や、”なぎらけんいち”の”怪盗ゴールデンバットの唄”は、この飛び入りコーナーで有名になった曲である。
十数人のアマチュアの時間が終わると、いよいよ本番のコンサートである。
アテンションプリーズ、小野和子、のこいの子、グループ「愚」・・・盛りだくさんのシンガーが歌い叫び、否応無くお祭り気分が盛り上がっていく。
加川良・高田渡・岩井宏の臨時のユニットで歌い始めた”教訓Ⅰ”や”自衛隊に入ろう””自転車に乗って”なんなかを一緒に歌ったり、俺の興奮は止めようが無かった。
夕暮れ時になると、風が少し涼しくなってくる。
山々の木々の匂いを漂わせながら、爽やかな風が興奮した男や女の間を燕のようにすり抜けてゆく。
野外コンサートでしか味わえない素敵な瞬間だ。
辺りは次第に暗くなってゆき、真夏のコバルト・ブルーの光る空の色が、ウルトラマリンの油絵の具のような深い群青色に変化して行く。
それらは、ステージの上のフォークシンガーを盛り立てる自然の舞台装置でもあった。
先ほどのシンガーが舞台を下り、次のシンガーが現れる。
その男はギター1本を抱えながら、テンガロンハットを被りヨレヨレのジーンズを引きずるように登場した。
そして、マイクの前にセットされた椅子に座ると、いきなりギターを鋸でも挽くようにガッガッガッと演奏し始めた。
”君は待ってたんだ~~~!!・・・・・・”
遠藤賢司である。
彼のパワフルな弾くギターは、まるでロックバンドのようにエネルギッシュに会場全体を包み込んだ。
とてもギター1本の演奏とは思えない迫力に、観客は圧倒され度肝を抜かれたようだった。
”なんか良い事ないかと・・夜汽車は走ってゆくのですぅ・・・・”
”遠藤賢司”の名前が、全てのフォーク・フリークの脳裏に刻み込まれた瞬間であった。
そして、何度もアンコールが連呼され、彼のステージはなかなか終わらない。
数曲のアンコールを歌い、なのこり惜しい溜息と共に、遠藤賢司はステージを後にした。
興奮冷めやらぬ観客は、まだまだどよめいている中、男3人と女1人のグループが颯爽と登場した。
”五つの赤い風船”である。
彼らが”遠い世界へ”を歌い始めると、会場全体が1つの固まりになったかのように、観客も一緒に歌い始める。
ラジオの深夜放送で幾度となく聞いている、忘れることも出来ない名曲だった。
歌い終わると、流暢な大阪弁で”西岡たかし”が観客を笑わせながら、次への曲へと導いていく。
”おぉぉ~!今も昔も変わらないはずなのに~~~・・・・!!”
ドッと押し寄せる波のように観客の拍手が椛の湖の山々に木霊した。
手拍子をとりながら立ち上がる男もいた。
肩を組みながらリズムを取る男女もいた。
西岡たかしの声と観客の声が一体となり、山々を揺るがすようだった。
演奏が終わっても拍手は鳴り止まない。
観客の興奮を鎮めるかのように”血まみれの鳩”が静かに演奏され、しだいに観客のどよめきも鎮静化されるかのようだった。
辺りはもう真っ暗になり、ライトに照らされたステージだけが真夏の夜の夢のように輝いていた。
”五つの赤い風船”も退場し、静かになった舞台上では、司会のはしだのりひこが次の出演者の紹介をしている。
次は、万国博覧会帰りの”スルク大舞踊団”である。
スルク大舞踊団の女性が、白いパンツもあらわに舞台の上を所狭しと乱舞している姿は、高額出演料の名に相応しい踊りには違いない。
”松岡実&ニューディメンション”の演奏する邦楽ジャズは、初めて聴いたロックのように新鮮だった。
小雨がパラパラと降ってきたが、傘を持っている観客たちは色とりどりの傘を差し、斬新な邦楽ジャズの”テイク5”に聞き入っていた。
傘など持ってきてもいないので、俺はそのまま小雨に当たったままステージに聞き入っていた。
すると唐突に横から傘がニューッと差し出されたので、俺はドキッとして横を見た。
「あんた月光仮面歌ってた人でしょう?」そう大阪弁で言いながら
そう大阪弁で言いながら、見知らぬ女が唐突に横から傘がニューッと差し出してきた。
俺はドキッとして横を見、「あ、そうです」と答えた。
そう答えたが、続きの言葉も出ない。
その隣の女も黙ったまま、見知らぬ同士の相合傘で、さらにコンサートは続く。
しだいに小雨もやみ、女は傘をたたんだ。
女は何か言いたそうだったが、スピーカーの音に圧倒されたのか、何も言わなかった。
俺も、軽く会釈をしただけで一瞬の相合傘は終わった。
見知らぬ男女が、野外コンサートで知り合いになるというパターンは良くある出来事であるが、俺はそのまま何もないまま、さらにさらにコンサート続く。
深夜に近くなると”浅川マキ”の登場だった。
寺山修司の歌詞を歌う浅川マキは、黒い服に身を包み、妙に妖艶だった。
”夜が明けたら・・・夜が明けたら・・・・”
呟くように歌う浅川マキの歌は、あの時代のやり場のない暗さのようなオーラを発しながら、深夜の星空に木霊していた。
深夜も深くなり午前1時ころになると、ついにフォークの神様とも呼ばれた”岡林信康”の登場だ。
”はっぴいえんど”の重圧なロックをバックに歌う岡林信康は、日本のボブ・ディランと命名されるのに相応しい貫禄で、深夜の椛の湖に響き渡る。
”私達の望むものは・・・!”
そう叫びながら、声もかすれて歌う岡林信康の勇姿に、観客は全員総立ちでシングアウトしている。
”・・・生きる喜びなのだぁっ!!”
俺も、スピーカーから流れる大音量の音に負けないくらいの声で歌っていた。
”まだ見ぬ幸せに、今飛び立つのだぁぁ・・・・!”
前面にあるスピーカーの音に、体全体が解けてしまうような錯覚を覚えながら、リズムに合わせて揺らす体は波に揺られている感じだった。
”はっぴいえんど”のドラムとギターの電気音が、椛の湖を、中津川を、山々を、星星をシュガーシロップのように覆い包んでいく。
人々の熱狂が、台風の目のようにグルグル見えない渦を作りながら、日本中を巻き込んでゆくような勢いだった。
長い長い興奮の時間が過ぎていく、俺は和製ロックの熱い音に包まれながら、真夏の夜の夢の真っ只中にいたのだ。
先ほどの小雨模様の空は、もうすっかり晴れ上がり、満天の星をキラキラと輝かせている。
深夜の3時ももう直ぐだ。
いつもなら、深夜放送を聞きながら、やりたくもない受験勉強をチンタラやっている時間である。
だが、今はここにこうやって見知らぬ人達だが、同じフォークソングという共通の音楽に酔いしれ、自由を謳歌している。
それは、世間知らずの高校生にとっては、未知でもある輝かしく満たされた至福の体験であった。
何度も何度もアンコールが沸き、そのつどに歌い続ける岡林信康とはっぴいえんどは、時代の象徴に相応しいミュージシャン達だった。
熱狂の演奏が終わると、観客はゴムがプツンッと切れたように静かになり、俺も猛烈に眠気が襲ってきたのだった。
所々では、寝袋に体を入れいびきをかきながら寝ている輩も居る。
少し肌寒い山の空気を感じ、体を丸めながら眠気を我慢しているが、俺もほとんど夢うつつの状態だった。
大半の観客が睡魔に襲われ、今にも夢に入り込もうとした瞬間に”南正人”の歌が始まってしまった。
”果てしない流れに咲く・・ひとすじの愛・・・・・”
ほとんど朦朧とした意識の中、そんな”南正人”歌を子守唄にしながら、俺と平井君は夢の中へ溶け込んでいったのだった。