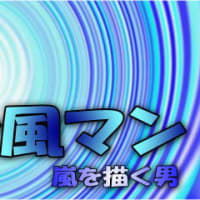伝説の野外コンサート・フォークジャンボリー青春画報
「だからそこに行く!その2」
その日の岐阜の町も平和そのものだった。
フォークジャンボリー開催当日、俺は同じ写真部の副部長の平井君と一緒に中津川まで行くことになった。
フォークソング仲間の村上は、結局参加できないというので、我々2人だけでの蒸気機関車に揺られながらの3時間近くの道中となった。
国鉄・中央本線・鈍行は、岐阜駅から中津川の坂下駅までは途中下車・乗り換えなしの直通である。
国鉄岐阜駅は、南口と北口が有り、南口は昭和初期に建てられた古い建築物のままだった。
「おーい!酒井く~ん!」平井君が駅で待ってる俺に向かって、手を振っている。
はあはあ言いながら、平井君は息せき切って走って来た。
アロハシャツに小さな鞄1つだけの軽装である。
それに引き換え、俺の装備といったら見るからに重装備である。
いつものギターにカメラ2台、おまけに8ミリ映写機まで担いでいる。
当時の8ミリ映写機はかなり重く、フィルムを途中で反転して入れ替える”Wフィルム”と、そのまま撮影できる”シングル・フィルム”と2種類あったが、俺の担いでいるのは古臭いWフィルムの使用できる映写機で、重さも軽いとは言いがたい代物だった。
そして肩に担いだバッグには、それらのフィルムやもろもろの物が入って、これも軽いとは言いがたいバッグだった。
「あと5分しかないで、はよ行こ!」そう言いながら、俺はまるでゴルゴダの丘に向かうキリストのように腰を屈めながら、苦しそうに駅の階段を上っていった。
そんな、俺を見かねた平井君がカメラの入ったバッグを持ってくれた”持つべきものは友である”ということである。
ジリリリリーンと発車のベルが鳴り響き、ピーッと汽笛を鳴らしながら、ゆっくりと蒸気機関車は中津川へ向かって出発していく。
汽車の蒸気がプラットホームに充満して、駅で見送る人々は、まるで霧に包まれたようにも見える。
しだいにスピードを早める蒸気機関車は、巨大な生物のように呻りながら、少しずつフォークジャンボリーの地へと俺たちを導いてくれるのだ。
幸いにも座席に腰掛けられた俺たちは、荷物を網棚に乗せ、ほっと一段落した。
「酒井君。荷物いっぱいやねぇ・・・」平井君が、俺の荷物を見つめながら言った。
「いやぁ・・岡林信康とか五つの赤い風船の写真とか撮りたくて・・」そういいながら、手に持っていたカメラのキャップを取り、平井君に向けて1枚パシャリとシャッターを切った。
右手でピース・サインを出し、ニコッと笑った平井君がファインダーに写りこんだ。
「平井君の紹介してくれたアルバイトは楽やったね」そう言いながら、俺はパシャリともう1枚シャッターを切った。
「そうやね、ほとんど昼飯を食いにいっただけのバイトやったね」
「道路掃除しとっただけやもんな!」
アハハハ・・と2人は同時に笑いこけた。
「おかげで、10日間で8000円も貰えたし、フィルム代も電車代も出たわ!」俺は、感謝しながら平井君に言った。
「僕は、このアロハシャツ買ったで!」平井君は、自分の着ている新品のアロハシャツを指差しながら、ちょっと自慢げに言って見せた。
天気は晴天で、汽車の窓から見える景色は、青い空をバックに夏の風景を鮮やかに展開させている。
俺たちのほかにも、ギターを抱えた青年や長髪の怪しげな男女が搭乗していて、彼らもフォークジャンボリーの参加者であることを表明しているかのようだった。
「そういえば、村上君は来んかったね・・」平井君が俺に言った。
「なんか用事があるみたいやで、来んかったは・・」俺は、ちょっと残念そうに言った。
ガタンゴトン揺れる蒸気機関車は、時折ピーッと汽笛を鳴らしながら一路中津川へ向かって走っていく。
途中の名古屋駅からは、大勢のギターを担いだ若者たちが乗ってきて、さながらフォークジャンボリー専用列車の様相を醸し出していた。
名古屋から岐阜の山間部に入るにしたがって、トンネルが多くなってくる。
長いトンネルでは、蒸気機関車特有の石炭の燃えるタール臭い黒い煙が大量に列車の窓から入り込み、乗客は一斉に窓を閉めるのだった。
中津川駅も近くなると、乗客がざわめき始めた。
「ジャンボリーは、ここの駅で降りるんじゃないか?」
「いや、違うよ、坂下駅で降りるんだぜ!」
「えっ?中津川でやるんじゃないの?」
「坂下駅から椛の湖までは、結構遠いらしいぜ!」
東京弁での会話が、あちこちで聞こえてきた。
実のところ、通称”中津川フォークジャンボリー”と呼ばれてはいたが、実際は岐阜県恵那郡坂下町の椛の湖畔で開催されたコンサートだった。
一番近い駅は坂下駅であるが、中津川駅で下車すると勘違いしていた人々も多いようだ。
汽車は中津川駅を過ぎ、坂下駅に到着した。
俺は急いで荷物を棚から下ろし、列車を降りた。
駅のホームは、ギターを肩に担いだ青年や色とりどりのチューリップハットを被った若者で一杯だった。
「椛の湖までは、どうやって行くんやろ?」平井君が俺に聞いてきた。
「地図が有るで、見てみよか」俺は地図を広げながら言った。
地図を見ると、駅から椛の湖まではさほど遠くないように見えた。
周りを見れば、歩いていく人々も大勢い居るのが見える。
会場までバスも出てはいるようだが、なにぶんお金も節約せねばならない身の上なので、やむなく歩いていくことにした。
「皆歩いていくみたいやで、結構近いんと違うか?」俺は、平井君に言った。
「そんな感じやね・・・」平井君も同感のようだった。
ゾロゾロと山並みの細い道を大勢の若者が行列を作って歩く姿は、さしづめフォークジャンボリー神社に向かう熊野詣や御伊勢参りのようなものだっただろう。
くねくねと曲がる山道は、思いのほか傾斜がきつく地図で見るよりよほど遠いように思われた。
山間部とはいえ夏の日差しはきつい。
その上、ギターやカメラを担いだ俺には、その山道が果てしなく続く巡礼の道のようにも見えるのだった。
汗が額を流れ、汗を拭くのも面倒なくらい手が痛い。
周りの行列の人々も、額に汗を流しながらも黙々と歩いている。
「・・・咽が渇いたなぁ・・」俺は独り言のように呟いた。
「・・・水でも飲みたい・・・」平井君もちょっと疲れ気味であった。
ペットボトルなんて洒落たものもあるはずもない時代である、平地ほどではないが炎天下の太陽は容赦なく俺達の咽を干上がらせていった。
しばらく歩いていくと、数人の人だかりがあった。
村の民家の庭で、数人の男女が水を飲んでいたのだった。
砂漠のオアシスとは、このことを言うのだ。
「水を飲ませてください」そう言いながら、俺と平井君は庭に入り込み、流れる蛇口から冷たい水を思う存分飲んだ。
「あんたらも、椛の湖まで行くら?」その民家のおばあさんはそう言いながら微笑んでいた。
「ああ、そうです・・」俺は答えた。
「大変やなぁ・・まぁ、適当に飲んでってなぁ」中津川弁でそう言うと、そのおばあさんは家の中に入っていってしまった。
「有難う御座います」と丁寧に挨拶し、俺と平井君はその民家を後にして、椛の湖までの長い巡礼の道のりをテクテクと歩いていった。