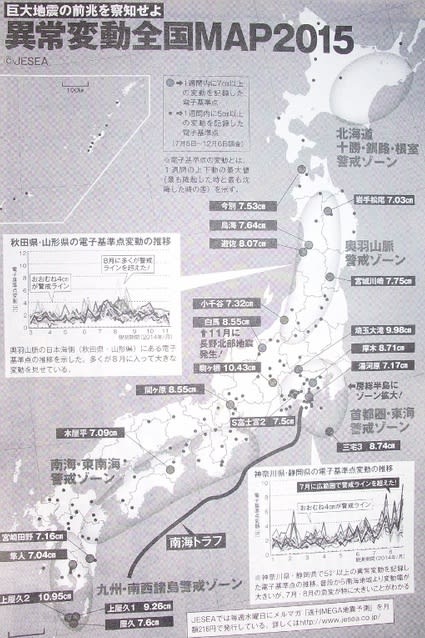電子基準点のデータを使い、有料メルマガ「週刊MEGA地震予測」などで地震予測サービスを行っている、東京大学名誉教授の村井俊治氏(JESEA・地震科学探査機構)という方がいます。
本ブログでは、彼らの電子基準点データの取り扱いはデタラメであり、実際に地震予測もほとんど当たっていないと説明してきました。先日、島村英紀・武蔵野学院大学特任教授も、ほぼ同じ論点で村井俊治氏らの地震予測サービスを批判しました。
当たって当たり前?「MEGA地震予測」を科学的にどう見るか
http://thepage.jp/detail/20150912-00000003-wordleaf
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6174160
http://thepage.jp/detail/20150912-00000003-wordleaf
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6174160
これに対し、村井俊治氏らJESEAが、ホームページで以下のような反論を発表しています。
YAHOO ニュースに取り上げられた記事について
http://www.jesea.co.jp/yahoo-news/
http://www.jesea.co.jp/yahoo-news/
…この村井氏らの反論を読みますと、全く批判に対する答えになっていないことが分かります。このような反論しかできないこと自体が、村井氏らが科学的に間違った態度で研究を行っていることを如実に示しているように思えます。以下に説明します。
■ ノイズをそのまま使っているという指摘に反論できていない
村井俊治氏らはこの反論において、以下のように主張しています(下線は本ブログによる)。

…これは話になりません。村井氏は、「異常なデータは棄却している」と主張していますが、1週間といった短期に起こる鉛直方向の数センチもの変動は、ほとんど全てが「ノイズ」すなわち「異常なデータ」なのです。近くにビルや樹木がなくても、電離層の状態や大気中の水蒸気量等の影響で電子基準点には数センチのノイズが簡単に出るのです。こうした棄却すべきノイズを全然棄却せずに「地殻変動だ!」と偽っているという批判に対し、彼らは全く反論できていません。
村井氏が、国土地理院が公開している数字を、そのまま使って地震予測をしていることは、メルマガや雑誌の記載から明らかです。たとえば、南関東での地震予測の根拠とした「山北で4.2cm、箱根で4cm、湯河原で4.3cm、静岡の宇佐美で5cm」といった数字は、国土地理院が公開したデータそのままであり、そして、これはノイズだと国土地理院がハッキリ見解を出しているのです。詳しくは、国土地理院からの回答を踏まえた以下の記事をご覧ください。
「週刊MEGA地震予測」の内容は、全く信頼できません
http://blog.goo.ne.jp/geophysics_lab/e/98691b7b417e3670144d0d61fe544e41
http://blog.goo.ne.jp/geophysics_lab/e/98691b7b417e3670144d0d61fe544e41
以上のとおり村井氏は、近くにビルがあるような基準点しか棄却せず、そのほかの基準点については、国土地理院がノイズであると言っている異常なデータを棄却せずそのまま使っている訳です。こうした指摘に対し、村井氏は全く回答ができていません。
■ 地殻変動の基準点についての反論も的外れ
また、村井氏らJESEAが使っている座標系について、以下のように反論しています。

…この反論も、お粗末極まりないですね。球面上で各点が移動しているとき、球面上の動きを記述する絶対的な基準を設定するなら、球面上に設定しなければなりません。「球の中心が固定されているでしょ」という反論は、全くナンセンスです。これくらいのことは、中学生レベルの幾何でも理解できるはずです。
地球中心座標系とは、地球の中心に対して任意にX軸、Y軸、Z軸を選んで固定したときの座標値を表します。一方、地球表面ではプレートテクトニクスの影響で、プレートに乗ったあらゆる点がプレートと共に動いています。極端な話、X軸、Y軸、Z軸(をどこにとるべきかの基準)も動いていると言えるのです。ですから、やはりたとえ地球(=球)の中心を基準として固定しても、地表(=球面上)でプレートテクトニクスで動いている各点については、絶対的な基準点は設定できないことになります。私や島村先生が指摘しているのは、そういう意味です。
実際、気象庁や国土地理院が発表する地殻変動のデータや説明図では、必ずどこか任意の観測点が基準局(固定局)として設定されています。小さい字で資料の隅に書いてあることが多いので気づかないかもしませんが、今後はぜひ注意してみてください。
また、そもそもXYZ座標系を使うこと自体がおかしいと言えます。JESEAの説明図でもわかりますが、ノイズが激しく残る鉛直成分が、XYZの全てに含まれてしまうのです。XYと言うといかにも水平成分に思えるかも知れませんが、違います。ですので、銚子と館山でXの増減が逆になっていたとしても、「東西方向で逆の動き」とは言えません。この意味でも、やはりメルマガの記載は間違っているのです。
※1 ただ、動きベクトルの差分を注意深くとれば、相対的な位置の変動はわかります。この指摘は単に、「逆方向に動いている」という言い方をする時点で、地殻変動の観測についての理解が乏しいのではないかと指摘したにすぎません(少なくとも私の意図は)。ただし、上述したとおりXYZには全て鉛直方向のノイズが含まれてしまうので、いずれにしても短期的にはノイズまみれになります。
※2 島村氏の指摘のなかに「銚子と館山の間の地点に基準点があるから逆方向に動いているように見える」とありますが、これについては島村氏が不正確です。銚子と館山の間になくても、銚子と館山と比べた場合に別方向に動いたどこかの基準点を不動点にとれば、銚子と館山が逆方向に動いて見えます。
※2 島村氏の指摘のなかに「銚子と館山の間の地点に基準点があるから逆方向に動いているように見える」とありますが、これについては島村氏が不正確です。銚子と館山の間になくても、銚子と館山と比べた場合に別方向に動いたどこかの基準点を不動点にとれば、銚子と館山が逆方向に動いて見えます。
■ 特許を「自分たちが正しい」ことの根拠とする愚
また、彼らは自分たちの特許を、自分たちが正しいという根拠を補強するものとして主張しています。

…もうこれは、無知なのか、よほど悪質なのか分かりませんが、呆れる他ありません。実は、地震や噴火の予知方法などという特許は、他の個人や団体によっても非常に多く出願され、登録さえされています。たとえば、以下の検索サービスで検索してみてください。
特許情報プラットフォーム J-PlatPat:
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
こうした特許が出願され、多くは登録すらされているのは、「この方法なら地震が予知できる」と審査官が認めたからではありません。ただ単に、「同様の方法が、それまでに特許出願等されていないから」に過ぎないのです。特許の審査は、ほとんど1人の審査官が行います。審査官に地震学者など、おそらく一人も居ないと思います。「地震や火山の予知方法」などという特許出願がされても、論文の査読のように、科学的な根拠を綿密に審査されるわけではないのです。
また、「国がその相関関係を認めた」などと主張していますが、実際に彼らの特許明細書をみると、電子基準点データに異常があってから地震が起きた例は、たった1例しか記載されていません。しかも、その1例も、間違っているのです。詳しくは、以下の記事をご覧ください。
地震科学探査機構(JESEA)による地震予測サービスについて
http://blog.goo.ne.jp/geophysics_lab/e/5b8a8daa27cdfa11240b6660d6ea0a5f
http://blog.goo.ne.jp/geophysics_lab/e/5b8a8daa27cdfa11240b6660d6ea0a5f
またそもそもこの特許の方法は、メルマガ「週刊MEGA地震予測」では使われていません。村井氏らの特許は、任意の3点でつくられる三角形の面積変動から地震予測をする、というものです。それに対し、メルマガ「週刊MEGA地震予測」では、単点の上下移動を「週間異常変動」として予測の根拠にしています。ですので、村井氏らのメルマガと、この特許は無関係であり、「週刊MEGA地震予測」が正しいという根拠には、全くなり得ないのです。
■
まとめますと、以上の村井俊治氏らJESEAによる反論は、全く反論にすらなっていない代物です。彼らのサービスの程度を、はからずも如実に示すものとなっています。
とにかく、最も重要な点は、村井俊治氏らJESEAが、国土地理院が「ノイズだから地殻変動を表すものとしてそのまま使うな」と警告しているデータを、そのまま使って有料の地震予測をしている点です。この点について、彼らがきちんと研究とサービスを見直し、科学的に真摯な態度に改めて頂くことを、強く希望します。
※本記事は彼らの反論を受け取り急ぎ書いたので、不正確な記述や間違いがあるかも知れません。適宜ご指摘いただけますと幸いです。それに応じて加筆等があるかも知れませんがご了承ください。また、このJESEAの反論は、メルマガ購読者に向けたもののようですが、島村氏の名誉のためにも、この反論も極めて的外れなものであることを指摘したく、ここに記事としたものです。