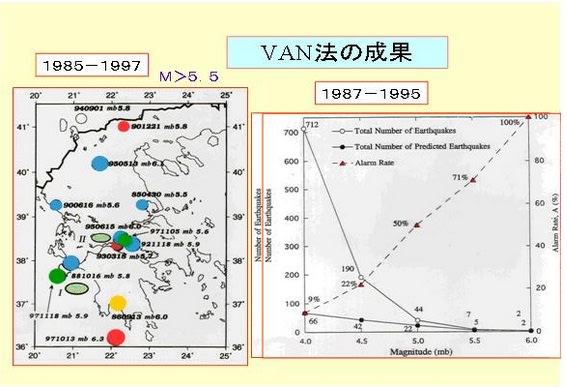2015年12月に、『地震前兆現象を科学する』(祥伝社新書)という本が出版されました。著者は、織原義明氏と長尾年恭氏で、おふた方とも、地電流異常や宏観異常現象を含めた地震予知の研究で知られた先生です。

以下に、本書で検証されている3つの民間の地震予知研究についての内容を中心に、紹介してみたいと思います。
■ 民間地震予知研究についての検証について
本書では、村井俊治氏のGPSによる予測、串田嘉男氏のFM電波による予測、早川正士氏のVLF電波による予測が、以下のように検証されています(75頁~93頁)。ここで、「適中率」は予測どおりに地震が発生した割合、「予測率」は地震を事前に予測していた割合を示します。
村井俊治氏: メルマガ(2014/10/1号) 適中率11%、予測率33%
メルマガ(2014/12/17号) 適中率25%、予測率100%
串田嘉男氏: 適中率6%、予測率9%
早川正士氏: 適中率15%、予測率13%
メルマガ(2014/12/17号) 適中率25%、予測率100%
串田嘉男氏: 適中率6%、予測率9%
早川正士氏: 適中率15%、予測率13%
…このように、一般に宣伝されているよりも低い数字が挙げられていて、地震予知を推進する著者らにしては客観的であると言って良いかも知れません。しかしながら、この検証には以下の意味で不備があり、村井氏と早川氏については、不当に甘い数字になってしまっています。
まず、村井氏のメルマガについては、予測精度が他と比べて高くなっているのが分かります。これは、公開されているメルマガのサンプル号のみを検証したものだからです。サンプルとして村井氏らが公開しているのは、予測どおりに地震が発生した号を、あとから宣伝のため選んだものですので、予測率等が高くなるのは当たり前です。これでは、意味のある検証とは到底言えません。また、串田氏や早川氏の予測に比べて、村井氏の予測は範囲も期間も非常に広いので、同じ尺度で検証したような数字で並べるのは公平さを欠きます。
串田氏については、近藤さや氏等による既存の評価(こちら)をそのまま紹介しているだけで、特に著者らが独自に検証した新しい内容はありません。
早川氏については、「早川氏らが的中と判定したもの」を「的中」として計算しています。つまり、ほとんど自己申告を信じて検証したものであり、甘い結果になっています。著者ら自身も、「栃木県から愛知県を結ぶ内陸エリアの予測に対して、千葉県東方沖の地震を当てた地震としていることに違和感を覚える」(92~93頁)と書いていますが、実はこれも「的中」として計算した数字なのです。もっと厳密に検証すれば、さらに低い数字が出るはずです。
そして、最大の問題は、彼らが提示するデータは実際の前兆を捉えたデータであるという前提を、鵜呑みにしてしまっている点です。著者らは、「GPSデータでとらえられる地殻変動も、FM電波やVLF電波の異常も、地震の前にみられる現象であると、筆者らは考えています」(94頁)と言っています。つまり、彼らが単に観測上のノイズを捉えているに過ぎないのではないかという点を、疑いもしていないのです。この点は、非常に物足りなさを感じざるを得ません。
しかしながら、以上のように甘い検証であっても、以上の3つの研究についてのまとめとして、「今の情報の出し方は世間に誤解を与えかねない」「疑似科学やニセ科学と言われてしまうかもしれません」(94頁)と厳しい書き方になっている点は、注目に値します。
■ その他、本書における違和感
ほかにも、気になる意見が散見されました。まず、地震予知は難しいとする大多数の地震学者を不当に批判するような書き方が、論理の妥当性を欠いていて、違和感を感じました。例えば、以下の記載です。
地震学者が使う観測装置の代表は地震計です。(中略)地震計は地震が発生しないと、動きません。(中略)そのため、地震学者の発言は「地震予知は極めて困難」ということになるのです。
また、彼らが地震前兆を捉えたと主張する、神津島での地電流観測の紹介にも違和感があります。58頁に、著者らが観測した地電流異常と発生地震とを時系列で並べた図があるのですが、「地電流異常後に発生した地震」が濃い実線で示されているのに対し、「地電流異常がなかったのに発生した地震」が薄いグレーの点線で表されており、意図的に目立たなくされています。上記した民間の3つの研究の情報の出し方を批判しながら、自身ではこのような図の書き方をするのは、フェアではありません。
また、東北地方太平洋沖地震(2011/3/11)の前に地下水位の異常が報告されていたとし、これは前兆現象である、前兆現象はたしかにあるのだ、という書き方になっていますが、これも疑問です。異常があっても地震がなかったケースや、異常がなくても起きた地震などが、精査されていません。また、昭和三陸地震の前には、井戸水のにごりが多数報告されている、としていますが、水位異常とにごりでは異なる現象ですし、またにごりが出ても地震がなかったケースの有無については同様に触れられていません。こうした偏った情報の見せ方は、著者らが最近研究しているという「RTM法」の説明についても、同様です。
■ 興味深かった点
一方、興味深く読ませて頂いたのは、一般の方を対象に行なったというアンケートです。詳しくは本書を読んで頂くこととしたいのですが、たとえば「動物の異常行動や、電気製品の誤作動が、地震前に起こる」と信じている人が、予想以上に多いのではないかと思わせるアンケート結果になっています。
また、上述したように、話題となっている民間の地震予測をわりと厳しく批判したうえで、「筆者らは、こうした姿勢の方々とは一線を画し」(158頁)などと毅然として言い放ち、あたかも「いま話題の出鱈目予知と筆者らの研究を一緒にしないでもらいたい」という意思表明と思われる記載があり、なかなか面白いと思いました。
著者らは「地震には前兆現象がある」と思い込んでいる(自らに思い込ませている)フシがあり、その思い込みの根拠が説得力のある形で提示されておらず、全面的に賛成できない記述も多いと言わざるを得ません。ただ、織原氏などは宏観異常現象にも手を出しながらも、いつも客観的に検証している(たとえばイルカやクジラの打ち上げと地震との相関検証など)印象がありますし、今後のご活躍に期待したいと思っています。