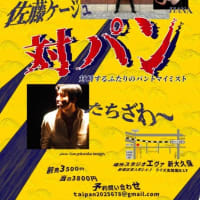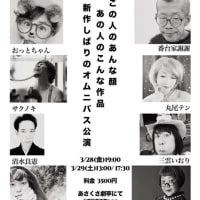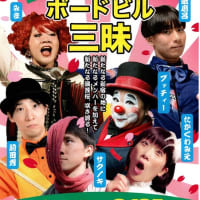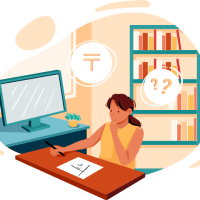佐々木 ところで、並木先生は、ソロ公演を頻繁にやっていたのですか。
細川 そんなに頻繁にやってなかったですね。でも、『花』、『蝶』、『煙草』いう短編は、私が東マ研に入る前に、演劇の学校公演でなさっていたということでした。演劇作品の前に、20分くらい先生のマイムを上演していたそうです。そこで短編を持って全国を回って年間200ステージくらいなさってたということを聞いたことがあります。パントマイム作品を観ている中学生の生徒さん達が最初はざわついているのに、段々と静まり作品に集中していくのが分かるとおっしゃってました。数多く舞台を踏むことで、作品が鍛えあげられたとも。
佐々木 先ほどの話では、並木先生は小学校などの学校公演を重視していたそうですが、『動物の謝肉祭』の他には、どんな作品をやっていたのですか。
細川 まだ他にもたくさんの作品があります。代表作としては、『ふしぎふしぎ』という作品があり、学校公演でやっていました。これは私がパントマイムをやり始めてから2、3年してから作ったと思います。
佐々木 『ふしぎふしぎ』は、先日のさくパンフェスでも上演して、子供たちに大変人気でしたね。1枚の新聞紙が魔法のように変化していくというシンプルな構成だけどパントマイムの魅力がいっぱい詰まっていて、僕も大好きな作品です。これは、並木先生が全部お作りになったのですか。
細川 この作品は、まず、並木先生の案でこんな感じというのがあって、みんなで考えながら作っていったと思います。一枚の新聞紙で、カメとかクジラとかをこんな感じにすると作れるんじゃないかなというのを元にして、大きな新聞紙で作りました。
佐々木 小さなサイズのモデルがあったのですね。
細川 そうなんです。昨年、『ふしぎふしぎ』をプチバルーンが復活させる際にも1枚の新聞でシミュレーションのお稽古をしたあと、大きな新聞を扱うという練習をしました。並木先生は「新聞」という存在を、世界や社会の象徴として捉えていて、3人で新聞を扱う『ふしぎふしぎ』の他にも、男子4人で演じる「創世記」や男女2人の作品もありました。どちらもとっても良い作品なので、復活に向けてがんばらねばと思っているところです。
佐々木 そうした並木先生のパントマイム理論について考えてみたいですが、並木先生は73年に渡仏して、マクシミリアン・ドクルー氏に師事されていますね。ドクルーさんって、どんな方ですか。
細川 マクシミリアンさんは、エティアンヌ・ドクルーさんの息子さんです。エティアンヌさんは、マイムの本『マイムの言葉』を書いた方で、お弟子さんには、パントマイムの神様といわれるマルセル・マルソーさんや『天井桟敷の人々』のジャン・ルイ・バローさんがいらっしゃいます。当時は、エティアンヌさんではなく、マクシミリアンさんが教えていたとのことでした。
佐々木 なるほど。では、並木先生の作品の中でドクルーの理論は、どれくらい影響しているのでしょうか。
細川 分解運動とか、フォルムとしての押す運動、ロープの動きなどの動き、テクニックの部分ではドクルーさんの流れだと思いますが、並木先生の作品についてはそんなに影響していなくて、並木先生の独自の表現だと思います。並木先生は、早稲田の演劇科のご出身で、演劇が好きだったから、芝居からパントマイムの表現に入っています。マイミストには、身体の動きやパントマイムのテクニックの面白さに魅かれてパントマイム表現を始める方と、演劇的な表現からパントマイムという表現に目覚める方と2種類の方がいらっしゃいます。分かりますか。
佐々木 ええ。でも、並木先生の作品は、パンフレットのコメントを拝見しますと、演劇的なストーリーよりも、動きそのものの抒情感を重視するというお考えですね。
細川 はい、文章を読むとそんな印象を受けますが、演劇的な作品作りをなさってると私は思います。セリフ的というわけではないですが、演劇的だと思います。試演会(東マ研の発表会)での作品作りや演技指導でも、「テクニック」よりも「想い」を大切にしてました。
佐々木 なるほど。
細川 並木先生の理論で一番重要だった事は、何だと思いますか?佐々木君!どこが伝わっているかが問題ですね。
佐々木 ハハハハハ…。やはり、「主役は無対象」ですね!
細川 そこですよ。そこが大きな違いですよ。「主役は無対象」!パントマイムをなさる他のアーティストの方の作品では、「主役が自分」と感じる事もありますが、並木先生はそうじゃないんです。そこが一番重要だったところです。見えてくる「空間が主役」、という事です。
佐々木 大変重要ですけど、難しいですよね。
細川 難しいけど、それが見えてこないと成り立ちません。パントマイムは、空間が観ているお客様に伝わって、感じられて、初めて成立するものです。舞台の上で演じている人間だけしか見えなくて、周りの空間が全く見えてこないとしたら、想像力も拡がらないし、感情移入もできなくなり、まったく作品を楽しめませんよ。「空間が主役」で、舞台上にたった一人しかいない「演者が脇役」、という捉え方です。
佐々木 そこは大きな違いですね。
細川 そうなんです!その表現だったからこそ、前もお話ししたけど、『ラプソディ』観た時にすごくびっくりして感動して、それで、私はパントマイムに取り組むようになったんです。
(つづく)
※脚注:佐々木は細川さん主催のTOKYOマイムカレッジの生徒です。
※参考:「主役は無対象」に関する並木氏の言葉
細川 そんなに頻繁にやってなかったですね。でも、『花』、『蝶』、『煙草』いう短編は、私が東マ研に入る前に、演劇の学校公演でなさっていたということでした。演劇作品の前に、20分くらい先生のマイムを上演していたそうです。そこで短編を持って全国を回って年間200ステージくらいなさってたということを聞いたことがあります。パントマイム作品を観ている中学生の生徒さん達が最初はざわついているのに、段々と静まり作品に集中していくのが分かるとおっしゃってました。数多く舞台を踏むことで、作品が鍛えあげられたとも。
佐々木 先ほどの話では、並木先生は小学校などの学校公演を重視していたそうですが、『動物の謝肉祭』の他には、どんな作品をやっていたのですか。
細川 まだ他にもたくさんの作品があります。代表作としては、『ふしぎふしぎ』という作品があり、学校公演でやっていました。これは私がパントマイムをやり始めてから2、3年してから作ったと思います。
佐々木 『ふしぎふしぎ』は、先日のさくパンフェスでも上演して、子供たちに大変人気でしたね。1枚の新聞紙が魔法のように変化していくというシンプルな構成だけどパントマイムの魅力がいっぱい詰まっていて、僕も大好きな作品です。これは、並木先生が全部お作りになったのですか。
細川 この作品は、まず、並木先生の案でこんな感じというのがあって、みんなで考えながら作っていったと思います。一枚の新聞紙で、カメとかクジラとかをこんな感じにすると作れるんじゃないかなというのを元にして、大きな新聞紙で作りました。
佐々木 小さなサイズのモデルがあったのですね。
細川 そうなんです。昨年、『ふしぎふしぎ』をプチバルーンが復活させる際にも1枚の新聞でシミュレーションのお稽古をしたあと、大きな新聞を扱うという練習をしました。並木先生は「新聞」という存在を、世界や社会の象徴として捉えていて、3人で新聞を扱う『ふしぎふしぎ』の他にも、男子4人で演じる「創世記」や男女2人の作品もありました。どちらもとっても良い作品なので、復活に向けてがんばらねばと思っているところです。
佐々木 そうした並木先生のパントマイム理論について考えてみたいですが、並木先生は73年に渡仏して、マクシミリアン・ドクルー氏に師事されていますね。ドクルーさんって、どんな方ですか。
細川 マクシミリアンさんは、エティアンヌ・ドクルーさんの息子さんです。エティアンヌさんは、マイムの本『マイムの言葉』を書いた方で、お弟子さんには、パントマイムの神様といわれるマルセル・マルソーさんや『天井桟敷の人々』のジャン・ルイ・バローさんがいらっしゃいます。当時は、エティアンヌさんではなく、マクシミリアンさんが教えていたとのことでした。
佐々木 なるほど。では、並木先生の作品の中でドクルーの理論は、どれくらい影響しているのでしょうか。
細川 分解運動とか、フォルムとしての押す運動、ロープの動きなどの動き、テクニックの部分ではドクルーさんの流れだと思いますが、並木先生の作品についてはそんなに影響していなくて、並木先生の独自の表現だと思います。並木先生は、早稲田の演劇科のご出身で、演劇が好きだったから、芝居からパントマイムの表現に入っています。マイミストには、身体の動きやパントマイムのテクニックの面白さに魅かれてパントマイム表現を始める方と、演劇的な表現からパントマイムという表現に目覚める方と2種類の方がいらっしゃいます。分かりますか。
佐々木 ええ。でも、並木先生の作品は、パンフレットのコメントを拝見しますと、演劇的なストーリーよりも、動きそのものの抒情感を重視するというお考えですね。
細川 はい、文章を読むとそんな印象を受けますが、演劇的な作品作りをなさってると私は思います。セリフ的というわけではないですが、演劇的だと思います。試演会(東マ研の発表会)での作品作りや演技指導でも、「テクニック」よりも「想い」を大切にしてました。
佐々木 なるほど。
細川 並木先生の理論で一番重要だった事は、何だと思いますか?佐々木君!どこが伝わっているかが問題ですね。
佐々木 ハハハハハ…。やはり、「主役は無対象」ですね!
細川 そこですよ。そこが大きな違いですよ。「主役は無対象」!パントマイムをなさる他のアーティストの方の作品では、「主役が自分」と感じる事もありますが、並木先生はそうじゃないんです。そこが一番重要だったところです。見えてくる「空間が主役」、という事です。
佐々木 大変重要ですけど、難しいですよね。
細川 難しいけど、それが見えてこないと成り立ちません。パントマイムは、空間が観ているお客様に伝わって、感じられて、初めて成立するものです。舞台の上で演じている人間だけしか見えなくて、周りの空間が全く見えてこないとしたら、想像力も拡がらないし、感情移入もできなくなり、まったく作品を楽しめませんよ。「空間が主役」で、舞台上にたった一人しかいない「演者が脇役」、という捉え方です。
佐々木 そこは大きな違いですね。
細川 そうなんです!その表現だったからこそ、前もお話ししたけど、『ラプソディ』観た時にすごくびっくりして感動して、それで、私はパントマイムに取り組むようになったんです。
(つづく)
※脚注:佐々木は細川さん主催のTOKYOマイムカレッジの生徒です。
※参考:「主役は無対象」に関する並木氏の言葉