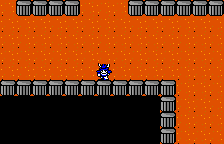とれび庵:「いくら吹き飛ばされても、僕らはまた花を植えるよ」
名著バカゲー専科の著者の一人である白川嘘一郎さん(ヨダレ団長)がなぜバカゲーについての記事を書くか…という話と、
あの頃のクソゲー本についてのあれこれ(コメント欄参照)
クソゲーという言葉については自分も前にも書いたけど、
「クソゲー」という言葉は必ずしもネガティブな使われ方をしていなかったと思ってます。
「うわ、これクソゲーだよ(笑い)」って感じで、クソゲーだと言いつつプレイしてしまう者もいたと思うし、今でもその文脈でクソゲーという表現を使ってる人もたまにいるし。
ただ、「一般的な評価だとちょっとアレな内容のゲーム」をクソゲーと呼んでいただけだと思う。
そして、だがしかし、その場合の「クソゲー」は、やっぱり褒め言葉じゃなかった。
「クソゲーだけど好きなゲーム」は存在しうるけど、それでも好きなゲームをあえてクソゲーと表現するのは少々の悪意が込められているはず。
ここで、上の記事で話題になった90年代後半のクソゲー本は、「クソゲー」という言葉のネガティブな側面ばかりを強調していた。
はっきり言うと、「嫌いなゲーム」をクソゲーとして紹介していたと思う。
四角い会社が作ったゲームとかね。全部がそうだというわけじゃないけど、そういうのもあった。
やっぱり「クソ」って言葉にはネガティブな意味が強いから、ある意味仕方ないと思いつつ、愛が足りないなあ、私怨で書いてて見苦しいなあ、みたいな文章も結構あった。
そこで「バカゲー」という言葉が使われ始めた。
誰が考えたのかは知らない。バカゲー専科の前身の連載がユーズドゲームズで始まるより前にもあったような気がする。
定義は、実は自分には説明できない。
「一般的な観点で見るとアレなゲームだけど見方によっては面白いゲーム」?
自分は広い意味での「クソゲー」に含まれる1カテゴリって感じだと認識している。好きになれるクソゲー、ポジティブな表現。
でも、違ってるかもしれない。単に「内容がぶっとんだゲーム」でもバカゲーで通るけど、クソゲーとは呼ばれない。
ともかく、バカゲーって言葉が広まれば、「好きだけど一般的にはアレなゲーム」を説明するときにクソゲーというネガティブな言葉を使わなくて済むから、今でも好んで使う人がいる。
でも、「バカゲー」も、褒め言葉じゃないかもしれない。少なくとも全部のゲーム開発者が喜ぶ表現じゃないと思う。
だってバカな内容のゲームを作りたくて作ったわけじゃないかもしれないし。
それどころか、バカゲー専科の記事にも、単に「嫌いなゲーム」をバカゲーと呼んでる(つまり、クソゲーを誌面の方針に合わせて言い換えただけ)のはあった。
さすがにひどいと思った。
自分も、何も全部のゲームを褒めたいわけではなく、バカゲーとすら呼べないどうしようもないゲームが存在することは知っている。
こないだ書いたPSPのFF1とか。
それをクソゲーとして断罪する行為が全て無意味とも思っていない。物事の批判は、絶えるべきではない。
AVGNの動画とかも面白いし…
だけど結局クソゲー本が廃れたのは何故なのかという答えは、愛が足りなかったから、客観性を欠いていったから、じゃないかと思います。
主観で面白い文章を書こうとするあまり、何か元のゲームをないがしろにしてしまった。
ゲーム愛の不足している文章は、ゲーマーが読むと嫌な気持ちになる記事だったりした。元のゲームがたとえクソゲーであっても、一定量の敬意を持つべきなのに。
(アンサガの回復アイテムの使い方がわかりにくすぎるって記事があったけど、そもそも回復アイテム自体がろくに存在しないことを知って書いたのだろうか?)
だから上の記事は「筆者の主観を一切入れずに語ることなどナンセンス」と書いてますが、その中で客観を欠いてなかったからこそバカゲー専科は面白かった、評価を集めたんだと思います。
自分はバカゲー専科の団長の記事を読まなかったら、FF8を(かなり後まで)プレイしなかったです。
でも自分のFF8プレイ後の感想は、バカゲー専科の記事とは異なるものでした。それは仕方ないでしょう。
自分も団長も間違ってるわけじゃないと思いたいです。
自分のようなヌルめのゲーマーは、メジャーなタイトルくらいしか追いきれないから、
それでもできることはないだろうかと、いろんなゲームに関する文章を書いてきました。
それが無意味なものではないと信じていたい。
名著バカゲー専科の著者の一人である白川嘘一郎さん(ヨダレ団長)がなぜバカゲーについての記事を書くか…という話と、
あの頃のクソゲー本についてのあれこれ(コメント欄参照)
クソゲーという言葉については自分も前にも書いたけど、
「クソゲー」という言葉は必ずしもネガティブな使われ方をしていなかったと思ってます。
「うわ、これクソゲーだよ(笑い)」って感じで、クソゲーだと言いつつプレイしてしまう者もいたと思うし、今でもその文脈でクソゲーという表現を使ってる人もたまにいるし。
ただ、「一般的な評価だとちょっとアレな内容のゲーム」をクソゲーと呼んでいただけだと思う。
そして、だがしかし、その場合の「クソゲー」は、やっぱり褒め言葉じゃなかった。
「クソゲーだけど好きなゲーム」は存在しうるけど、それでも好きなゲームをあえてクソゲーと表現するのは少々の悪意が込められているはず。
ここで、上の記事で話題になった90年代後半のクソゲー本は、「クソゲー」という言葉のネガティブな側面ばかりを強調していた。
はっきり言うと、「嫌いなゲーム」をクソゲーとして紹介していたと思う。
四角い会社が作ったゲームとかね。全部がそうだというわけじゃないけど、そういうのもあった。
やっぱり「クソ」って言葉にはネガティブな意味が強いから、ある意味仕方ないと思いつつ、愛が足りないなあ、私怨で書いてて見苦しいなあ、みたいな文章も結構あった。
そこで「バカゲー」という言葉が使われ始めた。
誰が考えたのかは知らない。バカゲー専科の前身の連載がユーズドゲームズで始まるより前にもあったような気がする。
定義は、実は自分には説明できない。
「一般的な観点で見るとアレなゲームだけど見方によっては面白いゲーム」?
自分は広い意味での「クソゲー」に含まれる1カテゴリって感じだと認識している。好きになれるクソゲー、ポジティブな表現。
でも、違ってるかもしれない。単に「内容がぶっとんだゲーム」でもバカゲーで通るけど、クソゲーとは呼ばれない。
ともかく、バカゲーって言葉が広まれば、「好きだけど一般的にはアレなゲーム」を説明するときにクソゲーというネガティブな言葉を使わなくて済むから、今でも好んで使う人がいる。
でも、「バカゲー」も、褒め言葉じゃないかもしれない。少なくとも全部のゲーム開発者が喜ぶ表現じゃないと思う。
だってバカな内容のゲームを作りたくて作ったわけじゃないかもしれないし。
それどころか、バカゲー専科の記事にも、単に「嫌いなゲーム」をバカゲーと呼んでる(つまり、クソゲーを誌面の方針に合わせて言い換えただけ)のはあった。
さすがにひどいと思った。
自分も、何も全部のゲームを褒めたいわけではなく、バカゲーとすら呼べないどうしようもないゲームが存在することは知っている。
こないだ書いたPSPのFF1とか。
それをクソゲーとして断罪する行為が全て無意味とも思っていない。物事の批判は、絶えるべきではない。
AVGNの動画とかも面白いし…
だけど結局クソゲー本が廃れたのは何故なのかという答えは、愛が足りなかったから、客観性を欠いていったから、じゃないかと思います。
主観で面白い文章を書こうとするあまり、何か元のゲームをないがしろにしてしまった。
ゲーム愛の不足している文章は、ゲーマーが読むと嫌な気持ちになる記事だったりした。元のゲームがたとえクソゲーであっても、一定量の敬意を持つべきなのに。
(アンサガの回復アイテムの使い方がわかりにくすぎるって記事があったけど、そもそも回復アイテム自体がろくに存在しないことを知って書いたのだろうか?)
だから上の記事は「筆者の主観を一切入れずに語ることなどナンセンス」と書いてますが、その中で客観を欠いてなかったからこそバカゲー専科は面白かった、評価を集めたんだと思います。
自分はバカゲー専科の団長の記事を読まなかったら、FF8を(かなり後まで)プレイしなかったです。
でも自分のFF8プレイ後の感想は、バカゲー専科の記事とは異なるものでした。それは仕方ないでしょう。
自分も団長も間違ってるわけじゃないと思いたいです。
自分のようなヌルめのゲーマーは、メジャーなタイトルくらいしか追いきれないから、
それでもできることはないだろうかと、いろんなゲームに関する文章を書いてきました。
それが無意味なものではないと信じていたい。