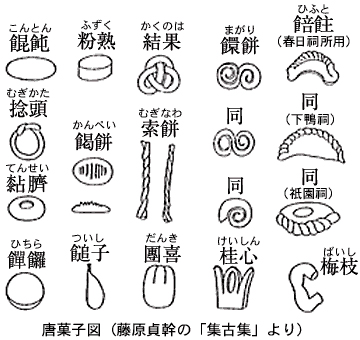本題に入る前に。 昨日の 「キッチンが走る」について。
昨日の 私の ブログの 疑問符をみて
平泉に住む方から メールが きました。
「あの石碑のある場所は たぶん 平泉の西行桜の森。
HPより
ここです。 この風景 画面に みえていました。(時期はちがう)
この 「あそぶ おおとり」 なんと読む ?
ユウボウ かな ユウホウ かな。
西行の森には 1度 行ってました、が あまり にも
昔で 記憶薄れていました。
木工館、 そとから みてきた ように 思います。
春が 来たら 行ってみたいと 思います。
という わけで
今日は 平泉関連を だします。xxxxxxx
xxxx 先月、 平泉で 講演会がある と の 知らせがきていた。
題 「 平泉時代の美味しいお話 …… ハクタク ・唐菓子 ETC …」
ハクタク って なんだろう。
唐菓子は からがし ?
ちがった。 「からくだもの」 と 読む んですって。
お菓子 が 果物 ? 果物は 自然のもの。
その おいしさ、甘さ を 表現したのが 菓子 だから ?
xxxxxx (残念だが) その12月24日は 雪になった。
行けなかった。 予習に調べた ことを、
資料に しておいた。 もったいないから、 それを 簡単に。
① 先に 唐菓子を。
唐朝から 伝わった 菓子。
「唐菓子 画像」 としたら たくさんの 絵がでてきた。
1枚だけ、 お借りする。 xxxxxxxxx
このような お菓子が 平安時代にあり、
平泉にも あった、 ということだろう。 xxxxxxxxxxxx
② 次は ハクタク …… ほうとう のこと。
放 蕩 … 思うままに振る舞うこと。特に、酒や女遊びにふけること。
食べ物ではない、から。 これではないだろう。
「ほうとう」 どっかの県の 名物になっていた な。
ほうとう 食べたことがないので わからない。
この辺で ・つめり ・はっと ・ひっつみ など と
いってるものと は ちがう のかな。
xxxxxxxx
餺 飥 説 ハタク・ハタキモノ 説 信玄 語源説
などが あった。
ほうとう … 唐菓子の 一種
小麦粉を こねて 平らにして 切りそろえたもの。
平安時代には 藤原長者が 春日大社で 食べた、とある。
「餺 飥」(はくたく) 語 源 説
「ほうとう」の名は 「 餺 飥 」の 音便したもの。
「餺飥」は 奈良時代の漢字辞書である『楊氏漢語抄』
(逸書。平安時代中期の古辞書『和名類聚抄』に引用)に見え、
院政期の漢和辞書である『色葉字類抄』に
「餺飥 ハクタク ハウタウ」 として登場する。
よって「ほうとう」は 「うどん」と同じく中国から伝来した料理の流れを
汲むもの、ということになる。
現代の 陝西方言で ワンタンのことを
「餛飩」と書いて 「ホウトウ」と発音することも 証拠のようだ。
ほかに 「ほうとう」の呼称は
江戸時代中期の甲府勤番士日記 『裏見寒話』にある。
文献上の 初出として
室町時代中期の古辞書『温故知新書』(1484年 / 文明16年)。
「ホウトウ」は 前記『色葉字類抄』、平安時代後期の『枕草子』や
南北朝時代〜室町時代初期の古辞書『頓要集』に
「はうたう」 「餺飥 ハウタウ」として みえている。
講座にいったら、 もっと 詳しく、 もしかしたら
もっと おもしろく 教えて いただけたかも。
冬の 講習会は 雪が 心配で 出かけられない。残念。
世の中 「冬」なら暇あるが、 夏は
遊んでいられない人のほうが 多い …… の だろうな。
このときの 講師の方が 今月は 水沢へ来る。
「平泉 フォーラム」 2日目の 1月25日(日)
やはり、平安時代を 語ってくださる、と。
雪 降りませんように。