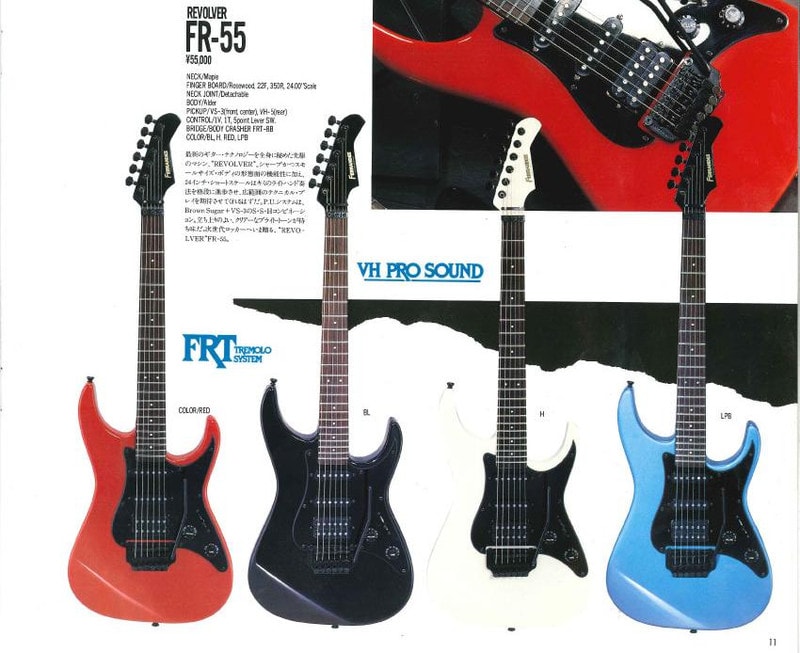ディマジオのピックアップの説明があったので備忘録。
【Fスペースとスタンダード・スペースの違い】
DiMarzioのハムバッカーピックアップには、各メーカーのブリッジ弦間に対応させる為に
2種類のタイプがあります。
Fスペースは、フェンダー系ブリッジ(シンクロブリッジ等)やフロイドローズ・ブリッジの
リア・ポジションでの弦間に合わせて、ポールピースの間隔を10.2mmに調整して作られた
モデルです。
対して、スタンダード・スペースはGibson系ブリッジ(TOMブリッジ等)でのリア・ポジションや、
フロント・ポジションにマウントする際に合うように、9.7mmの間隔で作られています。
ただ、絶対にポールピース上に弦がなければいけないというわけではなく、多少ズレても
デメリットはほとんどありません。
多くのギターはブリッジ形状に関わらず、ブリッジ・ポジションにFスペース、ネック・ポジション
にスタンダード・スペースを使用すれば誤差は少ないです。
特殊なギターを使っていて合うかどうか不安な場合は、ブリッジ上での各弦の間隔を測って
おくことをお薦めします。
【DiMarzioの特許技術】
□デュアル・レゾナンス・コイル
ハムバッカーの2つのコイルに、異なる周波数特性を持たせた構造。ターン数が違うコイルを
組み合わせることで非常に広い音域をカヴァーしています。
Steve's Special,Evolution,Breedなど
□エア・バッカー
マグネットとコイルの間に隙間を作ることで磁力をコントロールする技術。磁力が強いと
弦振動の妨げになってしまうが、この技術によってストリング・プルが軽減され、伸びやかな
ロング・サスティンとクリアで濁りのないサウンドを実現しました。
Air Zone,Air Norton,Air Classicなど
□ヴァーチャル・ヴィンテージ
様々なサウンドのピックアップに使われている技術ですが、元々はヴィンテージの
シングルコイルのサウンド・ルックスをそのままにノイズを軽減することを目的とした技術。
コイルを二段に積み重ねたスタック構造にU字型のプレートでコイルを包み込むことで
ハムバッカーに匹敵するほどノイズを減らしています。
Virtual Vintage Blues,Virtual solo,Area'58など
【スタックタイプ(背の高いピックアップ)の取り付けについて 】
シングルタイプのピックアップにもう1つコイルを付ける事で、ハムバッカーのようにノイズを
軽減する構造のものをスタックタイプと言います。
(Virtual Vintageシリーズ,Areaシリーズなど)
このタイプはコイルが2段積みになっていて、通常のシングルピックアップよりも3~4mm程
背が高い為、ギター本体に加工をしなければ取り付け出来ない場合があります。
大体のギターは余裕を持ってザグリが掘られてますが、深さには個体差があり、
また取り付けるポジションや取り付け方法(ピックガードに吊るしている、ボディに直付けしている等)
によっても変わってきてしまいます。
またシングルサイズ・ハムバッカーも同様に背が高いので注意が必要です。
(Fast Trackシリーズ,Chopper,Cruiserなど)
【ポールピースの形の違い】
ピックアップのサウンドを決める要因の1つに、ポールピースの形状があります。
DiMarzioではピックアップのキャラクターによって、様々なポールピースが使用されています。
フラット&マイナス・ポールピースは、PAFやToneZoneなどに使われており、一般的な
タイプでもあるため、ピックアップカバーの取り付けが可能であるなど汎用性の高い形状です。
Super Distortionなどに使われているヘクサ・ポールピースは、全てのポールピースの高さを
調節できるようになっており、各弦での細かいセッティングが可能です。
バー・ポールピースはその名の通り、1本のバー状のポールピースでDsonicなどのモデルに
使われてます。
チョーキングをしても弦がポールピース上から外れないので、音切れが無くスムースな
サウンド傾向にあります。
【ダブルクリームについて】
オープンタイプのピックアップといえばブラック、ゼブラ、クリームはスタンダードですが、
実はクリームはDiMarzioが最初に作って特許を取ってしまっているので、USAの他メーカー
では作っていません。
Gibsonのギターに乗ってるクリーム・カラーのものはDiMarzioピックアップです。
ただし特許はUSAでのみ有効なものなので、国産ピックアップではクリームも普及しています。