角型のマンホールから、ミストが充満する塔内に入る。
陽の光りが入らない塔内には、所々に据え置き式のサーチライト型蛍光灯を設置してある。
アルミ製の足場板を歩きながら、堂本が作業をしている壁面に近づくと、400Wの防水型水銀灯に照らされた堂本の姿が、はっきりと見える。
「・・・」
「・・・」
ハルと一緒に、じっと堂本の行動を観察する。
「!!」
ハルが堂本を指で差しながら、体を捩じらせて、立ったままもだえ出した。
「縦だよ…、今度は『縦』方向に線を引いてるよ…」
あれほどガンの撃ち方を私がレクチャーしたにも拘らず、堂本はガンのノズルを、じっくりと縦方向に動かしている。
「何で、ノズルを、回転させるって、教えてないの?」
ハルがジェスチャーで、私に質問する。
「俺は、きちんと、ノズルの回し方を、何度も、教えたって!」
私もジェスチャーで返答をすると、ハルは再び大笑いをする。騒音が激しい現場内では、慣れた人間同士なら、ジェスチャーの方が会話は早いのだ。
「!?、!!!」
ハルが堂本の行動を見て、私の肩をバシバシと叩く。
「見て、見て!」
「???」
私はジェスチャーをしているハルの前に出ると、堂本の様子を覗き見る。
「!!!!」
私の驚愕した顔を見て、ハルが腹を抱えて、足場板の上でしゃがみ込んだ。
「ぎごガガガガガガガ、キンキンキンキン!」
堂本が持っているガンの先端から、細かい火花が散っている。まるで手持花火の様だ。
「プシュッ、プシュッ、プシュッ!」
私は堂本のエアラインマスクに繋がるウレタンホースを握り込むと、三回エアーを遮断し、
「近づくぞ!」
の合図を送った。
「ギギギギギギンン!ゴガガガガガガ!」
だが堂本は全く合図に気付く事も無く、ひたすらガンの先端から火花を散らしまくる。ハルはそれを見て完全にツボに入ってしまい、手摺の単管パイプ(アルミの足場用パイプ)に掴まり、涙を浮かべている。
「ど・う・も・と・君!」
私は堂本の背後から近寄り、彼の両肩を軽く揺すった。
「!?」
堂本は驚いてガンのトリガーからは指を放し、エアラインマスクの目ガラス(四角いガラスをはめ込んだ覗き窓)から、怯えている様な目で私を見つめている。
「いや、あのね、どうして左手でノズルを回さないの?それからもう一つ、どうしてガンから火花が出るの!?」
堂本のエアラインマスクの耳元で、騒音に負けない大声で話し掛ける。
「???・・・」
質問の意味が理解出来ないのか、堂本の目が完全に逝き掛けている。パニックを起こしかねない雰囲気だ。
「あのね、どうして火花が出るの?」
質問を簡略化して、もう一度大声で質問する。
「・・・」
堂本は足場板の隙間を指差し、何度も私の顔を見る。
「あー、ああ、そう言うことね。確かに言ったね…」
私は堂本に出した指示を思い出していた。
足場が何層もある壁面を剥離する場合、一つだけ注意しなければならないことがある。それは今居る段の足場から、塗膜を剥がせるだけ剥がしておくと言う事だ。
境界線となる壁面は、極力上段から撃ち下ろしておくと、後が非常に楽になるのだ。逆に、下の段の足場から、境界線の壁面を撃ち上げるのは、想像以上に大変なのだ。
だから私は堂本に、
「撃てる所は、極力上から撃っておいてね!」
とは言った。だが、
「ノズルがぶつかって火花が出るほど、ノズルを壁面の鉄板に押し付けるように!」
などとは一言も言っていない。
私はゆっくりと言葉を選びながら、慎重に堂本に指示を出した。
「あのね、火花が出るほど、下まで撃たなくてもイイから…」
だが、こんな簡単な指示すら、本当に伝わっているのかどうかも怪しい。なぜなら、堂本の目付きが、完全に逝っている気がしたからだ。
私は笑い転げるハルを追いやり、マンホールから外に出た。
「はぁー…」
深いため息を吐く。
「大変だよ木田さん、これは。あの人、目が逝っちゃってるもんね」
「ハルさんもそう思いました?」
「だって、こんなだよ、こんな!」
ハルは堂本の目付きを真似して見せる。
「うはははは、そう、そういう雰囲気だった!」
「うひゃひゃひゃ、やばいよねぇ」
だが、笑い事では無い。これは仕事なのだ。
「あの人、どうやら一度に複数の事に、意識が向かないみたいですね」
「うひゃひゃひゃひゃ、ノズルの先から火花が出てたもんね。木田さん、ちゃんと教えてあげないと仕事になんないよぉ!」
ウヒャウヒャと笑うハルを見ながら、私は少しハルの立場を羨ましいと思った。
陽の光りが入らない塔内には、所々に据え置き式のサーチライト型蛍光灯を設置してある。
アルミ製の足場板を歩きながら、堂本が作業をしている壁面に近づくと、400Wの防水型水銀灯に照らされた堂本の姿が、はっきりと見える。
「・・・」
「・・・」
ハルと一緒に、じっと堂本の行動を観察する。
「!!」
ハルが堂本を指で差しながら、体を捩じらせて、立ったままもだえ出した。
「縦だよ…、今度は『縦』方向に線を引いてるよ…」
あれほどガンの撃ち方を私がレクチャーしたにも拘らず、堂本はガンのノズルを、じっくりと縦方向に動かしている。
「何で、ノズルを、回転させるって、教えてないの?」
ハルがジェスチャーで、私に質問する。
「俺は、きちんと、ノズルの回し方を、何度も、教えたって!」
私もジェスチャーで返答をすると、ハルは再び大笑いをする。騒音が激しい現場内では、慣れた人間同士なら、ジェスチャーの方が会話は早いのだ。
「!?、!!!」
ハルが堂本の行動を見て、私の肩をバシバシと叩く。
「見て、見て!」
「???」
私はジェスチャーをしているハルの前に出ると、堂本の様子を覗き見る。
「!!!!」
私の驚愕した顔を見て、ハルが腹を抱えて、足場板の上でしゃがみ込んだ。
「ぎごガガガガガガガ、キンキンキンキン!」
堂本が持っているガンの先端から、細かい火花が散っている。まるで手持花火の様だ。
「プシュッ、プシュッ、プシュッ!」
私は堂本のエアラインマスクに繋がるウレタンホースを握り込むと、三回エアーを遮断し、
「近づくぞ!」
の合図を送った。
「ギギギギギギンン!ゴガガガガガガ!」
だが堂本は全く合図に気付く事も無く、ひたすらガンの先端から火花を散らしまくる。ハルはそれを見て完全にツボに入ってしまい、手摺の単管パイプ(アルミの足場用パイプ)に掴まり、涙を浮かべている。
「ど・う・も・と・君!」
私は堂本の背後から近寄り、彼の両肩を軽く揺すった。
「!?」
堂本は驚いてガンのトリガーからは指を放し、エアラインマスクの目ガラス(四角いガラスをはめ込んだ覗き窓)から、怯えている様な目で私を見つめている。
「いや、あのね、どうして左手でノズルを回さないの?それからもう一つ、どうしてガンから火花が出るの!?」
堂本のエアラインマスクの耳元で、騒音に負けない大声で話し掛ける。
「???・・・」
質問の意味が理解出来ないのか、堂本の目が完全に逝き掛けている。パニックを起こしかねない雰囲気だ。
「あのね、どうして火花が出るの?」
質問を簡略化して、もう一度大声で質問する。
「・・・」
堂本は足場板の隙間を指差し、何度も私の顔を見る。
「あー、ああ、そう言うことね。確かに言ったね…」
私は堂本に出した指示を思い出していた。
足場が何層もある壁面を剥離する場合、一つだけ注意しなければならないことがある。それは今居る段の足場から、塗膜を剥がせるだけ剥がしておくと言う事だ。
境界線となる壁面は、極力上段から撃ち下ろしておくと、後が非常に楽になるのだ。逆に、下の段の足場から、境界線の壁面を撃ち上げるのは、想像以上に大変なのだ。
だから私は堂本に、
「撃てる所は、極力上から撃っておいてね!」
とは言った。だが、
「ノズルがぶつかって火花が出るほど、ノズルを壁面の鉄板に押し付けるように!」
などとは一言も言っていない。
私はゆっくりと言葉を選びながら、慎重に堂本に指示を出した。
「あのね、火花が出るほど、下まで撃たなくてもイイから…」
だが、こんな簡単な指示すら、本当に伝わっているのかどうかも怪しい。なぜなら、堂本の目付きが、完全に逝っている気がしたからだ。
私は笑い転げるハルを追いやり、マンホールから外に出た。
「はぁー…」
深いため息を吐く。
「大変だよ木田さん、これは。あの人、目が逝っちゃってるもんね」
「ハルさんもそう思いました?」
「だって、こんなだよ、こんな!」
ハルは堂本の目付きを真似して見せる。
「うはははは、そう、そういう雰囲気だった!」
「うひゃひゃひゃ、やばいよねぇ」
だが、笑い事では無い。これは仕事なのだ。
「あの人、どうやら一度に複数の事に、意識が向かないみたいですね」
「うひゃひゃひゃひゃ、ノズルの先から火花が出てたもんね。木田さん、ちゃんと教えてあげないと仕事になんないよぉ!」
ウヒャウヒャと笑うハルを見ながら、私は少しハルの立場を羨ましいと思った。


















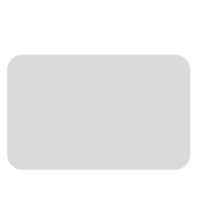

「ボインにターッチ!」
なんて笑っている場合じゃありませんね。
あ、そう言えば昔、携帯メールで貰った画像なんですが、あれってもしかして…。
いや、フィクションですよね。まだ私のパソコンの中に残ってますけど(笑)
せっかく弁護士とバトルをするんだから、もっと強力な武装で、ドンパチ殺り合いたいですよね。
マウントポジションは、一見マウントしている方が優勢に見えますが、相手が雀級の達人だと、自分の腰をやられます。
この歳になると、やはり日々安堵できる女性が一番だと思います。奔放な女性は、奔放に生きるべきだと、私は和解に至りました。
次は夏季講習を受けて、自分のマニアな幅を拡張したいと思います。もちろんこれは『フィクション』です(笑)