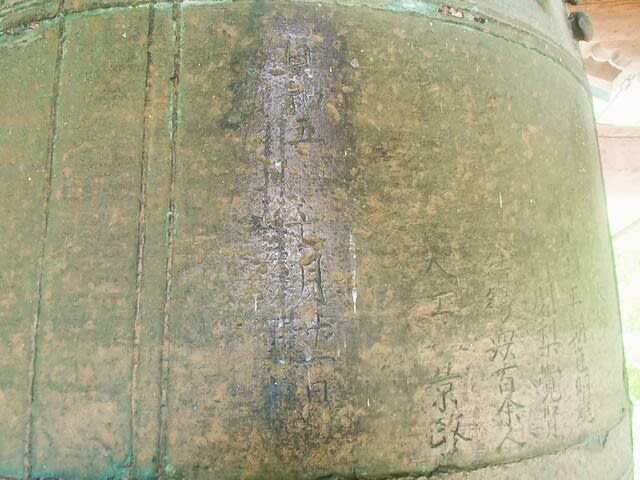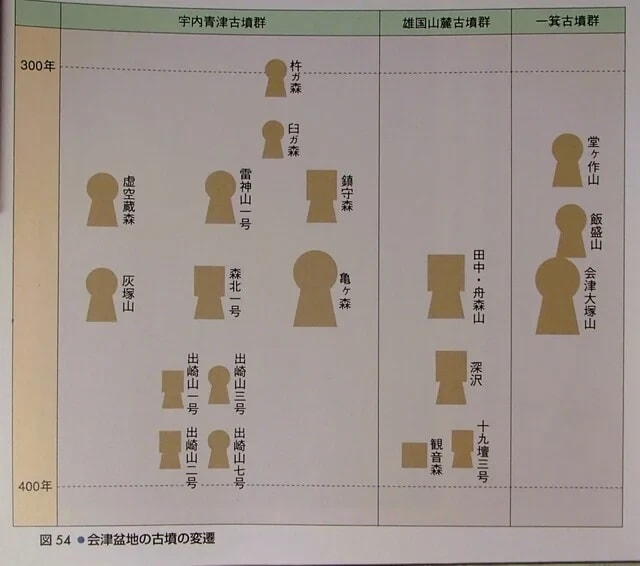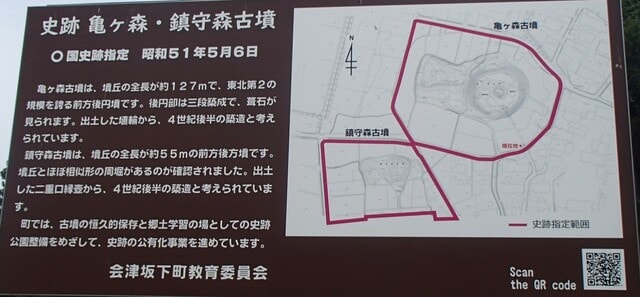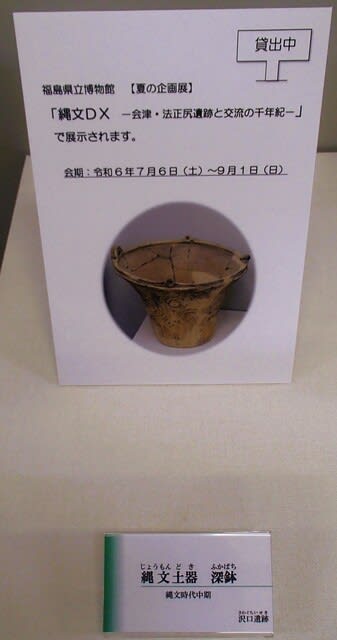喜多方「蔵の里」。福島県喜多方市押切。
2024年5月30日(木)。
喜多方市山都のそば伝承館で蕎麦を食べたのち、喜多方「蔵の里」へ向かった。喜多方は1980年代半ばに訪れており、喜多方ラーメンを食べて蔵めぐりをした。当時は駅近くに見学できる蔵があったはずだが、事前に調べた結果、駅から離れた「蔵の里」、「重伝建・小田付地区」、「三津谷集落の煉瓦蔵」の3か所を見学することにした。
喜多方「蔵の里」と喜多方プラザの共通駐車場に12時30分頃着いた。なぜか広い駐車場はほぼ満車だった。「蔵の里」とその入口はダイレクトには見えない。角を占める旧冠木家店蔵の駐車場から遠い側に入口があった。客はいなかったが、翌日からのイベントの準備をする職員が数人いた。

旧冠木家店蔵。
もとは呉服商の店蔵で、三方に下屋が取り付いた特徴的な外観を持っている。明治初期の建築と推定されるが、江戸期の店蔵の形式をとどめている。
明治初中期の大規模な呉服店の店蔵を象徴する二重屋根形式の優れた建築的構成を持つ点で、喜多方の住文化の保存継承に重要な意味を持つ。
板戸が上から引き出されるようになっていたり、土間の幅は、店員が働く板の間と帳場に比べきわめて狭く、応対する店員よりも客の数が増えないようにという昔ならではの配慮がうかかがえる。喜多方の土産販売もしている。

喜多方蔵の里は、約4500㎡の敷地内に、中庭を中心として店蔵、味噌蔵、穀物蔵、蔵座敷、郷頭曲り家等を配置している。
喜多方市は、かつて「北方」と呼ばれ、江戸時代には物資の集散地として、また若松城下と米沢を結ぶ街道のまちとして栄えた。喜多方市にはいまも4000棟以上の蔵が広く分布している。これだけ多くの蔵が建てられた主な理由として、「物資の貯えに必要だった」「醸造業や漆器業に最適だった」「明治13年の大火でその耐火性が見直された」「蔵を建てることは男の一生の夢だった」「蔵造りの名工が数多くいた」と言われている。

旧唐橋家味噌醸造蔵。
間口3間半×奥行8間の旧味噌醸造蔵で、内部は木造トラス組の架構をあらわし、2階吹き抜けの大きな空間を形づくっている。


金田実氏の蔵写真展示。
金田実氏は、昭和40年代の後半、どんどん壊されていく運命にある「蔵」に一抹の寂しさを感じて、蔵を撮り続けた。その写真に写された蔵の姿は、見る人に大きな感動を与え、「蔵のまち喜多方」を訪れる人々が増えるきっかけとなった。

旧猪俣家穀物蔵。
かつての宿場町、熊倉にあった蔵で、屋根、窓の配置など均整が取れ、観音開きの扉の意匠も美しい当地方の典型的な穀物蔵である。
内部には、明治の社会慈善家・瓜生岩子の資料を展示している。喜多方に生まれた瓜生岩子は、明治時代の初めに社会慈善家として活躍し、今日の日本社会福祉の礎を築き、その功績により藍綬褒章を受けている。




郷頭屋敷・旧外島家住宅。
江戸初期から幕末まで慶徳町豊岡地区で、郷頭(ごうがしら)を務めた外島家の住宅で、主棟および曲がり棟の創建は明和8年(1771)との記録が残っている。
旧東海林家酒造蔵。いったん、外に出て道路を渡り、別館のような2棟を見学をした。
大正12年に建てられたこの蔵の内部は熊野神社長床の建築資料や修養団創設者の蓮沼門三の資料が展示されている。

自由民権運動喜多方事件資料展示。
明治15年11月、弾正ヶ原及び喜多方警察署を舞台として、いわゆる喜多方事件が発生した。会津藩や幕府は朱子学を唯一の学問としていたが、喜多方地方は陽明学系の中江藤樹の学問が伝わっており、「知行合一」を唱え「知ることは行うこと」を説く学問が好まれていた。その土壌の中で自由民権運動が生まれた。

県令三島通庸が推進した会津三方道路建設工事が喜多方事件の原因とされる。

肝煎屋敷 旧手代木家住宅。
江戸後期から明治初期まで、下三宮村の肝煎を務めた手代木家の住宅で、異色ある間取りや鍵型に曲げられた造りなど江戸後期の形態をとどめている。
1時間ほど見学をして、小田付の重伝建地区へ向かった。


喜多方市小田付(おたづき)伝統的建造物群保存地区。
南端にある駐車場に駐車。北近くにある観光案内所「会陽館」は閉館していたので、詳細が分からず案内板に頼って見学し、中ほどにある馬車の駅まで行って引き返した。どこに行っても解説はなく、B級グルメも観光客もいなかった。2018年8月に選定されたばかりで、まだ観光化は遅れている。

小原酒造付近。

新金忠。明治蔵。
小田付は、喜多方市の中心市街地に位置し、天正10年(1582年)に町割が行われ、近村から定期市が移された。近世には酒や味噌、醤油の醸造業も盛んになり、会津北方の交易の中心地として発展してきた。江戸時代末期までに成立した道路、水路、宅地割が良く残されており、その上に店蔵など多様な土蔵等が建ち並ぶ町並みは、在郷町・醸造町としての特徴的な歴史的風致を形成している。
喜多方市は、古くは「北方」と称した。小田付は、喜多方市の中心部を南流する田付川の左岸にあり、東の須蟹沢川との間に南北約900m、東西約 500mの中心市街を形成する。田付川の自然堤防上の南北に長い町並みである。この付近は、田付川が形成する扇状地の扇端にあたり、湧水と地下水に恵まれている。
会津地方は、古代には陸奥国耶麻郡に属した。平安時代に越後の城氏が進出するが、源頼朝の奥州征伐後は相模三浦氏系の佐原氏が地頭職となり、一族の猪苗代氏、北田氏、金上氏、蘆名氏、加納氏、新宮氏が会津各地を分割支配した。14 世紀後半に勢力を伸ばした蘆名氏が永享5年(1433)に新宮氏を滅ぼして会津一円を領し、会津守護を名乗った。蘆名氏はその後、奥州を代表する戦国大名となった。
天正 17 年(1589)に蘆名義広が伊達政宗に敗れると、豊臣秀吉の奥羽仕置により、翌 18 年(1590)に蒲生氏郷が会津に入部した。その後、慶長3年(1598)に上杉景勝、同6年(1601)に蒲生秀行、寛永4年(1627)に加藤嘉明が領した。寛永 20 年(1643)に保科正之が入部、三代正容から松平姓を用いるようになり、会津松平家が近世末まで当地を治めた。
田付川中流の中田付では、中世から定期市が開かれていたが、蘆名氏重臣の佐瀬大和守は、立地が不便であることを理由に市の移転を決定した。天正 10 年(1582)に新たに市の町として開いたのが小田付の始まりとされる。周辺の 93 集落から労働力を徴し、佐瀬の知行地であった近傍の台・南条・古屋敷・小田付の4つの集落を集め、小田付村と名付けたという。小田付は毎月2と7の日に市が立つ六斎市であった。その後、小田付は田付川右岸の小荒井と市日の争論を繰り返しながら、会津地方北部を代表する市町として発展した。この地には、天明元年(1781)に郡役所、同8年(1788)に小田付組と小荒井組を支配する代官所が置かれた。近世の小田付は、喜多方地方の商業、政治の中心地であった。
会津地方では、18 世紀末には常設の店舗を開くものが現れるようになり、小田付においても 19 世紀中頃には定期市は年初、年末のほか数度開かれる程度まで衰退し、常設店が軒を並べるようになった。
明治 14 年(1881)には、耶麻郡役所が塩川村から小田付に移転した。明治 17 年(1884)には、県令三島通庸の計画した会津三方道路のうち、小田付から飯豊山地の大峠を越える米沢街道が開通する。
小田付は、余剰米と良質な水を利用した酒造業が盛んである。明暦3年(1657)に酒造株が制度化され、文化4年(1807)には、小田付村の5家が酒造株を持っていた。味噌醤油の醸造業も大規模に行うものがあり、明治 40 年(1907)に小田付の醸造家として5家を記録するが、うち3家は現在も操業を続けている。明治時代には、会津地方でも養蚕が盛んになり、小田付では製糸業が活況を呈した。
以上のように、小田付は近世以来、喜多方地方東部の農村を支える商業の中心であり続けた。
保存地区は、田付川とその東を流れる須蟹沢川に挟まれた南北約 900m、東西約 500mの範囲で、戦後の道路整備により部分的な改変はあるものの、近世初頭の町立てから近代初頭までに成立した道路、水路、宅地割などの地割が良く残されている。また、町並みを形成する建物の多くは、明治時代初期から昭和時代以降の建設で、会津地方の民家建築、とりわけ市町の建物の発展過程を示すものとして評価できる。
喜多方市は、蔵を撮影した写真家が昭和 47 年(1972)から各地で写真展を開催したことをきっかけとして、昭和 50 年(1975)にテレビで喜多方の蔵が紹介され、「蔵のまち」として全国的に有名となった。それによって観光客が激増し、同時に大正末期からの歴史をもつ喜多方ラーメンも全国区となった。
伝統的建造物の特性。
小田付の建物は、寄棟造茅葺の農家住宅を祖型とすると考えられる。道路側から座敷、居間、台所の床上部が並び、最奥が土間となる間取りである。建物は敷地の北側に寄せて建てられ、南側に通路をとって建物南面に玄関を設けるものが多い。
店舗の常設化に伴い、近世末期には、店舗の道路に面して下屋庇を設けて店舗空間を設けるもの【類型Ⅰ】と、独立した店舗棟を設けるもの【類型Ⅱ】が発生した。また、近代以降に現れた長屋形式のもの【類型Ⅲ】がある。
【類型Ⅰ】①主屋は寄棟造茅葺のまま、下屋庇を板葺ないし瓦葺としたもの。②主屋を切妻造の板葺ないし瓦葺としたもの。③主屋の座敷部分を大壁造土蔵塗の別棟とする。・主屋は道路側から店舗、座敷に用いられる。・敷地間口が比較的小さい例であり、板葺屋根は、後に瓦葺や金属板葺に改められる。
【類型Ⅱ】①店舗棟が二階建平入で、真壁造としたもの。②店舗棟が二階建平入で、大壁造土蔵塗としたもの。③店舗棟が妻入で、大壁造土蔵塗としたもの。・居住棟は切妻造の板葺ないし瓦葺(居室部分を茅葺とするものもある)とし、座敷は居住棟の表側に設ける。・店舗棟の二階に座敷を設けるものもある。・敷地間口にゆとりがある例であり、店舗の桁行は4間以上となるが、間口の狭い敷地では妻入の店蔵も存在する。
【類型Ⅲ】①二階の建ちが低く、背後に居住部分と水廻りを延ばすもの。②建ちが高い二階を居住部分にあて、背後に平屋で水廻りを設けるもの。
以上のように、小田付には近世以来の住宅と店舗の発展をたどることのできる建物が豊富に残されている。
小田付には、店舗に用いた店蔵、家財蔵、商品蔵、米などを収めた穀蔵、醸造業の大規模な醸造蔵、内部に座敷をしつらえた座敷蔵などの土蔵造の建物がある。建築年代が明らかな建物は少ないが、大善矢部家質蔵(文政9年)、花摘家家財蔵(嘉永元年)など江戸時代後末期に遡るものが確認された。大規模な醸造蔵は大正時代以降のものである。座敷蔵は大善矢部家(明治 31 年)など、19 世紀末以降に普及した。
土蔵の屋根には、置屋根形式の「二重屋」と軒先の蛇腹を漆喰で塗り込めたものがあり、塗り込めの断面形状には、直線状の「切っ立て」と円弧状の「繰り」がある。塗り込めのものも構造は置屋根で、置屋根の軒廻りに木摺下地を組んで漆喰を塗る。瓦の普及以前は板葺で置屋根とするのが普通であった。なお、喜多方地方でいわゆる「喜多方瓦」が生産されるようになるのは、明治 23 年(1890)である。現在は、瓦葺または金属板葺であるが、置屋根に由来する大きな軒の出が小田付の土蔵を特徴づけている。