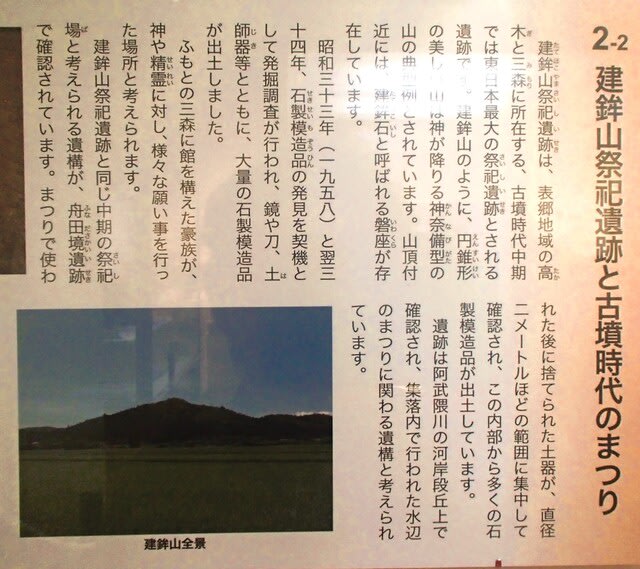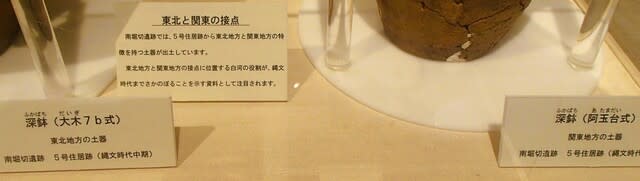国史跡・白川城跡。福島県白河市藤沢。
2024年6月1日(土)。
白河市歴史民俗資料館の見学を終え、小峰城に移転するまで白河結城氏の本城であった国史跡・白川城跡へ向かった。
歴史民俗資料館から近い場所にあるので入館時にアクセスを尋ねたら、出るときに受付の男性職員が地図をプリントして詳しく行き方を教えてくれた。2回脇道に入り、最後は山の麓の狭い道を数百m道なりに進むと狭い駐車場があり、解説板と本丸への階段がある。




白川城本丸跡。
白河市歴史民俗資料館には、国史跡・白川城跡の展示がある。

白川城跡は、中世、白河荘(福島県白河市及び西白河郡一帯)を拠点として陸奥国南部を支配した白河結城氏歴代の居城跡であり、搦目(からめ)城跡とも言う。
城跡は、白河市中心部の東南方約2km、阿武隈川右岸に南側から樹枝状に張り出した、比高約60mの丘陵部に所在する。


白河結城氏は、鎌倉武士として有名な下総結城氏の一族である。結城氏と白河との関係は、結城朝光が奥州合戦の恩賞として白河荘を賜ったことに由来する。朝光は、鎌倉幕府の評定衆に就任するなど幕政に重きをなしたが、白河には赴任せず、本代官を白河に派遣していたと考えられている。

鎌倉時代中期以降、結城氏の庶子が下総から白河に移住し、阿武隈川の南岸(南方(みなみかた))と北岸(北方(きたかた))において郷村の開発を行うようになった。
白河結城氏の祖とされる祐広(朝光の孫)は 13 世紀後半に白河に下向したと伝えられ、その子宗広の時代まで「白河荘南方」の地頭職として大村郷(白河市大地区)をはじめとした 10 程度の郷村を支配し、白川城を本拠としたとされる。
一方「北方」は一族の結城盛広が富沢郷(現在の白河市大信下小屋付近)を本拠とし、同様に 10 程度の郷村を支配していたとされる。
しかし、白河荘の中心である金勝寺(荒砥崎)は結城家惣領が領し、周辺の関(旗宿)・小田川・田島なども他の結城諸氏が支配していた。
このように鎌倉時代の白河荘は、結城氏という武士団の一族により現在につながる郷村の開発が行われていったが、この段階においては、祐広・宗広の白河結城氏はまだ結城一族のうちの一家という状況であり、地域に台頭するには至っていなかった。
白河結城氏が台頭するのは、祐広の子、宗広の時代である。宗広は、後醍醐天皇の鎌倉幕府倒幕の命に従い、鎌倉を攻める新田義貞らに呼応して幕府を滅亡に追い込んだ。後醍醐天皇の信頼を得た宗広は結城家の「惣領」となるよう命じられ、天皇に反旗を翻した足利尊氏と戦ってこれを破り、天皇から「公家(天皇家)の宝」とまで賞賛されている。
その後、天皇主導の政治(建武政権)に反感を持つ武士層を糾合して勢力を盛り返した尊氏は、後醍醐天皇を吉野に追いやり、後醍醐天皇の南朝と尊氏の北朝が対立する南北朝内乱時代を迎えるが、宗広は一貫して南朝側につき、南朝勢力の立て直しを図ろうとした。
南朝勢力の退潮により宗広の子親朝は尊氏による北朝・武家政権への転身を図り、家の存続に腐心し、その後の繁栄の基礎を固めた。この建武元年(1334)から明徳 3 年(1392)の約 60 年にわたる南北朝内乱期を経て、白河結城氏は白河荘全体を掌握・領有するとともに、福島県中通り一帯の軍事警察権を行使する検断職(けんだんしき)に任じられ、室町時代には奥州南部から北関東まで勢力を拡大するに至った。
しかし、永正7年(1510)、惣領の政朝が一族の小峰氏によって追放され(永正の変)、小峰氏の血統による新たな白河結城氏が成立した。また、この時期に結城氏の本拠も白川城から小峰城に移ったとされている。
その後、周辺の有力大名に押されて白河結城氏の影響力は次第に失われ、佐竹・葦名氏を経て伊達氏に従属するようになった。遂に天正18年(1590)の奥羽仕置で白河結城氏は改易、約400年に及ぶ南奥支配は終焉を迎えた。
江戸時代の文化4年(1807)には、宗広・親光親子を顕彰する「感忠銘(かんちゅうめい)」碑が城跡北側崖面の岩塊に彫られた。
白河結城氏については、800点以上に及ぶ文書が伝来し、当該期の動向を知ることができ、『白河市史』の編纂等もあって、近年、情報収集と研究が進捗している。
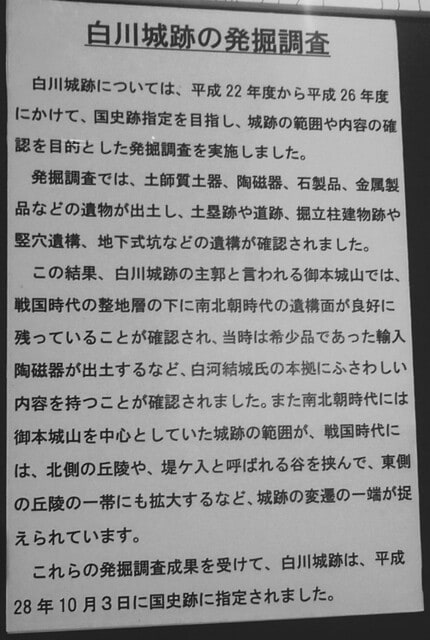



白河市教育委員会では、平成22年度から同27年度にかけて、城跡の範囲・内容確認を目的とした発掘調査等を実施し、東西約950m、南北約550mの範囲で多数の平場・土塁・堀等の遺構が良好に遺存することを確認した。
城跡は、御本城山(ごほんじょうやま)地区を中心として、北東方に伸びる中山地区、北西方の藤沢山地区・藤沢地区から成る西部遺構群と、谷部を挟んだ御本城山の東側で、搦目山とその西側に派生する鐘撞堂山(かねつきどうやま)と呼ばれる2本の尾根上を中心に展開する東部遺構群から成る。
御本城山地区では、1号平場において盛土による土地造成や土塁、柱列、竪穴遺構、溝等を検出し、14世紀代と16世紀代の遺構面を確認した。1号平場の北東部にある2号平場では、16世紀後半代の道・土塁、14世紀代の門の一部と考えられる遺構を検出した。14世紀代の遺物として、中国製青磁(酒海壺(しゅかいこ)・水盤)が出土した。
また、中山地区の西端には、延長約130mの堀が残る。一方、御本城山地区の東に存在する鐘撞堂山地区では、2条の長大な堀が南半分に展開し、丘陵頂部では平場造成、地下式坑の遺構のほか、桁行4間、梁行3間の総柱と思われる建物を確認した。また、搦目山地区では、丘陵頂部平場で建物、柱列、土塁を確認した。建物は、桁行4間、梁行2間の東西棟の身舎(もや)に、北・東・南側に庇または縁が付くもので、15~16世紀代に位置づけられる。
御本城山地区では、2号平場を中心に14世紀代の遺構・遺物を確認でき、南北朝期における城館の中心が御本城山地区であると考えられる。
その後、同地区の遺構は減少し、室町期以降の出土遺物は東部の遺構群に多い傾向があり、城館の中心が搦目山に移動した可能性が考えられる。
また、御本城山地区周辺では16世紀後半頃に南北朝期の遺構面を覆う形で行われた大規模な整地を確認でき、藤沢山地区等でも同様な状況を確認できることから、この時期に城全体で改修が行われたと推定できる。南北朝期の遺構が良好に残る大規模な城館として貴重な事例と評価される。
このように、白川城跡は、鎌倉時代後期に陸奥国白河荘を拠点として活動し、南北朝期以降、陸奥南部地域を支配下に収めて繁栄した白河結城氏の居城である。発掘調査によって南北朝期から戦国期にかけての遺構等が良好に遺存していることが確認された。

国指定史跡・名勝「南湖公園」。白河市南湖。
南湖は、日本最古といわれる公園で、寛政の改革で知られる白河藩主・松平定信により、身分の差に関係なく誰もが楽しめる「士民共楽」という理念のもと、享和元年(1801)に築造された。
当時の庭園は城内や大名屋敷内などに造られ、庶民は立ち入ることができなかったが、南湖には垣根がなく、いつでも誰でも訪れることのできる画期的なものであった。
「南湖」という名称は、唐の詩人・李白の詩「南湖秋水夜煙無」からと、小峰城の南側に位置していたことに由来するといわれている。
また、行楽だけでなく、湖水は灌漑用水、水練・操船訓練として利用され、造成工事は領民の救済事業としての性格も持っていた。
湖水面積は17.7ヘクタール、周囲は約2キロメートルあり、那須連峰や関山を借景に、松、奈良吉野の桜、京都嵐山の楓が植えられ、四季折々の景色を楽しめる。
白川城跡から南湖公園東駐車場までは5分ほどで着き、湖岸まで歩いた。景勝を眺望する中心地までは徒歩では遠そうなので、湖岸道路を西に抜けることにした。途中で中心地を眺めると人出が多く賑わっていた。福島県文化財センター白河館「まほろん」へ向かった。