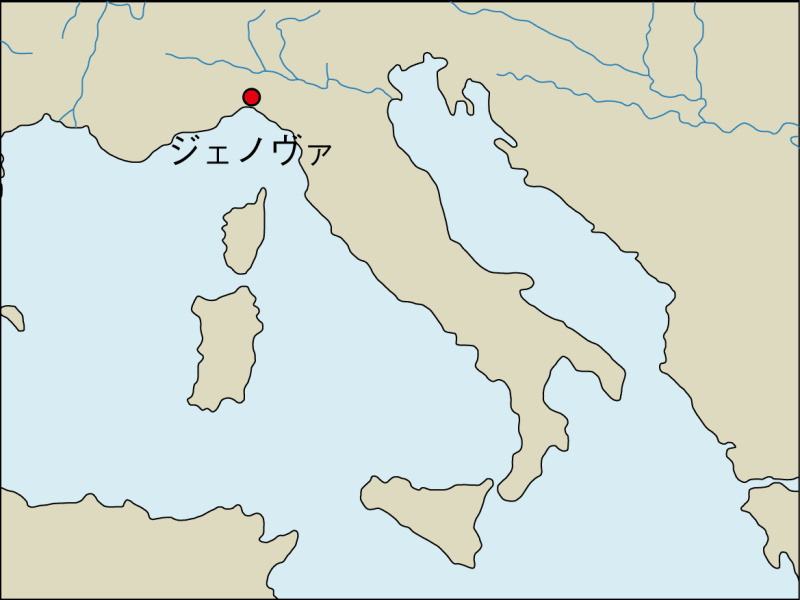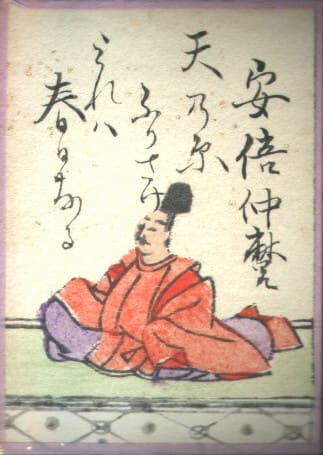アレクサンドロス大王がエジプト征服後、前331年、ナイル川デルタの西端に建設を始めた植民市。
プトレマイオス朝の首都としてヘレニズム時代の貿易・文化の中心となり、多くの著名な科学者を輩出した。
碁盤状の通りをもった市部と約1200mの突堤で結ばれた前面のファロス島からなり、市部には王宮・セラピス神殿・ムセイオンとその付属図書館、島の東端には高さ160mの大燈台があった。
ローマ時代には哲学者・神学者が現れ、いぜん活気があったが、641年にアラブ人に占領されてから衰えた。
19世紀初めにムハンマド=アリが現れてから再び繁栄し、イギリスの植民地化に反抗して、1881~82年アラービー=パシャの乱が起こった。
●キリスト教五本山
ベック式暗記法!
あれアンティーク 家コンロ。
アレクサンドリア
イェルサレム
コンスタンチノープル
ローマ