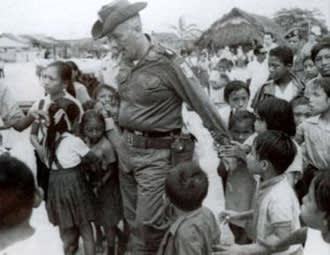1978年1月、ソモサは国家警備隊にチャモロを暗殺させた。この事件は、ニカラグア国民の反ソモサ感情をあおり、1979年5月、サンディニスタ民族解放戦線は、ニカラグアの全土で一斉蜂起。民主解放同盟も都市部でストライキやデモを組織し、8月にはニカラグア国内のほとんどすべての都市で市民が蜂起した。蜂起した一般市民に対し、国家警備隊は容赦なく無差別砲撃や空爆を行ない、ニカラグアは内乱状態に陥った。この内乱は全人口60万のうち4万人が死亡するほどの凄まじいものだった。
だが、サンディニスタ民族解放戦線が首都マナグアに迫った7月17日、孤立無援となったソモサはついに米国に逃亡。ソモサ独裁政権は崩壊した。ダニエル・ホセ・オルテガ・サアベドラ(Daniel José Ortega Saavedra・1945~)が国家再建会議議長に就任し、ニカラグア全土から集まったサンディニスタ民族解放戦線のゲリラ部隊は、民衆の大歓声に迎えられて、マナグア入城を果たした。
だが、革命政権の改革がうまく進んだのも1981年までだった。
「夕方の5時ごろになると決まって私を強姦しました。来る日も来る日も交替で犯したんです。膣が使い物にならないとみるや、今度はいっせいに肛門を犯しました。5日間にわたって60回も犯されたのです」
ニカラグア北部のエステリ州にあるサンディニスタ革命政権が作った集団農場のある二児の母親はこう語る。農場には、彼女を含め、8人の女と15人の男が住んでいたが、農場が「コントラ」の襲撃を受けたのだ。コントラは彼女が見ている前で、夫を殺し、もう一人の住民の眼球をえぐりだした。別の協同農場の住民はこう語る。
「農場には15歳の少年がいましたが、お腹をざっくりと切り裂かれ、腸が地面に引き伸ばされて置いてありました。まるで縄みたいに」
コントラによって、住民が面白半分に殺され、女たちは強姦される。少女を拉致して売春婦として売り飛ばす。赤ん坊を岩で叩き潰し、女たちの乳房を切り落したり、顔の皮を剥いだして、逆さ吊りにして出血死させる。刈り取った首を棒の先に突き刺す。1980年代のニカラグアではこんな状況は当たり前だった。
サンディニスタ政権は、キューバの社会主義革命をモデルにしているから、ニカラグアも、キューバに続いて社会主義国の仲間入りしてしまう恐れがあった。1981年にレーガンが米国大統領となると、第二のキューバ化を恐れた米国は、露骨な内政干渉を始める。まず、経済援助を停止して経済封鎖を行い、次には、ソモサの国家警備隊員や新政府から離脱した保守派等の反革命勢力を集結させた。反革命勢力「コントラ」は、米国からの強力な援助のもと、1981~1984年にかけ、ホンジュラスとコスタリカ国境を越え、南北からニカラグアに攻め込んだのだ。最盛期には兵力は15,000人にまでに膨れあがり、米国はホンジュラス領内で、コントラのための基地を建設、大規模な軍事演習も行なって支援したのである。米国は、毎年コントラに多額の援助を行って破壊活動や民間人の誘拐・殺害を繰り返させる。ニカラグア政府は、国際連盟やハーグ国際司法裁判所などを介して国際社会に訴えたが、米国は無視した。
コントラに対抗するために軍事費は限りなく増大し、教育や社会保障のための支出は削減された。1983年には国民の反対を押し切って徴兵制が導入された。だが、こうした状況下でも、1984年のソモサ打倒後初の大統領選挙では67%の圧勝で民族再建会議議長であったダニエル・オルテガが大統領に就任し、議会でもサンディニスタ民族解放戦線が過半数を大幅に上回る議席を獲得した。いまだにサンディニスタ民族解放戦線は、貧民層の信頼を失ってはいなかった。
だが、それでも米国は、ニカラグアへの攻勢の手を緩めない。1981年から始まった経済制裁は強化され、1985年には全面禁輸を行なった。これによって、ニカラグア経済は大混乱をきたし、1988年には20,000%というとほうもないインフレで、もはや紙幣は紙クズ同然となり、失業者が増大した。
コントラとの内戦長期化や経済制裁による生活窮乏化、そして、ソ連邦の崩壊に民衆は耐えられず、革命政権は11年続いた後、1990年の総選挙で敗れ、サンディニスタ革命は終焉した。ダニエル・オルテガは2001年の大統領選にも立候補したが、米国はサンディニスタ革命政権の復活を恐れ、公然と大統領選挙に干渉した。9月11日同時多発テロを背景に、オルテガをビンラディン同様のテロリスト呼ばわりすることによって、さまざまな反サンディニスタ革命政権キャンペーンを繰り広げることで、オルテガの当選を阻むことに成功したのである。めでたし、めでたし。













 マヌエル・アントニオ・ノリエガ(Manuel Antonio Noriega:1938~)は、トリッホスの死後、彼の後継者を名乗って、どさくさまぎれに1983年にパナマ軍最高位の「国防軍司令官の地位」という権力の座についた人物である。ノリエガが、フリーポートであるパナマの利点を利用し、密貿易、とりわけ、麻薬売買に手を染めていたことは間違いない。そして、麻薬密売の大本締めだったノリエガが「逮捕」されたならば、パナマの麻薬汚染はなくなるはずである。だが、米国の侵攻後になぜか、パナマの麻薬売買の量は格段に増えた。つまり、ノリエガの麻薬密輸は、侵攻の名目であり、米国には政治的にどうしても侵攻しなければならない理由があったのだ。
マヌエル・アントニオ・ノリエガ(Manuel Antonio Noriega:1938~)は、トリッホスの死後、彼の後継者を名乗って、どさくさまぎれに1983年にパナマ軍最高位の「国防軍司令官の地位」という権力の座についた人物である。ノリエガが、フリーポートであるパナマの利点を利用し、密貿易、とりわけ、麻薬売買に手を染めていたことは間違いない。そして、麻薬密売の大本締めだったノリエガが「逮捕」されたならば、パナマの麻薬汚染はなくなるはずである。だが、米国の侵攻後になぜか、パナマの麻薬売買の量は格段に増えた。つまり、ノリエガの麻薬密輸は、侵攻の名目であり、米国には政治的にどうしても侵攻しなければならない理由があったのだ。
 腐植説か。それとも無機栄養説か。決着を付ける壮大な研究が、リービッヒが理論を提唱した3年後の1843 年に始まる。この実験を始めたのは英国の地主、ジョン・ベネット・ローズ(John Bennet Lawes:1814~1900)だった。ローズは、ハートフォードシア(Hertfordshire)近郊のローザムステッド(Rothamsted)に地所を有する地主の一人息子として生まれた。オックスフォード大学を卒業したが、若い頃から、自分の領地で様々な薬用植物を育てることに熱中していた。ポットの中で色々な植物を栽培しては、肥料の効果を実験し、その後に研究は作物にまで広げられた。そして、1842年に29歳の若さで骨粉やリン鉱石を硫酸で処理した化学肥料の水溶性の「過りん酸石灰」製法特許を取得し、化学肥料の最初の工場の運営も始める。
腐植説か。それとも無機栄養説か。決着を付ける壮大な研究が、リービッヒが理論を提唱した3年後の1843 年に始まる。この実験を始めたのは英国の地主、ジョン・ベネット・ローズ(John Bennet Lawes:1814~1900)だった。ローズは、ハートフォードシア(Hertfordshire)近郊のローザムステッド(Rothamsted)に地所を有する地主の一人息子として生まれた。オックスフォード大学を卒業したが、若い頃から、自分の領地で様々な薬用植物を育てることに熱中していた。ポットの中で色々な植物を栽培しては、肥料の効果を実験し、その後に研究は作物にまで広げられた。そして、1842年に29歳の若さで骨粉やリン鉱石を硫酸で処理した化学肥料の水溶性の「過りん酸石灰」製法特許を取得し、化学肥料の最初の工場の運営も始める。

 「土壌の肥沃度は完全に腐植に依存している。腐植は水とは別にそれ単独で植物に養分をもたらす。腐植はまさに生命の産物であり、それは生命のひとつの状態でもある。腐植なくしては、いかなる個別生命も考えることはできない」
「土壌の肥沃度は完全に腐植に依存している。腐植は水とは別にそれ単独で植物に養分をもたらす。腐植はまさに生命の産物であり、それは生命のひとつの状態でもある。腐植なくしては、いかなる個別生命も考えることはできない」 たった種子がせいぜい
たった種子がせいぜい