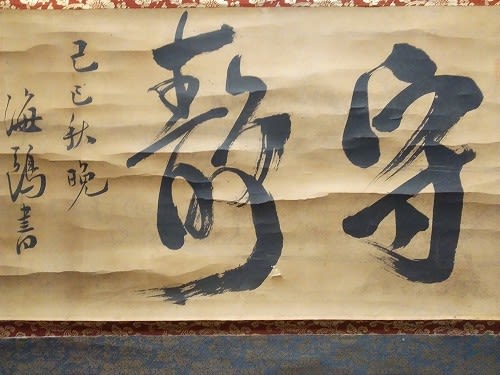コロナに負けるな、17回目です。
今回は、流れ仏です。

16x38 ㎝ (台座含)
流れ仏とは、ドザエモン(溺死者)のことですが、骨董界では、激しく風化した木彫の仏像を言います。川や海辺に流れ着いた物かも知れません。
この品が、元々、仏像であったかどうかはわかりません。むしろ、神像に近いものと思えます。
それにしても、体に比べて、顔が異様に大きい(^^;)
円空や木喰系の彫り物ではないし、素人の作にしては上手だし・・・・放浪僧か修験者が残していった?
正体不明の古い木彫ということで、宗教物や武具がご法度の故玩館に、かろうじて置かせてもらっています(^.^)

長い間、風雪に耐えてきたようです。

足元は、まるで段ボールのよう。

厳しい表情です。
しかし、反対側の横顔は・・・


グッと何かに耐えながら、思索にふけっているように見えます。

この世の乱れをただすために、これから瞑想に入ろうとされているのでしょうか。


車箪笥(長持ち)の上に鎮座して、人間界を見据えていらっしゃる。

『白磁のある静物』をバックにして、コロナウィルスに睨みをきかせています。でも、本当に睨みをきかせているのは、人間に対してかも知れませんね。
きっと、もう一つの慈悲深い顔で、私たちのために祈ってくれることでしょう。
コロナに負けないぞシリーズは、今回で終わります(-.-)