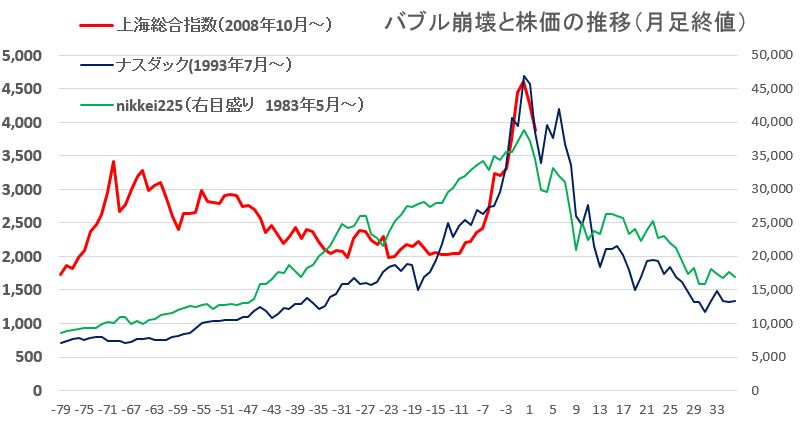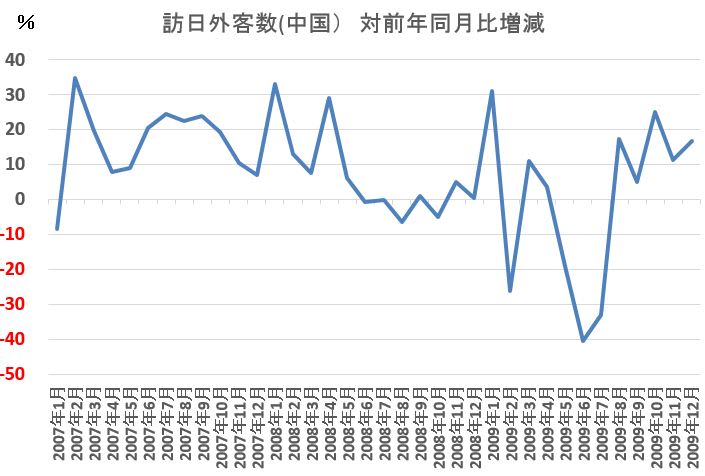2015年 07月 9日 06:06 JST ロイター
[ワシントン 8日 ロイター] - 米連邦準備理事会(FRB)が8日公表した6月16─17日開催の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨で、メンバーらは利上げに踏み切るには、米経済が強さを増しているという一段の兆候が必要と考えていたことが分かった。ギリシャの債務危機については重大な懸念が示された。
会合では、強弱まちまちの米経済指標や海外市場の混乱を踏まえ、年内に想定されている利上げをどのように進めるかが討議された。
議事要旨はこの点について「多くの参加者は政策正常化の開始基準を満たしたと判断するには、経済成長の強まりや労働市場状況の改善継続、さらにはインフレが委員会目標に向けて伸びていることを示す新たな情報が必要になる」と強調。早くても9月までは利上げはないとの市場の見方を後押しする内容だった。
参加者は、物価上昇圧力が依然として弱い中で時期尚早に利上げに踏み切れば、物価が弱含んだ場合のFRBの対応能力が疑問視されかねないとの懸念を示した。
FRBは6月のFOMCで事実上のゼロ金利政策を維持した。2008年12月以来ゼロ金利が続いている。ただ、FRBは今年後半に少なくても1度、場合によっては2度の利上げに向けて準備していることも示唆している。
6月のFOMC会合時点では、ギリシャは事実上の債務不履行(デフォルト)状態にはまだ陥っておらず、中国の株式相場も急落してはいなかった。
それでもなお参加者は「(ギリシャと債権団が)見解の相違を解消できない場合、ユーロ圏の金融市場が混乱したり、その影響が米国に飛び火したりする恐れがある」と強い懸念を表明した。中国の経済成長の鈍化も不安視された。6月のFOMC以降、中国の株式相場は大きく下落し、中国政府は対応に追われている。
ただ、こうした中でも議事要旨は「景気は引き続き、金融政策の正常化を正当化する基準に近づいてきている」と指摘し、FRBが依然として年内に利上げする意向であることを示した。