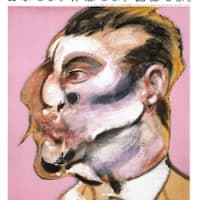俳人の阿部完市先生(現代俳句協会前副会長/同初代青年部長)が、2月19日(木)、逝去された。朝日新聞に掲載された同先生の訃報記事は次のとおり。「阿部完市さん(あべ・かんいち=俳人、現代俳句協会前副会長、精神科医)が19日、心不全で死去、81歳。葬儀は近親者で行った。連絡先は現代俳句協会(電話03・3839・8190)。1962年に金子兜太氏主宰の結社「海程」に入り、同人となる。70年に第17回現代俳句協会賞を受賞。第9回現代俳句大賞の受賞も決まっていた。朝日新聞埼玉版「埼玉文化」の俳句の選者を87年から務めた。著書に句集「無帽」「絵本の空」、評論集に「俳句幻形」などがある。」
私(須藤徹)は現代俳句協会青年部の勉強会が立ち上がった平成2年(1990年)の頃から、あれこれご指導いただく立場になり、約20年くらいのお付き合いをさせてもらった。特に不肖私が平成12年(2000年)から同協会の青年部長を担当することになってからは、幹事会などで直接お話する機会もふえ、さまざまなことを吸収させていただいたのである。特に青年部の事業運営につき、多くのアドバイスを賜り、いわば青年部の精神的・経営的支柱であった。阿部先生のご指導なくして、今日のシンポジウムや勉強会の繁栄はなかったと切に思う。衷心から、哀悼の意を表する。
阿部完市論は過去に3回執筆した。いずれも直接ご本人からのご依頼で、3回共に電話で先生自ら骨子をお話された。最初に書いたのは、阿部先生が所属する俳誌「海程」で、タイトルは「物語(レシ)としての完市俳句─阿部完市の方法と原理」とした。(1997年。)2回目は邑書林句集文庫の『阿部完市句集にもつは絵馬』の解説で、タイトルを「始原への旅─俳句とメタレベル」とした。(1998年。)3回目は秋田魁新報社の文化欄へ寄稿したもので、タイトルは「斬新で柔軟な世界を構築」とした。(2000年。)
第1回目に執筆した内容は、拙著『俳句という劇場』(深夜叢書社/1998年)に収載されているけれど、他の2本は単行本や雑誌などには未収録である。いずれ次の評論集を出す時には、この2本は積極的に収録してみよう。現俳壇を含めて、阿部完市論で出色なものは、残念ながらほどんどない。手前味噌になって恐縮だけれど、私の3本は、独特な阿部完市先生の俳句法を、私なりに解析したもので、いってみれば「メタレベル」としての俳句原理論である。これは、いうまでもなく俳句の「時間論」に通底するのだ。拙文の一部を転写する。
<邑書林句集文庫の『阿部完市句集にもつは絵馬』の解説「始原への旅─俳句とメタレベル」/1998年)
(前略)
「男ありむさしを歩く銀狐つれて 阿部完市
兎がはこぶわが名草の名きれいなり 同
葉のかたちのトーストいちまい青森にて 同
静かなうしろ紙の木紙の木の林 同
この野の上白い化粧のみんないる 同
どれも高名な阿部完市の作品である。もちろんこれらの俳句が、一俳人の領有する範疇にとどまるだけでなく、現代俳句史上に燦然と輝く逸品であることはほとんど衆目の一致するところであろう。こうした俳句が、一同に集まる『にもつは絵馬』という句集は、個人のみならず現代俳句の収穫でもあるのではないか。ここに掲げた俳句は、ことばとことばのインタラクティブな関係により共有される一つの同時性の進行プロセスの中で、結局は異次元のある像を獲得する。深層意識のどこかから、ざわめくような記憶が沸き立ち、さらに別の記憶を呼び寄せる。たとえばそのような記憶が集合的無意識であったり、既視現象(デジャヴュ)であったりするかもしれない。」(P101~P102/後略)。*「 」部分が引用部分。
2月21日(土)、ぶるうまりんの「東京句会」発足満一周年の記念として、「橋本夢道の住居地<月島>を訪ねて」として、「月島」及び「佃島」界隈の吟行会を大磯句会と東京句会の合同で行った。吟行のコースは、海水館跡(佃島)、住吉神社(同)、佃堀(同)、もんじゃストリート(月島)、都内最古の交番(同)、橋本夢道の住居地(同)など。写真は、江戸の情緒が残る佃掘の船掛かり。私が当日提出した作品は以下のとおり。
料峭(りょうしょう)へ泡立っている豆腐売り 須藤 徹
書けば、痒い 同
逃水を影が追い越す勝鬨橋 同
極道が穹(そら)に跳ねてる海市かな 同
ばるさみこ酢の春が低目に月島は 同
私(須藤徹)は現代俳句協会青年部の勉強会が立ち上がった平成2年(1990年)の頃から、あれこれご指導いただく立場になり、約20年くらいのお付き合いをさせてもらった。特に不肖私が平成12年(2000年)から同協会の青年部長を担当することになってからは、幹事会などで直接お話する機会もふえ、さまざまなことを吸収させていただいたのである。特に青年部の事業運営につき、多くのアドバイスを賜り、いわば青年部の精神的・経営的支柱であった。阿部先生のご指導なくして、今日のシンポジウムや勉強会の繁栄はなかったと切に思う。衷心から、哀悼の意を表する。
阿部完市論は過去に3回執筆した。いずれも直接ご本人からのご依頼で、3回共に電話で先生自ら骨子をお話された。最初に書いたのは、阿部先生が所属する俳誌「海程」で、タイトルは「物語(レシ)としての完市俳句─阿部完市の方法と原理」とした。(1997年。)2回目は邑書林句集文庫の『阿部完市句集にもつは絵馬』の解説で、タイトルを「始原への旅─俳句とメタレベル」とした。(1998年。)3回目は秋田魁新報社の文化欄へ寄稿したもので、タイトルは「斬新で柔軟な世界を構築」とした。(2000年。)
第1回目に執筆した内容は、拙著『俳句という劇場』(深夜叢書社/1998年)に収載されているけれど、他の2本は単行本や雑誌などには未収録である。いずれ次の評論集を出す時には、この2本は積極的に収録してみよう。現俳壇を含めて、阿部完市論で出色なものは、残念ながらほどんどない。手前味噌になって恐縮だけれど、私の3本は、独特な阿部完市先生の俳句法を、私なりに解析したもので、いってみれば「メタレベル」としての俳句原理論である。これは、いうまでもなく俳句の「時間論」に通底するのだ。拙文の一部を転写する。
<邑書林句集文庫の『阿部完市句集にもつは絵馬』の解説「始原への旅─俳句とメタレベル」/1998年)
(前略)
「男ありむさしを歩く銀狐つれて 阿部完市
兎がはこぶわが名草の名きれいなり 同
葉のかたちのトーストいちまい青森にて 同
静かなうしろ紙の木紙の木の林 同
この野の上白い化粧のみんないる 同
どれも高名な阿部完市の作品である。もちろんこれらの俳句が、一俳人の領有する範疇にとどまるだけでなく、現代俳句史上に燦然と輝く逸品であることはほとんど衆目の一致するところであろう。こうした俳句が、一同に集まる『にもつは絵馬』という句集は、個人のみならず現代俳句の収穫でもあるのではないか。ここに掲げた俳句は、ことばとことばのインタラクティブな関係により共有される一つの同時性の進行プロセスの中で、結局は異次元のある像を獲得する。深層意識のどこかから、ざわめくような記憶が沸き立ち、さらに別の記憶を呼び寄せる。たとえばそのような記憶が集合的無意識であったり、既視現象(デジャヴュ)であったりするかもしれない。」(P101~P102/後略)。*「 」部分が引用部分。
2月21日(土)、ぶるうまりんの「東京句会」発足満一周年の記念として、「橋本夢道の住居地<月島>を訪ねて」として、「月島」及び「佃島」界隈の吟行会を大磯句会と東京句会の合同で行った。吟行のコースは、海水館跡(佃島)、住吉神社(同)、佃堀(同)、もんじゃストリート(月島)、都内最古の交番(同)、橋本夢道の住居地(同)など。写真は、江戸の情緒が残る佃掘の船掛かり。私が当日提出した作品は以下のとおり。
料峭(りょうしょう)へ泡立っている豆腐売り 須藤 徹
書けば、痒い 同
逃水を影が追い越す勝鬨橋 同
極道が穹(そら)に跳ねてる海市かな 同
ばるさみこ酢の春が低目に月島は 同