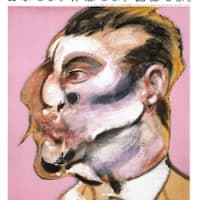[マルティン・ハイデガー『存在と時間』/第1部「時間性へ向けての現存在の解釈、および存在についての問いの先験的視界としての時間の解明」・第1編「現存在の予備的基礎分析」・第1章「現存在の予備的分析の課題を解明すること」・第11節「実存論的分析論と原始的な現存在の解釈。「自然的世界概念」を得るための種々の難しさ/1969年8月30日第11刷の桑木務訳岩波文庫]
現存の実証的な諸学問の要求に対して、存在論はただ間接的に寄与することができます。たとえ存在するものの告知を超えて、存在への問いが、すべての学問的探求の先端だとしても、実証科学はそれ自身のための独自の目標をもっているのです。
Zur Foerderung der bestehenden positiven Disziplinen kann Ontologie nur indirect beitragen. Sie hat fuer sich selbst eine eigenstaendige Abzweckung, wenn anders ueber eine Kenntnisnahme von Seiendem hinaus die Frage nach dem Sein der Stachel alles wissenshaftlichen Suchen ist.
今回の青色のリード文は、第11節の最終センテンスである。これをもって、第一編「現存在の予備的基礎分析」が終わる。第11節は、桑木務の訳文で、わずか55行だ。そのうち、活字を小さくした、エルンスト・カシーラ-についての解説が23行あるので、ハイデガーの示唆する当該文章は、32行ということになる。きわめて短い第11節において、ハイデガーが、いいたいことは、冒頭に掲出した文章につきる。
ハイデガーは、存在の哲学的探求者の自負をもって、「存在への問いが、すべての学問的探求の先端」としながらも、「実証的な諸学問」(実証科学)の役割をきちんと認める。すなわち「存在論」<Ontologie>の有用性を、自信をもって言及するにもかかわらず、それが他の実証科学への直接の鍵をあたえるのではなく、ただ「間接的に寄与」するだけなのだ、と謙虚にとらえるのである。
ところで、本節においてのもう一つの読みどころは、エルンスト・カシーラ-についての、活字を小さくした言及文(ドイツ語原文及び邦訳文)であろう。エルンスト・カシーラ-(1874-1945)は、ユダヤ系のドイツの哲学者で、いわゆる新カント学派に属する。「知識の現象学」を基に、シンボル(象徴)としての文化に関する、スケール豊かで明晰な哲学を構築した。ドイツ・イギリス・スウェーデンの各大学で教鞭をとり、最終的にアメリカにわたって、イェール大学とコロンビア大学で教えた。
「ちかごろエルンスト・カシーラ-は、神話的存在を哲学的解釈の主題にしていて、これについては、かれの『象徴的形式の哲学』の第二部『神話的思考』(1925年)参照のこと。この研究によって、もっと包括的な導きの糸が、民俗学的探求に提供されます。哲学的な問題提起から見れば、この解釈の基礎は充分に見通されているのかどうか、とくにカントの『純粋理性批判』の「建築術」とその体系的内容とが一般にこのような課題に対する可能な略図を提供することができるかどうか、あるいはそこに新たな、もっと根源的な手掛りが必要とされていないかどうか、などの疑問が残されています。(略。)」
カントの超越論的観念論を基礎に、独自の「象徴的形式の哲学」を打ち立てたカシーラ-と、ハイデガーは1929年に「ダヴォス討論」を行うけれど、一般的にこの討論は、ハイデガーが勝利したといわれる。
おんとろじーをぷねうまとするうまごやし 須藤 徹