 「ドドメ色って色がどういう色なの?」、こういう質問が成立することをはじめて知りました。
「ドドメ色って色がどういう色なの?」、こういう質問が成立することをはじめて知りました。
 ドドメ色って、「黒紫色」という一つの色を指していると考えるのはおかしいと思います。ドドメは赤いのもあるんです。
ドドメ色って、「黒紫色」という一つの色を指していると考えるのはおかしいと思います。ドドメは赤いのもあるんです。
 ドドメ色って、ドドメが薄赤色から赤色に、そして赤紫色から黒紫へと短い時間の中で変化するドドメの色、その色の変化全体を表現している言葉だと思うんです。
ドドメ色って、ドドメが薄赤色から赤色に、そして赤紫色から黒紫へと短い時間の中で変化するドドメの色、その色の変化全体を表現している言葉だと思うんです。
だから、ドドメを摘んで赤紫色に染まった掌も、ドドメ食べて真っ赤になったベロも、みんなドドメ色、不思議な色なんです…
それから、「月夜野閑話」って優しいブログの挿絵に、ドドメの語源を見っけました。なるほどって思える語源です。
 それと、隠語の世界でドドメの変化する色を、メラニン色素が沈着する女性の身体の一部と重ね合わせて使った人がいて、ドドメ色って「不潔」「汚い」「古い」というようなイメージができているよね。これって、明らかに女性差別だよね…
それと、隠語の世界でドドメの変化する色を、メラニン色素が沈着する女性の身体の一部と重ね合わせて使った人がいて、ドドメ色って「不潔」「汚い」「古い」というようなイメージができているよね。これって、明らかに女性差別だよね…
 毎年ドドメ食べてるヒゲおじさん、ドドメ色って素敵な色だと思うんですけど…、今ドドメが一番おいしい季節です。
毎年ドドメ食べてるヒゲおじさん、ドドメ色って素敵な色だと思うんですけど…、今ドドメが一番おいしい季節です。
 マニハ食品の工場のタイザンボクが大きな、真っ白い花をつけました。
マニハ食品の工場のタイザンボクが大きな、真っ白い花をつけました。
道端のイタドリが花をつけました。これは白だけど、ピンクや赤いのもあるんです。イタドリの花の色もいろいろです。
「イタドリの花の色は白でいいのですね!」
「色が分からなければ、イメージがわきません!」
去年の夏、おじさんは、若い女性に詰問されていました。挙句に…
「道端の植物の名前を知りたいなんて思っているひとは、私の世代にはほとんどいません!」
投げ捨てるように言われました。決して忘れることのないであろう記憶です。
 <困った人がいるんだよね、傷つかいね…>、毛のもようを笑いものにされた朝日町の猫が理解を示してくれました。
<困った人がいるんだよね、傷つかいね…>、毛のもようを笑いものにされた朝日町の猫が理解を示してくれました。
 <………>、石材店の横で出会った黒猫も何か言っていましたが、少し耳が悪いので聞こえませんでした。
<………>、石材店の横で出会った黒猫も何か言っていましたが、少し耳が悪いので聞こえませんでした。
 朝倉田んぼでは、大麦の収穫は終わっていました。間もなく小麦の刈り入れです。
朝倉田んぼでは、大麦の収穫は終わっていました。間もなく小麦の刈り入れです。
おまけに、シソジュース作ったんで…
よく洗った赤シソ一束を2㍑の水で煮ます。必ず茎ごと入れます。15分ほど煮出したらシソを取り出します。
 グラニュー糖1kgとクエン酸30グラムを加えて煮溶かしますます。黒紫色の煮出し液が鮮やかな赤色に変わります。ドドメの逆です。
グラニュー糖1kgとクエン酸30グラムを加えて煮溶かしますます。黒紫色の煮出し液が鮮やかな赤色に変わります。ドドメの逆です。
冷ましてから漉して瓶詰め、保存は冷蔵庫です。
 氷と水で二倍ほどに割って飲みます。さわやか、元気が出ます。これって、紫蘇色…
氷と水で二倍ほどに割って飲みます。さわやか、元気が出ます。これって、紫蘇色…














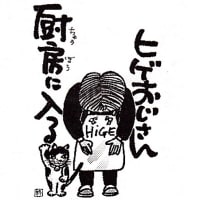
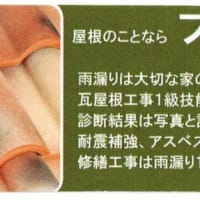


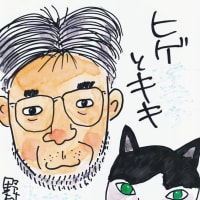
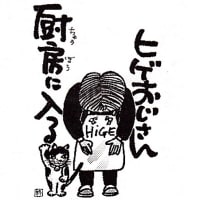
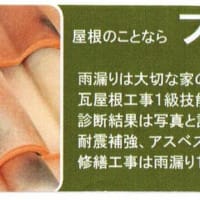



お散歩 の 通りみち に
大きな 白い お花を見せてくれています …
立派な くちなしのお花 と …
ずっと 勘違い。
道端の お花 …
とっても 可愛い ですね。
キキお姉様と同じ模様の猫が雉を狙って、そっと近ずくと、雄鶏がこっちだよと猫を誘い、雌鶏から遠ざけようと、庭の中を歩き回って居ました。猫が諦めて何処かに行ったら、雌鶏が草叢から出て来て、2羽で飛んでいっちゃいました。
仲が好いんですね~~
今年はドドメを食べる小学生が居ないんです、
近所のおば様が「貰っていい」と言って取って行きました。
道端の何気無い花を愛で、童謡を歌い繋ぐのがあたし達アラ還の使命でしょうか?
大蓮寺さんも嘆いてましたが、今の若い子は童謡、唱歌を知らないって。それは親が歌って聞かせなかったせいでもありますね。
美登利会の可愛い姿に癒されました。教えるのも大変でしょうが、こちらも伝承していただきたいものです。
ドドメ色という色名?は聞いたことがあったのですが、
実際どういう色かというのは知りませんでした。
聞いた当時、濁音の強い音感にイメージを支配されて、
まさか果実の色だとは思ってませんでした。
群馬の文化ですね。
今、伊勢崎の上の宮から戻ってきましたが、駒形でとてもおいしいドドメを見っけました。今、青井食堂におすそ分けして、残りは「ひろ子」。今日のは生食です。
おゆきさん
花屋の花以外は花でないと思っている人もいます。食べ物もコンビニ食が最高という人もいます。大変な時代になっちゃいました。
メイ太の母ちゃんさん
上の宮でキジに会いましたよ。
ドドメももらってくれる人がいるだけで幸せだと思います。
タッキーさん
この若い女性は余裕がなかったのではありません。社会に影響を与える立派な職業をお持ちの人でしたから。彼女の確信です。
イタドリはこのあたりではあまり食べません。九州・四国、東北では普通に食べられています。地面から15~20センチになった新芽を地面の中の部分も掘り起こして採取します。ちょうどアスパラみたいです。皮をむいてゆで、一晩水に漬けてあく抜きして食べます。其のままでも、煮たり炒めたり料理法は多様です。
イチゴさん
タイザンボクはアメリカを代表する花の一つです。でも、日本の風景にもとってもよくあう木ですし、花だと思っています。ヒゲクマも好きです。
の食糧を生む大切な桑を河川の護岸用に植えることなど考えられません。桑の苗木は高価なものでした。石垣積みの段々畑は小狭です。狭い畑の中心部はコンニャク、麦、大豆などの栽培場所となり、桑の木は畑の縁に植えられました。ちょうど石垣の近くになりますから、旺盛な根が土留めの役割を果たしたことでしょう。
月夜野閑話のみずぞうです。
ヒゲおじさん・・・ヒゲ園長さんのブログの時から
こっそり拝読させていただいてました^^
こっそりですみません。
リンクありがとうございます。
ドドメの季節になりましたね。
わしも群馬生まれ群馬育ちなので、下校途中の
ドドメのつまみ食いは懐かしい想い出です。
これからもヒゲおじさんとキキちゃんの素敵なブログを楽しみにしております^^
マルベリーか、馴染まないな。やっぱりドドメだな。
絹の里って言えば、頼まれている書類をまだ作ってんないや、作らなくっちゃ、ありがとうです、思い出させてくれて…
みずぞうさん
今年になってから、「月夜野閑話」に時々お邪魔していました。こちらこそすみません。
園長ブログ以来ですか、なんか少し恥ずかしくなります。これからもよろしく。
かおるさん
お蚕様は、多野でも「おこさま」と読んでいましたか?
昨日伊勢崎の上の宮にある倭文(しどり)神社に寄って来ました。稲作と養蚕の神さんとのことです。しどりは、からむしや麻で織った古代布と言われ、文様も定かでない伝説上のものです。
それから、前に遠野に行かせてもらったときに、千体の「おしらさま」を祀ったお堂が「御蚕様堂」という標記で「おしらどう」と読ませていたのに驚きました。
「おこさま」にまつわる話は、不思議です。