
ニッポンでは、事相などに通告される虐待件数がうなぎ登りなのですが、そもそも通報されない、何重にも保育をするようなネグレクトが、非常に多いのです。
ブルース・ペリー教授の The boy who was raised as a dog の第11章、「癒しのやり取り」のp.237の第3パラグラフから。
私どもが人々を教育する必要があると思うのは、赤ちゃんのニーズについてと、赤ちゃんのニーズに、もっと上手に応えることです。私どもは、赤ちゃんと関わる基礎訓練、子どもと関わる基礎訓練をちゃんとやる社会が必要です。そういう社会は、子どもと関わるすべての人が、何をしたらいいのかが分かる社会です。たとえば、コナーみたいに、赤ちゃんが全く泣かなくなったら、それは、その赤ちゃんが大泣きしているみたいに関心を引こうとしているためだ、ということが多いですよ、ということです。子どもの発達段階に見合う行動を理解するようになれれば、子ども達は必要な時に助けてもらえるようにもなりますからね。
かくして、赤ちゃんや子どもの発達についての基礎を学び、訓練することが必要です。それは単なる知的な学習ではありません。倫理を知的に知っていても、倫理的な人間とは限らないのと似ています。
基礎の学びは、ものの見方、心構えから、生活態度に至る迄、の訓練です。それは、フラナリー・オコーナーや大江健三郎さんの言葉で言えば、The habit of being 「生き方の習慣」です。
子どもと関わる時に必要なのは、この「生き方の習慣」です。これを見れば、どの程度の関わりを子どもとしているのか、すぐに分かります。











 みなさん、このまま流されてもいいの? 自分の頭で考えることを諦め、進んで行動する...
みなさん、このまま流されてもいいの? 自分の頭で考えることを諦め、進んで行動する...





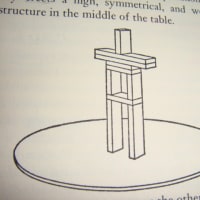






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます