
「裸の王様」として有名なアンデルセン童話は、本当のタイトルは「皇帝の新しい着物」と言います。意外に知られていないかもしれませんね。岩波文庫の赤740-1『完訳 アンデルセン童話集(一)』p.157-165にあります。
ストーリーは有名ですし、その結末も有名ですから、ここで再話しなくてもいいかもしれませんね。そこで、この寓話の意味を要点だけ、メモリアル的に記しておこうと思います。心理学的メモリアルです。
この王様は、「大変着物がお好きな皇帝」と言われます。私は、ファッションにはあまり時間とお金を掛けない主義(貧乏だからだけかもしれません)。でも、ファッションには、ある哲学を感じる場合が少なくないです。むしろ、ある哲学を衣装にしていると言えるのかもしれませんね。でも、この「大変着物がお好きな皇帝」は、いかさま師にやられます。いかさま師は、「言ってること」と「やってること」が違う人ですね。言葉を換えますと、「表側」と「内側」が違う。「表側」の着物は本来、その「内側」と一致する時に、一番輝くと思うのですが、いかさま師にやられる皇帝は、この二つが一致していなかったのじゃぁないかしらね。いかさま師と同じように、「言ってること」と「やってること」が別だった、「表側」と「内側」が別だった。しかも、この皇帝はそのことも分からなかったんだと思います。だからこそ、いかさま師にやられた。いかさま師が言ったウソは、ここで改めて申しません。そのウソを真に受けるほど「表側」と「内側」の一致、ということに、この皇帝は意識が向いておいで出なかった! ですから、見えるはずのない着物が「見えない」、と思っても、「私には着物が見えません」とは言わずに、黙ってた。逆に、心の中とは裏腹の「(その着物は)なかなか見事じゃのう!」と言っちゃった!
いかさま師にマンマとやられて、大枚を巻き上げられた皇帝は、そうとも知らずに裸のマンマで、悦に入っていた。その着物は行幸用、つまり、行列に着る着物でしたから、大勢の人の前に、この皇帝は、裸をさらすことになった。だけど、皇帝は、本当の自分を、ハッキリと認めて、言葉にすることができなかった。
そして、子どもの登場です。先の本には「小さな子ども」と出てきます。その子が、何のてらいもなく「だけど、なんにも着てやしないじゃないの!」とハッキリと言った。本当を子どもが言うんですね。子どもは、「表側」と「内側」が一致している人のことでして、年齢は関係ありません。ですから、単純に見て感じたままを、言葉にした訳ですね。それでも、この皇帝は、裸の行進は止めなかった!
ここから、どんなことを学ぶべきか?
それは、皆さんが考えてくださいね。











 治療的儀式化=新しい儀式化→新たな物の見方・価値の創造2013-07-30 03:06:57 |&n...
治療的儀式化=新しい儀式化→新たな物の見方・価値の創造2013-07-30 03:06:57 |&n...




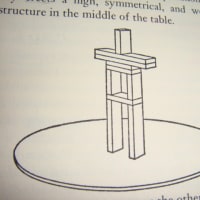











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます