 「北条得宗家の群像」アマゾン電子書籍紹介
「北条得宗家の群像」アマゾン電子書籍紹介「北条執権政治」鎌倉時代,源氏滅後130年間執権北条氏が幕府の実権を握り幕政を左右した体制。源頼朝の死後,北条時政は娘の政子とともに実権の掌握を意図し,将軍頼家の外祖父比企能員を建仁3(1203)に滅亡させ,実朝を将軍として,政所別当となったが,嫡子義時と対立して元久2年(1205)失脚した。これに代って義時が政所別当となり,建保1年 (1213)には和田義盛を滅ぼして侍所別当をも兼任し幕府の実権を握った。同7年,実朝が暗殺されて源氏の正統が絶え,承久の乱 (1221) にも圧倒的勝利で三上皇を隠岐、佐渡、土佐に流して逆賊となって権力をほしいままにした。義時の死後,執権職は嫡子の泰時が継ぎ,以後執権職は北条氏によって世襲されるようになった。泰時は,執権の補佐役として連署の制を始め,嘉禄1年 (1225) 年には評定衆を新設して,重要政務を評議させ,貞永1年 (1232)『御成敗式目』を制定し,執権政治の基礎を固めた。泰時の死後,執権職は経時が引継ぎ,経時がわずか4年で病死したのち,時頼が跡を継いだが,時頼は,幕府中枢機関を北条氏の嫡統の当主である得宗 (とくそう) を中心とする北条氏一門で独占することを意図した。寛元4年(1246)北条時頼が執権となったころから執権政治は変質し始める。時頼は、北条一門の不満分子である名越氏、有力御家人三浦氏、摂家将軍頼経・頼嗣ら反対勢力を次々に排除した。さらに院政を行う上皇(治天(ちてん)の君(きみ))や天皇の決定、摂関の人選をはじめ、朝廷の政治にも干渉した。時頼は執権を退いてのちも得宗として実権を握り、幕府権力の根源は執権よりも得宗に置かれるようになった。元弘3年・正慶2年(1333)後醍醐天皇が隠岐を脱出して伯耆国の船上山で挙兵すると、幕府は西国の倒幕勢力を鎮圧するため、北条一族の名越高家と御家人の筆頭である下野国の御家人足利高氏(尊氏)を京都へ派遣する。4月に高家は赤松則村(円心)の軍に討たれ、高氏は後醍醐天皇方に寝返って、5月7日に六波羅探題を攻略。同月8日、関東では上野国の御家人新田義貞が挙兵し、幕府軍を連破して鎌倉へ進撃する。18日に新田軍が鎌倉へ侵攻すると、22日に高時は北条家菩提寺の葛西ケ谷東勝寺へ退き、北条一族や家臣らとともに自刃した。享年30(満29歳)。










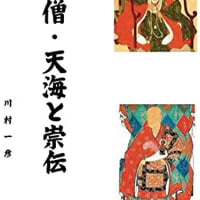

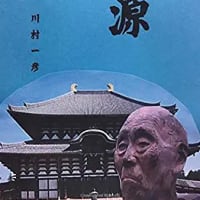
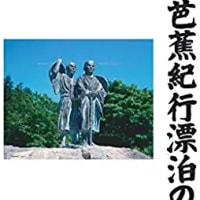
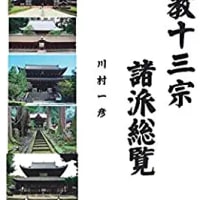
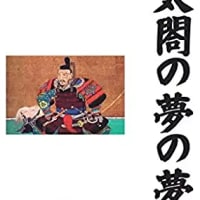
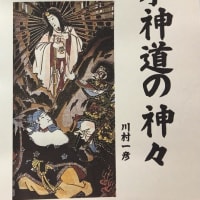
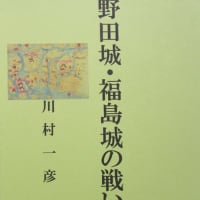
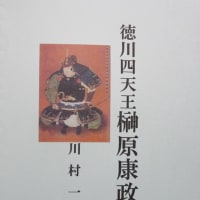
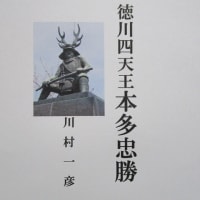
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます