
胡桃といえば「胡桃割る胡桃の中に使はぬ部屋 鷹羽狩行」がよく知られているが、さて皆さんはこの句をどう読むのだろうか。
ぼくは3月から何千という胡桃を割ってきた。その実績でいうと、「胡桃の中に使はぬ部屋」はほとんどない。ほとんど食べられる実体で満たされている。500個割って1個中身が空っぽのやつに遭遇するかどうか……。これは病気とかなにかの不調で実が入らなかったのであろう。したがって鷹羽句は、割ってほじった後の空間に抱いた感慨であると思う。
割った後の殻がつくる空間をいつも精妙に感じる。
なぜ胡桃は入り組んだフィヨルドのような形をよしとするのか……。
運悪くはやく落ちてしまった胡桃をおよそ800個多摩川で拾った。
中身はどうなっているか気になって30個ほど割ってみた。実が黄色のもの、黒いものが多く、正常の白いものが少ない。
写真の上のやつらは白くまあ正常範囲内であるが2段目のやつらは黄色。中がグリースのように粘着性があり口に入れるとなんともいえぬ複雑な味。苦み、えぐみがあり、ぼくはそれが嫌でないので食べるが刺激臭が残ったりする。
刺激臭というのは腐敗に至るものでありこのグリースはべちゃべちゃして腐る率が高い。しかしここから盛り返す黄色もあって水分が抜けて固まると食べられる状態になる。
右端の黒いやつらは黄色よりも実入りが悪く殻との間に隙間が生じてしまい、空気に触れてはやばや酸化したのかもしれない。すかすかですぐ殻から実が離脱する。
黄色いやつと同様味が濃くそれは不可思議な味わい。言葉が追い付かぬ味である。いつか友人に「黒いやつは人間でいえば黒人。おいしいです」といって胡桃を贈ったことがある。それは酸化したのではなく殻に実がずっしり満ちていた。よって酸化でなくて黒いのではないかと思っている。
それししても胡桃は外観もまちまちであるし中身もいろいろ。宇宙が凝縮されている。
小学1年生の孫の夏休みの宿題に「朝顔観察」があるのだそうだ。
そういう与えられたみんな同じ課題でいいのかなあ。ぢぢが胡桃を割るのを見て何かできないのか。俺はもしかして教師に向いていたのかもしれないと思う。










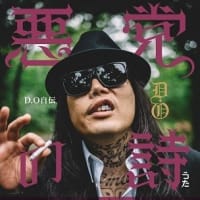



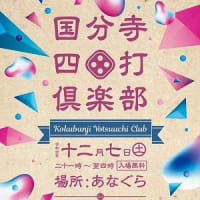
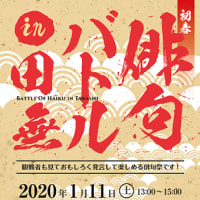


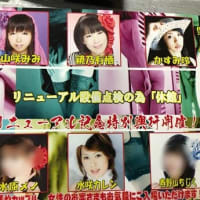

「ジャワ原人」と「北京原人」チームに別れて、木登りしたり、土器を作ったり、火を起こして芋を焼いたり、野生の実を採りに行きました(女子は私ひとりでした…)。
わたる先生は、そのときのクラブ顧問の先生にとてもよく似ています。
私が卒業して6年後、体育館裏でボヤ騒ぎがあり、廃部になったそうです…。先生も別の小学校へ行かれて、それっきりです。
ぜひ、「原人クラブ」を復活させて欲しいです😇
桑の実も、途中で先生におまかせしてしまったのは、この悪い癖が出てしまったからだと思います。申し訳ないです…💧
土器は作れるので…器だけ用意して先生の収穫を待ちたいと思います。