
晩秋の紫陽花に老いて艶ある岡田茉莉子を感じる。紫陽花は長持ちする花であり紫陽花といえばこの句を必ず思う。
紫陽花に秋冷いたる信濃かな 杉田久女
季重なりの秀句である。
紫陽花といえば必ずこの句を思うといったが主季語は「秋冷」であり歳時記のそこに収録されている。紫陽花の花期は梅雨時であるが花から色が抜けても花は散らずに秋、冬に至る。花びらに見えるものは萼(がく)であるからだろう。こういう花のありようゆえ「紫陽花に秋冷いたる」が実に的確なのである。下五に置いた「信濃」も絶妙。
久女が信濃へ旅をしたときの句と言われる。鹿児島生れではじめて信州へ来た久女は高山と晩秋の冷えに驚いだであろう。「秋冷」なる季語は高山を背景に空気が乾いて冷える土地柄のもの。東京の「秋冷」はなまぬるい。地名から見ても「信濃」は抜群の効き目となっている。
季重なりの秀句、わが鷹俳句会では以下の句を揚げたい。
交む蛇見しゆゑ夕焼ながかりき 小浜杜子男
橇の子を呼びとめてゐる春着の子 同
橇の子を呼びとめてゐる春着の子 同
久女の句は迷わず「秋冷」に分類されるが、小浜句のほうは少し考える。
『季語別鷹俳句集』では後出の「夕焼」「春着」の句として収録していてそれは妥当だが、「蛇」と「夕焼」、「橇の子」と「春着の子」の軽重関係はほぼ対等。季節も同じ中での季重なりである。ふつう二つの季語を配す場合、軽重を必ず意識する。小浜杜子男もむろんそれは承知していて敢えて互角の季語を正面衝突させたことにいまでも驚嘆している。
季重なりで句をなす難度をいえば久女を上回るかもしれぬ。
ちなみに季重なりについて月刊『俳句』11月号の第65回角川俳句賞の選考座談会において興味深い議論がなされた。
問題の句は
蜘蛛の脚二三欠けをり冬近し 小野あらた
についてである。受賞作でないのに選考委員3人がえらく論じていて小生も興味を持った。
小澤 <蜘蛛の脚二三>は季語を<蜘蛛>だけでやってはいけないのでしょうか。
と疑問を呈すると、
岸本 晩秋の<蜘蛛>として私は鑑賞しました。夏の季語でもいいのですが、哀れな感じを出すために「秋の蜘蛛」としたかったんだろう。
こう原句を擁護すると、
正木 では、「秋の蜘蛛」として、<冬近し>をやめればいいのかな。
と発展させる。すると、
岸本 <冬近し>を入れることによって背景の空気感が出ますので、無駄ではないと思います。
ぼくは小澤さんが一物で決着せよというのは理解できるが、それはハードルが高い。
岸本さんの鑑賞に納得し、正木さんが提案する「秋の蜘蛛」は拒否したい。「秋の蜘蛛」を安易に許すと「秋の髪」も「秋のペン」も通用することになりそれは俳句の堕落に通じる。
季重なりは、蜘蛛と離して別の季語を立てそれを主季語とした小野さんの作り方でいいと思う。
いずれにせよ二つの季語を一句に入れるには細心の注意が必要だろう。










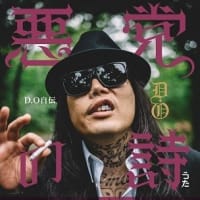



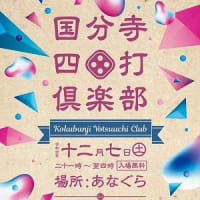
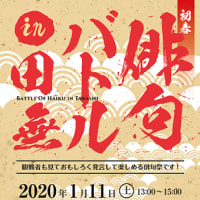


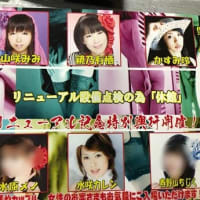

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます