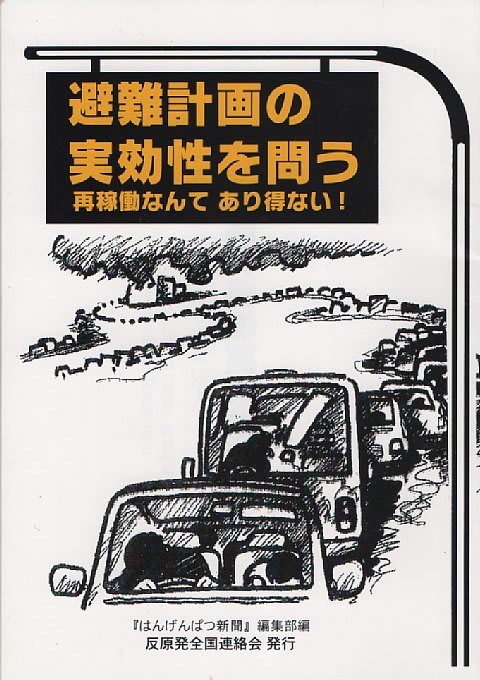
9月23日に反原発運動全国連絡会から原子力防災をテーマにしたパンフ「避難計画の実効性を問う」が発行された。
紹介が遅れたが、来月2、3日には志賀原発での原子力防災訓練も予定されているので、ぜひご一読いただければと思う。
このパンフは2部構成になっており、第一部は各地の原子力防災計画に共通する問題点について解説してある。
第二部は各立地地域固有の避難計画の問題点に取り上げている。
志賀原発については私が書いている。
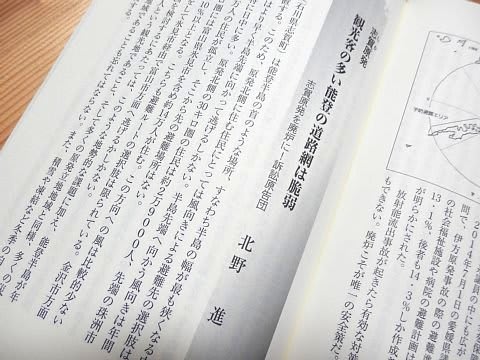
行きどまりとなる半島先端部、冬季の避難対策、災害時要援護者対策、限られた避難道路など問題は山積しているが、編集部は観光客に着目したタイトルをつけてくれた。
このパンフはタイトルにもあるように原子力防災計画の実効性を問うもので、結論として全く実効性などないということだが、実効性を高めるために防災訓練の準備に取り組んでいる各自治体はじめとした防災関係者の方に以下申し上げたい。
国の原子力災害対策指針では過酷事故は起こりうるとする。
それに備えた防災計画を策定するが、それは3.11前と違って住民の被ばくは避けられない、できる限り被ばくを低減するという中身となっている。
そこで端的に過酷事故に対する原子力防災の限界を指摘しておきたい。
1.実効性を高めると言っても、住民の被ばくをより低減するという意味での「実効性」だということ。
2.運よく急性放射線障害を発症する被ばく線量を下回っても、低線量の被ばくは避けられないから、住民はガンをはじめとした晩発性放射線障害のリスクは避けられないこと。
3.仮に計画通り、被曝線量を低減して逃げることができても、家や田畑、山林などの不動産は持って行きようがないということ。もちろん漁業者も漁場を抱えて逃げることはできない。
4.つまり、仕事、生活、財産、コミュニティを守れる防災計画ではないということ。
(後は金銭補償となるが、そこは東電や国の被害者への対応から学ぶこと大である)
5.避難という事態は生命・健康という人格権の侵害であり、あわせて重大な財産権の侵害である。
発電手段の一つでしかない原発、しかも原発なしでも電力供給に支障はなにのに、なぜこのような万に一つもあってはならない原発事故に備えなければならないのか。
能登半島は年間入込700万人という観光地である。
住民すら被ばくなしでは逃げられない。観光客が優先で逃げられるはずもない。
ちなみに防災計画では、不特定多数の者が利用する施設の管理者は「避難誘導に係る計画の作成、及び訓練の実施に努めるものとする」と努力義務どまりである。
そんなリスクのあるところに観光客を呼ぶという発想はどう考えても異常である。
まして来年3月14日には北陸新幹線金沢開業を迎え、さらに観光客の増加を目指しているのに矛盾も甚だしい。
もういい加減、自治体関係者は目の前の事態を普通の感覚で捉えなおした方がいい。
3.11までは、原発の賛否に係らず原発が存在するという前提で原発防災を考えなければならなかった。
いま、私たちは原発なしで暮らしているという現実から原発防災を考え直すべきだ。
自治体関係者は原子力防災計画の実効性を高める努力よりも、原発を再稼働させない行動を私たちとともしてほしい。
もちろん、原発は停止していても核燃料がある限り危険は伴う。
原発サイト内にある核燃料や使用済み燃料のリスクを減らすため、速やかに乾式貯蔵に変更し、より自然災害のリスクの少ない場所に移すよう北電はじめ全原発事業者に求めるべきだ。
その上で、韓国や中国、台湾の原発事故に対する防災計画が必要との認識で一致するなら、脱原発の国際連帯と並行し、対策を考えていきたい。










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます