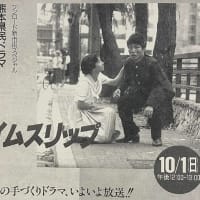2007年7月29日にスタートした住民ディレクターNewsは ひと、光る。ドラマ発見 イキイキと生きる普通の人々のNewsをお伝えしてきました。その発信の源は住民ディレクターを発案し1996年4月から住民ディレクター養成、番組づくりを通して総合的な企画力を養い地域の活性化に貢献することを主目的とした活動をはじめたことでした。その後有限会社プリズムとして起業しました。現在は株式会社です。
熊本県山江村で住民ディレクターのモデルを村民の皆さんと共に創り、九州から、アットランダムでしたが徐々に東上し、現在では岩手県までの約30地域に伝播し、様々なカタチで地域づくりの手法として動いています。
当初はパブリックアクセスやメディアリテラシーという市民メディアとして注目され、全国から新しいメディアを模索する人々が多く訪ねてきました。わたしが熊本の民放で14年間、報道・制作現場に身をおき、地域興し番組や住民手作りドラマなどを数多く手がけ、住民ディレクター番組もすぐに民放で(在籍した局ではなかった)の放送を実現したことが関心を集めたと考えます。
実際、この住民ディレクター番組を視察され、制作の手法、プロセスを現場で見られた多くのテレビ経験者が「目から鱗」ということばを発せられるのを聞きました。そして全国で富山の民放をはじめケーブルテレビなどで多くの住民参加番組が生まれました。このへんからわたしの全国行脚のスピードが速まりました。
わたしは最初からずっと話してきましたが住民ディレクターを始めたのはまちづくりを目的としていました。ですから「番組はオマケ」でした。番組が目的となると14年間やっていたことと同じく発信することに追われ、何のために発信するかを失います。まちづくりのために発信する情報をいかに創造するか?その情報が嘘をつかない、過大な表現にならない、できるだけありのままの情報として伝わり、受け取った方々に情報の実体に触れ安心、信頼してもらえる「情報発信」を目指していました。
市民メディアという切り口でも住民ディレクターは語れますが、番組が目的の市民メディアはわたしにとってはマスコミと同じに見えます。実際わたしのように元々マスコミにいた方々はやはりマスコミの中で時間に迫られた状況でずっと鍛えられてきたので、一人一人の市民の日常や身幅に合った活動を継続的に創って行くという地味な仕事は苦手な方が多かったようでした。わたしはというと5年余りかけて当時の熊本県内98市町村を2周半するというのんびりした取材生活もできていたのです。勿論、これを実践するための莫大なエネルギーは必要ではあったのですが・・・。
最近、わたしは福岡県の東峰村の皆さんと地域SNSで5時間ライブを企画、発信しました。全国の住民ディレクターのみなさんの協力のもとで6間中継でした。しかし番組の中味は基本的には13年前の山江村の番組づくりと何も変わってません。使うメディアがITの進化で大きく変わったので変わったように見えるだけで番組の現場はほとんど「山江村」です。
目的は地域づくりです。
これまでこの目的を一貫して活用してきたメディアはケーブルテレビ、民放、インターネットTV、衛星放送、ストリーミング配信、ネットテレビ電話、ネットテレビ会議室、携帯電話、ブログ、地域SNS、ネットライブ配信等です。
活用してきた現場は農業、生涯教育、地域振興、商店街、福祉、漁業、学校教育、IT、林業、離島、伝統産業、医療、企業などなどほとんどの分野に入りました。
参加していただいた住民の皆さんは6歳から80歳まで老若男女です。
活動主体は自治体、住民の任意グループ、NPO、企業、財団、任意団体など様々です。
こうして書いてくると見えるはずですが、全部集めて一望してもらうと住民ディレクターは「地域」全体を守備範囲にすべてのメディアを使い切る人々の活動として俯瞰できるでしょう。しかもまた全く違う主体がリードしている様々な活動です。
さて、住民ディレクターは13年間実に様々な方々に出会い、地域に出会いました。1回の講演で終わってしまった地域もありますが、わたしの知らないところではじまっている地域も多くあるようです。実際ネットで検索してみればよくわかります。良いも悪いもなくそれはうれしいことです。
しかし、わたしは「住民ディレクター」という呼称ににこだわってはいません。スタート当時はテレビ局で活躍する通信員さんや、住民のリポーター、ビデオカメラマンの皆さんと混同されることが多かったので(ここも良い悪いは関係なく)目的は地域づくりであることを明確にするために「住民ディレクター」という呼称をあえてつけたということはありました。なぜかというとどうしても「番組が物差し」になりやすかったからです。オマケなので番組の質は20年間は問わないと考え、スタートしたのが住民ディレクターなのです。
しかし、時代はわたしが予想したよりは随分早く来ました。
つづく・・・。
熊本県山江村で住民ディレクターのモデルを村民の皆さんと共に創り、九州から、アットランダムでしたが徐々に東上し、現在では岩手県までの約30地域に伝播し、様々なカタチで地域づくりの手法として動いています。
当初はパブリックアクセスやメディアリテラシーという市民メディアとして注目され、全国から新しいメディアを模索する人々が多く訪ねてきました。わたしが熊本の民放で14年間、報道・制作現場に身をおき、地域興し番組や住民手作りドラマなどを数多く手がけ、住民ディレクター番組もすぐに民放で(在籍した局ではなかった)の放送を実現したことが関心を集めたと考えます。
実際、この住民ディレクター番組を視察され、制作の手法、プロセスを現場で見られた多くのテレビ経験者が「目から鱗」ということばを発せられるのを聞きました。そして全国で富山の民放をはじめケーブルテレビなどで多くの住民参加番組が生まれました。このへんからわたしの全国行脚のスピードが速まりました。
わたしは最初からずっと話してきましたが住民ディレクターを始めたのはまちづくりを目的としていました。ですから「番組はオマケ」でした。番組が目的となると14年間やっていたことと同じく発信することに追われ、何のために発信するかを失います。まちづくりのために発信する情報をいかに創造するか?その情報が嘘をつかない、過大な表現にならない、できるだけありのままの情報として伝わり、受け取った方々に情報の実体に触れ安心、信頼してもらえる「情報発信」を目指していました。
市民メディアという切り口でも住民ディレクターは語れますが、番組が目的の市民メディアはわたしにとってはマスコミと同じに見えます。実際わたしのように元々マスコミにいた方々はやはりマスコミの中で時間に迫られた状況でずっと鍛えられてきたので、一人一人の市民の日常や身幅に合った活動を継続的に創って行くという地味な仕事は苦手な方が多かったようでした。わたしはというと5年余りかけて当時の熊本県内98市町村を2周半するというのんびりした取材生活もできていたのです。勿論、これを実践するための莫大なエネルギーは必要ではあったのですが・・・。
最近、わたしは福岡県の東峰村の皆さんと地域SNSで5時間ライブを企画、発信しました。全国の住民ディレクターのみなさんの協力のもとで6間中継でした。しかし番組の中味は基本的には13年前の山江村の番組づくりと何も変わってません。使うメディアがITの進化で大きく変わったので変わったように見えるだけで番組の現場はほとんど「山江村」です。
目的は地域づくりです。
これまでこの目的を一貫して活用してきたメディアはケーブルテレビ、民放、インターネットTV、衛星放送、ストリーミング配信、ネットテレビ電話、ネットテレビ会議室、携帯電話、ブログ、地域SNS、ネットライブ配信等です。
活用してきた現場は農業、生涯教育、地域振興、商店街、福祉、漁業、学校教育、IT、林業、離島、伝統産業、医療、企業などなどほとんどの分野に入りました。
参加していただいた住民の皆さんは6歳から80歳まで老若男女です。
活動主体は自治体、住民の任意グループ、NPO、企業、財団、任意団体など様々です。
こうして書いてくると見えるはずですが、全部集めて一望してもらうと住民ディレクターは「地域」全体を守備範囲にすべてのメディアを使い切る人々の活動として俯瞰できるでしょう。しかもまた全く違う主体がリードしている様々な活動です。
さて、住民ディレクターは13年間実に様々な方々に出会い、地域に出会いました。1回の講演で終わってしまった地域もありますが、わたしの知らないところではじまっている地域も多くあるようです。実際ネットで検索してみればよくわかります。良いも悪いもなくそれはうれしいことです。
しかし、わたしは「住民ディレクター」という呼称ににこだわってはいません。スタート当時はテレビ局で活躍する通信員さんや、住民のリポーター、ビデオカメラマンの皆さんと混同されることが多かったので(ここも良い悪いは関係なく)目的は地域づくりであることを明確にするために「住民ディレクター」という呼称をあえてつけたということはありました。なぜかというとどうしても「番組が物差し」になりやすかったからです。オマケなので番組の質は20年間は問わないと考え、スタートしたのが住民ディレクターなのです。
しかし、時代はわたしが予想したよりは随分早く来ました。
つづく・・・。