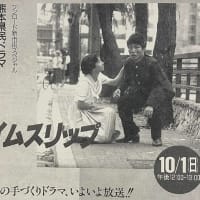地域を変えるとはどういうことか?昨年1年間はこの課題が各地で起こっていました。全体的に時代がそういうところに来たと感じます。このことは30歳代前半からずっと考えてきました。しかしいつもある地点へ舞い戻ります。「所詮こんなものだな、世の中は。」
20歳代後半にテレビ局で仕事をするようになってから実に多くの人に会ってきました。全国からやってくる凄い人といわれるひと、変わった人といわれるひと、作家や科学者から市民運動家や芸能人まで随分と幅広くお会いできました。興味をもって追いかける人も確かに多くいました。そして大きなカメラをかかえて取材をスタートします。ニュース企画、ドキュメンタリーのはじまりです。しかし、ほとんどの方は1年2年と付き合うと興味を失います。嘘が見えるからです。嘘ではなくても頑張って虚像を作りつづけているのがわかるからです。わたしが追い掛けるというのはとことんいきます。酒も飲みますが、自宅にも行きます。いろんなところにお付き合いしその方の全体を見ようとしました。
しかしこちらにも大きな課題がありました。「見ようとする」と書きましたが、やはりどこかでカメラのレンズを通して相手を見る癖がついていっているのです。カメラをもっていないと付き合えない職業病のような状態になってしまいます。逆にカメラがないときの自分がとても小さく感じていました。スタッフのカメラマンをみていてそれはすぐに気づいたのです。カメラを持っているときの「取材対象」である人々への対応と、取材が一段落してから「一人の人間になった」ときのおとなしい姿が驚くほど変わってしまうのです。ジキルとハイドのようです。しかしこれがまさにテレビ局の人間の限界であり、前回書いた他人事のように番組を作ってしまう癖になっていきます。レンズや画面を通してしか人と付き合えない人間になりやすいのです。
「地域を変える」ということは取材で成るものではないことをこの頃から感じていました。一緒に考え、行動する。勿論、その地元で生きるわけではありませんから、「すべて一緒に」などできません。ただ「自分が変わる」ことなくして地域を変えることはできないということは感じとしてわかっていました。自分が変わるためにも先人や先哲に学び現代に生きる「そのような人」を探していました。
一方で有名無名を問わず多くの方々とお付き合いして行く中で次第に失望感が深まっていきました。1,2年もするとどの方からも魅力を感じなくなってしまう自分がいました。
その頃です、いだきしん氏と出会ったのは。
会場に来られた方一人一人の生命の状態や土地の風土、歴史をそのまま受け即興でピアノ演奏する、ピアノのある一音が内臓感覚に響き、他の音も経験的練習を積み即興演奏が可能になった。などと書かれているコンサートのチラシを読んでもさっぱり意味がわかりませんでした。しかもこの人が日本で初めての機能を持った特別養護老人ホームを作った人でした。デイケアやショートスティ、入浴サービスも実践の中から創られた介護のシステムでした。
そこでいつものようにニュース企画で取材をすることにしました。熊本の県立劇場でのコンサートを前に北九州に来られるということで、小倉の会場にお邪魔しました。リハーサル中にお邪魔しましたが「リハーサルではない」との事でした。即興なのでいつも本番であること、生きること自体もともとみな即興なので「今、この時」の表現しかない、などのお話はその人物から発せられることばの独特の響きもあり、内心「只者ではない人」だ、とすぐに感じました。
一般的には「リハーサル」といわれるピアノ演奏を終え、インタビューの時間になりました。この時の一言一言はほとんど覚えていませんが、ずっと自分の中にあった状態は今でもはっきりと覚えています。わたしが質問し、答がはじまりますと「えっ?」とまず感じます。そして「うかがっていることはそういうことではなくて・・・」と口に出そうになります。しかし、我慢して聞いていると「なるほどなるほど、よくわかりました、そういうことですね。」となります。そこで、次に関連して「ところでそれならこういうことはどうでしょう?」というようにうかがいます。するとまた「えっ?」となります。・・・、しかし、聞いていると先ほどと同じように「なるほど」、となります。だんだん「なるほど」が深まっていくのを感じます。実に何回これを繰り返したでしょう!?
はじめての経験でした。今までこんなにわかりにくく、またこんなにわかりやすい話を聞いたことはありません。気づけば時間がない中1時間以上インタビューしているということになってしまいました。随分たってからお聞きしましたが、いだきしん氏のほうも「あれほどしつこく聞いてきた記者やディレクターはいなかったので面白かった」ということでした。
この時は、「不思議なピアノ」というタイトルでニュース企画にしましたが、しばらくして熊本でコンサートがあり取材ではなく一個人として行きました。北九州でお話をうかがった時、この人はレンズを通して「見ていて」は理解できない人だと直観的に感じたのです。コンサートを観客として経験して、いよいよわたしの本格的な追っかけがはじまりました。・・・つづく
(写真は4/5鹿児島で開催されたコンサートのチラシ「桜島」:撮影はいだきしん氏)
いだきしんコンサート
京都コンサートホール大ホール
2009年 4/26(日) 14:30開場 15:00開演
全席指定 S6000円(完売) A5000円
主催 特定非営利活動法人 高麗 (NPO KOMA)
いだきしんコンサート案内 http://www.idaki.co.jp/idakishinConcert/index.html
いだきしんプロフィール http://www.idaki.co.jp/aboutus/profile.html
いだきしん平和コンサートの歩み http://www.idaki.co.jp/worldConcert/others/index.html
◎お問い合わせは
岸本 晃メルアド prism.k@nifty.com まで
*現在 prismの ホームページは新たに制作中です。時間がかかりますので初めての方は上記メルアドにお願いします。
20歳代後半にテレビ局で仕事をするようになってから実に多くの人に会ってきました。全国からやってくる凄い人といわれるひと、変わった人といわれるひと、作家や科学者から市民運動家や芸能人まで随分と幅広くお会いできました。興味をもって追いかける人も確かに多くいました。そして大きなカメラをかかえて取材をスタートします。ニュース企画、ドキュメンタリーのはじまりです。しかし、ほとんどの方は1年2年と付き合うと興味を失います。嘘が見えるからです。嘘ではなくても頑張って虚像を作りつづけているのがわかるからです。わたしが追い掛けるというのはとことんいきます。酒も飲みますが、自宅にも行きます。いろんなところにお付き合いしその方の全体を見ようとしました。
しかしこちらにも大きな課題がありました。「見ようとする」と書きましたが、やはりどこかでカメラのレンズを通して相手を見る癖がついていっているのです。カメラをもっていないと付き合えない職業病のような状態になってしまいます。逆にカメラがないときの自分がとても小さく感じていました。スタッフのカメラマンをみていてそれはすぐに気づいたのです。カメラを持っているときの「取材対象」である人々への対応と、取材が一段落してから「一人の人間になった」ときのおとなしい姿が驚くほど変わってしまうのです。ジキルとハイドのようです。しかしこれがまさにテレビ局の人間の限界であり、前回書いた他人事のように番組を作ってしまう癖になっていきます。レンズや画面を通してしか人と付き合えない人間になりやすいのです。
「地域を変える」ということは取材で成るものではないことをこの頃から感じていました。一緒に考え、行動する。勿論、その地元で生きるわけではありませんから、「すべて一緒に」などできません。ただ「自分が変わる」ことなくして地域を変えることはできないということは感じとしてわかっていました。自分が変わるためにも先人や先哲に学び現代に生きる「そのような人」を探していました。
一方で有名無名を問わず多くの方々とお付き合いして行く中で次第に失望感が深まっていきました。1,2年もするとどの方からも魅力を感じなくなってしまう自分がいました。
その頃です、いだきしん氏と出会ったのは。
会場に来られた方一人一人の生命の状態や土地の風土、歴史をそのまま受け即興でピアノ演奏する、ピアノのある一音が内臓感覚に響き、他の音も経験的練習を積み即興演奏が可能になった。などと書かれているコンサートのチラシを読んでもさっぱり意味がわかりませんでした。しかもこの人が日本で初めての機能を持った特別養護老人ホームを作った人でした。デイケアやショートスティ、入浴サービスも実践の中から創られた介護のシステムでした。
そこでいつものようにニュース企画で取材をすることにしました。熊本の県立劇場でのコンサートを前に北九州に来られるということで、小倉の会場にお邪魔しました。リハーサル中にお邪魔しましたが「リハーサルではない」との事でした。即興なのでいつも本番であること、生きること自体もともとみな即興なので「今、この時」の表現しかない、などのお話はその人物から発せられることばの独特の響きもあり、内心「只者ではない人」だ、とすぐに感じました。
一般的には「リハーサル」といわれるピアノ演奏を終え、インタビューの時間になりました。この時の一言一言はほとんど覚えていませんが、ずっと自分の中にあった状態は今でもはっきりと覚えています。わたしが質問し、答がはじまりますと「えっ?」とまず感じます。そして「うかがっていることはそういうことではなくて・・・」と口に出そうになります。しかし、我慢して聞いていると「なるほどなるほど、よくわかりました、そういうことですね。」となります。そこで、次に関連して「ところでそれならこういうことはどうでしょう?」というようにうかがいます。するとまた「えっ?」となります。・・・、しかし、聞いていると先ほどと同じように「なるほど」、となります。だんだん「なるほど」が深まっていくのを感じます。実に何回これを繰り返したでしょう!?
はじめての経験でした。今までこんなにわかりにくく、またこんなにわかりやすい話を聞いたことはありません。気づけば時間がない中1時間以上インタビューしているということになってしまいました。随分たってからお聞きしましたが、いだきしん氏のほうも「あれほどしつこく聞いてきた記者やディレクターはいなかったので面白かった」ということでした。
この時は、「不思議なピアノ」というタイトルでニュース企画にしましたが、しばらくして熊本でコンサートがあり取材ではなく一個人として行きました。北九州でお話をうかがった時、この人はレンズを通して「見ていて」は理解できない人だと直観的に感じたのです。コンサートを観客として経験して、いよいよわたしの本格的な追っかけがはじまりました。・・・つづく
(写真は4/5鹿児島で開催されたコンサートのチラシ「桜島」:撮影はいだきしん氏)
いだきしんコンサート
京都コンサートホール大ホール
2009年 4/26(日) 14:30開場 15:00開演
全席指定 S6000円(完売) A5000円
主催 特定非営利活動法人 高麗 (NPO KOMA)
いだきしんコンサート案内 http://www.idaki.co.jp/idakishinConcert/index.html
いだきしんプロフィール http://www.idaki.co.jp/aboutus/profile.html
いだきしん平和コンサートの歩み http://www.idaki.co.jp/worldConcert/others/index.html
◎お問い合わせは
岸本 晃メルアド prism.k@nifty.com まで
*現在 prismの ホームページは新たに制作中です。時間がかかりますので初めての方は上記メルアドにお願いします。