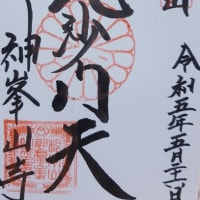可憐な八重桜がとても美しかった兵主神社から、
30分ほど車を走らせ石龕寺という古刹へ。
昔でいう丹波国の神社仏閣は新しい発見や、
無名な神社であっても神域感を感じて感動することも多く、
参拝していてとても楽しい。
自宅からもうちょっと丹波が近ければなぁ、
と思うことしばしば。
この石龕寺も丹波古刹十五ヶ寺霊場の札所だし、
参拝するのがとても楽しみです。
所在地:兵庫県丹波市山南町岩屋2番地
宗派:高野山真言宗
御本尊:聖観音菩薩
創建:(伝)用明天皇2年(587)
開基:(伝)聖徳太子
札所:丹波古刹十五ヶ寺霊場、氷上郡西国霊場
【縁起】

用明天皇の丁未の年である587年、
聖徳太子による創建と伝えられる。
聖徳太子が深く帰依した毘沙門天を本尊とする。
鎌倉時代から室町時代に隆盛を極める。
寺号の龕とは仏像等を安置する厨子や壁面の窪みを意味する。
本堂から山上約800mに奥の院があり、
その石窟が石龕寺の寺号の由来となっている。
南北朝・室町時代に入ると、
丹波国井原庄の石龕寺の修験者達の活動が知られるようになる。
中世末期の戦国時代には織田信長(明智光秀)の丹波攻略を受け、
1579年(天正7年)には兵火により全山ことごとく焼失、
仁王門を残すのみとなる。
江戸時代以降に徐々に復興。
以来、歴代の住職、檀信徒達の尽力により、
奥の院、毘沙門堂、鐘楼堂、持仏堂、庫裏、客殿等が再建された。
境内には紅葉が多く、毎年11月第3日曜日には、
もみじ祭りが催され護摩供養、武者行列等の行事が催され、
多くの参拝客で賑わいを見せる。
【風景】

凄く長閑です。
あの桜の場所が下の無料駐車場です。
【桜】


駐車場の桜も綺麗でした。(^^
【鐘楼堂】

うん?
何やら山に何か見える。

ズームアップして見ると、
あれは鐘楼堂ではないか!
何故あんな所に鐘楼堂が?
あんなのがあるとは全く知らなかった。(^^;
しかし、ドえらい場所にあるなぁ。
あそこまで登るには靴とか心構えが必要なんだが、
何にも用意していない。
うーむ、靴もペラペラだしなぁ。
...
熟考すること3秒・・・
うん、見なかったことにしよう。(^^;
そう思いながらお寺を探す。
ここの駐車場からはお寺がどこにあるのか分からない。
山の中の鐘楼堂もたまたま見つけただけだし。
案内板が無くて困ったが、
とりあえず車で進むと仁王門を発見。(^^
【仁王門】

仁王門の手前に5,6台停めれる無料駐車場がありました。
どうやら下の駐車場は秋のもみじ祭の時に使われるようです。
また、その時は入山料300円が必要になります。
【仁王像】


定慶作の重要文化財。
定慶作ってマジか?
こんな所でビッグネームの仏師の仁王像が見れるとは。
【参道】

【修行大師】

【磨崖仏】



【案内板】
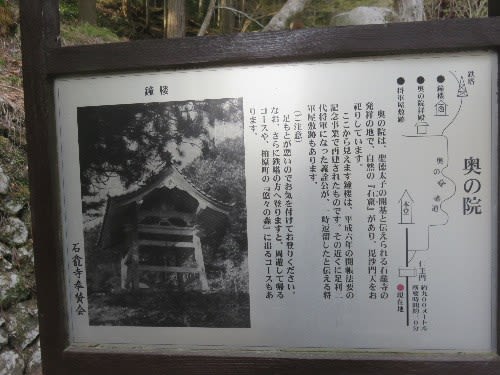
あー、あの鐘楼堂がある場所が奥の院だったのか。
うん、見なかったことにしよう。(コピペ)
【地蔵菩薩】

【水琴窟】

石段を登ると庫裏の前にありました。
どこの水琴窟も音色は変わりませんね。(^^
【参道】


秋になるとこの辺りの紅葉が見事なようです。
【本堂】


残念ながら本堂は閉まっていました。

横からみると少しくたびれた感がありますね。
【不動明王】

【石標】

左が行者さん、右が奥の院。
うん、見なかったことにしよう。(コピペ)
【参道】

行者さん行き。

奥の院行き。
約800メートルかぁ。
山の道の800メートルは舐めてはいけません。
えーえーえー、
勿論、行きませんとも。(^^;
【七福神】

【薬師堂】

以前の薬師堂は素朴で小さなお堂でしたが、
近年建て替えられたらしく、綺麗な新品同様のお堂でした。
【参道】

こんな道を進んで行く。
【境内社】


【境内】

薬師堂と本堂です。
【焼尾神社】


雪害から守る為に覆屋で守られていますね。

鎮守として市杵島比売命が祀られているとのこと。
【蔵】

【御朱印】


御不在でしたので書置きを二体いただきました。
御本尊聖観音菩薩の御朱印は無いようですね。
30分ほど車を走らせ石龕寺という古刹へ。
昔でいう丹波国の神社仏閣は新しい発見や、
無名な神社であっても神域感を感じて感動することも多く、
参拝していてとても楽しい。
自宅からもうちょっと丹波が近ければなぁ、
と思うことしばしば。
この石龕寺も丹波古刹十五ヶ寺霊場の札所だし、
参拝するのがとても楽しみです。
所在地:兵庫県丹波市山南町岩屋2番地
宗派:高野山真言宗
御本尊:聖観音菩薩
創建:(伝)用明天皇2年(587)
開基:(伝)聖徳太子
札所:丹波古刹十五ヶ寺霊場、氷上郡西国霊場
【縁起】

用明天皇の丁未の年である587年、
聖徳太子による創建と伝えられる。
聖徳太子が深く帰依した毘沙門天を本尊とする。
鎌倉時代から室町時代に隆盛を極める。
寺号の龕とは仏像等を安置する厨子や壁面の窪みを意味する。
本堂から山上約800mに奥の院があり、
その石窟が石龕寺の寺号の由来となっている。
南北朝・室町時代に入ると、
丹波国井原庄の石龕寺の修験者達の活動が知られるようになる。
中世末期の戦国時代には織田信長(明智光秀)の丹波攻略を受け、
1579年(天正7年)には兵火により全山ことごとく焼失、
仁王門を残すのみとなる。
江戸時代以降に徐々に復興。
以来、歴代の住職、檀信徒達の尽力により、
奥の院、毘沙門堂、鐘楼堂、持仏堂、庫裏、客殿等が再建された。
境内には紅葉が多く、毎年11月第3日曜日には、
もみじ祭りが催され護摩供養、武者行列等の行事が催され、
多くの参拝客で賑わいを見せる。
【風景】

凄く長閑です。
あの桜の場所が下の無料駐車場です。
【桜】


駐車場の桜も綺麗でした。(^^
【鐘楼堂】

うん?
何やら山に何か見える。

ズームアップして見ると、
あれは鐘楼堂ではないか!
何故あんな所に鐘楼堂が?
あんなのがあるとは全く知らなかった。(^^;
しかし、ドえらい場所にあるなぁ。
あそこまで登るには靴とか心構えが必要なんだが、
何にも用意していない。
うーむ、靴もペラペラだしなぁ。
...
熟考すること3秒・・・
うん、見なかったことにしよう。(^^;
そう思いながらお寺を探す。
ここの駐車場からはお寺がどこにあるのか分からない。
山の中の鐘楼堂もたまたま見つけただけだし。
案内板が無くて困ったが、
とりあえず車で進むと仁王門を発見。(^^
【仁王門】

仁王門の手前に5,6台停めれる無料駐車場がありました。
どうやら下の駐車場は秋のもみじ祭の時に使われるようです。
また、その時は入山料300円が必要になります。
【仁王像】


定慶作の重要文化財。
定慶作ってマジか?
こんな所でビッグネームの仏師の仁王像が見れるとは。
【参道】

【修行大師】

【磨崖仏】



【案内板】
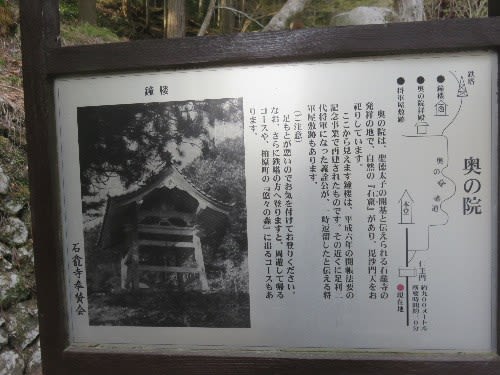
あー、あの鐘楼堂がある場所が奥の院だったのか。
うん、見なかったことにしよう。(コピペ)
【地蔵菩薩】

【水琴窟】

石段を登ると庫裏の前にありました。
どこの水琴窟も音色は変わりませんね。(^^
【参道】


秋になるとこの辺りの紅葉が見事なようです。
【本堂】


残念ながら本堂は閉まっていました。

横からみると少しくたびれた感がありますね。
【不動明王】

【石標】

左が行者さん、右が奥の院。
うん、見なかったことにしよう。(コピペ)
【参道】

行者さん行き。

奥の院行き。
約800メートルかぁ。
山の道の800メートルは舐めてはいけません。
えーえーえー、
勿論、行きませんとも。(^^;
【七福神】

【薬師堂】

以前の薬師堂は素朴で小さなお堂でしたが、
近年建て替えられたらしく、綺麗な新品同様のお堂でした。
【参道】

こんな道を進んで行く。
【境内社】


【境内】

薬師堂と本堂です。
【焼尾神社】


雪害から守る為に覆屋で守られていますね。

鎮守として市杵島比売命が祀られているとのこと。
【蔵】

【御朱印】


御不在でしたので書置きを二体いただきました。
御本尊聖観音菩薩の御朱印は無いようですね。