さて、今度の大地君の本には実用的な情報を入れようと思っているんですけど
その一つがお手伝い。
昨日小暮画伯とも打ち合わせしました。
どうも白くま母さんはうまいことやっているようだ。
何をって?
お手伝いと感覚のトレーニングと遊びとをうまく組み合わせているようだ。
これってなかなか頭脳労働だと思うので
その一端を披露してもらった。
どうやったらお手伝い上手にできるのか
白くま母さんのやり方からヒントをもらえるかもしれません。
おうちの中で役割をもつことは
社会の中で役割をもつ前段階になるもんね。
お手伝いをしてお給料を得るのは
社会に出るいいシミュレーションだもんね。
それ以外にも色々社会の縮図を味わっているみたいですよ、大地君は。
大地君は昨冬
ママがアルバイトして買った食器洗い機の導入で機械化による失業を味わった。
でも特需があった。
大雪だ。
雪かきは身体の小さい妹ちゃんたちにはできない。
大地君はシェア100%の寡占雪かきプレイヤーとして活躍した。
私は教えてあげた。大人はそれを「ビジネスチャンス」と呼ぶのだと。
でも、春になって雪解けしたら失業してしまった。
こうやって季節労働者の悲哀も味わった。
大人になって仕事につくときは、季節に左右されない仕事のほうが安定するね。
小さいときからお手伝いの習慣があったことが
今こうやって実っているお話もあります。
「重度の子だから」と、一生誰かに世話してもらうことを前提に
「接待され上手」に育てるのも自由ですが
小さいころからお手伝いの習慣を身につけ
今ではiPod Touchを利用して作業実習に取り組んでいるお子さんもいる。
挑戦する権利は、それぞれにあるからね。
そういえば先日の講演に
「言葉のない子と明日を探したころ」の
真行寺英子さん、英司さん親子がご来場くださいました。

英司さんはさわやかな中年男性です。
なんというか、親父くささが全然ないですよ。
「障害の重さにかけては東の横綱」と言われながら四半世紀以上正社員として勤務され
お父様の遺した土地に自分の資産でおうちを建て直されたそうですが
やはり小さいころから家族のために身体を動かすことをいとわない方だったそうです。
その一つがお手伝い。
昨日小暮画伯とも打ち合わせしました。
どうも白くま母さんはうまいことやっているようだ。
何をって?
お手伝いと感覚のトレーニングと遊びとをうまく組み合わせているようだ。
これってなかなか頭脳労働だと思うので
その一端を披露してもらった。
どうやったらお手伝い上手にできるのか
白くま母さんのやり方からヒントをもらえるかもしれません。
おうちの中で役割をもつことは
社会の中で役割をもつ前段階になるもんね。
お手伝いをしてお給料を得るのは
社会に出るいいシミュレーションだもんね。
それ以外にも色々社会の縮図を味わっているみたいですよ、大地君は。
大地君は昨冬
ママがアルバイトして買った食器洗い機の導入で機械化による失業を味わった。
でも特需があった。
大雪だ。
雪かきは身体の小さい妹ちゃんたちにはできない。
大地君はシェア100%の寡占雪かきプレイヤーとして活躍した。
私は教えてあげた。大人はそれを「ビジネスチャンス」と呼ぶのだと。
でも、春になって雪解けしたら失業してしまった。
こうやって季節労働者の悲哀も味わった。
大人になって仕事につくときは、季節に左右されない仕事のほうが安定するね。
小さいときからお手伝いの習慣があったことが
今こうやって実っているお話もあります。
「重度の子だから」と、一生誰かに世話してもらうことを前提に
「接待され上手」に育てるのも自由ですが
小さいころからお手伝いの習慣を身につけ
今ではiPod Touchを利用して作業実習に取り組んでいるお子さんもいる。
挑戦する権利は、それぞれにあるからね。
そういえば先日の講演に
「言葉のない子と明日を探したころ」の
真行寺英子さん、英司さん親子がご来場くださいました。

英司さんはさわやかな中年男性です。
なんというか、親父くささが全然ないですよ。
「障害の重さにかけては東の横綱」と言われながら四半世紀以上正社員として勤務され
お父様の遺した土地に自分の資産でおうちを建て直されたそうですが
やはり小さいころから家族のために身体を動かすことをいとわない方だったそうです。














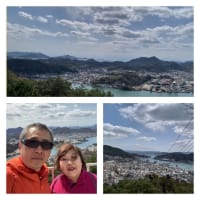





こちらこそご愛読いただきありがとうございます。この本は派手な内容ではありませんが、親子が言葉の壁を乗り越えて絆を築いていく様子がありありと描かれ、再刊してよかったとしみじみ思っております。
今後ともよろしくお願いいたします。
うちの子供は高機能なのですが、やはり通っている療育機関から「毎日のお手伝い」を習慣化させるよう一貫して指導を受けています。
まずは身辺自立を徹底、そして、お手伝いを通じて手先の器用さ、作業の手順、家族の一員として評価されることによる自己肯定感を高め、就業につなげていくという考えです。
ここはかなり重度の子も指導していますが、指導内容のレベルこそ違えど、基本姿勢はまったく同じです。なのでここの卒業生たちは重度の方たちでもお仕事を続けている方たちが多いようです。
療育機関などで指導されたわけでもないのに、こういったことご家庭できちんと実行されている白熊母さんはさすがだなとおもいます。
このような方針の方の本を、積極的に出版してくださっている浅見さんにも感謝しています。
でも「どうやって始めたらいいかわからない」という方からのお便りもたくさんいただいたので
一つの例として載せることにしました。
「みようみまねで」「怒られながら覚える」ことが苦手な人たちだと思うのですね。
白くま母さんはそのあたりの特性に配慮して、うまいやり方をしています。
どうぞ楽しみにしていてください!