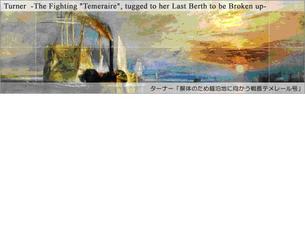ハズレがないと全部読んでいる作家の一人。
一人の悪女の生き様を周囲の人間の目を通して描く10個の章からなる小説。
主人公の21歳から27歳までが描かれる。
ヒロインの内面がけして描かれないところ、章と章の間で何が起こったか読者の想像に任せるところは東野圭吾『白夜行』にも通じる。
作品の完成度はさすがだが、作者が『最悪』『無理』などでも描いてきた地方都市(奥田の出身地でもある岐阜が舞台)の閉塞感やしがらみにしばられた不正や狎れ合いが罷り通る現実への痛切な告発が一貫している。
(私の学部は地域の政策などを研究しているので、私は地方都市の問題を抉ったものとして学生に『無理』を読むことを勧めている)
また、ジェンダーの視点からも秀逸である。
ヒロインの短大の同級生のセリフ
「平凡な結婚をして、子供を二人産んで、小さな建売住宅を買って、家事と育児とローンに追われて、田舎の女はそういう人生の船にしか乗れんやん。でも糸井さんは、女の細腕で自分の船を漕ぎ出し、大海原を航行しとるんやもん。金持ちの愛人を一人殺すぐらい、女には正当防衛やと思う」
「世界中どの国でも、女に殺される男の数より、男に殺される女の数の方がはるかに多いやん。やったら方りうもバランスを取るべきやと思う。女が男の百倍殺されとるなら、女が男を殺しても、罪の重さは百分の一やて。」
確かに、地方都市ってこんなに腐っているのかと驚かされる。
①警察は幹部が異動する度に餞別と称して大金を地域から徴集(そのかわりに駐車違反のお目こぼし等がある)
←これは横山秀夫の『64』にも出てきた。
②市営住宅の半分は市役所職員等のコネで決まる。職員の口利き料は10万円。
③公共事業の受注の談合は当たり前
④カルチャースクール・料理教室の講師は親戚の教育委員のコネでしかも親族のスーパーの売れ残りの悪くなった食材を使う。
等々。
これらを登場人物は全員「田舎で生きるということはこういうことだ」と諦めている。
私にはとてもできない。
ヒロインの美幸は、④については直談判して講師を代えさせたり、知り合いの女性を食い逃げした男にヤクザの弟を使ってヤキを入れたり、何より男を食物にする生き方自体が、こうした男中心の腐敗に大きくnoを突きつけているようにも見える。
それが、ほかの悪女ものと一線を画す痛快さになっている。
ただ、短大時代に大きく変貌した彼女だが、そのきっかけに一体何があったのか、出てくると思ったらこなかったのでそこは残念。
ちなみに全部読んでいる(読む方針の)作家は下記
三島由紀夫
笙野頼子
桐野夏生(グロテスク最高)
奥田英朗
角田光代(八日目の蝉最高)
貫井徳郎(乱反射最高)
津村記久子(女性会社員小説の白眉)
群ようこ(無印シリーズ最高)
平安寿子
林真理子(白蓮れんれんを読んでから)
湊かなえ
全部ではないが大体読んでいる
芥川
夏目
川端
鴎外
太宰治
横溝正史(金田一モノと由利モノは全部)
姫野カオルコ(エッセイは全部)
酒井順子
西村賢太(なぜかクセになる)
諏訪哲史(アサッテの人は三島と似た世界観、実際ファンだそうだ)
東野圭吾(玉石混交)
中村うさぎ
岸本葉子(教養の見田ゼミの先輩)
有川浩
伊坂幸太郎
ナンシー関
これから全部読もうかと思っている
中島京子(FUTONがすばらしかった)
奥泉光(桑潟ものは抱腹絶倒、笑いすぎて電車で読めない。シューマンの指はなぜこのミスの一位でなかったか不思議)
横山秀夫(受賞作より、64、震度ゼロがすごい)
一人の悪女の生き様を周囲の人間の目を通して描く10個の章からなる小説。
主人公の21歳から27歳までが描かれる。
ヒロインの内面がけして描かれないところ、章と章の間で何が起こったか読者の想像に任せるところは東野圭吾『白夜行』にも通じる。
作品の完成度はさすがだが、作者が『最悪』『無理』などでも描いてきた地方都市(奥田の出身地でもある岐阜が舞台)の閉塞感やしがらみにしばられた不正や狎れ合いが罷り通る現実への痛切な告発が一貫している。
(私の学部は地域の政策などを研究しているので、私は地方都市の問題を抉ったものとして学生に『無理』を読むことを勧めている)
また、ジェンダーの視点からも秀逸である。
ヒロインの短大の同級生のセリフ
「平凡な結婚をして、子供を二人産んで、小さな建売住宅を買って、家事と育児とローンに追われて、田舎の女はそういう人生の船にしか乗れんやん。でも糸井さんは、女の細腕で自分の船を漕ぎ出し、大海原を航行しとるんやもん。金持ちの愛人を一人殺すぐらい、女には正当防衛やと思う」
「世界中どの国でも、女に殺される男の数より、男に殺される女の数の方がはるかに多いやん。やったら方りうもバランスを取るべきやと思う。女が男の百倍殺されとるなら、女が男を殺しても、罪の重さは百分の一やて。」
確かに、地方都市ってこんなに腐っているのかと驚かされる。
①警察は幹部が異動する度に餞別と称して大金を地域から徴集(そのかわりに駐車違反のお目こぼし等がある)
←これは横山秀夫の『64』にも出てきた。
②市営住宅の半分は市役所職員等のコネで決まる。職員の口利き料は10万円。
③公共事業の受注の談合は当たり前
④カルチャースクール・料理教室の講師は親戚の教育委員のコネでしかも親族のスーパーの売れ残りの悪くなった食材を使う。
等々。
これらを登場人物は全員「田舎で生きるということはこういうことだ」と諦めている。
私にはとてもできない。
ヒロインの美幸は、④については直談判して講師を代えさせたり、知り合いの女性を食い逃げした男にヤクザの弟を使ってヤキを入れたり、何より男を食物にする生き方自体が、こうした男中心の腐敗に大きくnoを突きつけているようにも見える。
それが、ほかの悪女ものと一線を画す痛快さになっている。
ただ、短大時代に大きく変貌した彼女だが、そのきっかけに一体何があったのか、出てくると思ったらこなかったのでそこは残念。
ちなみに全部読んでいる(読む方針の)作家は下記
三島由紀夫
笙野頼子
桐野夏生(グロテスク最高)
奥田英朗
角田光代(八日目の蝉最高)
貫井徳郎(乱反射最高)
津村記久子(女性会社員小説の白眉)
群ようこ(無印シリーズ最高)
平安寿子
林真理子(白蓮れんれんを読んでから)
湊かなえ
全部ではないが大体読んでいる
芥川
夏目
川端
鴎外
太宰治
横溝正史(金田一モノと由利モノは全部)
姫野カオルコ(エッセイは全部)
酒井順子
西村賢太(なぜかクセになる)
諏訪哲史(アサッテの人は三島と似た世界観、実際ファンだそうだ)
東野圭吾(玉石混交)
中村うさぎ
岸本葉子(教養の見田ゼミの先輩)
有川浩
伊坂幸太郎
ナンシー関
これから全部読もうかと思っている
中島京子(FUTONがすばらしかった)
奥泉光(桑潟ものは抱腹絶倒、笑いすぎて電車で読めない。シューマンの指はなぜこのミスの一位でなかったか不思議)
横山秀夫(受賞作より、64、震度ゼロがすごい)












 ほぼ1年ぶりの更新である。閲覧してくださる人が毎日いるというのがありがたくまた申し訳ない。
ほぼ1年ぶりの更新である。閲覧してくださる人が毎日いるというのがありがたくまた申し訳ない。