先日の 「第26回てつがくカフェ@ふくしま」 では 「老い」 について話し合いました。
そのときの議論の中身はすでにてつカフェのブログにアップされています。
ひじょうに深い議論が交わされたなあと思いますし、
1人で考えていたときよりもはるかに思考を深めることができました。
私もインスパイアされていろいろと言いたいこともあったのですが、
今回は初めての会場で、モニターにパソコンをつないでマインドマネージャというソフトを使い、
マインドマップを打ち込みながらのてつカフェだったため、
 (クリックすると拡大)
(クリックすると拡大)
1回発言しただけであとは書記に徹していました。
そのためちょっとモヤモヤ感が残ってしまったので、まだ考え中ではありますが、
とりあえず考えたことを忘れないうちに書き留めておくことにします。
その前にすでにこのブログ内で、老いについて考えたこと感じたことを書いたことがあります。
それを思い出しておきましょう。
内容的に整理はできないので、古い順に並べておきます。
 「哲学者は長生きしたもんの勝ち」 2009.9.21.
「哲学者は長生きしたもんの勝ち」 2009.9.21.
 「満腹感」 2010.5.15.
「満腹感」 2010.5.15.
 「老いるとは?」 2010.5.24.
「老いるとは?」 2010.5.24.
 「1リットルの男」 2010.5.26.
「1リットルの男」 2010.5.26.
 「老化 (?) 現象」 2010.6.8.
「老化 (?) 現象」 2010.6.8.
 「スポーツ選手と老い」 2010.10.24
「スポーツ選手と老い」 2010.10.24
この中で、私の老いの哲学の根幹は 「老いるとは?」 に書いたことになります。
その中心テーゼはこれですね。
「私はもうできない、にもかかわらず私は存在する」
”I can’t any more, nevertheless I am”
老いをこのように定式化するならば当然、老いることは悪いことになります。
今回のてつカフェでまた問いの立て方 (老いることは悪いことか?) が間違っていると指摘され、
老いは自然現象であってよいことでも悪いことでもないと集中砲火を浴びてしまいましたが、
私はやはり老いというのはそもそも基本的には悪いことなんじゃないかと思っています。
もちろん、本来悪いことである老いを個人的・主観的にポジティブに受け止めることは可能です。
というか、むしろそうすべきだと思いますし、
私がいつも 「受け止め方の問題」 と言っているのはまさにそういうことです。
そして、「1リットルの男」 や 「老化 (?) 現象」 で書いたことは、
そのように老いをポジティブに受け止める試みだったと言えるでしょう。
ただ、基本的に 「老い」 という言葉は分かちがたく負の価値を背負った言葉であると思うのです。
今回のてつカフェの冒頭で、老いとは成長の放物線の後半部分だという発言がありました。
放物線の譬えはなかなかわかりやすいと思います。
人間はだんだんといろいろなことができるようになっていき、
そしてある時点を過ぎると今度はそれを失っていきます。
ただ、その放物線の全体を 「成長の放物線」 と名づけてよいのか疑問に思いました。
というのは 「成長」 という言葉は 「老い」 と対照的に正の価値をもつ言葉だと思うからです。
そこで考えたのは、この放物線の全体は 「歳をとること (エイジング)」 と名づけるべきであり、
その前半部分、つまりできることが増えていく段階が 「成長」 であり、
後半部分、できることが失われていく段階が 「老い」 なのではないか、ということでした。
それで言うならば、「歳をとること (エイジング)」 はまさに自然の流れであって、
そこに価値的な意味は含まれません。
つまり、よいことでも悪いことでもないわけです。
その中で正の側面 (=増加部分) を 「成長」 と呼び、
負の側面 (=喪失部分) を 「老い」 と呼んでいるのではないか、と思うのです。
このようにもうすでに日本語として、成長はよいこと、老いは悪いこと、
というふうに使い分けられているのではないかと思うのです。
ここからさらに、1人の人間のエイジング曲線は1本の放物線では表せない気もしてきました。
人間の能力というのは果てしなく多様ですから、
それらの能力がすべて同じタイミングで高まっていき、ある時点を境にすべてが減少に転ずる、
なんていうことはどう考えてもありえないと思うのです。
スポーツ選手の例で言うならば、速い球を投げるとか何回転もジャンプするという能力は、
比較的、早い時期にピークに達してまだ若いうちに喪失の段階を迎えますが、
コントロールや組み立てで打ち取るとか、芸術的表現力などは経験を積めば積むほど高まります。
身体的機能だけをとってもこのようにエイジング曲線にはズレが生じています。
精神的能力に関しても、暗記力や数学で使う直観的ひらめきは早くに失われるかもしれませんが、
すでに知っている知識や経験をもとに判断を下す能力は歳とともに増していくでしょう。
ここにさらにコミュニケーション能力とか人間的魅力を加えていくと、
それらのピークは相当歳をとった後にやってくるということがわかるでしょう。
身体的老いが始まったとしても、精神的・人間的にはまだ成長中ということは普通にありえるのです。
今思うと、今回てつカフェの議論が若干錯綜したのは、歳をとること、成長、老いの三つを、
みんながそれぞれ好き勝手に使っていたからではないかという気がしてきました。
それはとりもなおさず世話人の私たちがこの三つをきちんと整理した上で問いを立てなかったからで、
「歳をとることはよいことか悪いことか?」 という問いにしていたら、
歳をとるなかで成長していくことはよいことであり、老いることは悪いことである、
しかしながら、歳をとるなかでさまざまな成長と老いが同居しているので、
歳をとること自体はよいこととも悪いこととも言えない、
みたいな感じですっきりと合意することができたのではないでしょうか。
(いや、この説自体またボコボコにされるのがオチだろうなあ)
ま、てつカフェに参加してくるような皆さんは、どれだけ年配者の方でも、
多少身体的老化が始まっているとはいえ、大部分においてまだ成長段階にいる (みんな若い) ので、
「老い」(=せっかくできるようになったことがだんだんできなくなっていくこと) を
本格的に実感できていないのではないか、というのが私の抱いた感想でした。
私としては今回の議論を通じて、老いはあくまでも悪いことであり、
それをいかにポジティブに捉え返すことができるのかできないのか、
というところに問題の本質があるというふうに考えました。
反論どしどしお寄せください。
他にもまだ言いたいことがありましたが、それはまた別の機会に。
そのときの議論の中身はすでにてつカフェのブログにアップされています。
ひじょうに深い議論が交わされたなあと思いますし、
1人で考えていたときよりもはるかに思考を深めることができました。
私もインスパイアされていろいろと言いたいこともあったのですが、
今回は初めての会場で、モニターにパソコンをつないでマインドマネージャというソフトを使い、
マインドマップを打ち込みながらのてつカフェだったため、
 (クリックすると拡大)
(クリックすると拡大)1回発言しただけであとは書記に徹していました。
そのためちょっとモヤモヤ感が残ってしまったので、まだ考え中ではありますが、
とりあえず考えたことを忘れないうちに書き留めておくことにします。
その前にすでにこのブログ内で、老いについて考えたこと感じたことを書いたことがあります。
それを思い出しておきましょう。
内容的に整理はできないので、古い順に並べておきます。
 「哲学者は長生きしたもんの勝ち」 2009.9.21.
「哲学者は長生きしたもんの勝ち」 2009.9.21. 「満腹感」 2010.5.15.
「満腹感」 2010.5.15. 「老いるとは?」 2010.5.24.
「老いるとは?」 2010.5.24. 「1リットルの男」 2010.5.26.
「1リットルの男」 2010.5.26. 「老化 (?) 現象」 2010.6.8.
「老化 (?) 現象」 2010.6.8. 「スポーツ選手と老い」 2010.10.24
「スポーツ選手と老い」 2010.10.24この中で、私の老いの哲学の根幹は 「老いるとは?」 に書いたことになります。
その中心テーゼはこれですね。
「私はもうできない、にもかかわらず私は存在する」
”I can’t any more, nevertheless I am”
老いをこのように定式化するならば当然、老いることは悪いことになります。
今回のてつカフェでまた問いの立て方 (老いることは悪いことか?) が間違っていると指摘され、
老いは自然現象であってよいことでも悪いことでもないと集中砲火を浴びてしまいましたが、
私はやはり老いというのはそもそも基本的には悪いことなんじゃないかと思っています。
もちろん、本来悪いことである老いを個人的・主観的にポジティブに受け止めることは可能です。
というか、むしろそうすべきだと思いますし、
私がいつも 「受け止め方の問題」 と言っているのはまさにそういうことです。
そして、「1リットルの男」 や 「老化 (?) 現象」 で書いたことは、
そのように老いをポジティブに受け止める試みだったと言えるでしょう。
ただ、基本的に 「老い」 という言葉は分かちがたく負の価値を背負った言葉であると思うのです。
今回のてつカフェの冒頭で、老いとは成長の放物線の後半部分だという発言がありました。
放物線の譬えはなかなかわかりやすいと思います。
人間はだんだんといろいろなことができるようになっていき、
そしてある時点を過ぎると今度はそれを失っていきます。
ただ、その放物線の全体を 「成長の放物線」 と名づけてよいのか疑問に思いました。
というのは 「成長」 という言葉は 「老い」 と対照的に正の価値をもつ言葉だと思うからです。
そこで考えたのは、この放物線の全体は 「歳をとること (エイジング)」 と名づけるべきであり、
その前半部分、つまりできることが増えていく段階が 「成長」 であり、
後半部分、できることが失われていく段階が 「老い」 なのではないか、ということでした。
それで言うならば、「歳をとること (エイジング)」 はまさに自然の流れであって、
そこに価値的な意味は含まれません。
つまり、よいことでも悪いことでもないわけです。
その中で正の側面 (=増加部分) を 「成長」 と呼び、
負の側面 (=喪失部分) を 「老い」 と呼んでいるのではないか、と思うのです。
このようにもうすでに日本語として、成長はよいこと、老いは悪いこと、
というふうに使い分けられているのではないかと思うのです。
ここからさらに、1人の人間のエイジング曲線は1本の放物線では表せない気もしてきました。
人間の能力というのは果てしなく多様ですから、
それらの能力がすべて同じタイミングで高まっていき、ある時点を境にすべてが減少に転ずる、
なんていうことはどう考えてもありえないと思うのです。
スポーツ選手の例で言うならば、速い球を投げるとか何回転もジャンプするという能力は、
比較的、早い時期にピークに達してまだ若いうちに喪失の段階を迎えますが、
コントロールや組み立てで打ち取るとか、芸術的表現力などは経験を積めば積むほど高まります。
身体的機能だけをとってもこのようにエイジング曲線にはズレが生じています。
精神的能力に関しても、暗記力や数学で使う直観的ひらめきは早くに失われるかもしれませんが、
すでに知っている知識や経験をもとに判断を下す能力は歳とともに増していくでしょう。
ここにさらにコミュニケーション能力とか人間的魅力を加えていくと、
それらのピークは相当歳をとった後にやってくるということがわかるでしょう。
身体的老いが始まったとしても、精神的・人間的にはまだ成長中ということは普通にありえるのです。
今思うと、今回てつカフェの議論が若干錯綜したのは、歳をとること、成長、老いの三つを、
みんながそれぞれ好き勝手に使っていたからではないかという気がしてきました。
それはとりもなおさず世話人の私たちがこの三つをきちんと整理した上で問いを立てなかったからで、
「歳をとることはよいことか悪いことか?」 という問いにしていたら、
歳をとるなかで成長していくことはよいことであり、老いることは悪いことである、
しかしながら、歳をとるなかでさまざまな成長と老いが同居しているので、
歳をとること自体はよいこととも悪いこととも言えない、
みたいな感じですっきりと合意することができたのではないでしょうか。
(いや、この説自体またボコボコにされるのがオチだろうなあ)
ま、てつカフェに参加してくるような皆さんは、どれだけ年配者の方でも、
多少身体的老化が始まっているとはいえ、大部分においてまだ成長段階にいる (みんな若い) ので、
「老い」(=せっかくできるようになったことがだんだんできなくなっていくこと) を
本格的に実感できていないのではないか、というのが私の抱いた感想でした。
私としては今回の議論を通じて、老いはあくまでも悪いことであり、
それをいかにポジティブに捉え返すことができるのかできないのか、
というところに問題の本質があるというふうに考えました。
反論どしどしお寄せください。
他にもまだ言いたいことがありましたが、それはまた別の機会に。










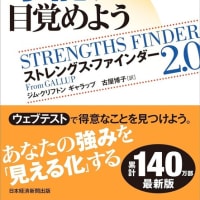















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます