移動大学は、川喜田二郎(文化人類学)が東工大を1969年に辞め、少人数で世界各地を回りながらフィールドワークで学習する新たな試みとして始めたものだ。如何にも川喜田らしい発想で、教育手法として当時、注目を集めた。これは、学生が教師を選んで、大学を移ってゆくドイツ等のヨーロッパでの方法と似ていなくもない。今でも、その制度の考え方は残っているようだ。
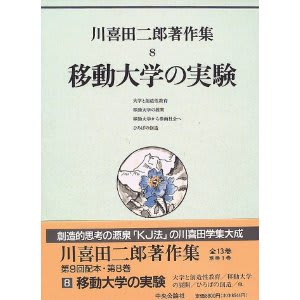
「移動大学の実験」(著作集第8巻 中央公論社)
一方、八ヶ岳大学は、後に三木内閣の文部大臣となった永井道雄(教育社会学)が、東工大紛争当時1969年に発表した「大学の可能性」(中央公論社)で提案したもので、東大に代表される最高峰の大学を各地に構築するものだ。
永井道雄氏もまた、東工大を辞して、朝日新聞論説委員へと転出した。筆者は当時、社会学の講義を受けていたので、川喜田と一緒に恒例として行われた「最終講義」を聞いた。また、その後、本当の最終講義も受けて、その講義の最後に、近代日本の自叙伝的歴史書のなかで、石光真清の四部作を冷静に、正直に書かれた最高峰の作品として評価し、学生たちに一読を勧めていたのを覚えている。
さて、ここで表題の「あれか、これか」に戻る。
4年生のとき、永井陽之助氏の総合講義第二の授業での座談が終わって、話がふたりと二つの大学に及んで、どちらを評価するのかとの話になった際、氏は「移動大学の方を評価する」と、明快に断言した。
何故なら、「八ヶ岳大学は既存の東大を単に増やすだけだ。これが解とは思えない。」「移動大学は少人数による新しい試みで、時代の先を切り開くのはこのような少数例だ」と指摘された。確かに4年生での授業は、10名程度の少人数で、永井教授を囲む様にソファに座って話をする形式で行われていた。
「現代の開かれた社会は、情報が自由に交換される社会であり、人間は互いに摸倣し合い、同調し、容易く画一化された生活形態になりやすい」「反面、学歴というパスポート取得の争奪戦は、青春期を閉鎖状態に追いやる」。
(『柔構造社会における学生の反逆』初出1968,「柔構造社会と暴力」所収)
上記の、約50年前における永井の認識は当時の大学生を想定したものだが、今日、大学院生あるいはポスドク群を想定しても当てはまるだろう。当時の東大紛争は医学部・大学病院での万年助手、医局員なども含めた参加者があったことを改めて想い起こすべきなのだ。
そして、この状況下において、永井の川喜田評価と少人数の座談形式の授業は、彼自身が到達した大学教育の方法論に沿っているのだ。
続けて氏は、「“教える”ということは、政治、芸術と同じで専門技術ではない。ひとつの“わざ”であり、もって生まれた人間の資質と、伝習的な英知のちくせきから生まれてくるものである」。「現代における“教育”の崩壊は“政治”の解体と同じ様に、伝習的英知に対する専門技術の優位と圧制から生じた一般的風潮に他ならないのである」と云う。
従って、「大学教育の改革は…小クラスのゼミを中心に、専門研究者、教授が現在取っ組んでいる生の問題を学生にぶつけて、具体的な問題解決を共同で志向していく、新しい実戦教育の確立にある」。このような、教授と学生の人間的な接触の回復が、技術的知識と伝習的知識を統合していくものなのだ。
翻って、現在の小保方・博士論文が提供した早大の実態は、教授が学生を全く指導せず、人間的接触もない中を「論文の引用の仕方」を学ぼうとせずにスイスイと、泳ぎ渡ってきた象徴的な人物の姿をシルエットとして浮かび上がらせる。勿論、これは早大においてもごく一部であると考える。しかし、日本の大学の現状を象徴する姿でもあることを否定できないはずだ。
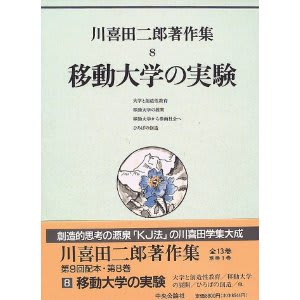
「移動大学の実験」(著作集第8巻 中央公論社)
一方、八ヶ岳大学は、後に三木内閣の文部大臣となった永井道雄(教育社会学)が、東工大紛争当時1969年に発表した「大学の可能性」(中央公論社)で提案したもので、東大に代表される最高峰の大学を各地に構築するものだ。
永井道雄氏もまた、東工大を辞して、朝日新聞論説委員へと転出した。筆者は当時、社会学の講義を受けていたので、川喜田と一緒に恒例として行われた「最終講義」を聞いた。また、その後、本当の最終講義も受けて、その講義の最後に、近代日本の自叙伝的歴史書のなかで、石光真清の四部作を冷静に、正直に書かれた最高峰の作品として評価し、学生たちに一読を勧めていたのを覚えている。
さて、ここで表題の「あれか、これか」に戻る。
4年生のとき、永井陽之助氏の総合講義第二の授業での座談が終わって、話がふたりと二つの大学に及んで、どちらを評価するのかとの話になった際、氏は「移動大学の方を評価する」と、明快に断言した。
何故なら、「八ヶ岳大学は既存の東大を単に増やすだけだ。これが解とは思えない。」「移動大学は少人数による新しい試みで、時代の先を切り開くのはこのような少数例だ」と指摘された。確かに4年生での授業は、10名程度の少人数で、永井教授を囲む様にソファに座って話をする形式で行われていた。
「現代の開かれた社会は、情報が自由に交換される社会であり、人間は互いに摸倣し合い、同調し、容易く画一化された生活形態になりやすい」「反面、学歴というパスポート取得の争奪戦は、青春期を閉鎖状態に追いやる」。
(『柔構造社会における学生の反逆』初出1968,「柔構造社会と暴力」所収)
上記の、約50年前における永井の認識は当時の大学生を想定したものだが、今日、大学院生あるいはポスドク群を想定しても当てはまるだろう。当時の東大紛争は医学部・大学病院での万年助手、医局員なども含めた参加者があったことを改めて想い起こすべきなのだ。
そして、この状況下において、永井の川喜田評価と少人数の座談形式の授業は、彼自身が到達した大学教育の方法論に沿っているのだ。
続けて氏は、「“教える”ということは、政治、芸術と同じで専門技術ではない。ひとつの“わざ”であり、もって生まれた人間の資質と、伝習的な英知のちくせきから生まれてくるものである」。「現代における“教育”の崩壊は“政治”の解体と同じ様に、伝習的英知に対する専門技術の優位と圧制から生じた一般的風潮に他ならないのである」と云う。
従って、「大学教育の改革は…小クラスのゼミを中心に、専門研究者、教授が現在取っ組んでいる生の問題を学生にぶつけて、具体的な問題解決を共同で志向していく、新しい実戦教育の確立にある」。このような、教授と学生の人間的な接触の回復が、技術的知識と伝習的知識を統合していくものなのだ。
翻って、現在の小保方・博士論文が提供した早大の実態は、教授が学生を全く指導せず、人間的接触もない中を「論文の引用の仕方」を学ぼうとせずにスイスイと、泳ぎ渡ってきた象徴的な人物の姿をシルエットとして浮かび上がらせる。勿論、これは早大においてもごく一部であると考える。しかし、日本の大学の現状を象徴する姿でもあることを否定できないはずだ。










