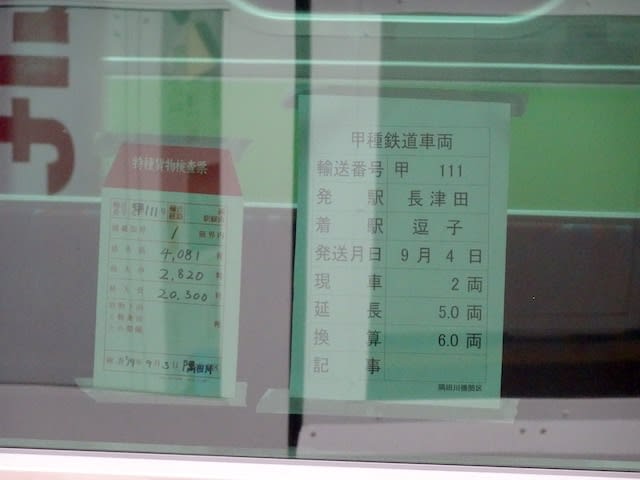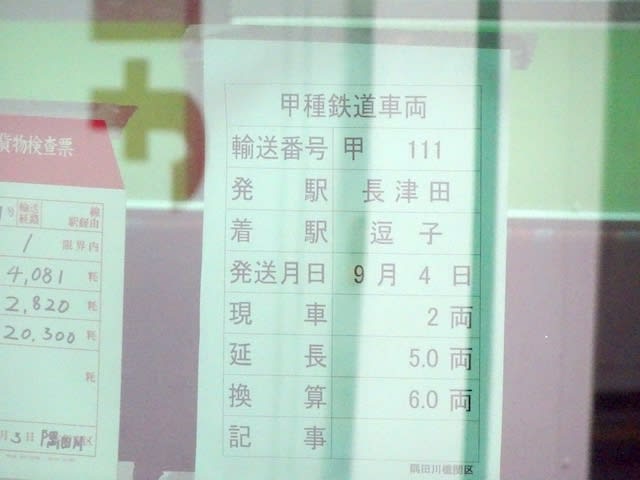1.一生、そればかりか死んでからも関係してくる租税
「揺り籠から墓場まで」(from the cradle to the grave)という言葉がある。元々はイギリスの「ベバレッジ報告」(1942年)に登場した言葉であるとも、イギリスの労働党が唱えたものであるともいい、社会保障制度の充実を表現する言葉である。
しかし、視点を変えると実は租税についても同じようなことが言える。我々がこの現代社会に生きている限り、ごく僅かな例外を除けば、租税と全く関わりのない生活を送ることはできない。例えば道路を歩くのであれ、自動車を運転するのであれ、列車や船や飛行機に乗るのであれ、租税と無関係ではいられない。個人で事業を営むのであれ、会社などに雇われて勤労をするのであれ、株式などに投資するのであれ、いかなる生活を送るにせよ、所得税や住民税などと全く無縁であるということは考えにくい。預貯金口座を持っていれば、預貯金の利子に所得税がかかる。実際には利子から所得税が天引きされ(これを源泉徴収などという)、残りが口座に入る訳であるが、このこと一つをとっても、我々が租税と無縁の生活を送っている訳ではないことがわかるであろう。
しかも、個人が死んだらそれでおしまい、という訳にもいかない。文字通りの意味で何物も残す(遺す)ことなく死ぬ者はいない。遺体を含めて、個人は必ず何かを残す(遺す)。残した(遺した)ものがどれだけの経済的価値を持つかということは、別の問題である。そればかりか、残した(遺した)ものの中に借金などの債務があるかもしれない。いや、実は、日本において生活する人は、借金はなくとも、何らかの形で債務を残して死ぬのである。租税はその代表であり、故人の後始末という形で、遺族は準確定申告などを行わなければならない。誰かが亡くなれば、相続または遺贈ということになって、遺族などが相続税の納税義務を負うことにもなる。
〈初回にいきなり死だの債務だの墓場だのと暗い話で申し訳ございません。言い訳をしておきますと、法律学に携われば、私生活はともあれ、何らかの形でこういうことに関わらざるをえないのです。私が大分大学教育学部・教育福祉科学部で法律学概論という講義を担当していた時に、少なからぬ学生から話の内容が暗いとか物騒だとかという苦情(?)を寄せられたのですが、仕方のないことなのです。〉
現在の日本には、所得税、法人税、消費税、相続税・贈与税、固定資産税など、多くの種類の租税、わかりやすい言葉を選べば税金がある。後の回において述べるが、日本の租税は大別して国税と地方税と分かれ、国、都道府県、市町村、特別区が課税主体として租税を徴収する。
2.日本国憲法にも法律にも租税の定義はない
ところで、皆さんは租税とは一体何であろうと考えたことがあるであろうか。
所得税法、法人税法などの法律で定められたものである、という簡単な答えもある。しかし、これは「法律が税金であると決めたから税金である」と言っているに過ぎず、答えらしい答えにはなっていない。我々は、租税、税金という言葉を耳にして、漠然としてはいても何かのイメージを思い浮かべるであろう。租税というからには、例えば電車や路線バスの運賃とは違うものであるということはわかる。
所得税法、法人税法、さらには国税通則法などの法律があるのであるから、法律に「租税とは何ぞや」ということくらいは書かれているだろう、とお思いの方もおられるであろう。まして、日本国憲法があるではないか。日本国憲法の第30条には納税の義務が定められている。憲法が定める国民の三大義務の一つとして、高等学校の政治・経済の教科書にも書かれている。このように考える方もおられるに違いない。
それでは、日本国憲法を読み直してみよう。確かに、第30条に納税の義務が規定されている。そして、第84条および第30条に租税法律主義が規定されている。租税という言葉は第84条に登場する。しかし、第30条、第84条のいずれにも、租税の定義は示されていない。
租税法律主義については後の回において取り上げるが、憲法学における通説的な見解は、租税法律主義の根拠として第84条のみをあげるようである。しかし、租税法学においては、租税法律主義の根拠に関して見解が分かれており、第84条および第30条を根拠とする見解が多い。租税法律主義は、単に国家財政運営上の原則に留まらないものである、と解されるべきである。従って、第84条と第30条の双方を根拠とする見解のほうが妥当であろう。この点については、拙稿「租税法律主義の射程距離(1)―旭川市国民保険条例訴訟大法廷判決の検討を中心に―」税務弘報54巻12号(2006年9月号)129頁注1、同「租税特別措置法附則27条による同法31条の遡及適用が違憲無効と判断された事例」速報判例解説編集委員会編『速報判例解説』(法学セミナー増刊)3号(2008年)288頁も参照。
このことは、法律などについても同様であり、租税法とされる法律のいずれを参照しても、租税の定義はなされていない。
一方、租税法学や財政学などの教科書を参照すると、たいてい、租税の定義に関する記述がある。もっとも、定義づけはそれほど容易なことではない。そればかりか、定義の実用性を疑う見解も存在する。おそらく、「あまり実益がないから」、あるいは「難解な記述となるから」ということもできる。 たしかに、谷口勢津夫教授が指摘するように「個々の税目については、その意義および内容が法律や条例で定められる」から「租税の定義をめぐって、法律や条例の解釈上問題が生じることはない」〈谷口勢津夫『税法基本講義』〔第6版〕(2018年、弘文堂)8頁〉。しかし、実際には、租税に限らず、我々が国家や地方公共団体に納める(支払う)金銭などの債務は多いし、租税と言いながらそれ以外のもの、例えば負担金と区別し難いものも存在する。また、租税とは異なるはずの社会保険料などについても、租税と同様の問題が生じる場合も存在する。例えば、私を含め、多くの給料鳥(誤字ではない)が受け取る給料は、あらかじめ、租税と社会保険料が天引きされたものである。
そこで、この回においては、租税とはいかなるものであり、租税法とはいかなるものであるのか、ということについて話を進めていく。
なお、以下における租税の法的定義などについて、ほぼ同じ趣旨を拙稿・前掲税務弘報論文135頁においても述べている。
3.租税の法的(法律学的)定義
既に述べたように、日本においては、租税についての法的定義がなされていない。
もっとも、国税通則法第2条第1号および国税徴収法第2条第1号は「国税」を「国が課する税のうち関税、とん税及び特別とん税以外のものをいう」と定義し、国税徴収法第2条第2号は「地方税」を「地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都、特別区及び全部事務組合のこれに相当する徴収金を含む。)をいう」と定義する。これらは、国税通則法、国税徴収法のそれぞれの適用に必要な範囲を決めるための定義であり、租税そのものの定義でないことは明らかである。
しかし、 公租公課として、国家(および地方公共団体)が国民から徴収する財貨(金銭など)は、租税ばかりでなく、負担金、手数料などの形式をとる場合もある。従って、或る程度、租税のメルクマールを明らかにしておく必要がある。
租税の法的定義を行った例として有名なものは、1919年に制定されたドイツ(ヴァイマール共和国期)のReichsabgabenordnung(一般的にライヒ租税通則法と訳す。直訳ではライヒ公課法となる) である。同法の第1条第1項は、「租税とは、特別の給付に対する反対給付ではなく、給付義務につき法律が定める要件に該当するすべての者に対し、収入を得る目的をもって公法上の団体が課する一回かぎり又は継続的な金銭給付をいう。関税はこれに該当するが、行政行為を特別に請求することに対する手数料及び負担金(受益者負担)は、これに該当しない」と規定する〈訳は、田中二郎『租税法』〔第三版〕(1990年、有斐閣)1頁による〉。
また、1977年に制定されたドイツ(連邦共和国)の租税通則法(公課法。Abgabenordnung)第3条第1項は、「租税とは、特別の給付に対する反対給付ではなく、法律が給付義務について定める要件に該当する者に対し、公法上の団体によって収入を得るためにのみ課される金銭給付をいう。収入を得ることは付随的目的たりうる 」と規定する〈この条文の訳は、私自身によるものである〉。
日本においては、上記の定義(とくにライヒ租税通則法第1条第1項)を基として、法律学などにおいて様々な定義がなされている。若干の例をあげておく。
「租税とは、国又は地方公共団体が、その課税権に基づき、特定の給付に対する反対給付としてではなく、これらの団体の経費に充てるための財力調達の目的をもって、法律の定める課税要件に該当するすべての者に対し、一般的標準により、均等に賦課する金銭給付である」〈田中・前掲書1頁〉。
「国(または地方公共団体)が、国の主権に服する者から、公的・一般的収入の目的をもって、法律(または条例)に定める要件を充足する事実があり、金銭的給付義務が確定するときに、強制的に、収納する金銭的給付である」〈新井隆一『租税法の基礎理論』〔第三版〕(1997年、日本評論社)2頁〉。
「国家が、特別の給付に対する反対給付としてではなく、公共サービスを提供するための資金を調達する目的で、法律の定めに基づいて私人に課する金銭給付である」〈金子宏『租税法』〔第二十三版〕(2019年、弘文堂)9頁〉。
以上は学説による定義であるが、最高裁判所も判決の理由において租税の定義を述べている。まず、大嶋訴訟として有名な最大判昭和60年3月27日民集39巻2号247頁は「租税は、国家が、その課税権に基づき、特別の給付に対する反対給付としてでなく、その経費に充てるための資金を調達する目的をもつて、一定の要件に該当するすべての者に課する金銭給付である」と述べる。これは、上記の諸定義と同じ趣旨と考えてよいであろう。
また、旭川市国民健康保険条例訴訟として有名な最大判平成18年3月1日民集60巻2号587頁も「国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たるというべきである」と述べる。これも、上記の諸定義と同じ趣旨と考えてよい。
4.租税のメルクマール
先に掲げた諸定義には、一定の共通する内容が含まれている。しかし、統一的な定義がなされている訳ではない。
もっとも、これは日本だけの現象ではない。租税の定義を実定法において示すドイツの例は、むしろ、世界的にも珍しいほうである。おそらく、憲法上の争点となりうることを含め、実益の点などを考慮したのであろう。そして、日本においては、ドイツとは逆に、租税を法的に定義することには実益がないという考え方のほうが一般的であるかもしれない。
たしかに、通常の場合は、先に示した谷口教授の指摘にあるように、法律によって国税および地方税とされているものを租税とする形式的思考法が簡便でもあるし、それで事足りることが多い。
また、北野弘久博士は、租税の定義について根本的な疑義を述べる。北野博士は、租税について「法認識論のレベル」における定義と「法実践論のレベル」における定義とが区別される必要がある旨を指摘し、その上で、「従来の租税概念は、明治憲法のもとでのそれを、日本国憲法のもとにおいても無批判的に踏襲してきたものであ」り、「明治憲法のもとでと同じレベルで日本国憲法のもとでの税財政に関する法概念・法理論を構築することは学問的には誤謬である」と批判する〈北野弘久(黒川功補訂)『税法学原論』〔第7版〕(2016年、勁草書房)18頁、20頁。北野弘久編『現代税法講義』〔五訂版〕(2009年、法律文化社)4頁[北野弘久担当]も参照〉。
甲斐素直教授も、先に示した田中二郎博士による定義を引用しつつ「これが税法学の対象となる租税の定義を述べているに」留まり、憲法第84条と「まったく結びつきをもっていない」と批判する〈甲斐素直「租税法律主義における租税概念の外延について」日本法学60巻3号(1994年)132頁。なお、同論文では憲法学の学説についても批判が展開されている〉。
これまでの租税法学や憲法学などにおける租税の定義に、不十分な点があることは否定できない。とくに、租税法学と憲法学との間には、決して短くない距離がある〈拙稿・前掲税務弘報論文137頁。拙稿「日本国憲法における『租税』の概念と租税法律主義との関連についての試論」税制研究56号(2009年)137頁も参照〉。このため、さらに検討を重ねる必要性は高い。ただ、形式的思考法によっては、租税とそれ以外の公課とを上手く区別できないこともあるし、租税法律主義の射程距離を画定する際などには困難を生じる。
私は、実定法において租税を定義する実益はあるものと考える。とりわけ、憲法において定義を示す必要性はあると考える。この点に関連して、税理士の山本守之氏が、国税徴収法第2条における定義を「定義の実益だけを考えて規定している例である」とした上で、憲法第84条が租税法律主義の根拠規定となっているために「実定法において租税を定義する必要はあるように思われる」と述べており、参考になる〈山本守之『租税法の基礎理論』〔新版〕(2008年、税務経理協会)4頁〉。
既に示した諸定義には、若干の差異があるように読み取りうる。これは、後に述べる租税観、さらに言うならば国家観の相違によると考えられる部分もあるが、多くは表現上の問題である。これらの定義に共通する部分を見出せば、租税のメルクマールを明らかにすることができよう。 租税のメルクマールについては、次のように整理することができる。
この整理は、主に佐藤進=伊東弘文『入門租税論』〔改訂版〕(1994年、三嶺書房)1頁による。また、より一般的に、肥後和夫編『財政学要論』〔第4版〕(1993年、有斐閣)115頁[西村紀三郎担当]、片桐正俊編『財政学―転換期の日本財政―』(1997年、東洋経済新報社)209頁[長沼進一担当]、吉田克己『現代租税論の展開』(2005年、八千代出版)9頁、宮入興一編著『現代日本租税論』(2006年、税務経理協会)1頁[松井吉三担当]、神野直彦『財政学』〔改訂版〕(2007年、有斐閣)149頁、星野泉=小野島真編『現代財政論』(2007年、学陽書房)55頁[小野島真担当]、室山義正『財政学』(2008年、ミネルヴァ書房)205頁も参照。なお、拙稿・前掲税務弘報論文135頁も参照。
(1)強制性
租税は、根本的に公権力を背景とした強制性を備える、とされる。しかし、これだけでは手数料や負担金と区別し難い。
(2)無償性
ここにいう無償性とは、何らかの対価としての性格、または反対給付としての性格が認められないことをいう。
手数料は、国家などによる何らかの特定の給付に対する反対給付である。例えば、公園の入園料などを考えればよい〈但し、地方自治法第231条の3第2項、地方税法第67条、同第72条の67などに規定される督促手数料に注意する必要がある〉。また、負担金は、例えば宅地開発のように、開発などによって利益―手数料の場合よりも、より一般的な利益―を受ける者に対し、その利益に着目して課されるものである。従って、手数料および負担金の場合には無償性が認められないことになる〈この点をとくに強調するのが、神野・前掲書164頁である〉。
これに対し、租税には無償性が認められる。例えば、所得税の申告を期限までに行い、法律に定められたとおりに申告をしても、それによって選挙権の行使に特典が認められる、などというようなことはない。青色申告については若干の優遇措置が認められるが、これは政策的なものであるし、国政全般について何らかの反対給付が得られる訳でもないし、そもそも国からの何らかのサーヴィスに対する直接的な対価という意味を有する訳でもない。
しかし、無償性についても問題がある。前掲最大判平成18年3月1日および前掲最判平成18年3月28日の根本的な難点は、かような部分にあるのかもしれない〈拙稿・前掲税制研究56号139頁〉。
第一点は、既に示した北野教授の根本的な疑義に関わる。大日本帝国憲法第62条は、第1項において「新ニ租税を課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ」としつつ、第2項において「但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス」と定めていた。このような規定であれば、無償性は当然のこととして承認されるであろう。しかし、日本国憲法第84条には大日本帝国憲法第62条第2項のような明文が存在しない。従って、日本国憲法第84条は、無償性を有する公課のみを租税と扱うものとすべき説の根拠にならないのではなかろうか。
第二点は、反対給付または対価性の意味ないし範囲の不明確性であり、無償性の意味との関連において無視しえない問題である。ここでは、たとえば目的税を考えてみるとよい。
本来、目的税は行政側の利益提供に対する反対給付として位置づけられるものではない。しかし、実際には受益者負担論的(または原因者負担的)な観点から、何らかの対価性を有するものと考えられることが少なくないようである〈消費税の福祉目的税化の議論はその典型であろう〉。そうであるならば、反対給付ないし対価性は、手数料のように直接的な租税負担との対応を必要としないことになる〈増田英敏『リーガルマインド租税法』〔第4版〕(2013年、成文堂)227頁は「租税の非対価性は直接的な対応関係がないという意味で用いられている」と指摘する〉。しかし、これでは租税たる目的税とその他の公課との区別が曖昧になり、「何らかの行政目的が存在する場合に、強制的に徴収する必要があれば税の名を借り、柔軟な対応をすべき場合は負担金や分担金といった形式を選択するとの便宜的な運用が行われてきた」と評価されるのもやむをえない〈伊川正樹「地方目的税の今後の可能性―『本来的目的税』の提言を基礎として―」日本租税理論学会編『地方自治と税財政制度(租税理論研究叢書16)』(2006年、法律文化社)37頁〉。実際に、自動車取得税・入猟税・水利地益税などのように、負担金との区別がつきにくいものもあるし、都市計画税のように曖昧な性格を有するものもある。
なお、ヴァーグナー(Adolf Wagner)は租税に「一般的報償性」を認めたが、ノイマルク(Fritz Neumark)により批判された。
(3)道具的性格
租税は、第一次的に国家の資金調達を目的とするものである。かつてはこれがメルクマールとして強調されていた。国家自身が財貨などを得る場合が多いからである。
しかし、国家が租税を徴収しつつも、その徴収額を第三者に譲渡することもある。その代表例として、地方譲与税、地方交付税、補助金をあげることができる。
また、経済政策、景気政策などの手段に用いられることもある。前掲最大判昭和60年3月27日も指摘するように、租税には所得の再分配、資源の適正配分、景気の調整などの機能があることも認められる〈この趣旨は、最判平成4年12月25日民集46巻9号2829頁(酒類販売免許制訴訟)において引用されている〉。先にあげた地方譲与税、地方交付税や補助金などは、このような機能を担うものとして捉えられるであろう。また、最近では自動車取得税などにおいて、環境政策の一環として用いられることがある。
(4)一連の租税の調達過程における課税の一方的性格
これは、徴税手続などにおける権力的要素などを指す。 現在、通説は租税を私人の法定債務であると考える。私もこの説を支持するのであるが、これは税額や税率が法定されているという実体法的観点に着目したものであり、租税の徴収という手続法的観点からすれば、申告納税という方法が多くの租税において採られているものの、更正、推計課税、さらに税務調査など、権力的な側面が強いことも否めない。
(5)法律の根拠
近代立憲主義において、私有財産の不可侵は重要な原則である。この原則は現代立憲主義において若干の修正を受けたが、日本国憲法は、私有財産制度の存在を前提とし、私有財産の保護を規定する。しかし、租税は、上述のように、国民から強制的に、直接的な反対給付を伴うことなく徴収されるものである。従って、課税権の行使は、国民の財産権に対する一方的な侵害にあたる。そのために、恣意的な課税権の発動がなされてはならない。
また、本来ならば租税こそが国家の資金調達の最終手段でなければならないが、近年は公債に依存する傾向が大きい。日本は代表的であり、先進国の中でも最悪の水準である。
但し、ここで注意しなければならないことがある。
上記における租税の定義は租税法学あるいは財政学におけるものであり、行政の観点からのものとも言いうる。租税、手数料、負担金などは、それぞれ根拠法規を異にするし、取扱も異なる。しかし、日本国憲法第84条における「租税」の意義については、別に考えなければならない。この点は、租税法の講義というより、むしろ憲法や財政法の講義において扱うべきものであるため、ここでは詳しく取り上げないこととする。
拙稿・前掲税務弘報54巻12号137頁、同・拙稿前掲税制研究56号136頁を参照。
▲第3版における履歴:2019年9月26日掲載。
▲第2版における履歴:2011年3月15日掲載
2011年3月21日修正。
2011年3月22日補訂。
2011年3月31日修正。
2011年4月5日修正。
2012年8月5日修正。
2013年3月29日修正。
2013年8月1日修正。
2014年3月3日修正。
2018年1月24日補訂。
2018年7月23日修正。
2019年9月26日掲載。