(原題:HENRY & JUNE )作家アナイス・ニンの日記を基に、まだ無名だったヘンリー・ミラーとその妻ジューンとの関係を描く。90年アメリカ作品。フィリップ・カウフマン監督といえば、「ライトスタッフ」(83年)そして「存在の耐えられない軽さ」(88年)でキャリアの絶頂を迎えたものの、本作を境に高評価を得ることが出来なくなったことに思い当たる。
1931年、アナイス・ニンは銀行家の夫ヒューゴーの仕事のため、キューバのハバナからパリに引っ越してくる。ある日、アナイスは別荘に客として招かれた無名の作家ヘンリー・ミラーを一目見て好きになり、彼も彼女の妖しい魅力に惹かれる。ヘンリーの妻ジューンはニューヨークで女優をしているのだが、彼女は夫を養うために金持ちのパトロンに囲われていた。
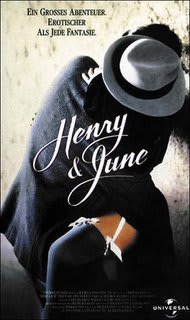
やがてジューンもパリへやって来るが、実はバイ・セクシュアルであるアナイスは彼女にも惹きつけられ、愛し合うようになる。だが、ジューンはヘンリーの書いている小説のモデルになっている自分の姿が現実と違うことに怒りを覚え、ニューヨークへ帰ってしまう。仕方なくヘンリーはアナイスと本格的に付き合うことにするが、彼女はその顛末をヒューゴーが隣で寝ているのも構わず、日記に書き留めるのであった。
前作「存在の耐えられない軽さ」でも多用されたクローズショットが、ここでも大々的に採用されている。登場人物の生理的な次元にまで肉迫するような接写の連続で、息苦しくも圧倒的なインパクトは受けるのであるが、どこか余所余所しい。各キャラクターの“生理”は見えるが、“内面”が伝わってこないのだ。
聞けばカウフマンはベルイマンをはじめとするヨーロッパのアート・フィルムに心酔していたとのことだが、何やら表面的な部分だけを模倣しているように思える。
実は「存在の耐えられない軽さ」にもそういうテイストは感じられたのだが、主演の3人の素晴らしい存在感と、“プラハの春”という厳然たる歴史的事実を背景にしたおかげで、見応えのある展開になっていた。ところが本作のキャストはあまりにも弱い。ヘンリー役のフレッド・ウォード、ジューンに扮するユマ・サーマン、そしてアナイスを演じるマリア・デ・メディロスという配役は、前作のダニエル・デイ・ルイス、ジュリエット・ビノシュ、レナ・オリンという超強力キャスティングと比べたら、まるで月とスッポンである。
ついでに言うと、大道具小道具が凝っているわりには時代色が出ていない。単に小綺麗なだけである。外観はヨーロッパ映画風だが、作っている連中はハリウッド娯楽映画路線の担い手であるというミスマッチが、最後まで足を引っ張っているようなシャシンだ。
1931年、アナイス・ニンは銀行家の夫ヒューゴーの仕事のため、キューバのハバナからパリに引っ越してくる。ある日、アナイスは別荘に客として招かれた無名の作家ヘンリー・ミラーを一目見て好きになり、彼も彼女の妖しい魅力に惹かれる。ヘンリーの妻ジューンはニューヨークで女優をしているのだが、彼女は夫を養うために金持ちのパトロンに囲われていた。
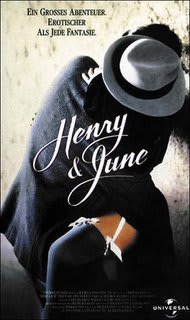
やがてジューンもパリへやって来るが、実はバイ・セクシュアルであるアナイスは彼女にも惹きつけられ、愛し合うようになる。だが、ジューンはヘンリーの書いている小説のモデルになっている自分の姿が現実と違うことに怒りを覚え、ニューヨークへ帰ってしまう。仕方なくヘンリーはアナイスと本格的に付き合うことにするが、彼女はその顛末をヒューゴーが隣で寝ているのも構わず、日記に書き留めるのであった。
前作「存在の耐えられない軽さ」でも多用されたクローズショットが、ここでも大々的に採用されている。登場人物の生理的な次元にまで肉迫するような接写の連続で、息苦しくも圧倒的なインパクトは受けるのであるが、どこか余所余所しい。各キャラクターの“生理”は見えるが、“内面”が伝わってこないのだ。
聞けばカウフマンはベルイマンをはじめとするヨーロッパのアート・フィルムに心酔していたとのことだが、何やら表面的な部分だけを模倣しているように思える。
実は「存在の耐えられない軽さ」にもそういうテイストは感じられたのだが、主演の3人の素晴らしい存在感と、“プラハの春”という厳然たる歴史的事実を背景にしたおかげで、見応えのある展開になっていた。ところが本作のキャストはあまりにも弱い。ヘンリー役のフレッド・ウォード、ジューンに扮するユマ・サーマン、そしてアナイスを演じるマリア・デ・メディロスという配役は、前作のダニエル・デイ・ルイス、ジュリエット・ビノシュ、レナ・オリンという超強力キャスティングと比べたら、まるで月とスッポンである。
ついでに言うと、大道具小道具が凝っているわりには時代色が出ていない。単に小綺麗なだけである。外観はヨーロッパ映画風だが、作っている連中はハリウッド娯楽映画路線の担い手であるというミスマッチが、最後まで足を引っ張っているようなシャシンだ。

























