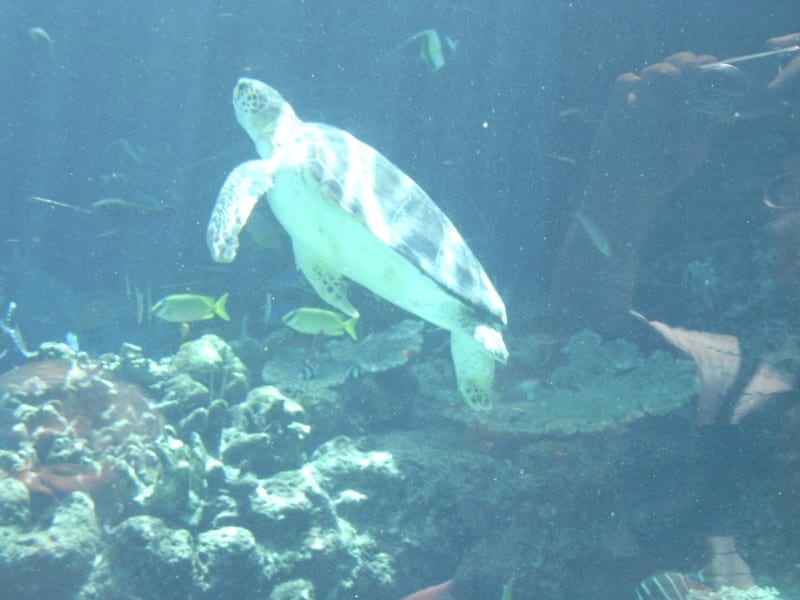「サーカスに売られる」など暗いイメージがあったのは遠い昔の話、今やオリムピック競技を芸術レベルで楽しみたいという時代になった
お台場で公演中の「シルク・ド・ソレイユ」のシルクとはサーカスのことだった
1984年にカナダの大道芸人から始まったというこの集団は4千人のスタッフを抱える大企業
スポーツ音痴で高所恐怖症、泳げない、と三点揃って非の打ちどころがない私にとって、こうしたショーで気になるのは音響と全体のコントロール機能
巨大な仮設ドーム内の空調や照明、音響機器、そしてそのコントロールはどうなっているのであろう
ドーム上部からロープを下げたり吊り上げたり瞬時に空中ブランコをする「ロープさばきのメカニズム」は電子制御されているに違いないなどと想像する
30余年の歴史はこうしたメカニックの開発を伴ってきたのだろう
中央のステージに向かう花道は人を乗せて大蛇のように自在に曲がる
ドーム内に設置された音響機器はハウリングや箱鳴りを制御しながら、なお音の伝達スピードを計算している
あたかも天から落ちてくるような太鼓の音が聴こえたり、大音量の音楽の世界に巻き込む
プログラミングされた音源に10数名のミュージシャンたちが会場で音を重ねる
テーマ音楽が流れる中で、ショーの進行に同期してドラムスや効果音が鳴る
舞台の奥まった上段にオーケストラボックスのようなスペースがあり、そこでショーを見ながら演奏をするのだろう
そうしたミュージシャンたちがステージに出てきて演奏する場面は新鮮だった
フラメンコをイメージした場面でギターが二人、ギタロンのような形状のベースとパーカッショニストたち
どこまでが生音なのかわからないが、奏者が見えるだけで納得する向きもある
テーマごとの公演を世界各国の常設またはツアー会場で行っているようだ
世界から集う演者たちが生活を共にする日常も気になるところ、人間関係がうまく行かなければ大事故につながる
ビートルズやプレスリー楽曲をテーマにした公演もあったようだ
大道芸からサーカスへ、ミュージカルの要素を取り入れたり、、、
アートから展開するビジネスモデル、新たな世界を垣間見た
Cirque Du Soleil - Totem
Quidam - Cirque du Soleil
review of Cirque du Soleil's new show Kurios
Top 10 Cirque du Soleil Shows
Cirque du Soleil: "Totem" ? - 01 Omé Kayo