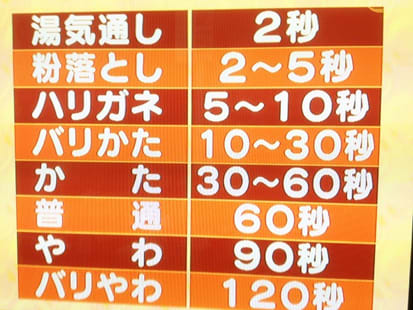以前、中学だったかの国語の試験に、「○肉○食」とあって、「○」を補い四字熟語を完成させよ、という設問があり、その複数の回答に、「焼肉定食」というのがあったと聞いたことがある。
もちろん正解は「弱肉強食」である。そもそも「焼肉定食」は四字熟語ではない。
だけど、ま、それほどまでに「焼肉」という食文化は普通に普及しているということだ。
(か)さんや(お)さんやダランを含め、我々の世代の子供の頃は、そもそも「外食」という行為は、一年に数回程度しかない特別のものだった。少なくとも普段の日常のなかにそういうサイクルはなかった。
つまり、母親や主婦たちは、ほぼ年中欠かさず食事の用意をしていたのだ。だから、年に一度か二度のたまの旅行の上膳据膳が何より贅沢だったというのも聞いたことがある。
たぶん、70年代半ばまでは確実にそうだったとおもう。

Websiteより。
で、おそらく70年代後半から俗にいう「ニューファミリー」やサラリーマン核家族といった人々が大衆消費社会に影響するようになると、もっと自由な食生活のスタイルが生まれるようになったのだとおもわれる。
いわゆる「団塊の世代」たちである。60年代に学生だった世代、「ヤング」と言われて闊歩した世代の走りでもある。
そうね、その世代は800万人近くいるというから、いまでもそうだが、彼らの動向や志向性は消費市場を大きく左右するようになる。それが顕著になってきたのが、80年代であろう。
彼らは、子供を連れて、週に一回は「外食」するようになる。で、この頃モテハヤされるようになったのがいわゆる「ファミレス」である。ファミリー以前の我々も深夜の時間なら少しは行かせてもらったが・・・。
最初は洋食中心だったファミレス文化は、その後、「焼肉」や「回転寿し」とジャンルを広げ、週一ペース、家族四人で食べても、ま、なんとかなるくらいの料金設定で、「新しい家族」のライフスタイルをつくったともいえるかもしれない。
その子供たちが、若くして大トロやカルビの味を覚えてしまったから始末がわるい(けして本物とは言いがたい面もあるが)。
寿司屋で「大将、ウニ、サビ抜きで」とか頼んでいるガキをみると、大外刈りにかけたくなる。

日本最初のファミレスといわれるチェーン店の看板(スカイラークHPより)。
先日、事務所の若いスタッフがいつもよく働いてくれるので、たまには飲みに行くか、ということになった。そうなれば当然、僕が支払うことになる。いいようなそうでもないような慣習であるが、ま、これもしょうがない。
で、こちらは「飲みに行く」気でいたら、どうも最近の若者はそういう感覚がないらしく、「食事」をご馳走してもらえる、という風に認識した、らしい。たしかに、そういうものかもしれないが、ちと、なよなよしい限りだ。
で、何がいい? と訊くと、間髪入れず、「焼肉っ!」、と即答。そうか、やっぱり君たちも子供の頃刷り込まれているんだな。
僕らの子供の頃も焼肉屋に近いものもあるにはあったが、それはどちらかというと「ホルモン焼き」の店で、そう、あまり堅気っぽくない人、風体のよろしくない人たちが行く店だった。だから子供の頃、焼肉を家族で食べた、という経験はほぼない。

ただ、おごる立場からすると、いいこともある。
よく焼肉屋でお父さんが子供に「先にごはんを食べなさい」と言うそうだ。ごはんでお腹を満たせば安く済むからだろうが、実際、彼らにとっても、焼肉とごはんは条件反射に近いらしい。
で、まず、キムチとナムルとサンチェ、タン塩、カルビを一通り頼んだあと、こちらはゆっくりとビールでも飲みながらチビチビ、とかおもっているところに、「すみません、ごはん頼んでいいですか?」ときた。ガッツリいきたいのだ。
「もちろんいいよ、どうぞどうぞ」(しめしめ、思う壷だ、とはおもったが・・・)。
おもえば僕もそうだった。海の幸が豊富だった場所で育ったせいか、若い頃、刺身があるとどうしてもごはんが食べたくなってしまう。刺身で酒が飲めるようになるまでには随分時間がかかったものだ。

左がカルビで、右が上カルビ。
いままでカルビは安い方がうまい、と勝手におもっていたが、久々に上を食べてみてわかった。
失礼、やっぱり、上には上の理由がある。
だけど、そうおもったのもつかの間、彼ら、食べる食べる。結局、ごはんがあろうがなかろうが、あるいは、ごはんがあるせいで、逆に焼肉がすすむようだ。追加のついでに、結局、韓国焼酎まで飲む始末。
おまけに会計に行ったら、ええ?そんなにいった?・・・しかもカードが使えない。「ウチは現金だけなんですよね~」。しまった、そうだ、中華と韓国料理は現金商売だ。彼ら、現金しか信用していないのだ。
でも僕はウッチャンよりはプライドがあるので(わからない人はごめんなさい)、なんとか現金で払った。ら、
「領収書いりますか?」・・・「う、うん、はい、じゃ、一応」。
「宛名と但し書きはどうなさいますか?」・・・「う、うん、じゃ、マスゾエ様で。但しがきは日韓文化交流費と書いてもらえますか」・・・(すいやせん、ウソつきやした)。
たしかにまあ、プロジェクト打上げ、というなら経費にしてもおかしくはないが、うちの経理はそんなに甘くない。そう簡単に収支報告書には記載させてくれはしない。
「誰と食べたんですか?・・・身内スタッフだけじゃないですよね」と訊かれれば、「うん、まあ、例の出版の件で、昔から懇意にしている出版社社長と・・・」、「名前は?」、「いやそれは相手に迷惑がかかるといけないので・・・」となる。
ああ、やっぱダメダメ。そうして小心者の僕は、この領収書を捨てもせず、まだ机に引き出しにしまったままだ・・・まあいいか、いずれ確定申告だ。
ダランも、学生に誘われれば飲み会には行かざるを得ないだろうし、研究費にすることもできないし、家計圧迫も辛いから、結局ガムランで稼いだお金から出すことにある。
だんだん上役になるのはいいが、そこにはそれなりの苦労は絶えない。年齢ごとの悩みもある。
でも、金は天下の回りもの、そうやって、みんな歳を重ねていく善良な小市民なのだ。
それにまして、某都知事は大した男よのう。(は/237)
もちろん正解は「弱肉強食」である。そもそも「焼肉定食」は四字熟語ではない。
だけど、ま、それほどまでに「焼肉」という食文化は普通に普及しているということだ。
(か)さんや(お)さんやダランを含め、我々の世代の子供の頃は、そもそも「外食」という行為は、一年に数回程度しかない特別のものだった。少なくとも普段の日常のなかにそういうサイクルはなかった。
つまり、母親や主婦たちは、ほぼ年中欠かさず食事の用意をしていたのだ。だから、年に一度か二度のたまの旅行の上膳据膳が何より贅沢だったというのも聞いたことがある。
たぶん、70年代半ばまでは確実にそうだったとおもう。

Websiteより。
で、おそらく70年代後半から俗にいう「ニューファミリー」やサラリーマン核家族といった人々が大衆消費社会に影響するようになると、もっと自由な食生活のスタイルが生まれるようになったのだとおもわれる。
いわゆる「団塊の世代」たちである。60年代に学生だった世代、「ヤング」と言われて闊歩した世代の走りでもある。
そうね、その世代は800万人近くいるというから、いまでもそうだが、彼らの動向や志向性は消費市場を大きく左右するようになる。それが顕著になってきたのが、80年代であろう。
彼らは、子供を連れて、週に一回は「外食」するようになる。で、この頃モテハヤされるようになったのがいわゆる「ファミレス」である。ファミリー以前の我々も深夜の時間なら少しは行かせてもらったが・・・。
最初は洋食中心だったファミレス文化は、その後、「焼肉」や「回転寿し」とジャンルを広げ、週一ペース、家族四人で食べても、ま、なんとかなるくらいの料金設定で、「新しい家族」のライフスタイルをつくったともいえるかもしれない。
その子供たちが、若くして大トロやカルビの味を覚えてしまったから始末がわるい(けして本物とは言いがたい面もあるが)。
寿司屋で「大将、ウニ、サビ抜きで」とか頼んでいるガキをみると、大外刈りにかけたくなる。

日本最初のファミレスといわれるチェーン店の看板(スカイラークHPより)。
先日、事務所の若いスタッフがいつもよく働いてくれるので、たまには飲みに行くか、ということになった。そうなれば当然、僕が支払うことになる。いいようなそうでもないような慣習であるが、ま、これもしょうがない。
で、こちらは「飲みに行く」気でいたら、どうも最近の若者はそういう感覚がないらしく、「食事」をご馳走してもらえる、という風に認識した、らしい。たしかに、そういうものかもしれないが、ちと、なよなよしい限りだ。
で、何がいい? と訊くと、間髪入れず、「焼肉っ!」、と即答。そうか、やっぱり君たちも子供の頃刷り込まれているんだな。
僕らの子供の頃も焼肉屋に近いものもあるにはあったが、それはどちらかというと「ホルモン焼き」の店で、そう、あまり堅気っぽくない人、風体のよろしくない人たちが行く店だった。だから子供の頃、焼肉を家族で食べた、という経験はほぼない。

ただ、おごる立場からすると、いいこともある。
よく焼肉屋でお父さんが子供に「先にごはんを食べなさい」と言うそうだ。ごはんでお腹を満たせば安く済むからだろうが、実際、彼らにとっても、焼肉とごはんは条件反射に近いらしい。
で、まず、キムチとナムルとサンチェ、タン塩、カルビを一通り頼んだあと、こちらはゆっくりとビールでも飲みながらチビチビ、とかおもっているところに、「すみません、ごはん頼んでいいですか?」ときた。ガッツリいきたいのだ。
「もちろんいいよ、どうぞどうぞ」(しめしめ、思う壷だ、とはおもったが・・・)。
おもえば僕もそうだった。海の幸が豊富だった場所で育ったせいか、若い頃、刺身があるとどうしてもごはんが食べたくなってしまう。刺身で酒が飲めるようになるまでには随分時間がかかったものだ。

左がカルビで、右が上カルビ。
いままでカルビは安い方がうまい、と勝手におもっていたが、久々に上を食べてみてわかった。
失礼、やっぱり、上には上の理由がある。
だけど、そうおもったのもつかの間、彼ら、食べる食べる。結局、ごはんがあろうがなかろうが、あるいは、ごはんがあるせいで、逆に焼肉がすすむようだ。追加のついでに、結局、韓国焼酎まで飲む始末。
おまけに会計に行ったら、ええ?そんなにいった?・・・しかもカードが使えない。「ウチは現金だけなんですよね~」。しまった、そうだ、中華と韓国料理は現金商売だ。彼ら、現金しか信用していないのだ。
でも僕はウッチャンよりはプライドがあるので(わからない人はごめんなさい)、なんとか現金で払った。ら、
「領収書いりますか?」・・・「う、うん、はい、じゃ、一応」。
「宛名と但し書きはどうなさいますか?」・・・「う、うん、じゃ、マスゾエ様で。但しがきは日韓文化交流費と書いてもらえますか」・・・(すいやせん、ウソつきやした)。
たしかにまあ、プロジェクト打上げ、というなら経費にしてもおかしくはないが、うちの経理はそんなに甘くない。そう簡単に収支報告書には記載させてくれはしない。
「誰と食べたんですか?・・・身内スタッフだけじゃないですよね」と訊かれれば、「うん、まあ、例の出版の件で、昔から懇意にしている出版社社長と・・・」、「名前は?」、「いやそれは相手に迷惑がかかるといけないので・・・」となる。
ああ、やっぱダメダメ。そうして小心者の僕は、この領収書を捨てもせず、まだ机に引き出しにしまったままだ・・・まあいいか、いずれ確定申告だ。
ダランも、学生に誘われれば飲み会には行かざるを得ないだろうし、研究費にすることもできないし、家計圧迫も辛いから、結局ガムランで稼いだお金から出すことにある。
だんだん上役になるのはいいが、そこにはそれなりの苦労は絶えない。年齢ごとの悩みもある。
でも、金は天下の回りもの、そうやって、みんな歳を重ねていく善良な小市民なのだ。
それにまして、某都知事は大した男よのう。(は/237)