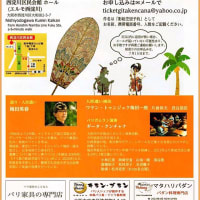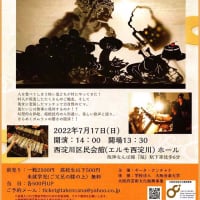昨日、TBSの「天皇の料理番」という番組を観ていたら、主人公の秋山篤蔵が、なんとパリのリッツで働いていて、エスコフィエがグランシェフだった。
「天皇の料理番」は高校生の頃、堺正章主演でドラマ化されたことがった。受験勉強(あまりしなかったけど)の合間に観たりしていたが、ま、そのリメイクということらしいのと、主題歌が威風堂々だったので観る気になった。
当時の放映は半年クールだった気がする。TVドラマも子供の頃は大河ドラマのように1年という単位が多かったが、それがだんだん短くなって、いまでは3ヶ月、といっても前後は特番なので、だいたい10回程度の放映スケジュールが定番になっている。なので、気がつくと終わっていた、なんとこともよくある。
視聴者が飽きやすいのと、スポンサーがあまりバクチをしなくなったためだろうか・・・。その分、高い視聴率を取った番組は、その後、セカンドシーズンやサードシーズンができて、飽きられるまでつづく。これは海外の手法だろうか、「24」や最近もやっていた「ダウントン・アビー」などもその口だ。
関係ないけど、それに比べたら韓流はすごいね。
ともあれ、このお話の主人公、秋山篤蔵は実在の人物である。もちろんフィクションや演出はあるだろうけれど、実話というのは説得力がある。実際にパリにも行ったし、日本にフランス料理を広めた人物でもある。
その篤蔵が最後に師事したのが、オーギュスト・エスコフィエだったのだ。
エスコフィエは、セザール・リッツとともにフランス料理の近代化とホテルのレストランやサービスやオペレーション・システムというものを確立した人物である。
なぜ、そんなことを知っているかというと、仕事の関係で、単純にいろいろホテル史をかじったからだけど、まあ、まず基本のひとつ。おそらくホテルマンで彼の名前を知らない人はいないだろう。
簡単にいうなら、近代のホテルというのは、欧米の共和制民主化によって生まれた都市の社交場兼迎賓館というべき場所。フランスなんかでは、もう王侯貴族はいないわけだから、資本家と裕福な市民が、ルイ王朝の様式や贅を模倣してつくったというべきかもしれない。
一般にそれは「グランドホテル」というスタイルを差し、世界中に波及した。日本にもそういう名前、結構あるね。ちょっとリアリティないけど。
そう、だから、レストランとか高級ホテルというのは、フランス革命以降、職にあぶれたシェフや執事たちの働き場でもあったのだ。


セザール・リッツとオーギュスト・エスコフィエ
そこに革命的成果を出したのが、リッツとエスコフィエのコンビである。
リッツは、スイスのあまり裕福ではない家の10人以上いる兄弟の末っ子として生まれた。当日の末っ子というのは、遺産相続なんて期待できない。もう勝手にどこにでも行け、という扱いである。
だから、彼は靴磨きや売春宿なんかでも働いたし、ヨーロッパ各地をまわって、手当たり次第に修行したという。才覚のある人というのは、そういうのを全部無駄にしない。人は何を喜び、何を求めるのか・・・、きっとそういう時代に学んだのだ。
とくに、南仏で伝染病が流行るとホテルというものは経営がおかしくなるという経験をして以降、ともかく衛生面を徹底的にする方法をつくりだした。これがよかったらしい。ヨーロッパといえども、当時は衛生的ではなかったということを物語っている。ホテルは安心できる場所でなければならないのだ。
で、ま、エスコフィエと運命的な出会いをしてからは、さまざまなホテルの近代化を成し遂げて行く。
たとえば、浴室の設置(当時、風呂は部屋にはなかったのだ)、専用電話の設置(最新鋭の装置ということ)、カスタムメイドのデザイン(インテリアや家具だけでなく、コースターにまでロゴを入れるのはこのときから)、ダイレクトメールや顧客管理システム(だから上客は名前で呼ばれる)、販促イベントの実施(ホテルイベントの原型)など・・・、で、あとは有名人の宿泊強化。
パリのリッツには、ココシャネルが住んでいたし、ヘミングウェイやプルースト、サルトルやチャップリンも常連だったし、近年では、ダイアナ妃が最後に食事したのもリッツだった。
映画なら、ヘップバーンの「昼下がりの情事」やショーン・コネリーの「ロシアより愛をこめて」などで記憶している人も多い。以来、誰が泊まったかはホテルの大切な物語になった。
いま、常識的にいわれている「お客様は常に正しい」とか「私たちはお客様に満足を売っている」などのホテルマンの常套句は、彼によって生まれた概念なのである。全部19世紀後半の話である。
ま、帝国ホテルとか、そういう種類の一流と呼ばれたいホテルが目指すある種のひな形なのだ。
ちなみに、ヌサドゥワにあるリッツカールトンは、彼らとは関係ないアメリカ企業ですが。
一方、エスコフィエもいろんなことを近代化した。
たとえば、コース料理の創出。
当時のレストランというのは、一度に全部出してしまう形式で、これではだんだん冷めてしまって味がキープできないし、順番通りワインを楽しむこともままならなければ、サプライズもやりにくい。
日本でも、茶の湯の懐石が、スペースもなかったということもあるだろうけれど、暖かいものは暖かいうちに、ということで、順番に出す方法を生み出したのと似ている。それまではだいたいが本膳料理。つまり、銘々膳に一挙に食事を並べる方式だ。いまでも温泉旅館や地方の宴会などではこれが主流だね。
他にも、ホテル内の料理人を部門化したことなどが有名である。つまり、このときにパティシエとかパン職人とかソムリエとか、いろいろ分化専門化したのである。
これは、ホテルとしては実に効率的なのだ。たしかに縦割主義や癒着等の功罪はあるにしても、モチベーションや専門性は高まるであろうし、管理も統一できるというものだ。
そして何よりの功績は、料理のレシピ本「料理の手引き」という本をまとめたことである。約5,000種類のフランス料理のレシピが入っているという。
1903年に出版されているので、篤蔵がパリに行った頃にはすでに出ていた、ということになる。日本で手に入ればねえ・・・、などとかみさんと話しながら観ていた。
ただし、このふたり、必ずしも良い人だったかどうかはわからない。山っけもあるし、投資家とのやり取りの記録を読むと、苦労人でもあったかもしれないけれど、そののし上がり方は十分商売人でもあった。
「真心」が通用するかどうかはわからない。

カトリーヌ・ド・メディチの肖像
フランス料理ももともとはイタリアからやってきたものである。メディチ家のカトリーヌ・ド・メディチがフランス王アンリ二世と結婚したときに、スプーンやフォークやマナーという概念、ついでにアイスクリームなんかを持ち込んだといわれている。
以降、宮廷を中心として発達したフランス料理は「オートキュイジーヌ」と呼ばれ、ヨーロッパ各地の晩餐料理になっていった。いわゆる正式な高級料理という意味だ。
それを改良、発展させ、ホテル・レストランとしての様式を確立したのが、エスコフィエであったのだ。
だから、篤蔵が行った頃のエスコフィエといえば、天下一のシェフという地位にいたわけだ。
で、それが長らく料理の王道として発達していったが、それから半世紀ほど経って流行り始めた「ヌーヴェル・キュイジーヌ」(新しい料理)は、皮肉にも、エスコフィエのつくりだしたものへのアンチから生まれたのである。
もうゴテゴテの料理や皿は出さない、ときに絵画のように美しく、素材重視のスモール・ポーションがいい、というわけなのだ。これが世界にウケた。
いまではさらにそれが発展して、スペインのエル・ブジや各地のアラン・デュカスの店やNYのブーレやロブションなど先端的料理になっていったけれど、そこに絶対的影響を与えたのが、実は日本料理なのであった。彼らは毎年日本に来ている。

エル・ブジの厨房
だからいまのフランス料理は、日本料理なしでは語れないし、フランスなどから多くの料理人が日本に勉強に来ているのだ。ShoyuやShitakeやKombu、UMAMIを知らない料理人はいない。
日本料理はいまでは世界遺産。巡り巡って、そんな時代になったのだ。
エスコフィエや篤蔵が生きていたら、どうおもうだろう・・・?(は/110)

秋山篤蔵
「天皇の料理番」は高校生の頃、堺正章主演でドラマ化されたことがった。受験勉強(あまりしなかったけど)の合間に観たりしていたが、ま、そのリメイクということらしいのと、主題歌が威風堂々だったので観る気になった。
当時の放映は半年クールだった気がする。TVドラマも子供の頃は大河ドラマのように1年という単位が多かったが、それがだんだん短くなって、いまでは3ヶ月、といっても前後は特番なので、だいたい10回程度の放映スケジュールが定番になっている。なので、気がつくと終わっていた、なんとこともよくある。
視聴者が飽きやすいのと、スポンサーがあまりバクチをしなくなったためだろうか・・・。その分、高い視聴率を取った番組は、その後、セカンドシーズンやサードシーズンができて、飽きられるまでつづく。これは海外の手法だろうか、「24」や最近もやっていた「ダウントン・アビー」などもその口だ。
関係ないけど、それに比べたら韓流はすごいね。
ともあれ、このお話の主人公、秋山篤蔵は実在の人物である。もちろんフィクションや演出はあるだろうけれど、実話というのは説得力がある。実際にパリにも行ったし、日本にフランス料理を広めた人物でもある。
その篤蔵が最後に師事したのが、オーギュスト・エスコフィエだったのだ。
エスコフィエは、セザール・リッツとともにフランス料理の近代化とホテルのレストランやサービスやオペレーション・システムというものを確立した人物である。
なぜ、そんなことを知っているかというと、仕事の関係で、単純にいろいろホテル史をかじったからだけど、まあ、まず基本のひとつ。おそらくホテルマンで彼の名前を知らない人はいないだろう。
簡単にいうなら、近代のホテルというのは、欧米の共和制民主化によって生まれた都市の社交場兼迎賓館というべき場所。フランスなんかでは、もう王侯貴族はいないわけだから、資本家と裕福な市民が、ルイ王朝の様式や贅を模倣してつくったというべきかもしれない。
一般にそれは「グランドホテル」というスタイルを差し、世界中に波及した。日本にもそういう名前、結構あるね。ちょっとリアリティないけど。
そう、だから、レストランとか高級ホテルというのは、フランス革命以降、職にあぶれたシェフや執事たちの働き場でもあったのだ。


セザール・リッツとオーギュスト・エスコフィエ
そこに革命的成果を出したのが、リッツとエスコフィエのコンビである。
リッツは、スイスのあまり裕福ではない家の10人以上いる兄弟の末っ子として生まれた。当日の末っ子というのは、遺産相続なんて期待できない。もう勝手にどこにでも行け、という扱いである。
だから、彼は靴磨きや売春宿なんかでも働いたし、ヨーロッパ各地をまわって、手当たり次第に修行したという。才覚のある人というのは、そういうのを全部無駄にしない。人は何を喜び、何を求めるのか・・・、きっとそういう時代に学んだのだ。
とくに、南仏で伝染病が流行るとホテルというものは経営がおかしくなるという経験をして以降、ともかく衛生面を徹底的にする方法をつくりだした。これがよかったらしい。ヨーロッパといえども、当時は衛生的ではなかったということを物語っている。ホテルは安心できる場所でなければならないのだ。
で、ま、エスコフィエと運命的な出会いをしてからは、さまざまなホテルの近代化を成し遂げて行く。
たとえば、浴室の設置(当時、風呂は部屋にはなかったのだ)、専用電話の設置(最新鋭の装置ということ)、カスタムメイドのデザイン(インテリアや家具だけでなく、コースターにまでロゴを入れるのはこのときから)、ダイレクトメールや顧客管理システム(だから上客は名前で呼ばれる)、販促イベントの実施(ホテルイベントの原型)など・・・、で、あとは有名人の宿泊強化。
パリのリッツには、ココシャネルが住んでいたし、ヘミングウェイやプルースト、サルトルやチャップリンも常連だったし、近年では、ダイアナ妃が最後に食事したのもリッツだった。
映画なら、ヘップバーンの「昼下がりの情事」やショーン・コネリーの「ロシアより愛をこめて」などで記憶している人も多い。以来、誰が泊まったかはホテルの大切な物語になった。
いま、常識的にいわれている「お客様は常に正しい」とか「私たちはお客様に満足を売っている」などのホテルマンの常套句は、彼によって生まれた概念なのである。全部19世紀後半の話である。
ま、帝国ホテルとか、そういう種類の一流と呼ばれたいホテルが目指すある種のひな形なのだ。
ちなみに、ヌサドゥワにあるリッツカールトンは、彼らとは関係ないアメリカ企業ですが。
一方、エスコフィエもいろんなことを近代化した。
たとえば、コース料理の創出。
当時のレストランというのは、一度に全部出してしまう形式で、これではだんだん冷めてしまって味がキープできないし、順番通りワインを楽しむこともままならなければ、サプライズもやりにくい。
日本でも、茶の湯の懐石が、スペースもなかったということもあるだろうけれど、暖かいものは暖かいうちに、ということで、順番に出す方法を生み出したのと似ている。それまではだいたいが本膳料理。つまり、銘々膳に一挙に食事を並べる方式だ。いまでも温泉旅館や地方の宴会などではこれが主流だね。
他にも、ホテル内の料理人を部門化したことなどが有名である。つまり、このときにパティシエとかパン職人とかソムリエとか、いろいろ分化専門化したのである。
これは、ホテルとしては実に効率的なのだ。たしかに縦割主義や癒着等の功罪はあるにしても、モチベーションや専門性は高まるであろうし、管理も統一できるというものだ。
そして何よりの功績は、料理のレシピ本「料理の手引き」という本をまとめたことである。約5,000種類のフランス料理のレシピが入っているという。
1903年に出版されているので、篤蔵がパリに行った頃にはすでに出ていた、ということになる。日本で手に入ればねえ・・・、などとかみさんと話しながら観ていた。
ただし、このふたり、必ずしも良い人だったかどうかはわからない。山っけもあるし、投資家とのやり取りの記録を読むと、苦労人でもあったかもしれないけれど、そののし上がり方は十分商売人でもあった。
「真心」が通用するかどうかはわからない。

カトリーヌ・ド・メディチの肖像
フランス料理ももともとはイタリアからやってきたものである。メディチ家のカトリーヌ・ド・メディチがフランス王アンリ二世と結婚したときに、スプーンやフォークやマナーという概念、ついでにアイスクリームなんかを持ち込んだといわれている。
以降、宮廷を中心として発達したフランス料理は「オートキュイジーヌ」と呼ばれ、ヨーロッパ各地の晩餐料理になっていった。いわゆる正式な高級料理という意味だ。
それを改良、発展させ、ホテル・レストランとしての様式を確立したのが、エスコフィエであったのだ。
だから、篤蔵が行った頃のエスコフィエといえば、天下一のシェフという地位にいたわけだ。
で、それが長らく料理の王道として発達していったが、それから半世紀ほど経って流行り始めた「ヌーヴェル・キュイジーヌ」(新しい料理)は、皮肉にも、エスコフィエのつくりだしたものへのアンチから生まれたのである。
もうゴテゴテの料理や皿は出さない、ときに絵画のように美しく、素材重視のスモール・ポーションがいい、というわけなのだ。これが世界にウケた。
いまではさらにそれが発展して、スペインのエル・ブジや各地のアラン・デュカスの店やNYのブーレやロブションなど先端的料理になっていったけれど、そこに絶対的影響を与えたのが、実は日本料理なのであった。彼らは毎年日本に来ている。

エル・ブジの厨房
だからいまのフランス料理は、日本料理なしでは語れないし、フランスなどから多くの料理人が日本に勉強に来ているのだ。ShoyuやShitakeやKombu、UMAMIを知らない料理人はいない。
日本料理はいまでは世界遺産。巡り巡って、そんな時代になったのだ。
エスコフィエや篤蔵が生きていたら、どうおもうだろう・・・?(は/110)

秋山篤蔵