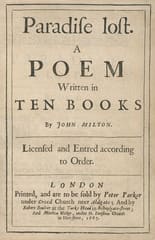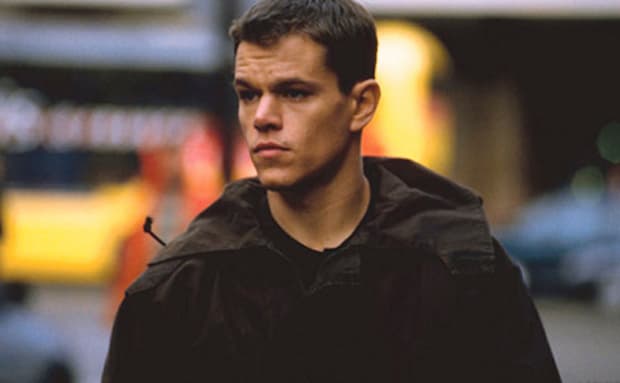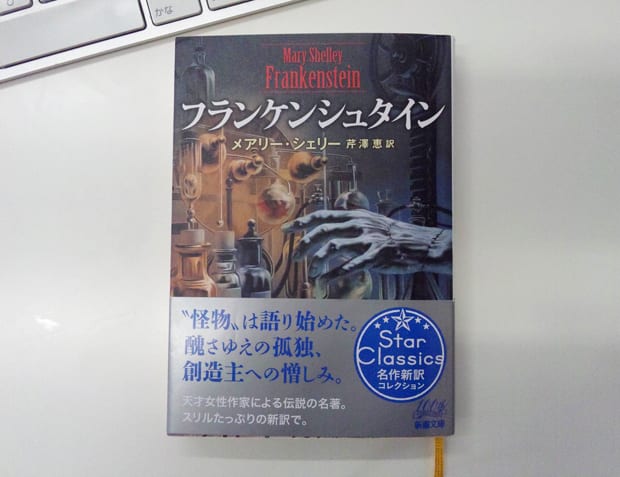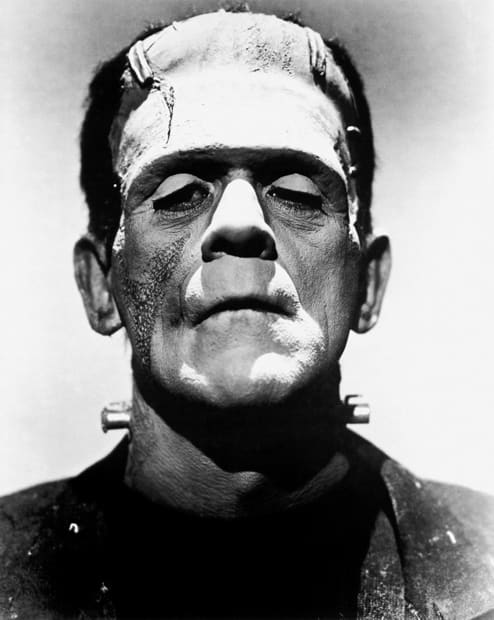先月、松谷みよ子さんが亡くなった。享年89歳の大往生である。
松谷さんは、児童文学の作家でもあるが、昔話や民話の収集家でも知られている、とかみさんに教わった。
は「松谷みよ子って誰だっけ?」
か「えっ? 児童文学の・・・ほら、なら、まず「ふたりのイーダ」を読んだらいい」
は「ああ、そう・・・なんか昔出会ったような・・・、記憶の奥にくすぶっているなにか・・・」・・・・・ふわふわふわ、パチン。
僕自身は、あまり児童文学は読むタイプではない。
だから子供の頃でさえ、いわゆる世界の名作ものといわれる何冊かは少しは読んだけれど、どうせ、女子供の読むものだ、くらいの感じである(子供なのに)。
童話や絵本、日本の児童文学となると、もっと心もとない。
大学生になってからは、ミヒャエル・エンデやレオ・レオーニくらいは・・・、ああ、そう、「シナのごにんきょうだい」は復刻版を買った。シナが差別用語にあたるそうで、長らく廃刊になっていたものだ。
でも、そういえば、小学生の頃はシャーロック・ホームズにハマっていた時期もあったっけ。そのせいで、バイオリン習いたいと言って親を困らせたこともある。
いまでは、かみさん所有のバイオリンを何度か弾いてみたりするけど、そりゃま、一朝一夕にはいかないわけで・・・、最初、いきなり「天然の美」を弾いたので、かみさんは驚いていたが、ネタは、チンドン屋だ。踊りながら弾くと雰囲気だ。子供の頃習っていたら、もう少しグンデルも上達したかもしれないのに・・・。
ともかく、ま、日本の本となると、とんと記憶にない。もっと後で、宮沢賢治や灰谷健次郎くらいかなぁ・・・。
で、あとがきを読んでみたらよくわかった。松谷さんの先生は坪田譲治で、「びわの実学校」で師事したという。坪田といえば、小川未明とともに早大童話会だ。なんだ、あっちか・・・それなら少しわかる。未明は新潟出身者ということで少しだけ親近感があるけれど、なぜかあまり好きになれなかった。
当時多数いただろうプロレタリア志向の児童文学や人形劇団などの若者たちは申し訳ないけれど、どこか怪しいというか、馴染めないものがある・・・。それぞれ子供は好きなのかもしれないけれど、大人同士は大人社会そのものというか、社会派や理論家であってもいいとして、揶揄や罵倒、追求などあって、心の隙間や遊びがない。小川未明のように短気だとなお始末に悪い。
でまあ、その早大童話会から発生した「びわの実会」は、坪田のつくったサークルが起源である。自宅にあったびわの木から取られたらしいが、その後、雑誌「びわの実学校」からは多くの名作が生まれた。そこに合流したのが松谷だったのである。

坪田譲治
坪田自身は「赤い鳥」などにも共鳴していた人。「赤い鳥」といえば、大正の開放的機運のなか鈴木三重吉によって誕生した近代児童文学の金字塔、表紙絵の清水良雄は、デザイン史をやっているときもよく取り上げられてきた。
後世に「赤い鳥運動」として多くの影響を生むことになるが、三重吉がそうした運動の核として「赤い鳥」を発刊したのは、大正時代の機運でもあろうが、それ以前のおとぎ話や小学唱歌が気に入らず、もっとこれからの子供のためにやるべきことがあると言いたかったのだ。一緒にデザインの黎明期が伺えるのが面白い。
その創刊号では、芥川龍之介、北原白秋、高浜虚子、有島武郎、泉鏡花、徳田秋声といったそうそうたる作家が集まった。「蜘蛛の糸」や「一房の葡萄」などはこのときの作品である。
鈴木三重吉も「広島」の生まれで、東大では夏目漱石の講義を受けた経験がある立派な文学者だ。往時の児童文学黎明期にそうやって苦労した人である。

鈴木三重吉。意外と写真は少ない。
「ふたりのイーダ」でも司修の挿絵は重要である。文学もそうだが、絵画の質の高さは子供たちの奥にある審美眼に大きな影響を残すものだ。
この絵の記憶は微かにあったが、もしかしたら司修の絵そのものに記憶があったのかもしれない。内容は全然知らなかったので、遅ればせながらざっと読んでみた。
でも、200頁を越えるので、子供にもたいへんかもしれないが、ひらがなとカタカナのオンパレードで、カタカナの苦手な大人にも結構面倒だ。急に読むペースがダウンする。
ストーリーは、まず、東京に住む直樹とゆう子の兄妹が、母に連れられて、実家のある広島の「花浦」という駅に降り立つところから始まる。花浦は架空の町である。絵に描いたようなおじいさんとおばあさんが出迎えてくれる。
母親の仕事の都合で、夏休みの子供たちを実家に預けに来たのだ。
直樹は小学4年生、ゆう子はたぶん3才くらいだろう。出版が1969年だから、直樹は私より2才上だ。私にもちょうど同じくらいの妹がいたので、時代的にも設定としても妙に実感がわく。ゆう子の描写がリアルだ。
このゆう子が、別名「イーダ」だ。当時はよくいじめられたり嫌な人がいると「イ~ダ!」と顔をしかめて叫ぶのが流行っていた。というか普通にそういう子はいた。
舞台が「広島」という時点で、もうテーマの一端は予測がついた。
直樹はある日、「イナイ・・・イナイ」とつぶやきながら「歩くイス」に出会い、とある廃屋に導かれるが、ある日、イーダもそこにいて、イスと仲良くしている。イスは、「コノコハワタシガカエリヲマッテイタイーダダ」という。
このよくしゃべるイスの言葉が全部カタナナで苦労する。
でも、イーダは自分の妹だ。イスのイーダであるわけがない。この時点で「ふたりのイーダ」がいることになる。ちょうどおじいさんから「世界の生れ変わり物語」のお話を聞いたばかりの直樹は、もし、妹が生れ変わりだったらどうしようと気になっていく。
で、直樹は、この家のことをいろいろ調べはじめるが、ときどき二人のお守りを頼まれていたりつ子という女性がそれを手伝ってくれた。
で、どうも、その家には、殿様の家具もつくった立派な家具職人がいて、その孫が「イーダ」という女の子であったらしい。家の日めくりカレンダーが、8月6日でそのままになっている。やっぱり・・・。
直樹にはその意味はわからなかったが、今日はちょうど8月6日、りつ子が、直樹を広島に連れて行き、精霊流しをしながら、広島の悲惨が過去を話してあげる。
直樹は、イスにそのことを告げ、イーダはもう帰らないこと、ゆう子には背中にはイーダの証であるほくろがないことをいうと、イスはものの見事にバラバラに壊れてしまう。過去とのつながりが断たれ、おもいが喪失したのだ。
直樹の短い夏休みは終わり、東京に帰るが、りつ子から、ある告白の長い手紙が届く、というエンディング。りつ子は白血病で、何度目かの病院からの手紙であった。
直樹の成長、イーダの童心、りつ子の自分探し・・・奇妙なイスがシュールだが、それはそれ、昔話ならよくあることだ。物にも魂はある。思いあまって外に飛び出すこともあるだろう。もしかしたらこれも子供にだけ見える世界があるのかもしれない。そうして、誰もイメージと現実、世界と歴史を引き取っていくのだ。
これは他人事ではない。直樹やイーダの世代が10年分くらいあったとして、約3千万人で、半分が女性だから、そのうちの3分の2がイーダの経験者だとすると、世の中には、ざっと1千万人くらいのイーダがいることになる。
だから、日本では「1千万人にイーダの可能性はある」のだ・・・、あなたももしかしたら未来のイーダかもしれない。

広島も今年70年。いまだに米大統領は来ていない。沖縄の現在と未来も道の見えない政治だが、それでもこれから少しづつ話をすればいい。ただし、民主主義を失ってはいけない。地元の声こそ民の声だ。
何年か前に出た松尾文夫の「オバマ大統領がヒロシマに献花する日」という本が脳裏に浮かぶ。オバマならもしかしたら、とおもった人もたくさんいただろう。
オバマが広島に花を手向け、日本の総理が真珠湾に献花すればいいだけのことだ。お互いにforgive usと言えばいい。過去は過去、あいこの引分けでいいではないか。未来はそこから始まる。
今年8月15日、終戦の日、故筑紫哲也なら「敗戦の日」というかもしれない日に、横浜でワヤンが決まったそうだ。果たして演目は何か・・・、ダランは何を告げるであろう・・・。
広島も、戦争を知らない子供たちも、長い戦後はまだ終わらない。(は)

松谷みよ子さん。
今回いろいろ改めて考えさせてくれた松谷さんのご冥福を心よりお祈りいたします。