大川周明 --ウィキペディア

大川周明 「米英東亜侵略史」
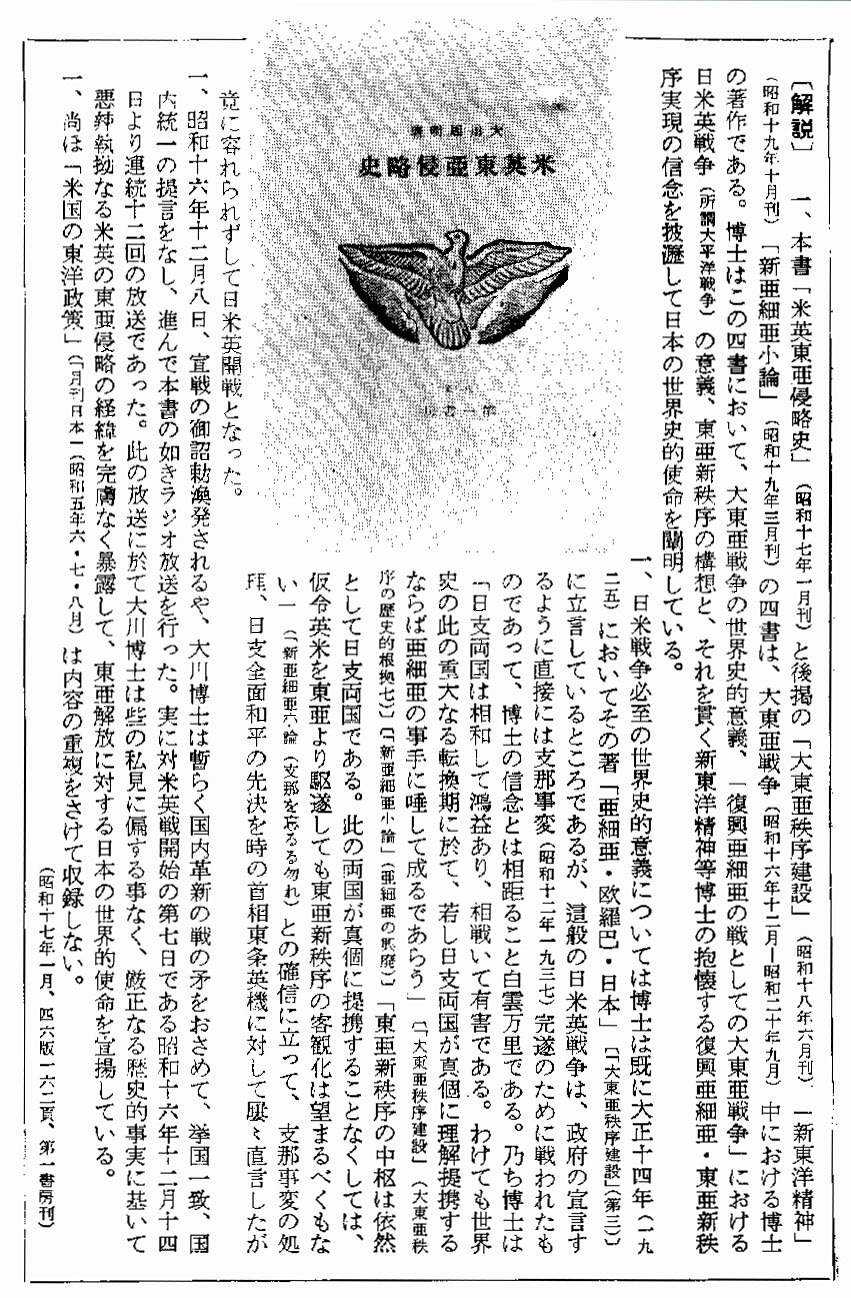
【第一日】 大川周明 「米英東亜侵略史」 序、(第一日)ペルリの日本来航と幕府の対応
第二日
さて第十九世紀前半のアメリカは、
実に急速なる領土拡張の時代でありましたが、其の拡張は植民と征服と買収との三つの方法を以て行はれ、面積は半世紀間に3倍半となつて居ります。此の領土拡張に伴つて当然人口も増加し、是亦約3倍半になつて居ります。
而して此の頃から東洋貿易への参加といふことが次第にアメリカの関心を惹き初めわけても無限の富を包蔵すると思はれた支那市場が彼等の大なる誘惑となり、大西洋を横ぎつて阿弗利加を回り、丁度ペルリが通つた航路によつて印度洋及び支那海に至るアメリカ商船は年々其の数を加へて来たのであります。
従って、此の頃はアメリカ造船業の黄金時代でもあり、1861年の統計に拠りますと、アメリカ商船の総噸数は554万噸、イギリスのそれは591万噸、英米両国を除く世界諸国のそれが580万噸、即ちアメリカは世界商船総噸数の三分の一を占め、イギリスと雁行する商船国となつて居るのであります。
恰も斯かる時に当り、カワフォルニアに金山が発見され、
東部のアメリカ人は言ふ迄もなく、世界各国の人々が、アメリカの太平洋沿岸に殺到して来たので、沿岸一帯は急激なる発展を見るに至りましたが、就中支那労働者の米国に渡航する者が俄に多数となり、同時に米国商品の対支輸出も次第に盛況に赴いたので、従来の如く大酉洋.・印度洋を経て支那海に至る迂回路を棄て太平洋夕横ぎつて支那に至る直接航路を開く必要が迫つて来たのであります。
加之、太平洋はムニつの意味でアメリカ人の心を惹き付けたのであります。第18世紀から第19世紀にかけて捕鯨はアメリカ及びロシアの最も重要なる産業の一つでありましたが、第19世紀初頭に至つて大西洋の鯨は殆んど捕り尽され、同時に北太平洋に夥しき鯨の居ることが知られたので、此の方面に於げる捕鯨船の活躍が頓に目覚ましくなりました。
殊に1842年、米露両国の間に条約が結ばれ、両国互に其の領海内に入つて鯨を捕り得るやうになつたので、アメリカ捕鯨船の日本近海に出没するもの俄に多くなり、1840年代には既に1200隻に及んだと言はれて居ります。
当時何故に彼等がそれほど捕鯨に熱心であつたかと申せば、
蠣燭の原料にする油を取るためであつたのであります。其の頃の欧羅巳は、植民地から搾取した富によつて生活は豪奢となり、各国の宮廷を初め、貴族富豪は競つて長夜の宴を張つて、飲み且つ踊つて居たのであります。
其の宴会揚を真昼の如く明るくするために、数限りなく蝋燭を灯したのでありますが、其の蝋燭の白蝋が鯨油から取れるので、贅沢が増せば増すほど、鯨が蝋燭に化けて欧羅巴の金殿玉楼を照らすことになつたのであります。
斯様な次第で太平洋に出漁する捕鯨船のためにも、暴風や難破の際の救謹所又は避難所が必要になり、米支直接航路のためには中間の貯炭所又は食料補給所が必要になり、かくの如き必要のためにアメリカは我国に着目するに至ったのであります。
さういふ経緯を経てアメリヵに於ける日本訪問の機が次第に熟し、1850年には米国議会が此の事を決議し遂にペルリの日本派遣となつたのでありますが、其の時に政府がペルリに与えた訓令の要旨は下の如きものであります。
即ち第一には
アメリカ船舶が日本近海で難船し又は暴風を避けて日本の港湾に入つた場合、日本はアメリヵ人の生命財産を保護するやう永久的なる和親条約を結ぶこと、
第二はアメリカ船舶が燃料食糧の補給のために入港し得る港を選定すること、
第三には通商貿易のために二、三の港を開かせることであります。
ペルリは日米通商の下地を作つて帰国し、
其の後を受けて日米条約を締結したのはハリスであります。此の条約調印のために井伊大老の首が飛び明治維新の機運を激成したことは申上げるまでもありませぬが、私は当時の談判の経緯を仔細に書残せるハリスの日記から、二、三の重要なる箇処を紹介して置きます。
先づ彼は
『従来幕府の役人は、日本の主権者たるミカドに対して、動もすれば之を軽んずる傾向があつたが、近来は盛んにミカドの絶対権を主張するのを見て、大勢の推移したことが感ぜられる。予は従来将軍を以て事実上の日本の君主と思つて居たが、今やミカドが名実共に主権者にして、将軍は其の仮装的統治者であるやうに思はれ初めた』 と申して居ります。これはハリスの談判進行中に俄然として勤皇論が擡頭し来れることを示すものであります。
また彼は
『日本といふ此の不思議な国の数々の中で、ミカドの如く予の判断を苦しめたものは無い』 と書いて居ります。 此のミカドの不思議は、ひとりハリスのみのことでありませぬ。それは90年後の今日のアメリカ人に取つても、依然不思議のものとなつて居ります。
但し此度の日米戦争に於ける日本の勝利の根抵を奥深く探ることによつて、或はアメリカ人も初めて此の不思議を理解するに至るかも知れません。私は其の然らんことを切に祈つて止まぬものであります。
さて此の頃のアメリカは、
当時の大統領ビューカナンが1857年5月、支那使節に任命されたヰリアム・ピヅドに与へた教書に於て 『支那に於て我が同胞の通商と生命財産の保護以外には、如句なる目的をも追求せざることを銘記せよ』 と述べて居る通り、当時支那に起りつつありし長髪賊の乱に対しても傍観的態度を取り、ペヘルリが画策せる琉球占領計画をも 『面白からぬ提案』 として斥け、また之と時を同じうして台湾を米国の保護領とせよといふ宜教師パルケルの画策をも黙殺して居ります。
時の国務長官シュゥォードは、
将来太平洋が世界政局の中心舞台たるべきことを力強く主張したので、歴史家は好んで 『シュウォード時代』 又はシュウォード政策といふ言葉を用ゐまするが、実際に於ては、何等積極的活動を太平洋又は東洋に於て試みて居りませぬ。
1850年に至つて一旦は著しく活濃となつたアメリカの太平洋及び支那に対する活動は、1861年に始まれる南北戦争以後、1898年のフィリピン占領に至る四十年聞、甚だ消極的となつたのであります。
蓋し此の時代は未だ金融資本主義が現れず、
帝国主義の未だ確立せられない以前であつたので、欧米の東洋政策、わけても対支政策の領域を支配して居た産業資本は、支那を自国製品の販売市場として、又は原料生産地として、最大限度に之を利用することを主たる目的として居たのであります。
例へば1867年、アメリカ政府がロシアからアラスカを買収した時に、国民は政府の帝国主義的動向を激しく非難し、国内に未だ耕されぬ土地が彩しいのに、何の必要あつて斯様な無駄な買物をするのか、白熊でも飼ふつもりかと憤つて居ります。
また京城駐剳米国公使が、
朝鮮に於ける宣教師と共力してアメリカ勢力を京城に扶植せんとした時も、ワシントン政府は該公使に対して 『朝鮮の政治に干渉することは貴下の権限外なり』 とたしなめて居ります。日清戦争(1894~95年)の時も、時の国務長官グレシャムは 『米国は武力を行使し、又は欧羅巴列強と提携して此の戦争に干渉する意図なし。米国は表面は好意的中立を守り、内実は日本にのみ好意を寄せんとするものなり』 といふ訓令を、京城駐剳公使に与へて居ります。当時のアメリカは、日本の膨脹はアメリカを脅威せずと考へて居たのであります。
而も日清戦争は東亜政治史全体の偉大なる転回点となつたのであります。即ち日本に破れた支那が此の時初めて封建支那の無力と解体とを全面的に暴露せるに乗じて、恰も此の頃に擡頭し来れる帝国主義が、孤立無援の支那を掠奪の対象として、激しく殺到し初めたのであります。而して之と共にアメリカの東洋政策も、俄然面目を改めたのでおります。
さてシュウォードの太平洋制覇の理想は、
只今申上げた通り、約半世紀の間、アメリカの具体的政策とはならなかつたのでありますが、彼の理想は一部のアメリカ政治家によつて堅確に継承されて来たのであります。この理想は1880年代から次第にアメリカに浸潤し初めて来た帝国主義と相結んで、アメリカの東亜政策も漸く積極性を帯びみやうになりました。
而して此の新しき帝国主義の最も勇敢なる実行者は、今日の大統領フランクリン・ルーズヴェルトの伯父セオドル・ルーズヴェルトであり、其の最初の断行が1898年の米西戦争を好機として、フィリピン群島及潔グアム島を獲得したことであります。
戦争の当初に於て、時の大統領マッキンレーは
『アメリカはフィリピン群島の強制的併合を行はんとするものに非ず、予の道徳的規範によれば、かくの如きは犯罪的侵略なり』 と声明したに拘らず、後には 『神意』 と称してフィリピン統治をアメリカに委任することを要求したのであります。
その一切の献立を行つたのが、取りも直さず海軍長官であつたルーズヴェルトでありまず。アメリカはスペインの統治に不満なりしフィリピン独立運動者を煽動し、之を援助してマニラのスペイン守備隊を攻撃させました。
此の時アメリカは数々の約束を彼等に与へたが、
彼等を片付けるに足る軍隊がアメリカ本国から到着するに及んで一切の約束を蹂躙し去つたのであります。即ちフィリピン独立党はアメリカに欺かれて、其の手先となつてスペイン軍と戦ひ、然る後に彼等自身も葬り去られたのであります。
当時の日本人民間にはフィリピン独立運動に援助を与へた人々も多く、アメリカの悪辣なる手段を痛憤したのでありますが、日本政府は 『如何なる国が南太平洋で日本の隣邦となるよりも、アメリカが隣邦となることを欣ぶ』 として、米国のフィリピン併合に賛意を表したのであります。
いまやアメリカは
『イギリスが香港に拠る如く、我等はマニラに拠る』 と公言し、フィリピンを根城として東亜問題に容喙する実力を養ひ初め、1899年には国務長官ジョン・へーの名に於て、名高き支那の門戸開放を提唱し、翌1900年には、支那の領土保全を提唱したのであります。
此の二つの提唱は、アメリカ人の言分によれば、或る程度まで利他的政策であり、支那に同情し支那を援助せんとする希望から出たものであるといふのでありますが、それは偽りの標榜であります。
第一にジョン・へーは此の政策を提唱するに当つて、
毫も支那自身の希望や感情を顧みず、支那政府は門戸開放に同意なりや否やの問合をさヘアメリカから受けたことが無かつたのであります。ジョン・へーの提唱は、支那に対するアメリカの権利を一方的に主張したもので、要するに支那はアメリカの同意なくては如何なる国にも独占権を与へてはならぬ、関税率を決めてはならぬ、相互条約を結んでもならぬといふ要求であります。
蓋し欧羅巴列強は、アメリカに先んじて支那に於てそれぞれ勢力範囲又は利益範囲を確立して居たので、立遅れたアメリカは、支那に対する自国の政治的・経済的発展に大なる障碍の横はれるに当面し、之を撤去するために門戸開放を唱へたのであります。
また其の領土保全主義は、支那が列強によつて分割せらるる揚合、アメリカの現在の準備と立揚では、自分の分前が甚だ少なかるべきことを知つて居たので、支那に於ける自国の利益を消極的に守るために他ならなかつたのであります。
即ちロシア及びイギリスが、既に武力と襖土占領の手段によつて其の勢力を支那に張り、殊にロシアの如きは将来も同様の手段を遂行せんとするに対し、アメリカは門戸開放と領土保全とを提唱する以外、支那に於ける現在及び将来の帝国主義的利益を擁護するために、如句なる現実の手段をも有たなかつたのであります。
〔続く〕
大川周明 「米英東亜侵略史」(第三日) ハリマンの満鉄買収政策を巡る日米の確執


















