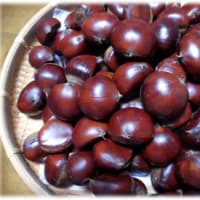今日から春とは言え、まだまだ寒い朝、晴れ 時々 曇り、最高気温14℃(+2)、洗濯指数40夕方までにはなんとか乾きそう、との予報。
時々雲にさえぎられるのですが、全般にやわらかい春の日が差し、そこそこ気温も上がり比較的過ごしやすい一日となった北摂。


今日は新しくボランティアガイドを目指している人の講座「歴史の散策入門」の富田コースに飛び入りのサポーターでコースの一部旧富田郷内にお邪魔してきました。
サポートといっても体力のないとっつあんが皆さんに付いていける訳でもなくコースを先行合流しながらとりあえず同じコースを歩いたというだけ。
寒さと体調不良と倦怠感で歩けなくなっていた体に鞭打って、久しぶりの4700歩でした、ちょっと頑張った感じ。
今日から弥生、春ということで、今日の1枚の写真は、昨年撮ったもので、春の訪れを感じる「チューリップの花」です。
「弥生」の由来は、「弥」には「いよいよ」「ますます」の意味があり、草木が、いよいよ生い茂る月の意味で、「木草弥(きくさいや)生い茂る月」→「きくさいやおいづき」→「やよい」となったという説が大多数です。
3月には、その他「花月(かげつ)」「花見月(はなみづき)」「桃月(とうげつ)」「桜月(さくらづき)」「花津月」「夢見月」などの異称があり、春爛漫の月です。
春が来た 春が来た どこに来た。 山に来た 里に来た、 野にも来た。
花がさく 花がさく どこにさく。 山にさく 里にさく、 野にもさく。
鳥がなく 鳥がなく どこでなく。 山で鳴く 里で鳴く、 野でも鳴く。
(「春が来た」高野辰之作詞・岡野貞一作曲/文部省唱歌(三年))
大きくてカラフルな花を咲かせるチューリップ、桜とともに陽気な春の色を感じさせる花です。
チューリップはトルコを原産地とするユリ科の植物で、オランダが有名な生産地です。
日本には江戸後期に伝わり、「ぼたんゆり」と呼ばれていた時期もありました。
名前の由来はトルコ語の「tulipan(ターバン)」。
チューリップ全般の花言葉は、「思いやり」「博愛」です。
赤い花の花言葉は「愛の告白」、黄色い花の花言葉は「望みのない恋」「名声」、オレンジ色の花の花言葉は「照れ屋」、白い花の花言葉は「失われた愛」「新しい愛」、紫色の花の花言葉は「永遠の愛」、ピンクの花の花言葉は「愛の芽生え」「誠実な愛」です。
チューリップは恋愛にまつわる伝説が多い花で、「男性からの積極的な求愛に困惑した美しい女性が、女神に頼んで花にしてもらったのがチューリップ」とか「恋人の死を知って身を投げた男性の真っ赤な血だまりからチューリップが咲いた」とか、情熱的でありながらどこか悲しい物語に登場します。
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
明日3月2日(戊戌 つちのえいぬ 友引)
●「遠山の金さんの日」
1840(天保11)年のこの日、遠山の金さんこと遠山左衛門尉景元(通称・金四郎)が北町奉行に任命されました。
遠山景元は天保の改革を行った老中・水野忠邦に近い人物として重用されました。
1843(天保14)年2月24日まで在職しています。
江戸には北町奉行所と南町奉行所があり、1ヶ月ごとに、交替で勤務にあたっていました。
●「ミニチュアの日」
3月2日「ミ(3)ニ(2)」の語呂合せから、ミニチュアや小さいものを愛そうという日です。
ミニチュアのボトルとか、ミニチュアハウス、豆本など、世の中にミニチュアは意外と多いです。ミニスカートの日ではないそうです。
●「中国残留孤児の日」

1981(昭和56)年、中国残留日本人孤児47名が、肉親探しの為に、厚生省の招待で初めて公式に来日しました。
このうち29名の身元が判明しました。
●「出会いの日」
人と人の出会いは友情を生み、愛を生む。出会いに感謝して新たな愛を育む日をと、再婚の人などに素敵な出会いを提供する会員制組織の株式会社カラットクラブの代表でライフアップコンサルタント、マリッジカウンセラーの岡野あつこ氏が制定しました。
日付は3と2で出会いを意味するミーツ(meets)と読む語呂合わせから。
●「若狭お水送り」
3月12日に奈良東大寺二月堂で行われる「お水取り」に先がけて、毎年3月2日に行われる小浜市神宮寺の「お水送り」は、奈良と若狭が昔から深い関係にあったことを物語る歴史的な行事です。
奈良のお水取りが終わると春が来る(^^♪ 関西の人々は、毎年この春の兆しを待ちわびます。
この奈良東大寺二月堂のお水取り(修ニ会の「お香水」汲み)は全国にも有名な春を告げる行事ですが、その「お香水」は、若狭鵜の瀬から10日間かけて奈良東大寺二月堂「若狭井」に届くといわれています。
午後5時半ごろ、白装束の僧がホラ貝を吹きながら山門をくぐり入場。午後6時からお堂で修二会を営み、「だったん」の行へ。7メートルもあろうかと思われる巨大松明を「エイッ、エイッ」とのかけ声とともに振り回します。
いよいよ大護摩に火がともされると、炎が水面に燃え広がったようになり、住職が送水文を読み上げ、邪気払いをし、香水を遠敷川に流します。香水は10日後、奈良東大寺の「お水取り」で汲み上げられます。
若狭神宮寺 福井県小浜市神宮寺30-4 TEL0770-56-1911
![]() 「にほんブログ村」ランキング参加中です。
「にほんブログ村」ランキング参加中です。
今回は4490よかった!と思われたつちのえとららポチっとお願いします。