
今日の大阪は、太陽がじりじり、気温もぐんぐん上がり、25。9度…、春を通り越し初夏の陽気となりました。
ウォーキングは、高槻の「新川の桜堤」から芥川を遡り、「ゆめ桜通り」と桜の名所を巡り、素晴らしい花を満喫し、旧西国街道を歩いてきました。約16,000歩でした。
高槻市の桜指定公園「新川の桜堤」は、昭和53年に開設されました。
高槻市内の中心部を南北に流れる芥川の左岸、城西橋から芥川大橋の間の新川沿いに南北900m地元の人が植えた約100余本の立派な桜が咲き誇り、市民の目を楽しませる桜の名所です。


芥川の左岸に沿って流れる新川は、元々農業用水として利用されていたそうですが、今は遊歩道なども整備されていて、花見の散歩には最適です。

満開の桜に、芥川から吹く風によって花びらが舞い散る光景は絶景です。

今年の花見は、地元中心にしていますが、近くに、こんなに素晴らしい、桜の名所が沢山あるのを、今まで知らなかったのですから、随分と損をした感じです。
ところで、「花見」といえば桜です。その桜にも、いろいろ種類がありますが、うすピンク色の「染井吉野(そめいよしの)」がもっとも有名で、日本の桜の8割以上は、この染井吉野だそうです。
染井吉野(ソメイヨシノ)は江戸時代に、江戸駒込の染井村から植栽が始められました。オオシマザクラとエドヒガンの雑種とされます。初めは見事な桜の代名詞として「吉野桜」と 呼ばれていましたが、誕生地の「染井」の名を加えて「染井吉野」になりました。
明日は「駅弁の日」です。
日本鉄道構内営業中央会が1933(平成5)年に駅弁のPRを目的に制定しました。
4月は駅弁の需要拡大が見込まれる行楽シーズンであり、「弁当」の「とう」から10日、さらに「4」と「十」を合成すると「弁」に見えることからです。
駅弁のおいしさ、楽しさをより多くの人に知ってもらうのが目的です。
日本初の駅弁登場は、1885(明治18)年7月16日の宇都宮駅という説が有名ですが、夏は弁当がいたみやすいため行楽シーズンの4月が選ばれました。
また「女性の日」です。
労働省(現在の厚生労働省)が1949(昭和24)年に「婦人の日」として制定。1998(平成10)年に「女性の日」に改称されました。
我が国の婦人が初めて参政権を行使した1946年(昭和21年)のこの日を記念して設けられたもので、この日から一週間を「婦人週間」として婦人の地位向上のための活動が行われます。
さらに「建具の日」です。
4月10日の語呂合せで「良い(4)戸(10)」の意味をこめて、全国建具組合連合会が1985年(昭和60年)に制定。
住宅の新築・増改築が盛んになり、建具に関心の集まる春にということもあります。
そして「天皇陛下結婚記念日」です。
皇太子明仁殿下と民間から初の皇太子妃となった美智子さまの結婚の儀が行われたのが1959(昭和34)年のこの日。
軽井沢のテニスコートでの出会いによる皇太子の一目惚れという運命的なエピソードと若く美しい美智子さまの清楚で可憐な様子、古くからの慣習を乗り越えてのご成婚は日本中を熱狂させるのに充分過ぎるほどでした。
6頭立てのオープン馬車で行われた皇居から東宮御所へのご成婚パレードには、“ミッチー”を一目見ようと約53万人が沿道に詰めかけました。
この模様を、NHKをはじめ、各テレビ局はこぞって生中継し、テレビの普及率アップに大いに貢献しました。
その他に「インテリアを考える日」「ヨットの日」「四万十の日」「瀬戸大橋開通記念日」「仕入れの日」「ステンレスボトルの日」でもあります。











 「ポチッ」とクリック、応援お願いします。私のポイントが上がります。
「ポチッ」とクリック、応援お願いします。私のポイントが上がります。


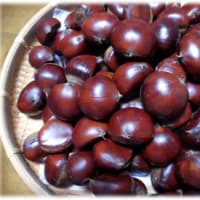






私は4時に起きて京都の哲学の道へ妖しい桜を見に行きました≧(´▽`)≦アハハハ早朝は人が少ないのでゆっくりと撮影できました。その後、山科の疎水へ行きました。こちらは散りかけで、散っている花びらを撮りたかったのですが、思うように撮れませんでした。今年はたくさん、桜を見ることが出来て大満足です。とっつあんさんもですよね?!
哲学の道も、山科の疎水も桜は素晴らしいですね。
今年は、足元を見つめなおしています。
意外なと言うか、知らなかった初めての所ばかり探しています。
芥川の桜は、子どもの頃に見たっきりで
こんなに綺麗だったんだ~、とうっとりしています。
うちでお花見気分を味わえました。
有難うございます~
半そで姿の子供も見かけました
ウォーキングしながら あちこちの桜見物なんていいですね
この景色も素敵ですね
これからは散りゆく桜になっていきますね
本当に日本は美しい国なんですね
薄ピンク
うっとりします~♪
チビ太さん
ぶぶさゆりさん
ありがとうございます。
今日も桜を求めて彷徨い歩いてきました。
少し山手なので、大丈夫と思っていたのですが、やっぱり散り始めていました。
紫の花は、芝桜、黄色い花はタンポポです。