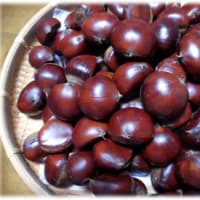春眠暁を覚えずの暖かい春の朝、晴れ、最高気温23℃(+1)、洗濯指数90バスタオルでも十分に乾きそう、との予報。
春本番、太陽ギラギラ日当たりは暑いほどのポカポカ陽気の北摂。


西河原公園から安威川へご近所の桜をと思っていたのですが、お腹の調子がすっきりせず、外出は残念…、いつになったらスッキリするのやら…。
今日の1枚の写真は、とっつあんちの団地の庭に咲いていた花がブドウの実のように見える「ムスカリ」です。
「ムスカリ」はキジカクシ科の多年草 で、花期は3月~5月です。
青や紫色をしたぶどうのような房状の花を咲かせる姿が印象的な球根植物です。
「ムスカリ」という名前は、ギリシア語の「moschos(ムスク)」(麝香)に由来し、原種にムスクの香りを思わせる芳香を持つ種があることからきているそうです。
品種によっては由来のとおり甘い香りを持つものもあります。
また、花がブドウの実のように見えることから、別名「ブドウヒアシンス」とも呼ばれます。
英名ではグレープヒヤシンス(Grape hyacinth)と呼ばれ、ブドウのような青紫色の花を咲かせるムスカリ。
花言葉は、「通じ合う心」「夢にかける思い」「寛大な愛」「明るい未来」「失望」「失意」「絶望」です。
ムスカリの花言葉は両極端な意味のを持ちます。
花言葉では紫色が悲しみのシンボルになることが多く、ムスカリの花言葉「失望」「失意」もこれにちなみます。
ギリシア神話において大量の血を流して死んでしまった美少年ヒュアキントスのその血から紫のヒヤシンスの花が咲いたといわれ、紫のヒヤシンスは悲しみのシンボルといわれるようになりました。
このムスカリ、1960年代に6万年前ネアンデルタール人が埋葬されたとされる土から、花粉が発見されたことにより、埋葬された死者に手向けられた最古の花としても話題になりました。
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
明日3月29日(庚申 かのえさる 友引)
●「マリモの日」
1952(昭和27)年のこの日、北海道・阿寒湖のマリモが国の特別天然記念物に指定されました。
まりもは淡水系の藻類で、本種はヨーロッパやシベリアなどにも分布していますが、北海道の阿寒湖が分布の南限となっているため、特別天然記念物に指定されています。ちなみに、特別天然記念物の「特別」とは場所が限定されていることを意味しています。
同時に、富山湾のホタルイカ群遊海面、鹿児島県出水市のナベヅル、高知のオナガドリなども国の特別天然記念物に指定されました。
●「八百屋お七の日」
1683(天和3)年、18歳の八百屋の娘・お七が、3日間の市中引回しの上、火あぶりの極刑に処せられました。
前年12月28日の大火で避難した寺で出会った寺小姓・生田庄之介のことが忘れられず、火事になればまた会えると考えて3月2日の夜に放火、火はすぐに消しとめられましたが、お七は御用となりました。
当時は放火の罪は火あぶりの極刑に処せられていましたが、17歳以下ならば極刑は免れることになっていました。
そこで奉行は、お七の刑を軽くする為に「おぬしは17だろう」と問いますが、その意味がわからなかったお七は正直に18歳だと答えてしまい、極刑に処せられることになってしまいました。
お七が丙午[ひのえうま]の年の生まれであったことから、丙午生まれの女子が疎まれるようになりました。
●「作業服の日」
ものづくり大国の日本では多くの労働者が第二次産業に従事しています。
日本の屋台骨を支えて日々労働に従事している作業服姿の人たちに感謝の気持ちを込め、作業服を販売する埼玉県川口市の「まいど屋」株式会社が、3(作業)29(服)の語呂合わせから制定しました。
新年度の4月1日から新しい作業服でさらに頑張ってもらいたいとの願いを込めてとのことです。
●毎月29日は、「肉の日」です。
●「求菩提山お田植祭り(松会)(くぼてさんおたうえまつり(まつえ)」
県指定無形民俗文化財で農作業の所作を御神歌に合わせて行う豊年予祝の行事です。演技の最後には参加者全員が場内を一巡し、秋の豊作を祈ります。
求菩提山で行われる御田植祭はお神歌が流れる中で、畦切りから田植えまでの農耕の実際をユーモラスなしぐさで表現します。
修験者たちによって、神仏習合の行事として毎年春にその年の豊作を祈って行ってきた祭りが「松会」です。
この「松会」の行事には御田植の行事と松柱の幣切り行事とがありましたが、現在、求菩提山ではお田植祭だけが毎年3月29日に国玉神社中宮で行われています。
国玉神社 福岡県豊前市求菩提 0979-82-1111(豊前市教育委員会) ![]() 「にほんブログ村」ランキング参加中です。
「にほんブログ村」ランキング参加中です。
今回は4146です。「よかった!」と思われたらポチっとお願いします。