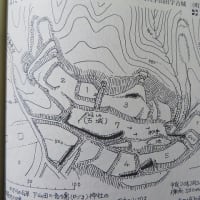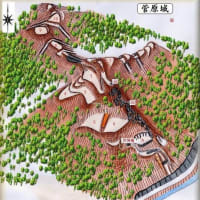北毛の抗争
天正十四年(1582)七月、吾妻・利根を支配する真田昌幸は家臣日置五左衛門尉を後北条方の陣に派遣し、恭順の意を表した。しかし、同年九月には突然徳川家康に従った。九月二十八日の書状で、家康は味方に付いて忠信を示せば、上州長野一跡に加え、甲州で二千貫文・信州諏訪郡と当知行地を保証すると述べている。長野一跡は長野氏の旧領の事であるが、この時は後北条氏の支配地であり、切り取りを認めるということを意味する。また、信州諏訪郡は諏訪頼忠が領有しており、諏訪氏の領地替えが必要であった。従ってこの約束は真田側からみれば、空手形に等しいものであった。
後北条方は昌幸の約束を「真田逆心」と捉え、この後、大戸口と赤城西麓方面から軍勢を送り込んで真田との戦いを進めた。真田の豹変の背景には、後北条氏と徳川氏との対立がある。家康は本能寺の変後、同年八月に甲斐を切り取るため進出し、新府に陣を敷き対陣していた。家康はこの戦いを有利にするため真田を寝返らせ、後北条氏の背後を混乱させようとしたのである。この対陣は十月に和睦となった。和睦の内容は甲斐・信濃は徳川領とする代わりに、上野は後北条氏の領国とする、家康の娘(督姫)が氏直の許に輿入れする。真田氏は家康に属し、吾妻・利根二郡を後北条氏に引き渡す、吾妻・利根二郡の替地を徳川が信濃で真田に与えるというものであった。
天正十二年に入ると、家康と秀吉の対立が深まり、同年三月には小牧・長久手で対陣することになった。この戦いで家康は後方の不安を除くため後北条氏との同盟を一層強力にする必要となった。そのために徳川・後北条氏の和睦の条件である真田領の吾妻・利根二郡の割譲の早期実行を推進しようとしたのである。しかし、ここへきて昌幸は吾妻・利根二郡は自力で切り取ったものであるとして引き渡しを拒否した。これは家康の面目をつぶすもので、徳川との関係を断絶することを意味した。そこで昌幸は秀吉に従っている上杉景勝に接近して、徳川の動きを牽制した。
天正十三年七月十五日、上杉景勝は昌幸に起請文を与えた。その内容は服属を認めること、敵(徳川)が攻めた場合後詰めの兵を送ること、沼田・吾妻・小県・坂木荘などの本領を安堵すること、加えて佐久郡と甲州で一郡、さらに「上州長野一跡」を与えるなどであった。これに対し家康は、八月についに上田城攻めを行った。徳川軍に加えて信濃の武士一万数千の兵が上田城を囲んだが、昌幸は地の利を生かした策略を用いて上田城を守り切った。その後も上田城攻めの機会を狙ったが、十一月に撤退した。その理由は、この頃徳川の重臣石川教正が秀吉の許に走り、家康側の機密がすべて筒抜けとなってしまうという事件が起こった為である。また、昌幸は秀吉に援助を求める書状を送り、その理解を得たことも有利に働いたとみられる。これ以降秀吉は家康を膝下に取り込むための道具として真田氏を利用する。天正十四年十月、家康も秀吉に臣従を誓い、大阪城に出仕した。
この石川教正の裏切りですが、絶妙なタイミングで真田氏を秀吉は援けることになります。真田と徳川との争いを見越していて、いつか決め手のカードとして用意していたのであれば秀吉恐るべしとなります。
次回 大戸浦野氏の没落
天正十四年(1582)七月、吾妻・利根を支配する真田昌幸は家臣日置五左衛門尉を後北条方の陣に派遣し、恭順の意を表した。しかし、同年九月には突然徳川家康に従った。九月二十八日の書状で、家康は味方に付いて忠信を示せば、上州長野一跡に加え、甲州で二千貫文・信州諏訪郡と当知行地を保証すると述べている。長野一跡は長野氏の旧領の事であるが、この時は後北条氏の支配地であり、切り取りを認めるということを意味する。また、信州諏訪郡は諏訪頼忠が領有しており、諏訪氏の領地替えが必要であった。従ってこの約束は真田側からみれば、空手形に等しいものであった。
後北条方は昌幸の約束を「真田逆心」と捉え、この後、大戸口と赤城西麓方面から軍勢を送り込んで真田との戦いを進めた。真田の豹変の背景には、後北条氏と徳川氏との対立がある。家康は本能寺の変後、同年八月に甲斐を切り取るため進出し、新府に陣を敷き対陣していた。家康はこの戦いを有利にするため真田を寝返らせ、後北条氏の背後を混乱させようとしたのである。この対陣は十月に和睦となった。和睦の内容は甲斐・信濃は徳川領とする代わりに、上野は後北条氏の領国とする、家康の娘(督姫)が氏直の許に輿入れする。真田氏は家康に属し、吾妻・利根二郡を後北条氏に引き渡す、吾妻・利根二郡の替地を徳川が信濃で真田に与えるというものであった。
天正十二年に入ると、家康と秀吉の対立が深まり、同年三月には小牧・長久手で対陣することになった。この戦いで家康は後方の不安を除くため後北条氏との同盟を一層強力にする必要となった。そのために徳川・後北条氏の和睦の条件である真田領の吾妻・利根二郡の割譲の早期実行を推進しようとしたのである。しかし、ここへきて昌幸は吾妻・利根二郡は自力で切り取ったものであるとして引き渡しを拒否した。これは家康の面目をつぶすもので、徳川との関係を断絶することを意味した。そこで昌幸は秀吉に従っている上杉景勝に接近して、徳川の動きを牽制した。
天正十三年七月十五日、上杉景勝は昌幸に起請文を与えた。その内容は服属を認めること、敵(徳川)が攻めた場合後詰めの兵を送ること、沼田・吾妻・小県・坂木荘などの本領を安堵すること、加えて佐久郡と甲州で一郡、さらに「上州長野一跡」を与えるなどであった。これに対し家康は、八月についに上田城攻めを行った。徳川軍に加えて信濃の武士一万数千の兵が上田城を囲んだが、昌幸は地の利を生かした策略を用いて上田城を守り切った。その後も上田城攻めの機会を狙ったが、十一月に撤退した。その理由は、この頃徳川の重臣石川教正が秀吉の許に走り、家康側の機密がすべて筒抜けとなってしまうという事件が起こった為である。また、昌幸は秀吉に援助を求める書状を送り、その理解を得たことも有利に働いたとみられる。これ以降秀吉は家康を膝下に取り込むための道具として真田氏を利用する。天正十四年十月、家康も秀吉に臣従を誓い、大阪城に出仕した。
この石川教正の裏切りですが、絶妙なタイミングで真田氏を秀吉は援けることになります。真田と徳川との争いを見越していて、いつか決め手のカードとして用意していたのであれば秀吉恐るべしとなります。
次回 大戸浦野氏の没落