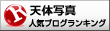高気圧が近づいていた。今夜は間違いなくすっきり晴れる。月は明るいが、それでもせっかくの休みだ。行かない手は無い。という訳で丘に上がったのは午後2時頃だった。11月も半ばなだけに日差しはずいぶん傾いていて、昼下がりにもかかわらずあたりが夕暮れのような色宇宙(そら)に続く丘ホームページ :http://taketorian.org合いだ。丘のみかんもずいぶん赤く見える。今年はみかんが豊作で、どの木にもたわわに実がなっている。時折間引いてきたが、それでも枝が折れそうなほどに実が付いていた。しかも今年はここにきて雨が多く、木に付いたまま腐っている実もあちこちに見られる。
先週丘に上がった時にはまだ葉が緑色をしていたこのネーブルの老木は一週間のうちに枯れてしまった。自分でつけた実を持ち堪えることが出来なかったのだ。実はほとんど熟れているように見える。でも食べたら多分渋みが有る。可哀想だけれどこのまま置いておくしかない。

今日ここに来たのは2台のカメラのテスト撮影が目的だった。一つは上の写真を撮ったコンデジCANONG7X。もう一つはちょうど1年前に手に入れた赤外線改造カメラEOSkissX6iだ。ハサミを手に、間引きを兼ねてみかんの収穫をしながら夕暮れを待った。
宇宙(そら)に続く丘ホームページ :http://taketorian.org/