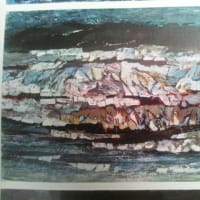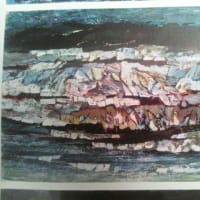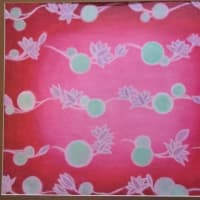一昔前の日本では、夫のDV被害に悩む妻が、
宗教団体に助けを求めることが多かった。
例えば、江戸時代には縁切りのための駆け込み寺があり、
現代のDVシェルターのような役割を果たしていた。
そこに三年間とどまれば、
夫と別れることができたのである。
そうした伝統からであろうか。
明治以降も、DV被害の妻たちが、
悩みの持ち込み先として新興宗教を選ぶ傾向があったと思う。
しかし、縁切り寺とは違い、
そこで教えられるのは夫から逃げることではなく、
自らの心得違いを治せば夫は変わる、という考えであることが多かった。
明治になって、庶民に対しても家父長的な制度が適用されたせいだろうか?
“夫は天であり、尊いものであるから、
女たるもの、無私の心構えで仕えなければならない”
夫が父長として、一家の大黒柱としてきちんと役割を果たし、
幸せな家庭が維持されることは、妻の働きに依るとの考えがあった。
そのため、DVに対して、逃げ出すという選択をするのではなく、
宗教の力を借りてなんとかしようとする傾向が生まれたのかもしれない。
***
しかし、DVの問題は一般に、妻の側だけに問題があることは少なく、
夫の側の問題の方が、より根深い方が多い。
DV対策の関係者の中には、DVを行う人格は、なにをしても治らない、
との意見さえあるのだ。
妻の背に何もかもを負わせるのは、明確に過重な負担である。
到底DVに耐えられない場合、妻がすべき適切な選択は、
多くの場合、逃げることであろう。
ことに、子供にまで暴力が及び、その精神的な健康に差し障りがある場合、
その健康な発達が妨げられつつある場合、
子供を守るために母がとるべき勇気ある行動とは何だろう?
自分の何が悪くて夫がこうであるか、思索を続けることだろうか?
神仏に、なんとか夫の暴力を止めてくれるよう、
夫が変わりますように、と祈ることだろうか?
いや、むしろ、子供を保護するためにも、
勇気を持って安全な場所へ逃げ出すことが、
一番現実的であり、潔いやり方なのではないか?
宗教によって夫を変えようとする試みが、
逃げ出して、自分で生活を立てていく事への不安、
あるいは、周囲や親族から後ろ指さされる事への不安などからくる、
単なる躊躇いではないか、よく考えてみる必要があるだろう。
***
宗教によって、夫が変わることがあるだろうか?
むしろ、宗教によって妻が内心の不満を隠し、
その決断力のなさに目をつぶって、躊躇を続けるための口実を
与えられることの方が多いように思う。
夫の人格的な問題は、本来、夫自身の問題であり、
妻ではなく、彼がその問題に立ち向かう必要がある。
また、夫婦が互いに、直霊の要求する相手ではない場合にも、
不満が募り、DVとして顕れる場合はあるだろう。
もちろん、妻の側が、
夫やその欠点を軽蔑する傾向を持ち、理解しようともせず、
対話に応じず、一方的に要求を通すばかり、
というように、明らかに妻の側に問題がある場合は別だけれど。
神仏の名を借りた、妻に対する一方的な道徳の押し付けは、
直霊の要求を殺してしまうこともある。
こうした宗教は、無意識のよき働きよりむしろ、
超自我を強めると考えた方がいいだろう。
***
深見の家庭はDV家庭だった。
彼の母親は、夫との関係による苦しみのために、宗教を必要とした。
深見は、成長過程で母親のパターンを取り入れて、
神によって父の無茶な要求に応え、神による父の変化を期待する、
という態度を身に付けたのだと思う。
神により、父から逃げ出し、自立する、
という方向ではなく。
そのため、深見の神は、無意識中の存在ではなく、
むしろ、耐えることの褒賞としてご利益をもたらす、
超自我的な存在なのである。
それが、現在の深見の教団の性質を、
形作っているのだ。
***
現在はむしろ、DVに耐えるというより、
日常の不満にも耐えられずに離婚をする女性も多いようだけれど、
相変わらず新興宗教の隆盛が続いているところをみれば、
やはり、環境を自らで切り開くよりはむしろ、
神に変えてもらおうとする傾向を持つ人も、まだ多いのかもしれない。
しかし、江戸時代の縁切り寺が正しいのであり、
本当の神は、無茶の帳尻あわせをするための存在ではないのだと思う。
宗教団体に助けを求めることが多かった。
例えば、江戸時代には縁切りのための駆け込み寺があり、
現代のDVシェルターのような役割を果たしていた。
そこに三年間とどまれば、
夫と別れることができたのである。
そうした伝統からであろうか。
明治以降も、DV被害の妻たちが、
悩みの持ち込み先として新興宗教を選ぶ傾向があったと思う。
しかし、縁切り寺とは違い、
そこで教えられるのは夫から逃げることではなく、
自らの心得違いを治せば夫は変わる、という考えであることが多かった。
明治になって、庶民に対しても家父長的な制度が適用されたせいだろうか?
“夫は天であり、尊いものであるから、
女たるもの、無私の心構えで仕えなければならない”
夫が父長として、一家の大黒柱としてきちんと役割を果たし、
幸せな家庭が維持されることは、妻の働きに依るとの考えがあった。
そのため、DVに対して、逃げ出すという選択をするのではなく、
宗教の力を借りてなんとかしようとする傾向が生まれたのかもしれない。
***
しかし、DVの問題は一般に、妻の側だけに問題があることは少なく、
夫の側の問題の方が、より根深い方が多い。
DV対策の関係者の中には、DVを行う人格は、なにをしても治らない、
との意見さえあるのだ。
妻の背に何もかもを負わせるのは、明確に過重な負担である。
到底DVに耐えられない場合、妻がすべき適切な選択は、
多くの場合、逃げることであろう。
ことに、子供にまで暴力が及び、その精神的な健康に差し障りがある場合、
その健康な発達が妨げられつつある場合、
子供を守るために母がとるべき勇気ある行動とは何だろう?
自分の何が悪くて夫がこうであるか、思索を続けることだろうか?
神仏に、なんとか夫の暴力を止めてくれるよう、
夫が変わりますように、と祈ることだろうか?
いや、むしろ、子供を保護するためにも、
勇気を持って安全な場所へ逃げ出すことが、
一番現実的であり、潔いやり方なのではないか?
宗教によって夫を変えようとする試みが、
逃げ出して、自分で生活を立てていく事への不安、
あるいは、周囲や親族から後ろ指さされる事への不安などからくる、
単なる躊躇いではないか、よく考えてみる必要があるだろう。
***
宗教によって、夫が変わることがあるだろうか?
むしろ、宗教によって妻が内心の不満を隠し、
その決断力のなさに目をつぶって、躊躇を続けるための口実を
与えられることの方が多いように思う。
夫の人格的な問題は、本来、夫自身の問題であり、
妻ではなく、彼がその問題に立ち向かう必要がある。
また、夫婦が互いに、直霊の要求する相手ではない場合にも、
不満が募り、DVとして顕れる場合はあるだろう。
もちろん、妻の側が、
夫やその欠点を軽蔑する傾向を持ち、理解しようともせず、
対話に応じず、一方的に要求を通すばかり、
というように、明らかに妻の側に問題がある場合は別だけれど。
神仏の名を借りた、妻に対する一方的な道徳の押し付けは、
直霊の要求を殺してしまうこともある。
こうした宗教は、無意識のよき働きよりむしろ、
超自我を強めると考えた方がいいだろう。
***
深見の家庭はDV家庭だった。
彼の母親は、夫との関係による苦しみのために、宗教を必要とした。
深見は、成長過程で母親のパターンを取り入れて、
神によって父の無茶な要求に応え、神による父の変化を期待する、
という態度を身に付けたのだと思う。
神により、父から逃げ出し、自立する、
という方向ではなく。
そのため、深見の神は、無意識中の存在ではなく、
むしろ、耐えることの褒賞としてご利益をもたらす、
超自我的な存在なのである。
それが、現在の深見の教団の性質を、
形作っているのだ。
***
現在はむしろ、DVに耐えるというより、
日常の不満にも耐えられずに離婚をする女性も多いようだけれど、
相変わらず新興宗教の隆盛が続いているところをみれば、
やはり、環境を自らで切り開くよりはむしろ、
神に変えてもらおうとする傾向を持つ人も、まだ多いのかもしれない。
しかし、江戸時代の縁切り寺が正しいのであり、
本当の神は、無茶の帳尻あわせをするための存在ではないのだと思う。