※ 以下、校正はして居無いので、誤字脱字、事実関係に誤りを見付けたらご一報下さい。
第10章 後の身は誰に遠慮すること無く、永遠に忠義を装う奸臣が論じられることに同情する
一、寂寞と西帰する
晩年の王安石は存分に山水に浸って、詩に依って禅のことを説明したりしていたのだが、然し、彼の心の中の苦痛と苦しみは覆い隠し難かった。最も彼が苦痛を感じたのは、身内が一人また一人と世を去ったことに勝るものは無かったのだが、初めは長男の王雱、更に次男の王旁と妻の呉氏だった。夫人の呉氏が亡くなったときには彼は最も酷い打撃を受け、晩年の彼にとっては感情の拠り所であり最も有能な伴侶でもあった人が亡くなったことは、如何に彼が自由闊達であろうとも、此れほどまでに痛切に心が痛む打撃を受けては堪えられない悲しみは止むことが無かったのだ。
身の回りの者達が逝って仕舞って彼は常に酷く苦しんでいたにも拘らず、彼はそれでも彼の心の中にある強烈な信念を、粘り強く愚直に伸ばし続け、学術の上でもある程度の成果を立てつつも、彼が自分の使命を完成しようとしたのは、彼は、嘗ては半生に心血を注いで取り組んだ変法の大事業を神宗が指導していたのを目の当たりにして強く感動し,其の成果を上げなければと、宋王朝を多年に亘って徹底的に改変をして貧しさを積む弱者の現状を変えることで、国を繁栄させ盛んにする目標に向かって一歩ずつ挺進する思いを新たにしていたからだ。だが、元豊八年(1085)の三月に彼には更に悲痛な働き盛りの神宗皇帝が亡くなったと言う訃報が齎されたのであった。
晩年の王安石は詩で禅を議論したのだが、政務に関する言は無かったが、此のことは決して彼が政治への関心を完全に持って無かったことを意味してはい無いのだ。彼には《杖藜》と言う詩がある:
杖藜は流れに任せて東岡に転じ、元気を取り戻そうと床に就く。
尭桀の是非を想いつつ寝ついて、知識を固め足り無いところを習ったのを未だ忘れず。
蔡寛夫の《詩話》を載せる:「荊公は鐘山に居て、或る日、昼寝していて、古式の衣冠を着た偉い人の夢を見たのだが、容貌は非常に偉そうで、曰く:『我は桀なり』と政治の道を言って憚らず、多くの反論が出ても、互いに折り合うところが無かった。公が目覚めると、身体が汗で濡れていたのだ。此のことを笑いの種とした者が曰く:『吾が悪い癖は猶もあったか!』とは小詩を生して知っていたこととは、詰り、此の詩のことだ」。
蔡上翔の《王荊公年譜略》の巻二十二では反駁を強め、故意に「人を謗る言葉を吐き」、恣意的目的を持って此の逸話を編んで王安石を誹謗したものとされるが、実は蔡上翔は些か過敏に過ぎる処があったので、此の逸話の真否は別としても、荊公に対して決して明確な誹謗の意思があったものでは無かったのかも知れ無い。然も、蔡上翔は此の詩で庄子の 「尭を是とし桀を非とした其のことは、両人が行ったことを忘れないように」という意から出たものと認められ、尭桀を以って是非を諭そうとしただけのものだったので、「是非がただ忘れ難いだけであると言うことで、尭桀に拘った訳では無い」と言うのが,正解であったのだ。此の逸話は明らかに字面だけを見て憶測解釈したものなので、本当に王安石が尭桀を夢に見たと思って仕舞ったものだったのだ。
「習気」とは仏教に出て来る言葉で、衆生に愛情を持っても、世が始まって以蓄積された業や戸惑いを未だに散逸せることが出来無かったのは、現世に影響が及ぶ悩煩が習気となったからで、此のような習気を取り除けることが出来て、漸く、本質を見極められ心を明らかにすることが出来るのだ。王安石は、晩年は一途に「因習を取り除く」ことを務にしたが、同時に、彼は、実際に国事への関心を完全に消し去ることが出来ずに、猶更、蓄積された因習を蔑むことを思い出し、拘りを捨てることが出来無かったのだ。然れども、此のことが修行に専念することの一種の障害になったことは否め無かったとしても、彼の国を愛して人民を愛する心からの求愛の心が一休みしていた仏教を退く口実にすることは決して無かったのだ。
元々感覚に優れ、然も、豊かな政治の経験がある王安石は、神宗が亡くなったことが変法の大事業にとって致命的な損失であることが分かっていたので、保守派が反撃の舞台に上るのは間違い無く、情勢が変化したことでどちらにどれだけ有利になるかは、彼さえ予想することが出来無かったが、其れでも、彼は依然と自分のやり方で神宗を褒め称えることで、変法の大事業を賛美したのだ。彼には《神宗皇帝挽詞二首》がある:
その一として
聖人が天から跳躍して、鬼謀を成すのだ。聡明さは四つ当初から達していて、俊義は隅々まで広く求める。
古代に無かった前例を一変し、歳を三つに上げた時になる。謳歌を子が開けて、禹の功に尊敬を念じて修める。
《論語?子罕》には「天から跳躍する真の聖人」と言う言葉があって、孔子を称賛したもので、其聖の知恵が天から齎されたものだと言う。《易》では「位を設ける天地があって、聖人には、人が鬼謀を謀る能力が備わっており、庶民も出来る」の文があり、聖人には神鬼を皆に集める能力があると言うのだ。此のことに関連付けて極めた神宗の賢明さを褒めたのだ。《尚書?舜典》には「四つで既に聡明で」の文があって、《尚書序》では 「儒教の正しい道理を常に追求して」と言い、《説命》で「常に俊才を招いて、諸々の力量を着けた」と言うのは、「何時も力の在る成人を求めて、団結してことに当った」と言うことなのだ。此れらの対聯が神宗にも当て嵌まるとして、一方では四つで聡明に達したことは知ら無いものは無いと言って、更に、一方では最高の俊才を探して、共に国事を助けたと言うのだ。
《論語》の「魯は一変し、道へと至る」と説き、変法は此処に喩えを借りたとしても古人も未だ嘗てやったことが無い大事業であり、百代の盛挙を超えるものだったのだ。《漢書?食貨志》には、人民は三年耕して、次の一年を食し、次の三年は食を「上げる」と言って、更に上げて「平」と言うが、次の六年は食べて、三つ上げて「太平」だと言い、次の九年は食し、其れから、漸く「徳の一気に流れだし、其処で初めて礼学が成るのだ」とすることが出来,これが王者の道なのだ。《尚書?盤庚》は「農夫が田の力で穀物を作ることに従うなら、又もや秋が来るのだ」と言う意味は、農民は最善を尽くして耕作するならば、秋には豊作を向かえることが出来るのだと言うことだ。此の歌詞は変法の偉業と効果を賛美したものだ。末句は哲宗が父の志を受け継ぐことを提示するもので、引き続き変法は千年の大業として、まるで夏が大きい禹を受け継ぐことのようである。
此の首の詩は神宗の賢明さを大いに称賛したものであるが、其の真意は変法の偉業を正面から肯定しておいて、後継者の育成を継続することを望むものになっていることだ。神宗は既に亡くなって仕舞って、変報派が支えを失った後の情況下で、王安石は依然として自分の立場を堅持して、彼の勇気と人格を変えることは無かった。詩の中の第二首で、彼は神宗が埋葬に出される光景を述べて、「老臣は過日涙し、湖海(げんせ)に遺った衣を想う」と,限りがない悲しみの心を表現している。
神宗が亡くなって変法を継続させるどころでは無く、変法派が威嚇による身の安全をも確保せねばならなくなり、王安石は早晩に山林を返していたとは言え、彼は嘗て変法の提唱者として事実上の指導者であったので、変法に対して憎しみ持つ守旧派は彼への八つ当たりを増す可能性があったのに、誰も庇う勇気が無く、更に、変法派の功績は余り評価されて無かったので、人は少なからず彼らは商を見習ったのかと説き、彼らは商鞅の功績に彼が肖ろうとする気は無かったのだとしたのだ。彼は別に死ぬことを怖がる年代では無いが、辱めだけは受けたく無かったのだが、だからと言って其の為に国家が揺れ動くことだけは避けたかったのだ。彼には《偶書》と言う詩がある:
穰侯は関中では老練であったが、長く諸侯や客子が来ると怖がった。
私も晩年は一心に山間に籠ったが、いつも車馬に会うと疑いを持って「ぎょ」とした
穰侯、つまり魏冉、秦昭の王母の弟、四度宰相を拝命して、功により穰侯に封じられた。彼が白起を将として任用すると、屡諸国を負かし、秦には功績を挙げたのだが、晩年には俸禄と爵位を貪り求め、只管保身を求め、常にある人が取って代わることを恐れていたので、賢才を納めなかった。《史記?范雎蔡澤列伝》に拠ると、王は使節として行って調べ上げて帰路において、車中密に範雎に隠し、路で穰侯にばったり遭うと、穰侯に問うて言う:「諸侯と客子を全て呼んで君に渇させようとしなかったのか?目的も無く、徒に人臣を乱して国を荒らすではないか!」。王は調査と偽って穰侯を騙し、范雎をすんなり秦に帰らせて、秦王は範雎を重用し、穰侯を罷免して仕舞い、秦国の勢力を更に盛んにならせたのだ。穰侯は権力を独占して専ら位を得て、賢才を排斥して、遠方の賢人が秦に入ることのみ気に掛けていたので、結果、不満が溢れたのに、王安石は其の教訓を歯牙にも掛けず良い所取りしたというのだ。《庄子?秋水》、井戸の中の蛙さえ「囲われた水に優れていても、其処から這い出せずに笑われては、此れまでのことだ」と自嘲するのに,得意満面となって、揚子江の大きさや東支那海の広さが分から無い。王安石は穰侯を井の中の蛙になぞって馬鹿にした上で、自分が井戸の中の蛙のように浅井戸の囲われた水の中で優れていてもと自嘲して、其処から這い出さなければならないと考えもしたのに、穰侯は権力を関中で独占し続けようとする為に、他の者が権力を奪い取りに来ることを非常に恐れる余り、車馬が走り去る度に憶測で猜疑していたのだ。王安石が本当に表現したかった意図は保守派が他の者に危害を加えるほど狂気じみかねないことを心配していたもので、けど、此のことは打ち明けることが出来ることでは無いので、此のように風刺の形式で曲げて暗示することしか出来無かったのだ。
時局に対する心配から、同じく背後の気がかりについても、世事を考え無いで、腹蔵無く禅を悦び、多くの歴史を詩に詠じようと、今古い諭しを借りて詩を創作して、自分の一生と政治の経験を総括して、後世の為に更に多くを残したものを参考にして王安石が受け継いだ思想は財産に値する。
史を読む
古来より功名はまた苦辛のこと、終には、何人も払いたいと思う。
其の時愚昧な誤りを受けたのにも拘らず、近年、風俗が入り乱れて更に本物と見分けがつかない。
酒の絞り糟は麹の旨味を其の儘伝えず、絵画も書きにくい心持だ。
如何でも好いような高い見識を振り回して、独り善がりに紙の上の塵の千秋を守る。
此の詩の中で、王安石は背後に居る他人が自分の憂慮するものを如何評価するかということを表沙汰にしたのだ。当時非難されて弁じられなくてはならなかったものも、歴史は此れ迄総てを言い切れず曖昧にして来たのだが、況してや遥か遠い後世に於いては猶更なのか?古人のことが広く伝わったのは微かなものでしか無く、正に《庄子?天道》の中では、「古人は人に伝えることが出来ずに死で行ったので、さすれば、君が伝記を読んでも、既に其れは、古人の魂の糟ばかりなのだ」と謂われており,本当に素晴らしいものは広く伝わった例が無いのだ。たとえ最も素晴らしい絵師だとしても、人の精神をも描写することは出来無い。其処で、史書は惟古い書籍や資料の山だけを造っただけなのに、何処に歴代の高賢の本当の意思を表現したものが在ると謂得るのか?
王安石は自分についての心配事を古人に替えて只、感慨を覚えただけでは無くて、彼はあのように保守的な勢力が彼を最早簡単に見逃すことがあり得無いと予感したのだが、彼に泥水を浴びせること迄後世に無理に押しつけることは間違い無く出来無い相談だったのだ。彼の此の詩も後世に注意を喚起するもので、所謂「正史」であっても彼に対する評価を簡単に信じ無いで貰いたいと言うものだ。幾重にも重なり合う深い霧を通して歴史の真相を追跡すべきだと言いたかったのだ。*/一月十七日
歴史を詠んだ一連の詩の作品を通じて、王安石は先人の通説を御破算にして、自分の政治的見解を著し、彼の独特な見方と深い思想を明らかに示したのだ。《賈生》と言う詩の中で、彼は先人と意見を異にして賈誼の才気溢れる説法が認められなかったことに溜息をつき、漢の文帝が賈誼と義を謀って最大限活用すると思ったのだが、如何して、亦、彼を軽視して冷たくあしらったのだろうか?あれらの爵位が高いだけで役に立たない公卿(三公)と較べて、賈誼が事実幸運を多く齎したのに。此のことは王安石自身を高い評価をしていることを表現するものであるが、自分の志を枉げてまで、高い爵位を求めたいということでは無いのだ。《韓信》と言う詩の中で、彼は韓信が身を捕虜に落とした李左車に対するやり方を非常に評価して教を受けたのは、韓信が先ずは礼を尽すべきだと考えて、教えを請うのを恥とせず、只管、此のような態度で臨んだことで漸く李左車を獲得することが出来たからで、同時に彼が「貧賎が富貴の驕りを侵すのは、功名には卑称があってはなら無いからで」と言ったことに対しては、貧賎な者が虐めや侮りを酷く受けるのは、富貴な者が横暴で節度が無いからで、社会の等級が益々厳重になれば、草を刈って薪を採る下層部の人民にとっては功名を上げることも無く高位に付く機会も無い現実には非常に落胆し、公平を目指し少無くとも、人と人の間の平等が固定化された社会を作り上げることを望んだと言うことであり、此れも仏教の影響を受けたからだと説いたのだ。
彼は長期に渡って試練を潜り抜けて来た老人として、内心とは言え非常に疚しい打算もあったことも確かだったので、次第に多くなる悪い知らせには流石の王安石も矢張り平静を保っていることは出来無かったのだ。司馬光、呂公が相として任命され、保守派は皇太后の庇護の下にあって捲土重来し、遠くの金陵の王安石にも圧力が益々強くなったと感じ取れるようになって来たのだ。
当時、侯は毎日書院にあって書を読むことしか出来無かったので、仏教と禅宗とを助けようと仲裁することも出来ずに彼は内心で苦痛を感じ得ず、絶えず腕を組んでは溜息ばかりついて、心の中は際限無い悲しみや苦しみがあったが、人と腹を割って話すことも叶わず、時の人は彼に笑みが出無いのを不思議がるばかりで、彼の気持ちを理解することが出来無かったのだ。
然れども、政治的迫害は直接彼の頭上には未だ訪れては無かったのだが、既に暗雲が差し迫る城を制圧するような息詰った雰囲気になっていて、彼の著作は密に取り締まられ、「《字説》を見てはならぬと指図するものが近くに忍び寄っている」と言うことを報らせることが無かったのは、命いくばくも無い老人が極めて大きい打撃を受ける目にあってはなら無いと言う配慮からで、彼の気持ちを丸ごと落ち着かせるには如何慰めてよいか分かる気配も無かったのだ。此のような情況の下では、身の回りの親友や家族は何も役に立たないと言うことを知っていて、更に多くの悪い報せで老人に刺激を与えてはいけ無いので、彼らのすることが出来るのは世事を知らせないようにしか出来無かったのだが、然し、彼は愚かでは無いので、此のような隠し事も一時的なものとなり、彼は案の定、続々と市易法、方田均税法、保甲法などが続々と廃棄された報せを感知していたのだが、此れに対してとっくに心構えがあった為、彼は更に力の限り身を支え、平静を保ってはいたが、彼が聞くところによると免役法をも取り除かれると聞いた時には、此れ以上,自身を我慢させることは出来無くなり、「此の法だけは絶対に取り除いてはなら無いのだ!安石と先帝とが二年も掛けて最善のものとなるように協議して出来たものなのに」と言ったのだが、此のことは、既に司馬光が完全に理性を失ったと彼に感じさせ、新法の利害の是非を取捨選択して決定するのでは無く、「押並べて新法は全て取り除く」「此れ全て遣り抜く」と成したのであって、此のような人では大権を独占して、国事は日々定まらず次第に傷を大きくされていくのだろうか?
恐ろしく大きく心血を潅いで自己が投入した事業を司馬光のような保守派は何の躊躇いも無くぶち壊してから、王安石が心中に受けた衝撃も遠く過去のものとなって過ぎて行ったが、此の比類無く強靱な老人も終に何度も受けた打撃を辛抱することが出来無くなり、元祐元年(1086)四月当初の六日、王安石は人の世に別れを告げて、彼の魂は西方に飛んで逝く極楽世界で、矢張り先に逝っていた妻や息子や娘も集まってとは、全く知る由も無いことだが、確かに言えるのは彼が終に人の世の苦痛と艱苦に別れを告げることが出来たことで、俗世間の変転浮沈を果たして、地下にある一方の国土で安らかに眠れたと言うことだ。
二、 後ろに物寂しい
一面に広がった悲惨な境遇の中で、王安石は永遠に立ち去った。既に逝って仕舞った王安石にどのように対応するかは、保守派に残った大きな難題であった。病気で家に居た司馬光は此の報を受けて、別の一人の宰相に手紙を書いたのだが、嘗ては王安石の友でもあり仇敵でもあった呂公に書いて言ったのだ:
介甫は文章での節義に過ぎる処が甚だ多い人ではあったが、然し本質として物事に理解が無く、喜びも薄く、忠実さや正直さにも疎遠であって、中傷を巧みに集中させて、徹底して人を傷付けたので、こう成って終ったのだ。今し方、其の失敗を改めることも無く、其れ改革の弊害、不幸にも介甫は世を去った。と、輩が繰り返して必ず百端を謗るのだ。ただ謂い得るのは、朝廷から優れて手厚く礼遇されたことで、振るい起されて浮ついた有り様。仮初にも所得が有るのに、欲張って稼ぐ。晦叔も知らずに如何為そうとしたのか?更に苛立つ事も無く筆札で答えて、扆前が力んで言うには即ち全て晦叔に頼ったのだ。
此の手紙の見掛けは荘厳で堂々として、まるで司馬光が極めて寛大で懐の大きい風を装っているが、「輩が繰り返して」と彼が謗られるのを防いで、王安石の印象を守ろうと言う姿勢を見せておいて、王安石の「優れて手厚く礼遇されたことで」と言って、実の処、別に言わんとするところがあったのだ。司馬光は王安石が「文章の節義」に優れた人であると肯定するに及んでいたが、然し、此のことは当時の公認の事実であって、黙殺したくても黙殺出来無い事実であって、司馬光が王安石を褒めちぎったこととは言えず、然も、此れも只、一つの添え物に過ぎず、司馬光が本当に言いたかったのは彼の筆鋒が回転し出すと、王安石の様々な不手際を論い始め、其の一つとして「本質は分からず」と言ったのは、道理を弁えて無いと言うことで、二つ目には不正を好むので、忠と奸とを逆様にし、三つ目は後に深刻な状況を齎させたことで、「忠直を疎かに」(司馬光と呂公が自分達に擬えて書いたのだが、彼ら両人は嘗て王安石とは同僚で親しい友人だったのだ)しと、中傷を巧みに集中させて、更に国事にあれこれと傷つけ、殆ど収拾がつかなくさせたのだ。
司馬光からすると、王安石の身の回りの変法派には一人も好い人はおらず、皆が中傷好きの小人で、此の種類の小人は王安石が勢いを得ている時には否をも無く媚諂う中傷好きの輩であって、彼が権勢を失うや否や又も否をも無く人の危急に付込んで何かと難癖をつけて打撃を加え、繰り返し謗る者達に変貌出来る輩だったのだ。其処で、王安石が「優れて手厚く礼遇された」と言ったのは目的があってのことで、先ず、王安石が優れて手厚く礼遇されるに値する程国に功労があった訳では無く、其の「文章の節義」等の個人として文学の才能や道徳的な品格に頷く処が有ったからで、だからと言って王安石本人の為に優遇したものでは無く、王安石の身辺の輩が前言を翻すのに対処する為、彼らの信念が無く、他に動かされ易い風潮を悔い改めらせる為だったのだ。司馬光が此のようにすっぱ抜いたのは徹底的に変法派を懲らしめる為で、甚だしきに至っては彼らに「過ちを悔い改めて生まれ変わる」機会も全く与えることも承知せず、彼は「一つも見逃すこと無く」、「降参」も許さ無かったのだ。新法を堅持しようとしたのは当然讒佞(目上の人にへつらって、他人を悪く言うこと)の輩で、新法を批判したのは間違い無く前言を翻した輩であって、要するに、変法派は押並べて小人で、必ず一網打尽にしなければならなかったのだ。司馬光は王安石の何処が「優れて手厚く礼遇された」に相応しかったのだと思っていたので、翻って、今は何も出来無い王安石を借りて、王安石が未だ生きていた時の以前の部下達が変法の力を蘇らせるのを用心して、残忍な計略を廻らし、司馬光が此のような政治の風波の中で数十年も奔走してやっと掴んだ老練さで一掃を目論んだとしか考えられないのだ。
司馬光の意図によって、北宋朝廷が王安石に追贈したのは太傅で、極めて上辺を飾る為だけに用意された死後の栄誉だった。時に中書舎人を任じた蘇軾は其風旨を承知して、哲宗の為に《王安石贈太傅制》を為したのだ:
朕は古初を基準にして、透徹した見解をもって天命とする:非常の大事があって、必ず世にも珍しい非凡な人を生んで、その高さを一時使用して、学は千年貫徹す;知恵は十分に其の道に達し、十分に行い其を論じて言う;素晴らしい文は美辞麗句で万物を飾り、この上ない業績の風は四方に広がった;限りある歳月の間を使わして、世の中の慣わしを変える風潮が生まれたのだ。
王安石が官を備えたのは、年少の頃には孔、孟を学び晩年には瞿、耼を師としたからだ;六芸(易経・詩経・書経・春秋・礼記・楽記(または周礼)の総称)の故人の原稿を網羅して、自分の意見を断った;役にも立たない百家を陳述し、改めて自分の意見とした。煕寧には有力視されていたので、集団に冠を為し首領となった。篤く信任されたことは、古今に例を見無かった。地方で需要があった功績を成そうと、慌てて山林を盛んにしようと立ち上がった。不安通りに、残したものは粗雑なものだ。何度も漁や伐採の場所を争ったが、四不像の群を乱さ無かった。進退の美、大らかで見るに値する。
朕の皇帝に関係するものに望む手法を始めるに当って、隠されて忸怩(じくじ)たる思いを抱いて悲しむ。朝廷の三代に亘る老臣を思いやって、心は遥かな大河の南にある。詰る所、手本となった、風采を思い浮かべる。如何したら死を告白するように追及しようかと、予は諒闇(りょうあん)(皇帝が其の父母の死に対し服する喪の期間)の最中と雖も、何故(なにゆえ)百年(人に許されうる寿命の限界)にも満たなかったのにと、因って一筋涙を流す!
ああ、生き死に身内を使いに出すような、誰が天に背くことが出来よう:香典と栄誉の文を贈る哀れみが、私には無いとでも言うのだろうか!師を臣の位で目を掛けて、文才の華麗さは儒者の光とする。何とか知ることが出来たのは、私の命に従って休んだと言うことだ。
蘇軾の此の《制詞》は極めて綺麗に纏められているが、併し、其の素晴らしさは彼の文章の質にあるのでは無く、文で誉めている処の全てに貶す真意を潜めている技量にあったのだ。
既に南宋の初年には郎曄が此のことを発見していて、「此れは全て言葉では誉めているが、実は微かに仄めかす意があって、良く見ると他意を見て取れるのだ」と言っていたのだ。
蘇軾は司馬光の意を汲んで、王安石の「文章の節義」を更に増して賞賛し、其の「文の素晴らしさ」、「卓絶して為せる」と称賛して、その知識が博学であることをも称賛して、「学は千年の長い間に徹し」、知恵がずば抜けていて、仏道も十分に修行していることなど、此れらは全て正直に褒め上げられるべきだとしたことに、決して嘘は無かったろうが、其の他の一くさりの言葉で実は褒め上げといて分から無いように貶していたのだ。
「非常の大事」、即ち変法を指すのだが、蘇軾は変法には粗反対なので、変法は確かに「非常の大事」であったが、併し、一体「非常に大変好い事」なのか、或いは「非常に大変悪い事」なのか、読む者が自分で如何理解して良いか分から無いのだ。王安石を「世にも稀なる非凡な人」にした迄は、勿論悪くは無かったが、併し、此の解釈も大きくて忠実な大賢人、大きい狡く大いに凶悪でと、二通りあって、両方共全て「世にも稀なる非凡な人」と解せるので、王安石は一体どちらであるか、自分では判断出来無いのだ。「十分に為して其を論じて言う」とは、言葉は禅弁を為すと褒めちぎっていて、実は他の者を強弁に依って説き伏せると言う嫌味を言ったもので、本人を追い落とそうとしたものだ。「一瞬のうちに有名になる」とは、名声なのか、悪名なのか?「世の習わしを変えた」とは、善くなったのか、それとも悪くなったのか?「年若い時には孔、孟を学び、晩年は瞿、耼を師とし」,儒学、仏教、道三家を皆学んだのだと言った事を、肯定的に理解すれば三教を完全に理解したと捉えられるが、悪く言えば雑駁で有耶無耶であると解釈出来、「仏陀は老子と似ているので、周や孔子の真を乱した」とも解せるのだ。礼・楽(・射・御・書・数の六芸、愚にもなら無い諸子百家を網羅して、自分勝手な新機軸を打ち出した心算で、役に立つものなので広くゆき渡ると約束出来ると言うが、既に吸収されて受け継がれ創造と発展も為されているものであり、更に、悪いことには「清く無ければ法で無いのだ」と言って、出鱈目に自分の意見を打ち立てた。「煕寧は前途悠々であった」として、前途に期待をして懸命に向上心を持って奮い立ったと理解出来るが、実は神宗が「功を焦った」ものと批判をし、仁宗の「軽率にならずに古の規則を直すこと無く」に及ばず、在るが儘にして将来に夢が持てるのであるとし、其の中には勿論王安石に対する批判を含ませたのだ。
「衆に優れて賢いので首として使って」は更に絶妙で、王安石が才知に優れることを理解出来ることになるが、衆に優れて賢いので、其処で首として使ってとは、王安石が予てより長い間勤めていた群賢(保守派)の列の者では無いとも理解することが出来て、神宗に衆を飛び越えて登用されたのだが、群賢を蔑ろにして登用されるべきでは無かったのだとの意味を含む。「新任の篤さは、古今に例が無く」は、時の皇帝の「朕と安石は一人のようだ」の感慨に合うものであったが、立場が異なれば、此れに対する評価も相反し、此のことに対する変法派は好意的だったが、二人だけの同盟が在っただけなので、変法派が最も信頼出来る権力の基礎と理解出来る迄には時間が掛かったのだ;保守派は此れに対して否定的で、此のことで彼らの結束を弱めることが出来無かったので、簡単に新法の推進に揺さぶりをかけられたのだ。「偉業は必ず成功を為す」もとっても面白く、変法の大業の功績があと一歩の所で失敗に終わったと既に理解されていたので、未だ、成功を為し得て無いのは、実際に偉業とは言え無いのではないかと言いたかったのだ。
王安石は激流の中で勇退したのを、蘇軾は非常に賞賛したのだが、富貴は不安定で如何なるか分から無いものなので、寛ぐ為に位を去り、退くことを上手に進めることが出来、出処進退は自在で、其の上彼が山林を帰した後では、一方ではのんびりと満ち足りていて、魚を捕り、薪を伐採するのだが、一方では未だ身分を維持して、慎重に守っているのだ。此れらは蘇軾の本心からの賛美であったのだが、彼は自分が此のようなことが出来無かったので、此れも保守派が自身の為にも成るという観点から心から価値を認める処で有り、彼らも王安石を早い時期に閑静な隠居所に返すことを切望したのだ。
以下の語句は皆決まり文句で、同じく王安石に対しての称賛と哀悼を含んでいて、決して貶す意を隠すものでは無かった。此の人纏りの文章は言葉を選んで此のように書かれたのには、複雑な原因があったのだ。保守派の掌握した朝廷の観点からすれば、表面上は王安石を誉めてはいたが、人の話の種には乗ら無かったが、本心から称揚を望んだものでは無かったのだが、表立って王安石を書で誉めたからには批判を公にすることは出来無かったので、誉めて於いて密にでも貶すことは出来無かっただけなのだ。
蘇軾自身の立場からすると、極めて矛盾しているのだが、彼は王安石の人柄と才気には感心していたのだが、其の政治の手法には反対で、王安石自身に対して仇も有り恩もあるので、其処で彼の内心では愛と恨みが入り交じっていたと言うことが出来るので、文書で書けば此のようになったのはいたし方が無いのだ。蘇軾は朝廷に替わり、司馬光に替わって高い文学の技巧で此の難題を解決したのだが、併し、司馬光が彼に対して矢張り余り満足することが無かったのは、総じて言えば王安石を誉め過ぎた(保守派の目から見れば)と感じた為で、司馬光は「文章の節義」と持ち上げ過ぎ、貶す部分が余りにも不明瞭だと言及したのだが、当時の司馬光の輩は勿論そういう見方を持っていたのだが、実情が分から無い人には只其れが誉めているだけだと捉えられ、其処にも貶す部分が在るとは分から無かったのだから、後世の人には尚更に分かり難く、只其の文章の上辺だけ見たらならば、朝廷が本当に本気で王安石を表彰するのだと思って仕舞うので、司馬光が納得出来る結果にはなって無かったのだ。其れ以来、蘇軾が貶されて追われた原因は此処にあったのだ。
司馬光は表面上では王安石に対して礼儀正しかったと言えるが、処が、内心では恨み骨髄に徹し、新法、詰り、変法派を徹底して一掃すること目論み、甚だしきに至っては神宗に対しても恭順の態度をとらなかったのは、新法に極めて関係があった全ての者として極度に憎んでいたからで、変法ついて最大に貢献した王安石は特に目の敵にしていたのに、目の上の瘤であった者を、彼が如何して心から賞賛を加えたいと思うことが出来ようか?其処で、表向き「忠を信じて余り有る」として、司馬光が王安石について「外部に緩く内に厳しく」裏表を使い分けることに手馴れた陰謀家であると言いふらし、一方では死後に太傅を贈ったが、一方はあらん限りの力で最大の迫害を尽くして最大の打撃を与えて、其の時、王安石は既に此の世に居無かったので幸いも自身は感じることは無かったのだが、此の種の重い圧力は王安石の周囲の人々の上を蔽い、彼ら皆を不安にさせたのだ。
保守派が「先朝の法律を変更して、安石が去った一派」は厳しい環境下にあったので、普通の人はうまく立ち回って身を守ったので、陸佃のように思い切って弟子を率いて泣いて弔いをする人は実際には余りにも少なく、 「忌み嫌う所に変わり」、敢えて、王安石と関係が有るとは想われたく無かったのだ。此のことは気高い宰相だったとして、死後に位を贈られた王安石にしては極めて寂しい扱いであった。張舜民の《画墁集》には《哀王荊公》の七絶句の四首がある:
其の一として
霊前に酒器を供えるのもせず、初から酒と粗末な食べ物すら多くは無かった。
弟は唯慟哭有るばかりで、客が来ても如何に応対するのか?
堂々とした相府の霊前には、意外にも手伝う人が無く、然も、霊前に贈られた弔いをする酒と食事も盛り沢山では無かった。うつむいて激しく泣き叫んだのは王安礼など、王安の直近の親戚だけであって、古い知り合いは全く姿を現さず、此の種の物寂しい光景は栄えれば人が寄り衰えれば人が去ることと形容する以外の何ものでも無く、前例の無い程緊迫した政治の空気を如実に体現していたのだ。
其の二として
郷里の人は仮初にも平伏して互いに悲しんで、高い地位への活路を得た者達は如何して来なかったのか?
若し、栄光には期限が無いと理解するならば、教え子ぐらいはちゃんとすべきではないか!
郷里の平民は手に手を取って平伏して哀悼の意を伝えに来たのだが、荊公の恩恵を受けてとんとん拍子に出世した高官達は皆嫌疑を避ける為にやって来無かったのだ。若しも、時間を巻き戻すことが出来るなら、あのような恩義を忘れる輩を無闇に育成すべきでは無かったのだ。劉禹錫の《游玄都観》の詩は「郷里に桃の木(教え子)千本を眺めたことさえ出鱈目として、劉郎が去った後には追い討ちを食らわせたのだ」と言うものだが,結果として執政を風刺するものであったと思われ、終には左遷されて仕舞った。此のことは教え子を育成して官吏に抜擢したことの比喩とされる。肉食(贅沢三昧の)の富貴の者達は人の情や人格など無視したが、郷里の朴訥な人たちは人情を十分弁えていて、王安石が郷野に退き生活し、地元の人とも友になり、共に山水に連れだって、そんなことで彼の人に対する情の機微に出会うことが出来、譬え時が移ろおうとも、死者への想いは蘇ることが出来、王安石は葬式にも来無かったあれらの弟子や旧知の者たちと言い争ったことすら無かったのは、彼が彼ら皆の言え無い苦しい胸の内を知っていたからだ。
其の三として
学者に去来するのは元来非情ということで、珍しい文であっても新しく試そうとは考え無いのだ。
今日の世の中では人から学んで、誰もが弟子は悼むと言うのだが。
最も優れた人は情を忘れず、王安石は元々悟りを得ていた上に、学を究めて天上の人と生り、人のことを気に掛けることは有り得無かったのだ。只、彼の《字説》、《三経新義》等で彼が創設した新学が伝承し続け難く、先王の道の偉大な志を発揚しても成功することが出来無かったのは、今日の学者の誰もが嘗ては王安石の弟子だったことを隠し立てする為で、更に公然と学術を議論することを躊躇ったからだ。
其の四として
江水は永遠に行って返ること無く、長く活動したことが罰則に値し無いと悲しむ。
儚くて頼り無いものこそ結構確りしていて、永遠に蒋山に拠って生息する。
江水(大河)は永遠に、返ること無く去って行き、ひとが死去するのも同じことで、如何して戻ってこられようか!世の中で活動したことは、流れる水のようで、目まぐるしく変わって漂って動き、居座ることなど出来無いのだ。一見頼り無く見えるものも確りしているものが有り、永遠に蒋山の近くに在って動か無いのだ。
張舜民の詩は物寂しくも感傷的だが、彼は矛先を単に王安石の親戚と旧知の友人だけに合わせ、一貫して此のような現状の暗い現実を齎した事実を責めること無く、恐らく止むを得無いことだったとしたので、彼が此のように勇気をもってしたことで荊公に悪態を付く人も極めて少なくなって来たのだ。
当時の政治的圧力の為、王安石の葬儀が極めていい加減に為されただけでは無く、更には、一代の文豪で、宰相荊公は皇帝の岳父でもあったのにも拘らず碑文をする人が誰一人として居無かったのは、本当に不思議なことだ。大雑把にいえば諸弟が自身で為すのは都合が悪く、他人に為されることは尚更、認められないことだったからだ。才能があって学論するには、蘇軾は最も適当な一人であったのだが、彼の一篇の文での言い回しの義が曖昧であると司馬光が不満を持ったからには、如何して功績や人徳を正直に誉める石碑を作ることが出来ようか?保守派に依って為されることは皆無で、若し彼の偉大さを誇示するような行為をするならば、政権側は必ず報復し、自ら問題を起こすことになるので、彼の親戚や旧友すら為すことが出来無かったのであり、彼らも最早非難の追撃をする対象になっていたので、更に、重大な過ちをすれば、いざこざを引き起こしかねなかったのだ;若し、蘇軾のように王安石に対して誉めたり,貶したりして、上辺で誉めて密に貶して、技巧を弄ぶならば、感情からもやってはなら無いことであり、此のように中途半端なことは受け入れられることでは無いのだ。聞くところに拠ると、則天武后は自分の意思で字碑を作らせなかったことには理由が有り、論争を引き起こさない為だと言われているのだが、事実、則天武后は論争を引き起こし兼ね無い人物だったので、適切な処置を為したと言えよう。雅か、王安石も墓誌銘を残したく無いと言う遺言状を残していたとでも言うのか?併し、此のような可能性は皆無とは言え無いが、其れを証明しても、一体どれだけの価値が有るかと言うことである。王安石は自信を持って一生心に曇りが無いと確信していたのだが、其のことを態々人に告げずとも良かったので、彼が則天武后を真似る必要があったのか?もしかすると彼は奥深い道理を十分に悟っていて、有名であることは無名であることに及ばないと理解していても、役立たずの学者のように虚名で身を隠そうと悩むことは無く、其処で、喜んで清潔に清潔を重ね、一々生き様を残そうとすることも無かったのだ。同じく前で述べたようなことは有り得ることで、当時は、両者共に墓誌銘を作ることには都合が悪かったが、時が経てば状況も変わる為、何時かは新党が勢いを噴き返すかもしれないが、章迁、曾布、蔡卞なども当時は作る助けもしたく無く、此のことをずっと遅らせて為そうとしていたのだ。勿論、此れらは全て推測で、実際には何も証拠が無い情況の下では、推測は推測でしか無く、然も、歴史の真相は推測でしか探求出来無いものなのだ。
「三、 何時の間にか変わる」に続く

















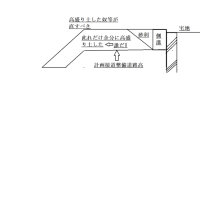
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます