五、高僧との付き合い
王安石は一生涯に多くの高僧と知り合いになったが、若い頃瑞新と大覚懐璉を代表として、都に逗留していた時などは智縁等とも親交を結び、晩年には蒋山賛元、宝覚、浄因、真浄克文等とも親交があったのだ。
蒋山賛元、字は万宗、鷔州の義烏人、俗姓は双林寺の傅高僧の後裔だったので傅と言う。三歳で出家して、七歳で既に大僧となった。もって生まれた性分はのんびり屋であり、穏やかで寡黙であって、外見は見劣りしたが、内には慧珠を隠していた。諸仏の書や伝記は読んで無い所が無く、語り口は比べるものも無く、人に及ぶ者がいなかった。歳十五才の時石霜に至り慈明楚円にお目にかかったが、寒暖を恐れずに米を搗いて柴を刈って、法を得た後には、次はあちこちに居場所を変えたのだが、後継者となった蒋山の兄弟子は禅僧の法座を心に留めて、正道の場として志す蒋山に居住したのだ。王安石が喪に服そうと兄弟のような義巳にあった賛元を頼って旅をしたのだが、以前開祖に人として踏み行うべき道は文明が発生する以前には如何に在ったのかと質問すると、されど其の為には、帝に申し上げて其の決定を求めることを範として師号に従うようにと諭された。煕寧年間の当初、王安石は適任であると認められて、程無く宰相として重く任用されても、旧友を忘れずいたが、夜は明かりも無く書も無い山に籠り限(きり)の賛元にずっとまみえる事が無くなったのだ。賛元は世を拗ねてこうしていた訳では無く、恐らく権勢のある高官の間は付き合いたく無かったので、王安石が官職を辞去するのを待って、閑静な隠居所でのんびり暮らすようになった時には、二人は再び元通り愉快に、一日中空論を論じ合い得ると考えていたのだ。
賛元が高く深く力を着けていたので、非凡に事を進められた。訪れる者達には貴賎の別無く平等に扱ったが、安否を問う以外に日常の挨拶以外に言葉は無く、何も言わずに直ぐ目から離れ、禅定に入って仕舞うので、訪問者は急いで辞去する外無い上に送迎も為すことが無かったのは、彼が接客の方法を知ら無かったからでは無く、修養に寸暇も惜しまなかったからだ。或る日炊事場が火事になり、皆は酷く慌てたが、彼は普通に食事を取り、何事も無かったかのようであった。更に今一つのことを言えば、彼が外出した時に、精神病の狂人が寺に入って来て、僧を一人殺して其の後自殺し、死体は枕を相為して置かれ、此の場は雑然として、右往左往と非常に驚き慌て、消息を知らせようと走ったので、彼が人垣に戻って来ると、何事も無く平然としており、死体の傍を通っても戸惑った様子は全く無く、寝室に行って直ぐ座禅し、全く平日と変わらぬ様子だったのだ。
王安石と賛元の友情はとても深く、彼には《覚海住職》の一詩がある:
城府と行き来して山林に居住することは、全く自由気儘であるとの一言に尽きる。
自説を押し出さずに真道を広めれば、縁故も結ばれ其の都度自ずと禅は深くなる。
舌根は只誰かを傷付けて仕舞うので、どんな実績も上げることが出来無いのだ。
年の瀬に北の窓辺に身を寄せると、葡萄の葉が半分程枯れ落ちていた。
法を会得すれば、往来は自由で、隔てられた山林とて決して例外で無いのだ。諸法は労せずとも、皆が信じるものだ。「一物たりとも違え無い」と典故にあるが、袁州南源の道明禅師は馬祖道の弟子で、洞山の良価が嘗て参礼に来たが、五日後に別れを告げた時に、師が訴えて曰く:
「多く仏法を学べば、大きな利益がある」。洞山曰く:「多く仏法を学ぶことを疑問に思わず、如何にして利を為し得ようか?」。師曰く:「全く間違いは無い」。仏陀は平等で大いに慈悲深くて優しくて、偏ること無く全ての衆生に与えて、だから真剣に修行する者でも、等しい愛情をもって同じように受け入れなければならず、一物たりとも違えて接してはなら無いのだ。禅宗は「一物たりとも違え無い」を主張し、一法も捨てず、拠って、正道は広く行き亘り、三千大千界をも収容することが出来るのだ;
胸中に三千大千世界への思いがあっても、知らず知らずのうちに迷いが出るが、事物も心と同様で、本質は空しくあるものなので、事物が心の妨げになることは無いのだ。禅定とは諸縁を断ち切ることではあるが、同時に其れを無視出来ず、縁によって物事が生ずるのは普遍なことではあるのだが、普遍なことも縁から生まれるものなので、山に居ても寂しく無く、街に居ても喧騒を感じ無いと、常に心を定めれば、街に在っても心は乱されることは無いのだ;逆に、山に在っても賑やかにすれば、心寂しくなら無いのだ。突然の出来事にも、動揺せず、我関せずと放って置くこともせず、摂生もせずと心乱さすこと無く、心底から静かに構えることが肝要で、どちらかと言うと静かな方が良いのだが、喧寂があるものとしても、改めてはならず、喧騒を避けて静寂を求めても、其の静けさは本物では無いのだ。水に浮かぶ蓮は、美しいが永遠のものでは無いのだ;火の中に蓮を育てようとしても、瞬く間に死んで仕舞う。縁あって他人と巡り逢えても直ぐに散り散りにならぬように、私は縁を大事にして定めに従って生きるのだ。舌根を控えれば、あらゆることに妙法が得られ、後悔することも無くなるのだ。仏教の高僧の多くは、入滅した後に、舌根の危うさで悪く言われることは滅多に無く、遠くは鳩摩羅什がいて、近くでは契嵩に教えられる。賛元が果てし無く広く高徳を行ったことを、氈鹿が角で引っ掛けがごときに、其の足跡を辿る筈が無かったのに、王安石は私がきっと功績を証明してみせると言っていたことで、二人の親密な交友が分かり、彼の揺ぎ無い自信も顕されていたのだ。
彼には《白鶴吟示覚海元公》が更にある:
鶴の声は哀れむが、紅鶴の声は煩わしい。白鶴は静かで数が少なく、紅鶴は喧しくて無数だ。
白鶴は招いても来無いが、紅鶴は追い払っても逃げ無い。久しく松が汚物で枯れて仕舞ったのは、紅鶴故の所為なのだ。
北山道士曰く:美しい者は美くしいのだから、私は訳も無く喜ぶのだ;凶悪な者は凶悪であると、私は訳も無く怒るのか? 自ら耳を欹てて、私はどんな過ちも許さ無かった;自ずと耳に入ったものを、私は如何して防ごうとも拒もうとし無かったのか? 私は喧騒に嫌気がさして静寂を求めた筈なのに、私は如何して素色を好まず朱色を好んだのか? 貴方は、松が枯れたのは自分の邪な行いからでは無いとでも謂うのか? 私はたった今から蔭を捨て露に座すのだ。
此の首の詩は感情を著したものだ。李壁の《王荊文公箋註》の第三巻には此れに対する詳細な解釈がある:
臨川に残っていた公(王安石)の此の詩の刻本を見付けたが、後半に後書きを見つけたので、今此れを付け加える:
白鶴が吟じて、鐘山の覚海がこの詩を残したのだ。初めに僧行詳と旧交を温めてから、公は山中に延居することに為ったのだ。詳は経論を通じて、善く論じる毎に名を為して来たのだが、禅宗の悪口をも言っていたのだ。先の師の普覚が、突然、西の庵で逝去したので、其の為、覚海は孤立し、逆に以前にも増して、詳は外目に分かる程驕り高ぶったのだ。師は争いを嫌い、何度も自らが庵席を辞することを求めたのだ。公は強く諫めたが、如何することも出来無かったが、恥も外聞も無く詳が騙したのが分かったので、直ぐに詳を追放して師を留め、作った詩が此れなのだ。白鶴とは、覚海である;紅鶴とを、行詳である;長松は、普覚である。詩を見て分かったことは、公と二師は既に知り合いで法外の契りを結んでいて、厚く親交があったと言うことだ。
景齊が久しく其の冊(さく)を隠したのだが、石版で印刷を命じていたので、此れが兼書と言われた所以だ。此の為に、白鶴とは賛元を指し、紅鶴とは行詳をさし、長松は普覚を指すことが分かったのだ。
行詳は元来、王安石の旧友で、王安石には《宿北山示行詳上人》一詩があって、其の中には「旅にあり他郷の都城に長く逗留するうちに、只上人は偉い人だと思ったのだ」の文があるので、二人が京城で知り合いになったことが分かるのだ。行詳は僧に経を教える程であり、経論に精通していて、弁舌は絶妙だったが、禅宗が修行を重視することを嘲り、何時も誹っていたのだ。此れに対して覚海賛元が、譲歩を加える毎に、更に行詳は思い上がって気焔を挙げ、賛元の師であった、西庵に居していた普覚が入滅すると、行詳は賛元を甘く見て、寺院を乗っ取ることを企むのだが、賛元がどちらかと言うと少しも気に掛ける様子を見せ無いので、何度も退くように求められ、終に庵席は行詳に譲ることになったのだ。王安石は当初は其のことを理解出来無かったので、賛元が退こうとの決意を持って求めても、強く賛元に残るように説得するばかりであったが、後に漸く行詳が揉め事の張本人だと分かったので、行詳を追い払って、賛元を慰留させたのだ。詩の中では紅鶴の理不尽に煩く言って長松を憤死させて争いを起こしたと記されたが、此のことから、普覚の死に行詳が深く関係があったことが見えて来るのだ。北山道士とは同じく賛元を指したもので、彼は元々綺麗であるから綺麗な人となるのだと考えて、凶悪だから凶悪な輩になるので、理由も無く喜びや怒りの感情を加えてするものでは無いと教えている;去る者は去らせ、来るものは来させ、去る者を追ってはいけ無く、来る者は拒む必要は無い。私は喧しいことに飽きて静かであることを求めたのだが、喧しさも静なことも心次第で如何にも為るものなのだ;私にとって朱色は手を加えた色とも言え無いので、丹素が心の中に何を為すのか?道安大師の此の大樹の為に死ぬなぞと思わずに、私が寄るべき者を無くしただけのことで、私は却って樹蔭を離れることが出来たので、自立して自から決定出来るようにすれば、彼に従う必要は無くなったのだ。
此の詩の中で、王安石は行詳の中傷と非難に対する賛元への同情と賞賛を表現した。賛元は仏道の内部闘争になら無いように配慮し、いざこざを引き起こさせ無いように願ったのだ。賛元は深く厚い定力(禅定によって、一切の煩悩や妄念を打破し心を寂静にして真理を見抜く力。禅定力)と、極高い境地を表すことで、行詳が利己的で貪り摂るのを際立たせ、出家であっても全て皆が貪欲に貪ることなど無いとは言い切ることが出来無いことを表明したのだ。
賛元は石霜楚円から秘伝を得て、其れは行を解かれることを意味し、機鋒は迅速で、依って、諸方は挙って心服したのだ。僧は聞く:「和尚の家風はどのようなものですか?」師は言う:「東の壁は西の壁を打つ」。東の壁は西の壁を打っても、元来何事も起こる筈は無いと言うことで、不可能を可能にするには、『遮意』、詰り一つの方法に拘らず、手を尽くして外部からも方法を得る努力をしなければならないのだ;二つ目は『照意』で、禅門の本領を直接顕かにすることで、本性を丸出しにさせ、環境に順応させ、自由に行わせることだ。更に問う:「客が来たら如何持成すのか?」。師曰く:「山上の薪、井戸の中で水」。客が来ても、山上には柴があって、井戸の中には水があり、客を持成す物は何処にもあるので、客を繋ぎ難い何があると言うのか?此の文には鋭い切っ先が潜んでいて、客が来た時に、若し、もてなさ無ければ失礼だが、騒がしくせずに静にもてなすことだ;もてなしを考えるなら、彼に応じて行うことが肝要で、物や働きで持成されては、却って客は気忙しくなり、ゆっくり出来無くなるのだ。賛元の答えは、自然体に応対すれば良いと言うもので、来る者は拒まず、去る者は追う必要は無く、来ても十分喜ばなくとも、気に病む必要は無く、付き合いが有っても、心を動じ無いのが肝心で、此の様な接客態度で臨めなければ、未だ客を迎える態勢とはなって無いのだ。僧が問う:「諸仏の出自は如何に?」 師曰く:「驢馬の胎児は馬の腹」。諸仏は元々気高いものだが、賛元は驢馬の胎児が馬のお腹の中で育つと敢えて言った真意は、諸仏の価値を下げる為では無く、学者の心の中の拘りを追い払う為であって、其れは仏病でも有り、所謂、金は屑でも価値が有り、目に入るだけでも有り難く、若し、仏への思いが固定化されて仕舞っているならば、常時、其の思いに囚われることになるので、必ず其れを心から追い払わなければならないのだ。然も、諸仏陀は大きくて果てし無いものなのに、如何して出自の如何に拘るのだ? 泥が積もった中でも蓮の花は生きられように、驢馬の胎児は馬の腹の中に在っても育ち、諸仏がどの様に生まれようとも育つことが出来る筈ではないのか? 諸仏は平等で、何ら高下の差は無く、摩耶(釈尊の母)とても気高いとまで言え無いのに、驢馬や馬が如何して賤しいのか?
聞く:「魯祖が壁に向かった真意は如何に?」 師曰く:「住職の地位は疲れるものだからだ」。魯祖宝雲も馬祖の弟子で、弁舌鋭く深遠で峻厳であったが、参来した或る人が、魯祖が何時も壁に向かって座っていたのを見て、壁に向かって座禅することを魯祖が禅門の倣いとしたと勘違いしたのだ。魯祖は壁に向うようになった経緯には、多くの深い意味があると考えて、学者が参元に元々の意味する処を聞くと、「住職の地位ともなると雑多な仕事を抱えるから」で、「壁に向かって休憩しているだけで、決して玄妙な理由など無く、色々詮索しても仕方が無い」と答え、極有触れた所為なのだと説明をしたのだ。学者は玄妙な答えを求めたのに、賛元が此のように答えたので、学者にとっては一生の思いとして残るものだったが、中々玄妙な意味から離れられない学者に、極自然な解釈をしてやることで、其の意味に玄妙を求める病から開放してやり、日常の行為の中でこそ真玄な大道が体得出来ることを教えたのだ。
問う:「大善知識とは如何なるものか?」 師曰く:「屠牛し羊を剥く」と言った:「如何してなのか?」 師曰く:「業の其のものがそうだから」。普通の理解に従えば、大善知識とは仏法に精通する為に、修行を極めた導師のことと解されていたのだが、大きく慈悲の心を備える人として賛元が屠畜人を挙げたことは、人の通常の見方とは強烈な対比を形成するものであった。 何故、屠畜人なのかと言うと、突飛なことを言うことで、人々の心の中に常に見えるものを捨てさせ、大善知識に対する誤解と拘りを取り除く為だった。併し、屠畜人が大善知識である訳が無く、若し、賛元が大善知識を本当に屠畜人と思っていたならば、とんでも無い誤りで、其れ故、更に「如何してなのか?」と聞くと、賛元は「答えは業の其のものがそうだから」と答えて言ったのだが、その意図する処は畜生道の中に身を落としたことで逆に命に愛情を持つようになると説き、世の中に悪業に手を染める切掛を無くし、牛や羊を扱うことで、屠畜や羊の皮を剥ぐことなど、色々な仕事も作ることになり、実際は悪業を無くすことに貢献し、そこで悪い道から遠ざかり、活路を見出せ、人が生まれ変わる為の天職ともなるのだとしたのだが、本当は屠畜や羊の皮を剥ぐ者のことを決して言ったものでは無く、生霊(いきりょう)を殺して成仏させる道祖のことを準えたのだ。
師は更に講堂に上がって言う:「此れは、虎に角を着けるが如くだ。其れをしないで、何を騒ぎ立てるのか?」。間を置いて自ずと言う:「驢馬が飢え馬も飢えることが、其れが自愛に関係することか!」。 実際に何が起きるかを予測出来るのは仏陀のみであるが、虎に角を着けたなら、『向かうところ敵無し』となるであろう。此のことを知ら無いければ、自分の本性も見出せず、未来永劫に浮かび上がれ無くなり、長く活路を見出せず、馬を飢えさせ驢馬を飢えさせ続ける以外無く、永遠に終わる処が無い。其処で肝心な点は事物の根源から考えて元来持つ性質を其の儘受け止めることが道理で、若しこう受け止めることが出来無いならば、驢馬も馬も同一視し、永遠に光明を見出せ無くなるのだ。
賛元の徳望は既に高く、王安石とは兄弟のような義巳にあり、遷化の時は、王安石は塔に上って慟哭し、《蒋山覚海元公真讃》を作ったのだ:
賢い人! 行いは厳しいが静かな佇まいがあり、寡黙であった。栄誉を喜ばず、人を謗ることを恥とした。威張ることも人を押さえつけることも無かったので、人は其の徳を賞賛した。無頼の輩から僧侶に到る迄、南から北迄至った。文句を言わず逆らわず、抵抗もし無ければ抑制もしなかった。贅沢を望まず、惟、分相応の暮らしを好んだ。何れが此れを受け継ぐかは、私は見失うことがある。
此の篇の中にも賛元のことが出てくるが、王安石は賛元を褒めちぎり、何事も行いは厳格であったが佇まいは穏やかであり、心で言葉用いて寡黙で通し、名誉も喜ばず、人を辱める等一切無かった。彼は傲慢でも尊大でも無く、また剛毅だから屈服することが無かったので、南から北まで、不逞の輩から僧侶まで、全て其徳を賞賛したのだ。彼は仮初にも諂うこと無く、安易に逆昂することも無かった;
対等の礼を執ら無いような驕り高ぶる人では無く、民衆にも媚びることは無かった。彼の暮らしは慎ましく、全く奢を好まず、惟食事も置かれた儘に目前の物を食べるのみで、贅沢は避けた。賛元の後継者は遺則、又は雪竇法雅、或いは丞煕応悦などであった。王安石には更に《祭北山元長老文》がある:
元豊三年九月四日、長老覚海大師の霊は北山に弔らわれた。自身は壮健であったので、公は世話をすることが出来た。今皆年を取ったが、公は先に逝った。逝けば何れも遠く雲となるが、十方は以前からの儘である。酒肴の陳(ならべ)を違えず告げるのは、世の礼として然り。尚も饗か!
知る所ではあるが二人は働き盛りの時に既に知り合いになって、然も、年齢も近く、同壮同老の仲だった。大家は死去するが、英霊は遠く無く、彼は浄土に至っても、此方と隔たりが無い。大師は西方に帰っても、何とか人の世で食べさせようと、謹んで精進料理を備えるのは、昔からの仕来りか。王安石は此の祭文の中で再度賛元の入滅の痛惜と感傷を著して、二人の間の深い情誼を説いたのだ。王安石と蒋山とは、道光と道安の二人の大師と大変密接な関係があり、其のことに関する多くの詩が残っている。
安大師に送る
道士は奥深い北山に家を為し、白露の眠る青色の朝焼けに宴座する。
手で木杖を支えるほど年老いたと雖も、尚も危険を冒して鹿を追い得るのだ。
堂に腰を下して何処を見下ろしているのだろうか?幽遠で静かな樛木が花梨に間近に迫る。
秋も深まり石路を尋ねると尚栗の実があって、私に茶を給わってくれた。道安は北山に宗一派を建て、高齢だが、体は更に壮健で、走って鹿を追うことも出来た。山中には他でも無く、白露の蒼天に朝焼けがあって、栗樹や榠樝(花梨に似た落葉の高木で、薔薇科、果実はみずみずしいが、味は渋く、薬用に用いる)も未だあるのだ。
王安石には更に又《贈安大師》が有る:
独龍の山は北で三番目に高く、偶にしか訪れることが無い訪問者が往復するとくたくたに為った。
破れ屋の間には青い靄が漂い、冷雲の深い所では鐘の音も聞こえ無い。
道安大師は此処に留まり、独龍(少数民族名の地名)の北で三番目に高い峰の上には、屋根が破れた儘に軒を成し、荒れて寂れて時刻を告げる鐘の音も無いのだが、青く煙が漂い、白雲が天を覆って、正に禅を行い修行するには適任の地と言えるのだ。「偶にしか訪れることが無い訪問者」とは《北山移文》に出て来る句で、王安石は自分の詩に援用したのだ。
此の詩からは王安石の道安大師に対する崇敬を見出すことが出来、彼は道光大師に対しても同じ気持ちだった。
道光大師に送る
秋雨は夜に朝に果てし無く、部屋の蔀(しとみ)から晴れ渡った空を眺めると嘆息せざるを得無くなる。
雑念を入れず座禅していたことは遥か遠くで知っていたのだが、万事全てが劫火に焼かれた。
秋雨は果てし無く、昼夜も止むこと無く、家の屋根がお粗末で、座っていても空の天辺まで見ることが出来る程なので、雨が数日間降り続くと雨漏りするので、他人にとっては苦行と見えるが、座禅を組む道士には其のような発想は無かったが、万事全ての物はやがては無くなるものなので、彼の考えを正すには、大火に会って一切焼かれてさっぱりするしか無いのだが、其れ以外更に解決の道があろうか?
彼には更に《寄碧岩道光法師》がある:
馬や車の往来で濛々と土煙が舞い上がり、久しく雲水に身を置かし難い。
碧岩の主を継ごうと異郷に留まり、況や寺を建立して人に法を説こうとするのか?
出家すると人は水が流れるが如く執着を断ち切る為に居所も定めず雲水となるのだが、此のことこそが「雲水の本領」であるのだ。街中は余りにも騒がしくて、車馬の往来で、紅塵が濛々と上がっても、雲水となった出家には身を寄せるところすら無いので、奥深く静かで煩わしいものが無い碧岩とは較べるべくも無いのだ。「碧岩の主を継ぐ人」とは、恐らく、王安石は冗談混じりに自分のことを言ったのだろうが、賛元が嘗て言ったところによると彼ら両人が良く馴れ親しみ始めた後にも、彼は生きている限り出家して僧に成る気は無く、又、其の様に出来る訳も無いのであり、だからこそ「碧岩の主を継ぐ人」等と言えたのだ。王安石は「半山園」でも未だに俗世間に居座る思いを表わしていたのであって、況してや道光のように寺を建立し人に説法を説いて聞かせようか?
道光住職は一箇所だけに留まっていた訳では無く、以前には霊岩寺の住職をも務めていたので、王安石には《送道光法師住持霊岩》がある:
霊岩は開かれてから何年も避けられていたのは、草木(そうもく)の不可解さと鳥獣すら神通力を持つと謂われる程であったからだ。
深遠で深さの景観に通じる紫苔に至ると、夥しい数の崖に青く靄が懸かり渓流の水音がした。
山の神が吼え乍集り禅室を荒らし、衆が思い慕う法筵も目茶目茶にされた有様だった。
雪が沢山積もっていたので足が重く痛んでも行かねばならなかったのは、 東人の焼香に差し障るからだった。
越州の霊岩寺には悠久の伝統があり、天下の四絶の一つと号され、天台の智顗曾経住職が建立したもので、此処では草木まで成仏出来る摩訶不思議さと、鳥獣にも神通力があると言われていたのだ。夥しい数の崖が優劣を競い合い、無数の渓流が争って流れ、紫苔には青く靄が懸かり、碧水に白い雲、霊山は景勝の地と称する程で、仙人の境地になれるのだ。山の神まで遠吠えで集まって、禅を聞こうとやって来たのだ;竜が暴れまわったような有様で、教えを説く席を気遣った。衆は皆大師が来るのを待ち焦がれていたのだが、大師は東山の人と会わねばならなかったので、疲れているからと旅を途中で辞める訳には行か無かったが、足が酷く痛み乍も、急いで取って返したのだ。
王安石には更に《示道光及安大師》と言う四言詩があって、其の中には「二人を懐かしみ、彼方の天空と谷に在る」の文で、二人への思念と崇敬を表現したのだ。
王安石と宝覚との関係はとても密接で、彼には《贈宝覚并序》がある:
宝覚とは京で知り合ったのは、全て主君に招聘されていたことの結果である。後に翰林学士に招かれ、一昔前に金山に泊まることがあったのだ。今又こうして会えたのだ。
城閣からの眺望が甚だ壮麗だと聞いて、登って眺めると、気儘な暮しを思い出し、作ったのが此の詩である。
大師は京国に久しくいたが、天下各地を巡ることに関心があった。仲間に教えを乞おうと訪ねて、金山の頂で一泊した、
名残惜しさに身を詰まされても心に引っ掛るのは、王事を朝廷に頼まれていたからだ。
何時でも来られる訳では無いと、激しく戸惑いが涌いた。
今朝出会い頭に、瞳がはっきり輝いた。夜に打ち解けて語り合うと、深い思いに見舞われた。
城郭は天の半ばまで張り出し、遠くには諸峰も望み見えるのだ。
中州の水際に白髪頭が振り向くと、小船が霞んで見えるのも当然のことと感じたのだ。
王安石と宝覚は首都で初めて知り合ったのだが、其の後、彼が丁(南方)の母を憂いて江寧に帰ったので、宝覚も付いて行ったのだ。煕寧当初、彼は翰林学士に招聘され、出発間際になって、宝覚、恵能等の人と伴って金山に一泊したのだ。その時彼は江寧での四年の隠遁生活の中での古くからの友達を非常に名残惜しがったが、王事が迫っていたので、如何しても京に行かねばならず、宝覚を江寧に残すのみだった。数年は帰ることが出来無いので、思いは非常に激しく、現在こうして出会えて、優しい言葉を掛け合って、深く思いに耽るのだ。城閣が天を突くばかりに雲に入って高く聳えるようだと聞くと、天の半ばに秀出ても、全てが遊(すさび)のことなのだ。この詩は王安石が初めて相を辞任する時に創ったもののようだ。彼は既に宝覚と金山で相分かれていて、一路都に向かっていたのだが、江寧に残した者達と出会得るのは何時のことか分から無かった。都へ行っても宝覚に合いに来ると言ったことが、詩の中にあって、更に城郭の一説で、城閣が長江の岸辺にあるということに借りて、同じ思いの例えとして、王安石は《化城閣》の一詩によって、極めて其れが雄壮で美しいと言ったのだが、其れ以後の作品と比較して考えると、未だ江寧に帰ったことが無かったのであれば、「中州の水際に白髪頭が振り向くと、小船が霞んで見えるのも理有ることだと思得たのだ」と言う文が有ることで、遠く都に居て、近くに居無い筈なのに、如何して「気儘な暮しを思い出し」得るものなのか?
この詩は王安石が相を辞職させられても元々の広い心の持ち主だったので恨むことなぞ無かったことを表現していて、彼には心眼があって、世間は朝廷の気高さにも遠く勝っていたので、世間の者を促して膝を交えて懇談しても時の政治にも勝って論評するに至り、東府(こうていのせいふ)が立派で堂々としているにも関らず、城閣の雄壮で美しく清らかさが東府の壮麗で堂々とした立派さに掛け離れて勝っているので、山林に放たれ返された彼にとっては正に処を得た思いであった。けれども、今回の放免から復帰する迄は短くて、彼の二回目の出馬は程無く訪れ、再度、宰相を拝命しなければならなかったのだ。再度の出馬に対しては、王安石は非常に困惑させられたので、彼の本音は、出馬したくは無かったけれど、断ることが出来無かったのは神宗からの申し出への情実で、努めて報いようと思ったからだが、出発間際になると、彼はもう一度宝覚と金山に登ろうとしたことから、広く世間に知れ渡る《泊船瓜州》と言う有名な詩句を残したのだ。
「五、高僧との付き合い」の②に続く

















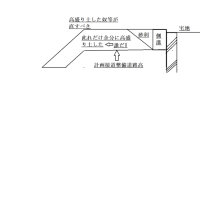
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます